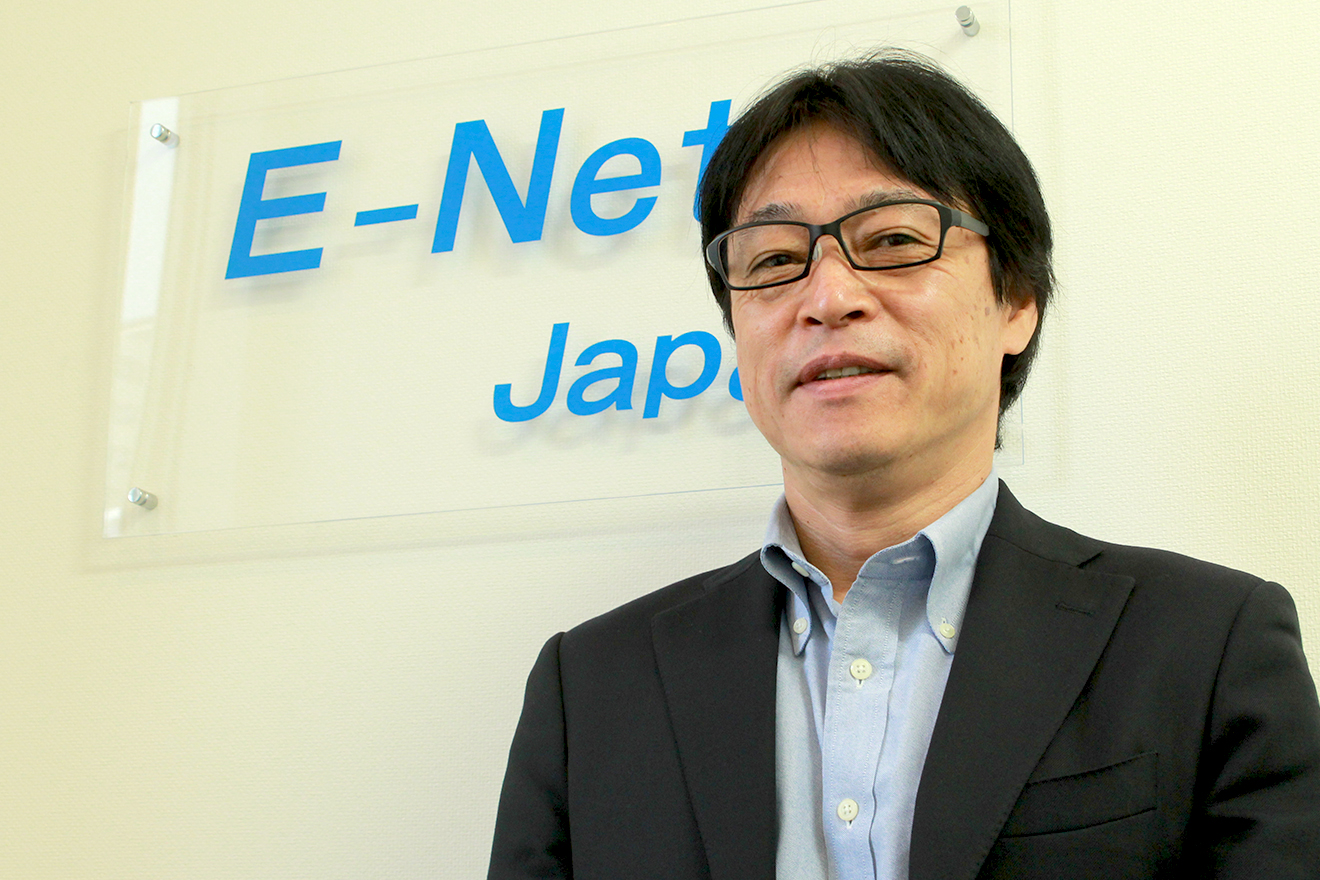「つけ蕎麦ぢゅるり」を手がけるのは2001年にIT事業で創業した会社

大晦日に蕎麦を食べる風習があるように、日本の食文化において蕎麦は欠かせない存在です。そんな日本蕎麦をつけ麺スタイルで提供するのが「つけ蕎麦ぢゅるり」です。
2011年に東京・赤坂に1号店をオープンして以来、「つけ蕎麦」という独自のスタイルはもちろん、リーズナブルかつ、おいしくてボリューミーなつけ蕎麦で他の蕎麦店との差別化に成功。ヘルシーかつ栄養価も高い日本蕎麦。健康志向の高まりから海外でも注目されており、今後は、2020年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向け、増加する訪日外国人特需を巻き込んだつけ蕎麦ブームが期待されています。
そんな「つけ蕎麦 ぢゅるり」を運営するのは、2001年9月に創業した株式会社イーネットジャパン。もちろん、創業当時から飲食関係の事業でスタート……と思いきや、実はIT関連を専門に取り扱う会社として産声を上げたのです。
「IT関連の事業内容はおもに3つ。ひとつは、クライアントとなる他企業さまのIT部門で主にインフラを構築するため、当社の社員をはじめとしたスペシャリストを派遣して構築、運用する事業。そして、公共事業における保守運用サービスと、IT系プロダクト製品の販売をしています」(鈴木)
そんな、IT業界に身を置くイーネットジャパンが、なぜ創業から10年の時を経て飲食業界に参入したのか。そして、数あるフードメニューの中から、なぜつけ蕎麦を選んだのでしょうか?
そこには、創業当時から抱いていた“ある思い”があったのです。
勝てる土俵を探して辿りついた飲食、そして蕎麦という選択

人工知能(AI)の発達により、銀行員の仕事が奪われる——これは、新聞やネットなどの各メディアが報じた一節です。現実のものとなるのか否かは実際にそうなってみないとわかりませんが、こんなことを10年前に誰が予測できたでしょうか。
少し前までは、安定した職業の代名詞のような存在だった銀行員が、人口知能に置き換わってしまっても不思議ではないレベルにまで到達しているのです。それほど、テクノロジーは日進月歩で進化していると言えます。
そして、イーネットジャパンが身を置いているIT業界も、めまぐるしく変わる技術の進歩により、次から次へと新しい技術やプロダクトが誕生しています。
「いずれはIT分野以外でも事業展開しようと考えて創業しました。この業界は移り変わりが非常に激しい業界なので、その流れについていくよりは、ITをひとつのステップにして新しい分野に参入しようと考えていました」(鈴木)
そうして、創業から8年ほど経過した2009年に行きついたのが飲食業界でした。そして、あまたある選択肢の中から、日本蕎麦に決めたのには、ある理由があったのです。
「ラーメンをはじめとした様々な業態を検討しましたが、どれも競合が非常に多くて差別化が難しい、と。そんななか、日本蕎麦に着目しました。業界を分析してみると、いわゆる“町のお蕎麦屋さん”が、ことごとく潰れていたんです。しかし、差別化を図るなど、きちんとした戦略を立てて戦えば、参入の余地は十分にあると考えました」(鈴木)
そこで、なぜ“町のお蕎麦屋さん”が閉店に追いやられているのか、鈴木はある仮説を立てるのです。
「まずは、メニュー構成が従来のままだから。高価格店はそれがブランドになるし、ファンもいるので潰れませんが、低価格店と中価格店はそうもいかない。また、後継者不足も理由のひとつとして考えた時に、今後さらに衰退していくと仮定しました。とはいえ、低価格店は乱立している傾向にあるので、そこで戦っても難しいな、と」(鈴木)
鈴木のいう「高価格店」というのは、歴史のある老舗蕎麦店。次に、地域密着で経営する、いわゆる“町のお蕎麦屋さん”が「中価格店」で、立ち食い蕎麦などが「低価格店」に該当します。この3つの分類の中でも、あえて衰退が激しい中価格店で勝負をすることで、十分に戦っていけると考えたのです。
つけ麺をヒントにつけ蕎麦店として開業、売上を伸ばす中さらなる追い風

ざる蕎麦や盛り蕎麦ではなく、なぜつけ麺スタイルの蕎麦なのか——それは、差別化はもちろん、つけ麺ブームが背景にあったのです。
かねて、関東を中心に人気を得ていたつけ麺ですが、2009年には、東京・日比谷でつけ麺に特化した大規模イベントの「つけ麺博覧会 大つけ麺博」がはじめて開催されました。ちょうどこの頃から、つけ麺が食のジャンルのひとつとして認知されるようになったのです。
そんなつけ麺をヒントに、つけ蕎麦で事業展開することに。とはいえ、IT業界をひた走ってきた当社。飲食店開業のノウハウがないということで、蕎麦業界で20年以上ものキャリアを持つスタッフ(現在はフランチャイズ本部のSVとして活躍)を採用。そして、2011年8月に「つけ蕎麦ぢゅるり」の直営店をオープンさせました。
実はこの当時、すでに東京都内に1店舗だけ、つけ蕎麦を提供する店舗があったのです。
「そのお店はメニューが限られているので、まずは、バリエーションを豊富にしたメニュー構成で差別化をしようと考えました。赤坂店がオープンしてもう7年目になりますが、つけ蕎麦だけでも30種類以上のメニューをラインナップしています」(鈴木)
しかし、それだけでは鈴木が考える差別化には程遠いと考え、別の付加価値を付けることで、つけ蕎麦を広く認知させようと考えたのです。
「高価格店は顕著ですが、1枚のざる蕎麦だけでは満腹にならないことってありませんか? ですので、1杯の蕎麦だけで満足してもらえるお店にしよう、と。蕎麦は老若男女が食べるものですが、お年寄りはオーソドックスな蕎麦を好む一方、若い世代はガッツリ系を好む傾向にあるので、蕎麦だけで満足できないそういう世代向けに、丼モノもラインナップに追加しました」(鈴木)
その結果、メニュー構成やスープの味など差別化要素を詰め込んだ「つけ蕎麦ぢゅるり」をオープンさせることに成功します。オープン時には、500円キャンペーンを実施したおかげもあり、鈴木はもちろん、社員総出でお店を切り盛りするほどの大盛況。確かな手応えを感じるとともに、少しずつファンを増やしていくのです。
2011年に1号店の赤坂店がオープンして6年以上が経過した「つけ蕎麦ぢゅるり」。おかげさまで客数や売上が年々伸びている理由に、競合がほとんどいないから——そう鈴木は分析しています。
「2012年と2016年でいうと売上が150%増、客数が185%増を達成しています。蕎麦店を競合視していないので、あえて競合として挙げるならつけ麺店になります。2020年には東京オリンピックが開催されるので、インバウンド消費も増えて先行者利益を得るには今がチャンスかな、と。以前、テレビで放送されたある番組で、『今年流行るものランキング』が発表されていて、そこにつけ麺がランクインしていたこともあり、需要は感じています」(鈴木)
誰もが成功できるパッケージを構築、フランチャイズでつけ蕎麦を世界へ

そんな「つけ蕎麦ぢゅるり」がフランチャイズ展開をスタートさせたのは2017年2月。それはもちろん、「つけ蕎麦」で戦っていくことに確かな手応えを感じているから——。
「売上増はもちろんですが、訪日外国人のお客さまにも来店いただく機会が多くなりました。私はラーメンやうどんに続き、これからは日本蕎麦、さらにいうと『つけ蕎麦』ブームがくると確信しています。こうした背景もあり、他店舗展開に動き始めました」(鈴木)
当初は直営店での店舗展開を考えた鈴木でしたが、1店舗増やすだけでも少なくとも2000万円は必要。それでは資金だけでなく時間もかかりすぎてしまう……。悩んだすえに導き出した答えがフランチャイズだったのです。
「1店舗増やす為に投資するよりも、さらなる多店舗展開を見据えて投資しよう、と。そこで専門のコンサルに依頼し、フランチャイズの仕組みを一から構築しました」(鈴木)
そうして始まった「つけ蕎麦ぢゅるり」のフランチャイズ化。まずはメニューをマイナーチェンジするところからスタート。
「フランチャイズ展開するということは、誰もが成功するパッケージにしないとけない。それまでは大盛りも普通盛りも830円だったんですが、普通盛りを740円にしました。従来は蕎麦だけでも満足できる量をコンセプトにしたので、がっつり食べたい世代向けに大盛りも値段は据え置きだったんですが、入り口を広くするためにも、幅広い年齢の方に来ていただかないといけない。そう考え、普通盛りがお得になるように設定しました」(鈴木)
さらに、開業前研修を28日に設定するなど、飲食未経験者を含めて問題なくオペレーションできる内容になっているのです。
「座学が4日で、残りの24日が店舗実習。調理はもちろん、朝の清掃から夜のレジ締めまで、研修が終わったら自分で店舗運営できるところまでを網羅した研修内容になっています。研修だけでは覚えられない部分もあるはずなので、店舗運営マニュアルも一から作りました」(鈴木)
まずは東京23区内のフランチャイズ展開を皮切りに、第二フェーズとして首都圏での展開を見据えている当社。将来的には、うどん文化が根付いている関西エリアも含め、全国につけ蕎麦の文化を広げることはもちろん、5年以内には、海外でも「つけ蕎麦ぢゅるり」の看板を見る日を目標に駆け抜けます。
※掲載情報は取材当時のものです。