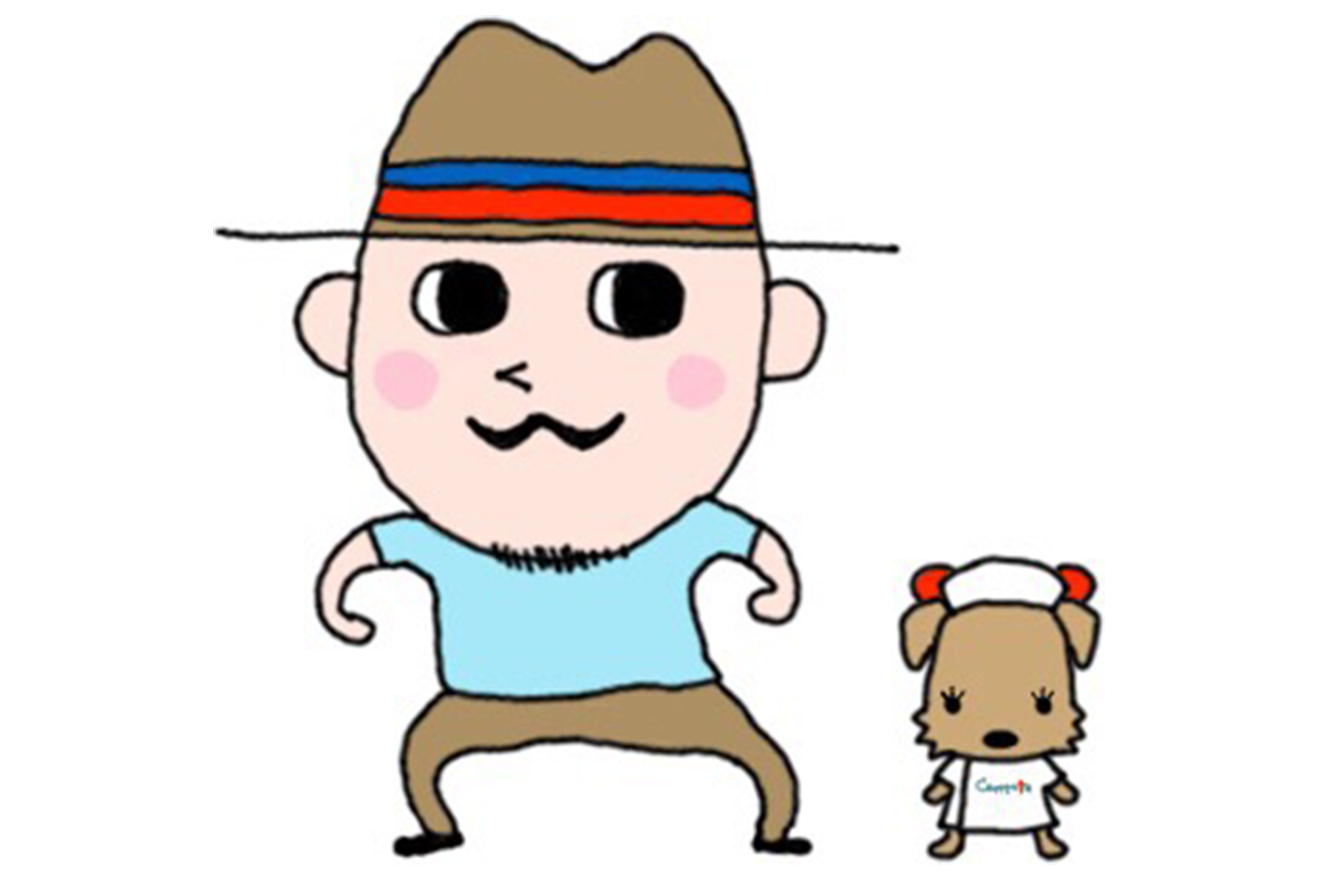ブラジルへのサッカー留学が福祉業界に進むきっかけに

「将来は、絶対にプロサッカー選手になってやる——」。
小学生でサッカーをはじめ、中学3年生のころにはサッカーの本場であるブラジルへ留学をするなど、10代のすべてをサッカーに捧げてきた藤田。当時、日本国内ではプロサッカーリーグのJリーグが開幕するなど、空前のサッカーブームが到来していました。
プロのサッカー選手になることを信じて疑わなかった彼ですが、その夢ははかなくも消え去ってしまうのです……。
「向こうで南米の選手との覚悟の違いを思い知りました。結果そのなかでの競争に勝ち残ることができなくて、サッカー選手になれないって分かった時点で『俺って、生きてる価値ないな』って思って、自暴自棄になってしまったんですよね(笑)」(藤田氏)
そして、次の夢を探しはじめたときに脳裏をよぎったのが「福祉業界」でした。多くの選択肢があるなかでも彼が福祉の世界に足を踏み入れたのは、サッカー留学でブラジルを訪れたことが最初のきっかけになっていたのです。
「ブラジルに行ったときに違和感を覚えたんですよね。というのも、30年近く前のブラジルは、貧困層と富裕層の格差が激しくて路上にはストリートチルドレンが溢れている時代。親がいない子どもがいるのはもちろん、ぼくと同じ中学生くらいの子どもたちが路上でモノを盗んで生活をしているような状況で……」(藤田氏)
一方、当時の日本はバブル景気で人々の生活は豊かになるばかり……。中学生ながらこのギャップがどうしても頭から離れなかった彼は、帰国してからもずっと「貧困」について考えていたのです。
「どうして貧困層が生まれるんだろう、どうすれば格差がなくなるんだろうってことに興味があったんですよ。その後も本を読んだり大学では社会福祉学科に入学するなどして『貧困』について学んでたんです。それで、サッカーを諦めてぶつける先を失っていた思いを、人の役に立つ仕事に向けようと考えたとき『福祉の仕事』をしよう思ったんですよね」(藤田氏)
未経験で飛び込んだ介護業界にはびこっていた「負」との戦い

1998年、22歳のときに福祉業界に足を踏み入れた藤田。
最初のキャリアは、埼玉県にある社会福祉法人で介護職員としてスタートします。すると、介護の世界では当たり前の慣例に、またしても大きな違和感を覚えたと振り返ります。
「入ってすぐ感じたのは、そもそもここで生活していて利用者は幸せなのかなって。今でもありますが、寝たきりって正しくは『寝かせっきり』なんですよ。本人が寝たいから寝てるみたいな表現になってますけど、そうしたほうが働いている職員がラクなので寝かせっきりにさせてるだけなんですよね」(藤田氏)
当時はベッドから落ちると危険だからという理由で、「身体拘束」すらもしているような時代……。虐待とも取れるその行為が問題視され、その後の2000年には身体拘束が原則的に禁止されました。
「寝かせっきりや身体拘束なんて、利用者に対して尊敬の念も何もないですよね。身体拘束をされて自分の好きなようにできない現状を、利用者はどう考えているんだろう、と」(藤田氏)
そんな利用者が、楽しみにしていた時間のひとつが入浴です。しかし、この入浴についても大きな違和感を抱いたと続けます。
「毎日入浴できるわけでなく、週2日や3日って決まってるんですよ。しかも、入る順番や所用時間も決まってる。なかには、ストップウォッチで入浴時間を計測したりして。オペレーションを考えたら効率的かもしれませんが、客観的に見たら刑務所と同じですよね。べつに何かモノを生産しているわけではないので、そこまでしなくてもいいと思ったんです」(藤田氏)
入浴だけがそうだったわけではありません。おむつやシーツ交換などといった通常業務のすべてにおいて、働くスタッフたちの効率化を重視するばかりで、利用者のQOL(生活の質)は無視……。そこで、彼は大きな改革に打ってでるのです。
「おむつ交換が早くできたスタッフがえらい、みたいな風土がありました……。でも、本来は効率優先ではなく、丁寧なほうが利用者の満足度は上がりますよね。なので、たとえば入浴については、利用者の希望に合わせて入浴する時間やタイミングを決めるようにしたり。あとは、施設にいると社会との接点がなくなるので、できるだけみんなで一緒に買い物に連れていったり、季節に応じて花見や温泉旅行などのイベントを企画したりしましたね」(藤田氏)
すると、利用者たちのQOLが向上。その結果として、リハビリの効果など、症状の改善が見込めるというのです。
「高齢者の方たちって、体が動かなくなって人生に楽しみが見出せないと、『死にたい』ってなるんです。でも、楽しみができると『楽しいから生きたい』って考えが変換されるばかりか、リハビリをすると効果が出るんですよ。『死にたい』って言ってる高齢者がリハビリをしても、そもそもそんなことしたくないので何も改善しないんですよ。歩けるようになったって意味なんてないんですから……」(藤田氏)
現場で感じた社会福祉法人の限界……

利用者に寄り添った介護で、介護業界の悪しき風習と戦っていた藤田。しかし、施設内ではそれができても、一歩施設の外に出てしまうと途端に無力になってしまうことを実感するのです。
「働いていたのは、特別養護老人ホームでありデイサービスも併設していた施設でした。デイサービスだと利用者の送り迎えがあるんですが、迎えにいくと利用者の家族が自分のおばあちゃんの背中を蹴っ飛ばしたりしてるんですよ」(藤田氏)
介護のストレスにより、家族による虐待が横行……。蹴ったり殴ったりはもちろん、最悪の場合は死に至るまでの虐待が行われている事実に直面するのです。
「当時は土日や正月は施設が休みだったので、長期休みの間、利用者は施設を使えない。つまり、自宅で介護を受けないといけないんです。1人で入浴するのは危険なので、その間は絶対に入浴をしちゃいけないって伝えるんです。でも、その教えを守らず入浴してしまい、休み明けに迎えに行ったら亡くなっていたり……」(藤田氏)
ほかにも、介護を放棄したことによる虐待死はもちろん、年金を使い込むなどといった経済的虐待なども蔓延していました。
「正月などの長期休暇の間もショートステイを利用できていたら、入浴中の事故も防げていたわけで……。家族によるストレスが限界を突破する以前にどこかに預けられていたら、そういう虐待からも護ってあげられますからね」(藤田氏)
しかし、高齢者の数に対して特別養護老人ホームの数が圧倒的に足りず、もし申し込んでも入居できるのは10年後……。待機高齢者は全体で42万人もいると言われていた時代だったのです。
「なので、当時は高齢者を預けられるといったらショートステイくらい。とはいえ、ショートステイを増やすこともなかなかできない世の中で……。というのも、ショートステイは基本的には介護保険制度の設備基準や人員基準など、あらゆる基準を満たさないと新しく作れない。しかもその基準がめちゃくちゃ高いので、なかなか数が増えなくて、虐待は増える一方なんですよね」(藤田氏)
それを解決するためには、社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設である特別養護老人ホームを増やす必要があります。しかし、施設を新しく作るには莫大な資金を必要とするだけでなく、そこで働く介護職員の労働環境も変える必要があったのです。
「たとえば、50人が入居できる特別養護老人ホームを作るとしたら、当時で8億円必要だったんです。それに対して国の補助金が8億から多い地域だと9億円も入る。さらに、社会福祉法人なので法人税を納めなくていいんです。すると、税収内では社会保障費が賄えず、国の財政を見たら毎年借金が増えているんです。そうして足りない部分のしわ寄せが職員の低賃金労働に繋がり、搾取しているような感じで……。施設が足りないのに、増やせば借金が膨れ上がり、施設を増やせないという構造をどうにかしないといけないな、と」(藤田氏)
1100ページにも及ぶ事業計画書から始まった藤田の挑戦

当時の構造から考えても、特別養護老人ホームが増えることは考えにくい状況。このあとに迫り来るであろう超高齢社会を乗り越えていくためには、構造自体を変える必要がある——そう考えた藤田は、自身で24時間対応のデイサービスを立ち上げることを決意するのです。
「当時は24時間対応しているデイサービスがなかったんです。夜間は保険外のサービスなので利用者は自費で支払わないといけないんですが、ストレスフルになる前に預けられる。つまり、虐待や最悪、死に至ることもなくなるんですよ」(藤田氏)
とはいえ、事業をはじめようにも当時の資金はわずか10万円……。いうまでもなく、独立するには資金が足りません。そこで、1,100ページにもおよぶ事業計画書を作成し、融資を受けられる銀行を練り歩くのです。
「熱意だけはありましたが、それだけでは銀行はお金を貸してくれませんからね(笑)。13行目にしてようやく400万円の融資を受けられて、なんとか起業することができました」(藤田氏)
まずは埼玉県・熊谷市で夜間対応型のデイサービスを設立すると利用者が殺到。多くの反響を得ることになるのです。いまでこそ当たり前となった24時間対応型のデイサービスですが、当時はこれが日本初のこと。なぜ、それまで存在すらしなかったのでしょうか。
「誰も制度を把握していないので、混合介護がオッケーだということを知らなかったんですよ。医療保険は混合医療がNGなんです。それによって診療報酬がむだに高くなったという反省のうえで介護保険が作られている。なので、基本は混合介護はOKなんです。最近ではインターネットで『混合介護』と検索するといろいろ出てきますが、自分がやったのが日本で一番最初の混合介護サービスなんです」(藤田氏)
その後は埼玉県の熊谷市内だけで47施設の夜間対応型デイサービスを展開。そして、起業から2年くらいで東京に本部を移し、本格的に全国展開へと舵を切り直すのです。
多くの賛同を得た藤田の挑戦。6年間で900施設まで拡大

全国展開にあたり、フランチャイズで加盟店を募ることとなった藤田。しかし、当時は介護業態のフランチャイズ自体が存在せず、完全に異質扱いだったと振り返ります。
「フランチャイズの展示会に出展したんですが、来場者の方々から理解してもらえませんでしたね。『24時間対応のデイサービスって何?』『そんなのできるの?』みたいな(笑)。フランチャイズっていったらコンビニとか飲食系、ハウスクリーニングがメインでしたし、当時は『介護』って言葉自体があまり使われてなかったので、すぐに理解してもらえないのもしょうがないんですけどね」(藤田氏)
とはいえ、藤田の思いや優位性などが認知されるのには、そう時間を必要としませんでした。その数は少しずつ増え、最終的には6年で900施設まで拡大することになるのです。


「言っちゃうと、数とか会社をでかくしたいなんてどうでもいんですよ。要は必要とされてるってことを示したかった。だって、900施設で4万人も利用してるんですよ。それだけニーズがあるんですから、国も作ったらいいじゃんみたいな感じでしたね(笑)」(藤田氏)
しかし、これだけ数が増えると国も黙ってはいません。
「厚生省とガチンコ勝負になったんですよ。ただ、厚生省のなかにも賛成派とアンチ派がいて……。なぜこれだけ利用者がいるのにアンチ派が発生するかというと、賛成してしまうと、これまで国が作った制度に欠陥があったことを認めることになる。結果としては、痛み分けみたいな感じで、規制ができたりメディアにリーク記事を書かれたりしました。戦わないほうが人生楽なんですが、どっちのほうが世の中にとってベターなのかを示したかったんですよね」(藤田氏)
動物が好きだから! 殺処分される保護犬や保護猫を救うための新たな挑戦

結果としては、藤田がいう通り「痛み分け」で終わりましたが、24時間対応型デイサービスは900拠点にして利用者は4万人にものぼり、彼が示したかったことは十分に実証できたといえるはずです。

そんな藤田が新たに立ち上げたのが、ペット共生型の障害者グループホーム「わおん」。障害者グループホームとは、身体・知的・精神障害者などが世話人の支援を受けながら共同で生活を行う住宅施設です。さらに、「わおん」は一般的な障害者グループホームとは異なり、施設開所の際に保護犬か猫のどちらか1匹を必ず引き取るというもの。
これは無類の動物好きという藤田が実現したいと思っている、ある問題を解決する取り組みでもありました。
「現在、日本で殺処分される保護犬や猫は年間35万頭もいます。そこにペット共生型グループホームという受け皿をつくることで、殺処分される保護犬や猫を救うことができるだけでなく、施設利用者のQOL(生活の質)も向上します。つまり、動物だけでなく人間もハッピーになれるんですよ」(藤田氏)
そんなバイタリティ溢れる藤田の原点は、日本とはまるで環境が異なるブラジルへのサッカー留学。そこで経験した貧困から、社会の問題に興味を持ち、人生をかけたサッカーに変わる情熱の注ぎ場所となった福祉業界で、彼が目指す理想の世界を実現するためにはこれからが正念場。
障害者の支援はもちろん、動物の殺処分をなくすという大きな社会問題を解決するため、彼の挑戦はまだまだ続きます。
※掲載情報は取材当時のものです。