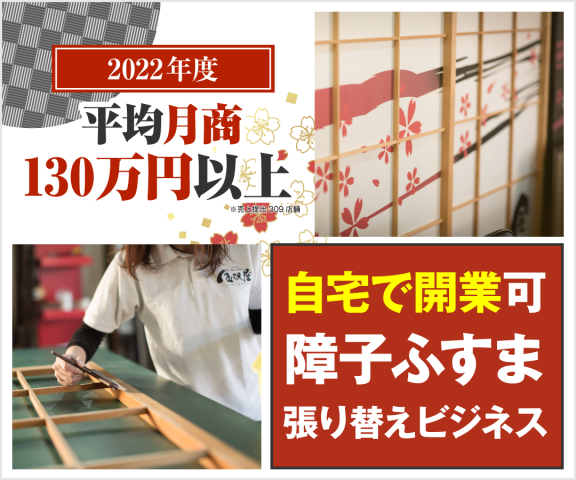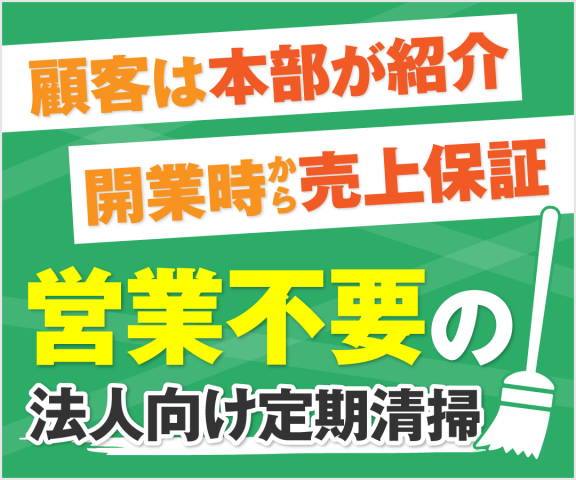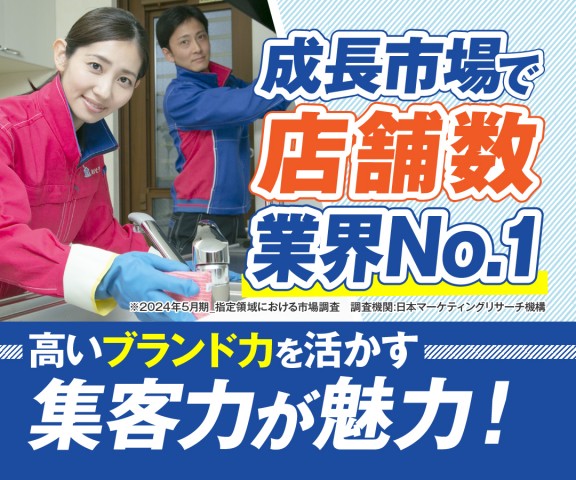フランチャイズの開業資金相場は?資金の内訳や資金調達・融資の種類も解説

フランチャイズ加盟して開業するためには、加盟金以外にも、保証金、研修費、物件費、内外装費など、いろいろな費用が必要です。経済産業省の調査では、小売業、外食業、サービス業のフランチャイズにおいて3,000万円以上の開業資金が必要という結果が出ているので、資金計画は慎重に行なわなければなりません。
この記事では、フランチャイズの開業資金にまつわる情報を解説します。調達方法として「FCの優遇制度、銀行融資、日本政策金融公庫の融資、中小企業向けの補助金・助成金」も紹介するので参考にしてください。
フランチャイズでの開業のために必要な資金とは?
まずは、フランチャイズに加盟して開業するための必要な資金について、基本のポイントを押さえておきましょう。経済産業省が、社団法人日本フランチャイズチェーン協会など、日本全国の小売業、外食業、サービス業の1200本部事業者に対し調査した「フランチャイズ・チェーン事業経営実態調査報告書(平成20年3月)」によると、加盟店側で店舗を用意する場合の平均金額は、保証金207万円、設備資金1,624万円、商品仕入れ等589万円、研修費44万円、その他経費(POS端末費用など)1,054万円となっています。
そのほか、物件取得費、内外装工事費、採用人件費もかかるので、開業資金はさらに金額は大きくなるでしょう。ちなみに、開業するための資金を業種別に見ると小売業が3,488万円と最も高く、次いで外食業3,292万円、サービス業3,087万円と続きます。
加盟金
フランチャイズの開業には加盟金が必要なことが一般的です。加盟金の支払いにより、ノウハウやマニュアルを提供してもらったり、商標を使用できたりします。加盟時に一回だけ支払い、契約を解除する際には返金されないのが通常です。
保証金
保証金とは、フランチャイズ契約の際に本部に納める一時金のことをいいます。フランチャイズに加盟して運営していくうえで、本部と加盟店はさまざまなお金のやり取りが発生します。
もし、加盟店が期日までに何かしらの費用を本部に支払えない場合は、この保証金から差し引かれます。そして、差し引かれた分の金額を補填し、元の保証金の額に戻す必要があります。また、基本的に保証金はフランチャイズ契約が終了した際に、加盟店に返却されます。
物件取得費

コンビニや飲食店など、店舗型のフランチャイズの場合は物件取得費が必要です。物件取得費とは、敷金や礼金、仲介手数料、保証金など、物件を取得する際に必要な費用のことをいいます。
仮に、敷金と仲介手数料がそれぞれ家賃の1ヶ月分、礼金が2ヶ月分、保証金が6ヶ月分、オープンまでの前払い賃料が2ヶ月分だとすると、11ヶ月分の費用が必要です。1ヶ月の家賃が15万円だとしても、トータルで165万円も用意しなくてはなりません。立地によっては保証金が家賃の10ヶ月分も必要になる物件もあります。
内外装工事費
物件が決まったら、今度は内外装を工事するための費用が必要です。なかには、フランチャイズ本部が指定する内外装業者に依頼しないといけないパターンもあります。飲食店であれば、厨房や什器などの設備も必要になってくるでしょう。
もし初期費用を抑えたい場合は、スケルトンではなく居抜き物件を選ぶのも一つの手です。居抜き物件とは、前のテナント利用者が使用していた厨房設備や水道まわりなどがそのまま残っている物件のこと。これらをそのまま使えるので、大幅に初期費用を削減できるのです。
開業前研修費

フランチャイズに加盟すると、1週間や1ヶ月間などフランチャイズ本部によって期間は様々ですが、本部が主催する研修を受けることになります。この研修にかかる費用が開業前研修費です。なかには、加盟金に含まれているパターンもあります。
オーナーだけ、スタッフ3人までなど、研修を受けられる人数が決まっていることが多く、もし規定の人数よりも多い人数で研修を受けたい場合は、追加で開業前研修費を支払う必要がある場合もあります。事前に本部に確認しておきましょう。
なお、開業前研修は東京や大阪にあるフランチャイズ本部で実施されることがほとんどです。その際にかかる交通費や宿泊費などが別途必要になってきます。
採用費・人件費
従業員を雇用する場合、採用するためにコストがかかりますし、働いてもらう以上は毎月人件費が発生します。特に、オープン当初はスムーズに営業するためにも従業員を多めに雇用する必要があるので、開業当初ほど人件費が高くなりがちです。店舗運営費のなかでも割合が高い人件費ですが、削減しすぎると店舗運営に支障をきたすおそれがあります。
その他に想定される費用
フランチャイズ本部のなかには、初期費用の内訳に「その他の開業費」を設けているケースが多くあります。その他の開業費には、開店準備金や営業許認可料、釣銭、運転資金、販促ツール代など、じつにさまざまな項目が該当します。
細かく見ていくと、自社専用のウェブサイト構築費用、開業告知の広報宣伝費、(飲食店なら)グルメサイトへの転載費用などの販促費用も、その他の開業に含まれます。また、POSシステム使用料、従業員用のユニフォーム購入費も同様です。項目が多いだけに、その他の開業費の金額が多くなってしまうケースは少なくありません。
用途が不明な場合は、納得のいくまでフランチャイズ本部に確認するようにしてください。
フランチャイズの初期費用は加盟金以外にもさまざま
フランチャイズに加盟すると、本部にロイヤリティを支払う必要があります。ロイヤリティには固定した金額を支払う定額方式と、売上や粗利から決められた割合で支払う歩合方式の2つがあります。
たとえば、売上歩合方式で売上の15%がロイヤリティと決められている場合、売上が200万円あれば30万円です。粗利歩合式の場合も同様に計算できます。どちらの歩合方式でも、売上や粗利が大きくなると支払う金額も増えるので、ロイヤリティのパーセンテージはしっかりと確認しておきましょう。
加盟金0円の秘密
なかには、加盟のハードルを下げる目的で、「加盟金0円」を謳っているフランチャイズ本部もあります。しかしその場合、保証金や毎月のロイヤリティの比率を上げてバランスを取っていることもあります。ほかにも、その他にシステム利用料といった別の名目で開業費にさまざまな項目が含まれていたりもします。
こういったことからも、加盟金の額だけを見て加盟するフランチャイズを選ぶのは避けたほうがよいでしょう。初期費用全体やロイヤリティをはじめ、毎月のランニングコストなども含めて検討するようにしましょう。
開業前にどれだけ資金を用意した?
フランチャイズの開業で資金をどれだけ用意するべきかについては、先輩オーナーの声が参考になります。「マイナビ独立」によると、加盟時に用意していた自己資金の金額で最も多いのは、300万円~500万円未満の23.7%でした。次いで、100万円~300万円未満の20.6%という結果です。意外なのは、自己資金を全く用意していなかった人が16.5%、100万円未満の人が15.5%もいることです。
一方で、1,000万円以上の自己資金を用意したのはわずか13.3%でした。半数を超えるフランチャイズオーナーが300万円未満、75%を超えるオーナーが500万円未満しか用意していなかった事実に驚いた人も多いかもしれません。では、実際のところ、フランチャイズの開業にはどれくらいの資金が必要なのでしょうか。
[PR]自己資金100万円以下で独立可能
開業資金の相場は?

日本政策金融公庫総合研究所が発表している「2020年度新規開業実態調査」によると、開業費用は500万円未満と回答した人が43.7%と最も多く、500万円~1,000万円未満が27.3%と続きました。年度を追うごとに、500万円未満と回答している人の割合が増えていることから、開業費用の低価格化が進んでいることがわかります。
また、先述の「マイナビ独立」によるフランチャイズの開業で実際にかかった金額を見て見ると、100万円未満と回答した人が25.8%と最も多く、次いで多かったのは300万円~500万円未満が23.7%、500万円~1,000万円未満が20.6%、100万円~300万円未満が13.4%でした。
自分で用意した開業資金が500万円未満の人が75%に対し、実際にかかった開業資金が500万円未満と回答した人は62.9%という結果ですから、自己資金では賄い切れなかった人が一定数いることがわかります。
業種別、開業資金相場
フランチャイズの開業資金は、業種別で大きく異なります。飲食業の場合、お店の規模が大きくなるほど多額の開業資金が必要になるのは当然ですが、キッチン設備のみで小規模の居抜き物件を活用できれば開業資金を100万円以内に抑えることも可能です。一方、小売業のなかでも古本・CD・DVD販売店は、オープン時点で在庫を抱える必要があるので、数千万円の開業資金が必要になるケースもあります。
また、サービス業の場合は自宅を活用して開業できる業態もあるため資金を抑えることが可能です。ただし、ハウスクリーニングや便利屋など一定のスキルが必要になるので、資金面以外の部分で苦労する可能性があるでしょう。
開業資金別、業種相場
開業資金を多く用意できるほど、フランチャイズで開業する業種の選択肢が広がります。たとえば、ファーストフード店や居酒屋などの業態は数千万円以上必要です。少ない開業資金で始めるなら、20万円以内で始められる無店舗型の弁当宅配サービスがあります。最近話題のゴーストキッチンなども飲食スペースが要らず、調理スペースのみで開業できるので100万円以下に抑えることもできるでしょう。
また、墓石クリーニングや終活に関するサービスも100万円以内で始められます。300万円程度まで用意できるなら、携帯電話販売店やラーメン屋、クリーニング店なども選択肢に入るでしょう。500万円程度の資金を準備できるなら、コンビニエンスストアや金券ショップ、リサイクルショップ、マッサージ店などの開業が可能です。
開業資金を調達するには?

先に紹介した日本政策金融公庫の調査によると、開業時の資金調達額は、調査を始めてから最も低い1,194万円でした。資金の調達先として多いのは金融機関等で、平均の借入額は825万円。自己資金の平均は266万円にとどまり、ほとんどの人は開業資金の大部分を融資で賄っているのが現状です。
なお、開業資金の調達には、中小企業庁の「創業支援等事業者補助金」もあります。補助金や助成金のなかには、フランチャイズの開業に利用できないものもありますが、利用できる場合は積極的に活用しましょう。
本部の優遇制度を利用
フランチャイズで開業する場合、本部が用意している優遇制度の利用によって資金の負担を軽減することが可能です。たとえば、ローソンでは、通常100万円かかる加盟金が免除される以下の制度を用意しています。
家族加盟支援制度
夫婦または2親等以内の専従者と加盟した場合に加盟金が免除
ローソンキャリア独立制度
加盟金の免除に加え、最大150万円のFC加盟奨励金、最大80万円の転居費・最大120万円の住居の支援
ローソンファミリー独立支援制度
加盟金の免除に加え、出資金の分割払いが可能、転居費100万円を支給
このような優遇制度はフランチャイズ本部ごとに用意されていてそれぞれ違いがあるので、じっくりと比較してみましょう。
金融機関から借り入れる
開業に向けた資金調達方法で最も多かった金融機関からの融資には、「保証協会付融資」「プロパー融資」の2種類あります。「保証協会付融資」は、保証協会に決められた保証料を支払う必要があるものの、審査が通りやすいのが魅力です。
「プロパー融資」は、審査は厳しいものの、毎月の支払額を低減できます。フランチャイズで初めて開業する場合、基本的に貸し倒れリスクの少ない保証協会付融資となるので、毎月の返済計画を綿密になることが必要です。
日本政策金融公庫(日本公庫)からの借り入れ
フランチャイズの開業を有利に進めるためには、日本政策金融公庫を利用するのもおすすめです。日本政策金融公庫は政府が100%出資する金融機関で、低金利で借入れがしやすいというメリットがあります。融資が決定されると、融資の実績ができ事業の信頼度が高まるので、次回以降は金融機関の審査も通りやすくでしょう。
たとえば、新たにフランチャイズを開業する場合は新創業融資制度を利用できます。担保や保証人が不要で最大3,000万円まで融資を受けることが可能です。
中小企業向けの補助金・助成金を利用
認知度はあまり高くないようですが、中小企業庁でも創業支援をはじめとする経営サポートを受けられます。たとえば、平成30年に行なわれた「創業支援事業者補助金」もそのひとつで、条件を満たすと1,000万円を上限に補助対象経費の3分の2まで補助金を受けられる制度でした。
物件取得や内装工事には活用できないものの、人件費や備品・設備費、販促費には利用できたので、利用価値は高かったと言えます。中小企業庁では、創業に関する情報も提供しているので定期的にチェックしておきましょう。
[PR]法人の多角化に最適
資金への細かな配慮が成功のポイント
フランチャイズでの開業は、大きな金額を用意する必要があると考えて身構えてしまう人も多いかもしれませんが、実際は500万円未満で開業している人も多く、なかには100万円未満で開業している人もいます。開業資金が高くなってしまう場合は日本政策金融公庫から融資を受ける方法もあります。
すべてを自己資金で賄おうとすると開業のタイミングを失い、大きなビジネスチャンスを逃してしまうおそれもあるでしょう。不足分は融資を受ける選択肢も用意したほうがフランチャイズオーナーへの道が開けるはずですよ。
[PR]未経験・初心者でも安心のビジネス