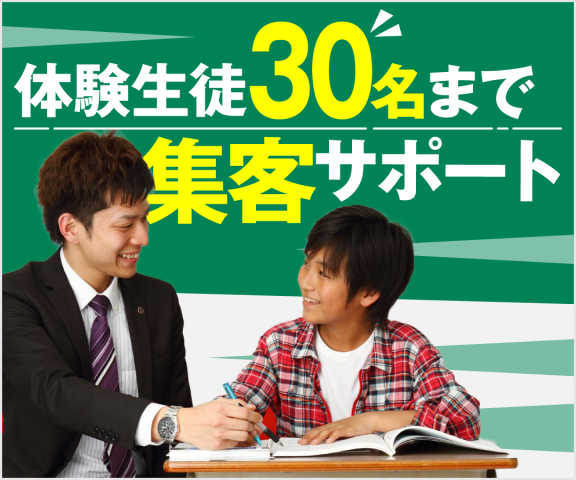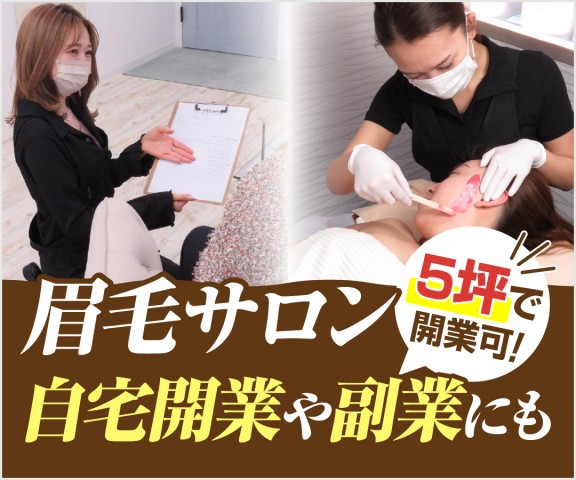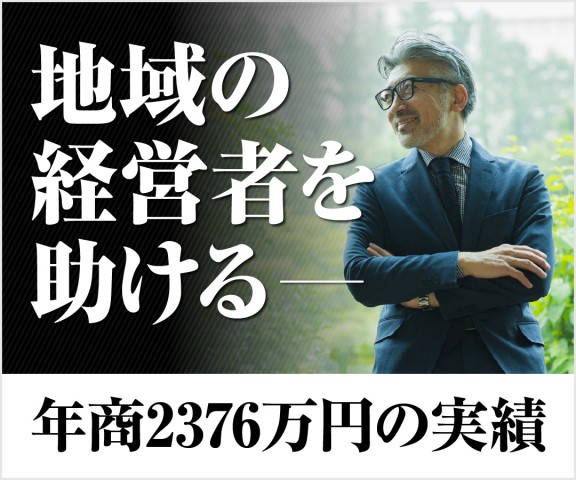個人事業主に外注!源泉徴収が必要なケースと納税方法について

会社で働いている人なら一度は耳にしたことがある「源泉徴収」ですが、事業主が個人事業主に外注した際に発生することもあります。
また、同じ外注でも、支払対象が個人事業主か法人かによっても源泉徴収を行なう範囲が変わってくるので、この記事では、どのような場合に源泉徴収が必要なのか、源泉徴収の対象や納税方法についても紹介します。
個人事業主に外注するときに注意!源泉徴収とはどんな制度?
源泉徴収とは、給料や報酬などを支払う側の人が、それらを支払う際にあらかじめ所得税などを金額から差し引いておく支払い制度のことです。最も知られているのは給与所得を対象とした源泉徴収ですが、他にもフリーランスや個人事業主などに対する報酬にも、源泉徴収が必要な場合があります。
[PR]安定収益が得られる
源泉徴収のメリット・デメリット
源泉徴収のメリット
安定した納税ができる
源泉徴収のメリット1つ目は、「効率よく税を収めることができる」ことで、これは徴収する側のメリットです。所得税というのは、主に源泉徴収で支払う「源泉所得税」と自分で申告を行う「申告所得税」があり、この内、源泉所得税の割合はおよそ8割を占めています。この割合の高さが源泉徴収の重要性を表しているといえるでしょう。
もし、仮に「申告所得」がメインになってしまった場合、申告書を提出する側だけでなく、受け取る税務署側も手続きの対応に追われて大変なことになってしまいます。また、税制も日々改正を繰り返しており、その制度を国民が全員正確に把握するのは難しいです。
そのため、所得税の払い過ぎや申告の漏れなど手続きのミスも発生し、適切な納税が行われない可能性も出てきます。さらに、所得税は基本的に1年の1月から12月のお金を計算して、翌年の2月から3月に納税を行なうのものなので、国が安定した税収を得るためにも正確な納税が必要になります。こういった問題を解決してくれるのが源泉徴収というわけです。
複雑な手続きがいらない
メリット2つ目は、「手続きが楽」ということで、これは主に税を納める側のメリットです。会社に勤めているのなら、源泉徴収で会社側が全て面倒な手続きを行ってくれるので、特別な知識もいらない上に、年末の手続きなども必要がなく、とても便利です。特に日本にはサラリーマンが多いため、非常に便利なシステムだといえます。
源泉徴収のデメリット
税金の仕組みや知識が身につかない
一方で、源泉徴収のデメリット1つ目は、「納税意識が低くなる」ことです。たとえば、アメリカにも源泉徴収のシステムはありますが、個人事業主であるかどうかに関わらず、源泉徴収された税の精算を行うために自分で確定申告をしなくてはならないという制度があります。
一方で日本の場合は、源泉徴収をする場合、基本的に全ての手続きを会社側がやってくれるため自分で申告をする必要がありません。そうなると、自分で税を納めているという意識もあまりなく、税金の仕組みも分からないままに税金としてお金だけが引かれているという状況になりかねないのです。
源泉徴収の対象から外れたときの負担
デメリット2つ目は、「納税する際の精神的ダメージが大きい」ことです。源泉徴収の対象者は毎月勝手に給与から所得税が引かれているため、税金を払っているという実感がほとんどありません。しかし、源泉徴収の対象でない自営業者などは、1年に3回も自分で直接納税をするため、精神的なダメージが大きく、源泉徴収者との差を感じてしまう場合があります。
個人事業主に源泉徴収をする必要がある「源泉徴収義務者」
源泉徴収を行なう義務がある人のことを「源泉徴収義務者」といいますが、法人だけでなく、個人事業主も源泉徴収義務者になる場合があります。ここでは対象となる条件を説明します。
源泉徴収義務者にならないケース
このケースには2種類あり、個人事業主で「基本的に2人以下で、家事の使用人などだけに給与を支払っている場合」と、「給与支払いがなく、弁護士などの報酬や料金を支払っている場合」です。つまり、従業員がおらず、1人で仕事をしているような個人事業主の場合は、源泉徴収の義務はありません。
源泉徴収義務者でなくてもホステス等は源泉徴収が必要
源泉徴収の義務がない個人事業主という場合もありますが、ホステスなどに報酬を支払う場合、源泉徴収を行なう必要が生じます。なぜなら、ホステスの業界には確定申告を忘れてしまう人や、副業でホステスをしていて会社に知られたくないなどの理由で、確定申告をそもそも行わない人が多いからです。
[PR]家族と一緒に独立開業
個人事業主に依頼する前に確認!源泉徴収の対象となるもの
支払いを受けるのが個人事業主かつ下記の場合は源泉徴収の対象となります。
・原稿料・講演料
・デザインの報酬
・弁護士・税理士など特定の資格を持っている人への報酬
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロスポーツ選手やモデル及び外交員などへの報酬
・芸能人・芸能事務所を経営している個人への報酬
・ホステスやコンパニオンなどへの報酬
・プロスポーツ選手への契約金
・広告の宣伝のための賞金
・馬主に支払う競馬の賞金など
これら以外にも、源泉徴収対象になるケースがあるので、国税庁のホームページや所得税法で調べておきましょう。
個人事業主からいくら徴収する必要がある?源泉徴収の計算方法
計算方法は、給与や報酬の額によって変わってきます。給与や報酬が100万円以下の場合は、支払金額に10.21%をかけ合わせると源泉徴収額が導き出せます。ところが、給与や報酬が100万円を上回る場合はもっと計算方法が複雑で、支払い金額から100万円を引いて、 20.42% をかけ合わせた後、最後に10万2100円を足すと源泉徴収額を出すことができます。
源泉徴収額はどうやって納税する?納税方法と期限について
納税の方法
納税を行なうためにはまず、金融機関の窓口にて納付書を手に入れる必要があります。ただし、金融機関に在庫がない場合もあるので、そのときは所轄の税務署に連絡をすれば手に入れることができます。納付書が手に入ったら、現金とともに金融機関あるいは所轄税務署の窓口に提出して完了です。また、源泉徴収の納税に手数料などは発生しません。
納税の期限
基本的には、外注を行なった業者などに給与や報酬を支払った翌月の10日までには納税をしなければなりません。ただし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は特例となり、源泉徴収が毎月から半年に1回という頻度になります。しかし、これはあくまでも給与の支払う従業員が常時10人未満の源泉徴収義務者の場合のみの特例です。また、特例対象であっても、従業員以外の外注などからの源泉徴収は、通常通り毎月の源泉徴収になるので注意が必要です。
[PR]自己資金100万円以下で独立可能
個人事業主に依頼されることも! 源泉徴収した場合の支払調書とは
支払調書というのは、報酬や料金、契約金・賞金の支払調書のことをいい、フリーランスや個人事業主に支払った報酬明細書のことを指します。支払調書は、会社員なら勤務先から1度は受け取ったことがある源泉徴収票と似たような役割を持っていて、確定申告の際に便利なので、個人事業主に対して交付する事業主が多いです。
源泉徴収との主な違いは、法的な義務があるかどうかです。源泉徴収が税務署への提出が法律で義務付けられているのに対し、支払調書は報酬支払者への発行義務はありません。支払調書というのはあくまでも、事業主側が個人事業主の確定申告の大変さを考えて、厚意として送ってくれているものです。なので、確定申告書に支払調書は必ずしも付ける必要はないということになります。
支払調書を作成するには、まず支払調書の用紙に支払金額や源泉徴収額、支払者の情報などの必要事項を記入します。記入が終わったら、翌年の1月いっぱいまでに管轄の税務署に提出をして完了です。
個人事業主へ源泉徴収が必要な場合を理解して正しく納税しよう
一部の人たちを除くとほとんどの人が、源泉徴収の制度を利用しており、日本においてもはや無くてはならない大変便利なシステムです。基本的には個人事業主に外注する場合、源泉徴収が必要となるので、個人事業主に支払いをする前に確認しておく必要があります。正しく納税するために、源泉徴収がどういう仕組みなのか、どのように計算して納税していくのかを理解しておきましょう。
[PR]家族と一緒に独立開業