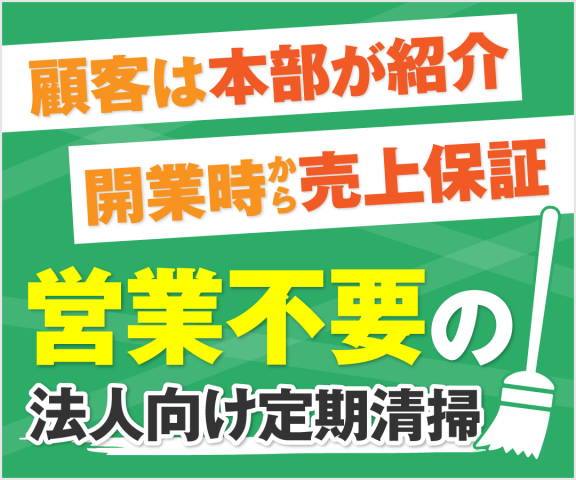働きたいという気持ちに応える「障害者就労支援」とは?開業方法や仕事内容・将来性を紹介

障害のある人の地域生活を促進する流れから、障害者就労支援のニーズが高まっています。国の障害福祉サービス関係の予算は2010年度と比べると2.5倍に増加、障害福祉サービスの市場そのものも拡大基調です。2021年3月からは障害者の法定雇用率が2.3%に上がり、障害者雇用義務の対象となる企業も増えています。 今回は、障害者就労支援サービスの特徴や開業方法、収支の試算について解説します。
働きたい人を支える障害者就労支援

近年、社会的に発達障害に関する認識や理解が深まっており、障害と向き合って生きる人が増えています。
令和2年版障害者白書(内閣府)によると、障害のある人は全国で約964万7千人と推計されており、3年前(平成29年)と比べると約100万人増えています。うち半数は知的障害・精神障害のある人です。
民間企業でも障害者雇用が進みつつあり、令和2年6月時点では約半数の企業で障害者法定雇用率をクリアしています。SDGs(Sustainable Development Goals。持続可能な開発目標)のゴールの一つである「ディーセントワーク」を推進する流れもあり、障害のある人を雇用する企業は今後増えていくでしょう。障害者雇用の流れを、障害福祉サービスという形で国は後押ししているのです。
いろいろな障害者向け支援がある
国の障害福祉サービスは、介護給付と訓練等給付の2つの体系で提供されています。施設に通って日常生活のケアを受けながら創作活動などの場の提供を受けられる生活介護(デイサービス)や、障害のある人が共同生活を営むグループホームも障害福祉サービスの一つです。
また地域社会で暮らす障害のある人の、「働きたい」という気持ちに応える支援として障害者就労支援が提供されています。障害者就労支援とは、国が進める雇用政策の一つで、障害や疾患などによって働くことが困難な人を対象に、就職し働き続けるためのサポートを行なう制度のことです。
以前までは、措置制度という制度が採用されており、障害者が利用できる福祉サービスを行政が決めていました。しかし、障害者就労支援においては、本人の意思によってさまざまな福祉サービスを利用することができます。
障害のある人が増えていることもあり、新たに障害者ビジネスに乗り出す人も増加傾向です。
[PR]社会貢献性が高いフランチャイズ
障害者総合支援法で定められた4種類のサービス
障害福祉サービスにはさまざまな種類があり、自治体から個別決定された支給量の範囲であれば本人が選んだ事業所・施設を利用できます。障害者就労支援サービスの場合は、できる限り本人の希望を尊重して支給決定を行なう方針です。ここでは障害者就労支援の、4つのサービス体系を紹介します。
就労継続支援A型(雇用型)
雇用契約を結び、「労働者」として働きながら、一般企業への就職を目指すことができる支援サービスです。
この支援を利用すると、就労継続支援A型事業所に登録している企業で実際に働きながら、仕事に必要な能力を磨きつつ、一般企業への就職を有利に進めることができるようになります。利用対象者は満18歳以上65歳未満で、障害のある人だけでなく、障害者総合支援法で指定された難病患者も利用可能です。年齢制限は原則18歳~65歳未満、利用者の平均月収は、令和元年度で78,975円(※1)です。
※1 出典:厚生労働省 障害者の就労移行支援対策の状況
就労継続支援B型
就労継続支援A型が事業所と雇用契約を結びながら働くのに対し、雇用契約を結ばず、自分のペースで働きながらスキルを磨いたり生活費を稼いだりすることができるのが、就労継続支援B型の特徴です。
自信やスキルが身に付けば、就労継続支援A型に移行したり、一般企業への就職を目指したりすることも可能です。年齢制限はありませんが、障害基礎年金1級受給者や一般企業での就業が難しい人など、比較的重い障害がある人が利用しています。利用者の平均月収は令和元年度で16,369円(※1)です。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す人に向けて、さまざまな職業訓練やトレーニングを行ってくれるサービスのことで、障害者向けの専門学校といえます。
就労継続支援A型事業所・B型事業所のように、給与が発生することはありませんが、一般企業への就職に活かせるスキルをいち早く身に付けることができるため、よりスピーディな就職を希望する人に向いていると言えるでしょう。年齢制限は原則18歳~65歳未満、利用期間は2年以内(一定の条件で最長1年まで更新可能)という期間のルールが設けられております。
就労定着支援
就労定着支援とは、就労移行支援や就労継続支援・生活介護事業所などを利用して一般企業に就職した人が利用対象です。月1回以上の面談を通じて実際に働く中での問題点や生活面での課題などの相談を受け、職場や医療機関などと連携しながらフォローしていきます。利用期間は最長3年間です。
障害者就労支援のプログラム

障害者就労支援の中身については、それらを実施する事業所によって異なる部分もありますが、例えば以下のようなプログラムが組まれており、一般企業への就職に繋がる内容となっています。
・グループワーク
・ビジネスマナー研修
・就職活動のコツ
・パソコン訓練
・社会人基礎力訓練
・企業実践
スキルを磨くのはもちろんですが、どうすれば自分をより良く表現することができるのか、そもそも自分のやりたい仕事は何かといった自身の内面に関するサポートも充実しており、より満足度の高い就職の実現を目指すことができるのです。
[PR]ニーズ拡大!テイクアウト特集
就労支援を受けるための手続きと流れ

利用者が、どのような流れで就労支援を受けるのかを説明します。
利用者や家族は、さまざまな方法で事業所の情報収集を行ないます。
・利用者が住んでいる地域の役所の障害福祉課の窓口での相談
・ハローワークや障害者就業・生活支援センターなどでの相談
・通っている医療機関などでパンフレットをもらう
・インターネットを使っての情報収集
地域の障害者相談支援事業所(相談室)や他の障害福祉サービス事業所などから、事業所の紹介を受ける場合があります。パンフレットなどを通じて、関係する機関へ定期的に事業所の情報提供を行なうのも、利用者を獲得する一つの方法です。WEBサイトを活用する場合は動画や写真を掲載すると、事業所の雰囲気が伝わりやすいです。
事業所の雰囲気はもちろん、スタッフの態度も利用者や家族に見られています。見学者が訪れた際だけ取り繕うというわけではありませんが、ていねいに対応するようにしましょう。交通の便やプログラムの内容・就職実績などもチェック対象なので、具体的に説明するようにします。
利用する事業所が決まったら、必ず契約手続きを行ないます。利用開始後にトラブルとならないよう、契約書と重要事項説明書の内容を読み合わせて、利用者・家族の理解を得るようにしましょう。障害福祉サービス利用の自己負担額に上限が設けられているので、他事業所の利用有無の確認が必須です。
障害者就労支援事業の業務内容
就労支援事業は国の障害福祉サービスとして位置づけられているため、サービスの利用料金は国で決められています。事業所独自で料金設定はできませんが、支援のプログラムや相談対応の質で差別化を図り、利用者の獲得につなげることは可能です。前述の4つのサービス体系に沿って、具体的な業務内容を紹介します。
就業移行支援
障害者向けの職業訓練所的な存在です。就職に向けて、挨拶・身だしなみなどのビジネスマナーや対人スキルの訓練を行ないます。利用者が応募する求人を開拓する場面があり、企業やハローワークの担当者と連携する場面も少なくありません。応募書類の作成や面接対策はもちろん、就職後の各種相談にも対応します。
就労継続支援A型事業所・B型事業所
就労継続支援A型事業所は障害者の割合が高い企業、就労継続支援B型事業所はA型事業所での勤務を目指す場所と考えるとわかりやすいでしょう。 いずれも、利用者に働く場所を提供して、利用者の社会生活をサポートします。カフェや軽食などの飲食サービスや物販など事業所のオリジナリティを活かした事業が展開されているのが特徴です。動画・イラストコンテンツの制作に携わる就労継続A型事業所もあります。
就労定着支援
就職後のアフターフォローを担当する事業所です。職場での働き方・コミュニケーションの課題をはじめ、自宅での生活リズムや体調管理などの相談に対応します。必要に応じて職場の上司や医療機関と話し合い、課題解決につなげます。
障害者就労継続支援事業A型・B型の違い
就労継続支援A型事業所・B型事業所の違いをまとめてみました。
| 就労継続支援A型事業所 | 就労継続支援B型事業所 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 生産活動 | 障害特性に配慮するも一般企業とほぼ同じ | 簡単なものづくり・作業(授産活動) |
| 給料(工賃) | 最低賃金以上 | 最低賃金以下の場合が多い |
| 年齢制限 | 満18歳~65歳 | なし(特別支援学校高等部の卒業が目安) |
障害者就労支援事業の収支について
就労支援事業の収支の簡単なシミュレーションも確認しておきましょう。利用料金のうち9割は国から入金されるため、料金未払いのリスクはほとんどありません。例えば、月の利用料金が14万円だった場合は、利用者から1万4千円を受け取り、残りは国(都道府県の国民健康団体連合会=国保連)から入金されます。入金サイクルが月末締め・翌々月27日払いなので、最低でも2ヶ月分の運転資金と給与原資の確保は必須です。
以下、就労継続支援A型事業所を例に、おおよその収支をシミュレーションします(助成金は考慮しない)。
・定員…10名(平均利用人数7名)
・職員…3名
・利用者の時給…900円
・営業日数…月20日
・1日の所定労働時間…7時間
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 障害福祉サービス報酬(※1) | 90万円 | 利用者の給与 | 88万円 |
| 処遇改善加算(※2) | 7万円 | 職員の人件費 | 70万円 |
| 収益事業からの収入 | 最低でも116万円 | 家賃などの諸経費 | 55万円 |
| 合計 | 213万円 | 合計 | 213万円 |
※1…就労継続支援A型サービス費(従業員配置7.5対1、定員20名以下、平均労働時間数7時間以上) ※2…処遇改善加算(Ⅰ)
障害福祉サービス報酬だけでの運営は困難で、収益事業でいかに売上を確保できるかが事業所運営の鍵となります。利用者が事業所外で就労した場合などの加算制度も複数設けられているので、条件を確認した上で加算獲得に取り組みたいものです。
障害者就労支援事業を開業するには
就労支援事業を開業するまでの流れを、簡単に説明します。合同会社などの法人でなければ障害福祉サービス事業所を開設できないので、法人設立がまだの人は自治体に開設申請する前に手続きを済ませましょう。
サービス管理責任者の候補者を探す
すべての事業所で、最低1名以上のサービス管理責任者の配置が義務づけられています。 事業所の管理者と兼務できますが、障害者の相談支援に関する実務経験(3年以上)または介護の実務経験(5年以上)が必須です。あなた自身に実務経験がない場合は、サービス管理責任者の候補者を確保しておきましょう。
事業所の候補物件が設備基準を満たすか確認する
事業所に必ず設置する部屋(作業室・相談室など)や広さなどの設備基準を満たしていなければ、自治体からの開設許可は下りません。賃貸契約あるいは建設設計前に、設備基準を必ず確認しておきましょう。
自治体の障害福祉課に開設の事前相談をする
事業所を開設したいと考えた段階で、自治体の障害福祉課に事前相談を行ないます。自治体によっては、新規開設を希望する人を対象にした説明会を開催している場合もあります。自治体によって設備基準の考え方などが異なる場合もあるため、疑問点は必ず解消しておくようにしましょう。なお、申請書類を提出後、事業所の開設許可が出るまでに2~3ヶ月かかるのが一般的です。
スタッフの募集をする
就労支援事業に携わるスタッフの募集を行ないます。職場定着の支援を担当する「職業指導員」や事業所内で利用者のケアを担当する「生活支援員」が主な職種です。無資格でも問題ありませんが障害の特性に合った対応が必須なので、介護職員初任者研修の修了者または介護福祉関係の有資格者の採用をおすすめします。介護福祉士や社会福祉士を配置すると利用料金の優遇(介護福祉サービス報酬の加算)を受けられる可能性があり、経営面でも有利です。
障害者就労支援事業は時代のニーズにマッチした事業
就労支援事業は障害のある人の社会参加・地域生活をサポートするビジネスです。SDGsの第8目標「ディーセントワーク」でも障害者雇用がうたわれており、時代のニーズにもマッチしています。特に就労継続支援A型事業所では、利用者が福祉面でのサポートを受けながら一般企業に似た形で働きます。事業所のオリジナリティを活かして、高収益を目指すことも可能です。
一方、開業に必要な手続きが多岐にわたるため、未経験者が一人で手続きを進めるのは難しい場面もあります。円滑に独立開業を目指すには、事業支援やフランチャイズの活用も選択肢の一つです。
[PR]社会貢献性が高いフランチャイズ