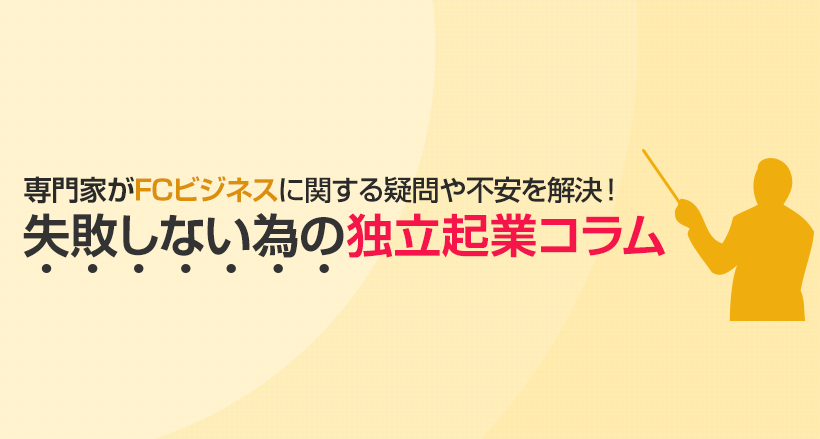|
2016-05-20 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム
合同会社FMDIフードビジネス多店舗展開研究所 代表
坂本 和彦 |
外国人スタッフを雇用するときに準備したい環境と育成事例

このコラムのポイント
人不足と言われる外食業界。シニアや女性と並んで外国人就労者の採用が重視されてきています。外国人就労者に最大限のパフォーマンスを行ってもらうため、具体的にどうアクションすべきか。外国人就労者を雇用している外食チェーンの実例とは。 外食業界の専門家である坂本和彦氏が解説します。
フランチャイズWEBリポート編集部
人不足の外食業界。外国人労働者採用の重要性と教育を意識せよ
近年、日本の外食業界で重要な戦力となっている外国人労働者。外国人労働者雇用の現状と彼らの対応(人材育成面)に関して解説していきます。
技能実習制度とは?
「技能実習制度」は外国人が日本で最長3年間働きながら技術を習得する制度のことです。建築、繊維、衣服、機械、金属、食品加工などの6業種、71職種が対象。法務省によると2014年末で16万7621人が技能実習制度を利活用しています。(詳細は厚生労働省HP参照)
スーパーのヤオコーも活用。技能実習制度で100人の外国人を受け入れ
働きながら技能を学ぶ「技能実習制度」が昨年の4月に拡充されたのを受けて積極的に外国人採用活用に動き出しているチェーン店があります。スーパーのヤオコーです。
昨年の4月から対象業種に「そうざい製造」「牛豚肉処理加工」が加わったことでスーパーのヤオコーは2016年末までに100人の外国人を受け入れるとしています。
すでに一部では働いているようですが、帰国後は母国に進出している日本企業への就職を希望している人が多いようです。
そもそも「技能実習制度」の目的とは国際貢献ですが、日本の企業にとって人材不足解消の対策にも役立っているのです。「そうざい製造」「牛豚肉処理加工」が加わったことは、ヤオコーだけでなく外食業界でも「技能実習制度」を登用するきっかけとなってきています。
国境の壁が低くなる今。働く人も国をまたいで移動している
労働力不足を解消しようとすると外国人労働者の採用が緊急の課題なのかもしれませんが、将来を見たときに就労の国際化が目の前に見えていることを意識することが店舗経営者様には必要であろうと思います。
地球規模のボーダーレス化が進んでいる中で、当然日本も国際化がどんどん進み、国境の壁が低くなっていきます。当然豊かさを求めて外国人労働者は流入してきます。また日本の企業もアジア全体がマーケットとなりどんどん進出していくことになりでしょう。
この、国際化に乗り遅れないことです。そのベースは働く人の移動です。
日本にやってきた外国人留学生の卒業後の進路希望では次のような結果が出ています。
『1番が「日本で就職を希望」65%、2番目が「日本での進学希望」45.2%である』ということです。
海外進出等の国際化を目指す外食企業であれば、社内のマインドを変える絶好の機会といえるでしょう。グローバル企業への一歩です。
しかし、実態は企業側が対応できていないケースが多いようです。
外国人留学生を採用しなかった理由として社内の受け入れ態勢が整っていないから(コミュニケーション問題等)44.9%と一番多く消極的な姿が見て取れます。
グローバル化する企業と働く人たちもグローバル化していくことは自然の流れ。日本人だけが特別ではないことをしっかりと認識することが重要です。

外国人就労者受け入れをするためにやりたいこと5つ
外国人就労者の受入れ体制として日々の業務でできることは何か、という具体策について解説します。これには『職場への溶け込み』がポイントであるとされています。厚生労働省のレポートによると下記のような対応策をあげていたのでご紹介します。
1.メンターの設置
日本での生活に馴染めないと外国人特有な悩みに気づいていないのが大きな問題であり、きめ細やかなケアの体制を作る、メンターの設置などが必要です。
2.母国との時差や慣習を個別で考慮する
外国人特有事情に合っていないということ―要するに周りの日本人との公平感、日本人前提の勤務体系休暇制度等に不安を感じられるケースがあるようです。母国との時差や慣習を考慮した個別対応が必要です。
3.日本組織の規律を直接的な表現で教える
外国人就労者は、日本人にとって当たり前の組織の規律に馴染めないことがあるようです。婉曲的な表現ではなく直接的な表現で何が良くて何が悪いか教えることが必要となります。
4.会議にも積極的に参加してもらう
日本語の問題もありチームの一員として認められない、例えば会議に参加させない等があるようです。積極的に参加してもらうことが重要になります。
5.時間を取って仕事の指示を理解させる・研修制度を用意する
日本人の暗黙の了解を汲むコミュニケーションは、外国人就労者にとって自分の仕事の役割を把握し難いようです。仕事の理由や指示が伝わらないという現象が実際に現場では起きています。少し時間を取り議論し別の言葉で確認させることが必要です。
同時に社内での外国人従業員向け研修制度等の充実も求められます。
2020年以降を見据えて。グローバルに動くかを見定めること
労働集約型産業である外食での労働力不足は深刻な状況であると言えます。人不足で繁盛店でも営業ができない状況が起きるんですから。
今後は、女性、シニア、外国人だと言われ各社アイデアを出し合っています。しかしなかなか進まない根底は国の規制が一方であります。税金関係、年金制度、外国人労働の規制と結局国の規制が円滑な経済の足を引っ張っている姿が見えます。現状に対応が付いて行っていない印象です。
企業が、外国人労働者の受け入れ体制をできていない以上に国の制度が追いついていません。日本は世界の流れから取り残されていると言い切る人もいます。
人口が減少していく中で、ビジネスはグローバル化していきます。それに伴って従業員もグローバル化していくということです。それなくしてグローバル化はあり得ません。
これから2020年以降を見据えた時、経営者の皆様は人口減少の続く日本に中だけでビジネスを展開するのか、アジアを含めてグローバルに展開するのか決断が迫られることでしょう。