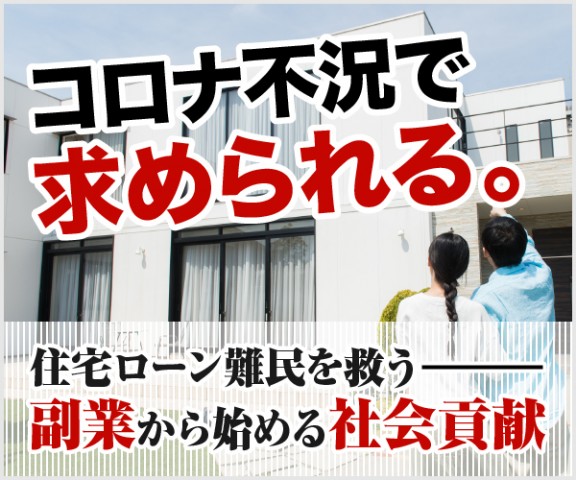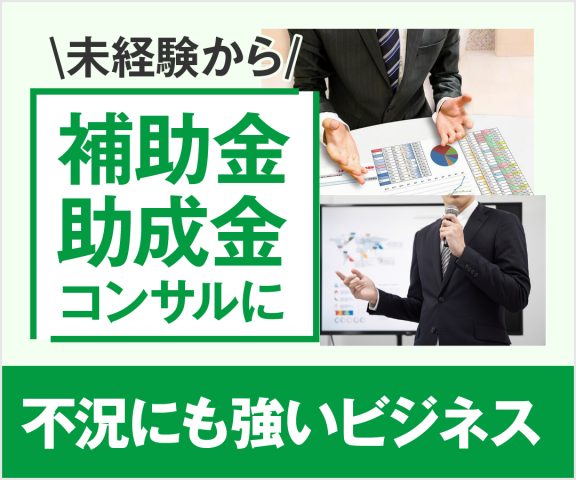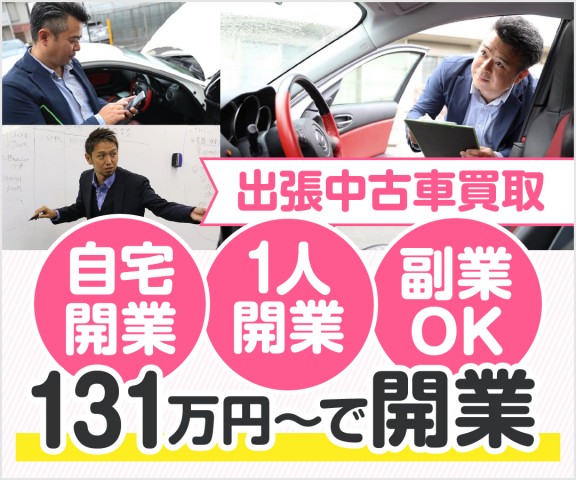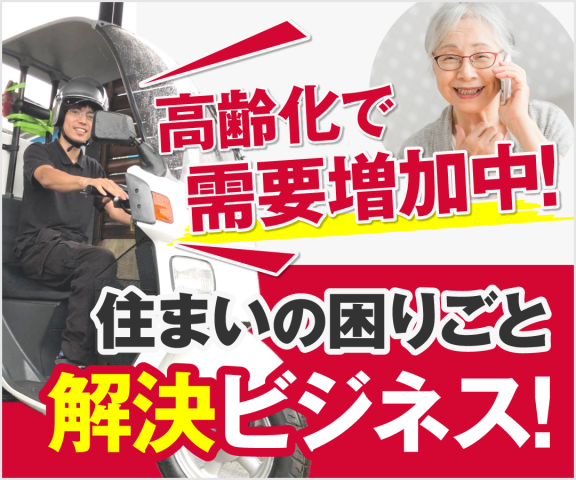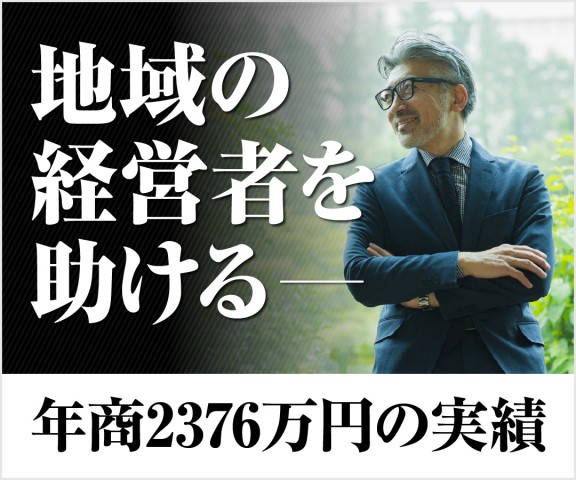外注費と給与は似て非なるもの!事業主が知っておくべき外注費のポイント

人を雇う代わりに、仕事を外注しているという事業主は多くいます。組織として重要度の低い業務を外注することにより、社内のスタッフが重要度の高い業務に集中しやすくなります。また、リソース不足を補ったり、人材採用や育成にかかる人件費の抑制につながったりすることなども外注のメリットです。しかし、「外注費」として計上したものが「給与」と指摘されるなど、税務調査でよく問題になる項目であることをご存知でしょうか?
事業の成功には、支出への知識を深めておくことも大切です。そこで、この記事では事業主が外注する際に発生する外注費と給与の違いや、計上するときの注意点について紹介します。
外注費はどんな場面で発生するのか
まず押さえておきたいのは、業務を行なううえで外注するか、雇用して依頼するかの選択がある点です。そもそも、外注費とは「業務の一部を外部の業者に委託し、代金を支払う場合に発生する費用」のことをいいます。
たとえば、清掃業者に自社オフィスの清掃を依頼したり、自社のホームページ作成を業者に依頼したりする場合です。こうしたケースでは、外注費が発生すると考えていいでしょう。外注費は、「外注工賃」や「業務委託費」とも呼ばれますが、どれも同じことを意味しています。
業務を外注にする場合、さまざまなメリットがあります。まずは消費税の節税です。税込経理を採用している場合、外注費にかかる消費税を必要経費に算入できるため、消費税を節税できます。
また、雇用契約を結ぶわけではないので社会保険料の支払いも発生しません。社員やアルバイトを雇用するよりも外注にしたほうが人件費を抑えられるのです。さらに、一般的に企業側が行なう源泉所得税の徴収がないうえに年末調整の必要もないため、経理業務の負担を軽減できます。
このようなメリットがあることから、なるべく外注費にしたいと考える事業主も多いでしょう。しかし、本来給与をとして払わなければいけないところを外注費に計上してしまうと、税務調査の際に指摘されるので気をつけましょう。
似たような業務でも外注費と給与の違いを知る
外注費と給与では、源泉所得税や消費税、社会保険の有無による違いがあります。また、請負契約を結んでいれば外注費、雇用契約を結んでいれば給与として処理するのも大きな違いです。ただし、すべての請負契約が外注費と認められるわけではなく、税務署から給与と判断されるケースもあるので気をつけましょう。
実際に、外注費と思って支払った報酬が、裁判所により給与だと判断された例は少なくありません。たとえば、ある大学の非常勤講師が講義をする場所と時間、内容を大学側に指定していたことから、一定期間の契約で毎月決まった報酬を外注費として支払われていましたが、これらの報酬は外注費ではなく給与と判断されたケースがあります。
また、建設会社が職人への報酬を外注費として支払ったものの、遅刻をした際は報酬から減額されていたこと、夜間手当や残業手当に相当する金額を支払っていたことなどの理由から、給与と判断された事例もあります。
このように、契約書の有無以外に実際の業務実態も判断材料になるので、外注費と給与の判断に迷った際は、次に紹介する判断基準を参考にしましょう。
[PR]競合が少ない
外注費と給与は似ている!? 2つを分ける判断基準
業務の専門性
外注費と給与を見分けるポイントとして、まず、「業務をほかの業者が代行できるかどうか」について考えてみましょう。このとき、代行できる業務内容である場合は外注費になります。
というのも、代行が不可能なケースでは、仕事を発注する方と受注する方の間には「雇用者」「従業員」と同様の関係性があると判断されるからです。この場合、両者の結びつきが強いため、外注費ではなく給与と考えられるのが一般的となります。
指揮監督命令
「事業者からの指揮監督命令を受けるかどうか」もポイントになってきます。もし、受ける場合は雇用契約とみなされて給与扱いとなります。
外注費として処理する場合、外注契約書や業務委託契約書などの契約が結ばれていることが前提です。そのうえで、業務の手順や流れについて指揮監督命令をしていなければ外注費として扱えます。ただし、荷物の配送時間を指定するなど、業務をするうえで不可欠の内容については指揮監督命令から除外されます。
時間的拘束
3つ目に「事業者から時間的な拘束があるかどうか」も、外注費と給与を見分ける判断材料です。外注費の場合は業務そのものに対して報酬が支払われますが、事業者によって労働時間が決められる場合は給与とみなされます。
責任の所在
そして、「責任の所在がどこにあるか」もポイントです。仮に引き渡しが完了していない商品が紛失・破損した場合にも報酬が受け取れる場合は、給与とみなされます。外注費の場合、仕上がったものに対する対価となるので、引き渡しが済まなければ基本的に報酬を請求できません。
利用する器具や材料の用意
5つ目に、「業務に関わる材料を誰が用意するか」についても考えてみましょう。会社が用意する場合は給与となり、業者が用意する場合は外注費となるため、はっきりと両者に違いがあることが分かります。
外注費と給与の違いは?支払いが外注費となる場合の影響
外注費と給与は、似ているようで実は異なった性質のものですが、特に税金面では大きく差が出てくるため、両者の違いについては理解しておく必要があります。そこで、ここでは外注費と給与の税金面での違いについて解説します。事業主としては知っておくべき重要なポイントなので、こちらもしっかりと理解しておきましょう。
社会保険料
社会保険料における外注費と給与の扱いですが、まず、この2つの違いが「雇用契約の有無」であることを頭に入れておきましょう。
その点について考えていくと、外注費は雇用契約がありません。つまり、外注費を支払ったからといって社会保険に加入する必要はないのです。社会保険料の半分は事業主が負担する仕組みになっているため、外注費とすれば経費の削減につながります。
消費税
消費税における外注費と給与の扱いについては、特に気を付けるポイントです。というのも、外注費として会計処理を行うと、外注費分を控除して消費税を収めることになるからです。もし、後から税務署が調査したときに、外注費として申請していたものが「給与である」と判断されると追徴課税されてしまう恐れがあります。実際の納税額より少なく納めていたことになるので、その分を支払う必要が出てくるのです。
源泉徴収
源泉徴収の場合も、消費税と同様に、特に気を付けたいポイントです。外注費は、特定の支払い先を除いて、基本的に源泉徴収する必要がありません。特定の支払い先とは、税理士などの専門家への支払いのことをいいます。
しかし、給与に関しては源泉徴収の必要があるため、外注費としていたものが税務調査で給与とみなされてしまうと追徴課税になるのです。場合によっては金額も高額になってしまう可能性があるので、十分注意しましょう。
[PR]副業からスタート
処理する前に知っておきたい!外注費として計上する場合の注意点
実際に外注費として計上する場合、気を付けるべきポイントがいくつかあります。最初は分かりづらいかもしれませんが、とても重要な部分なのでしっかりチェックしておきましょう。
外注費でも源泉徴収が必要な業種
外注費は、基本的に「源泉徴収する必要はない」とされていますが、中には源泉徴収が必要な業種もあります。まず、支払いを受けるのが法人か個人かによって、源泉徴収が必要な業種が異なることを覚えておきましょう。
たとえば、法人の場合には、馬主である法人に競馬の賞金を払う場合のみ源泉徴収が必要になってきます。
しかし、個人の場合にはさまざまなケースで源泉徴収が発生します。たとえば、先に挙げた弁護士や税理士などの特定の資格所有者への報酬や、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬などがそうです。
他にも、原稿料や講演料、デザイン報酬、それからプロスポーツ選手・モデル・外交員などへの報酬や、芸能人や芸能事務所を営む個人への報酬も該当します。また、ホステスやコンパニオンなどへの報酬、プロスポーツ選手の契約金、広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金なども対象です。 これら以外にも源泉徴収の対象となるケースがあるので、国税庁のホームページや所得税法で確認するようにしましょう。
なお、国税庁のホームページでは、報酬と料金の源泉徴収について詳しく知ることができます。どのような報酬や料金であれば源泉徴収が必要なのか、源泉徴収を行う際の注意事項など、法令を含めて知ることができるので、この機会に確認しておきましょう。
外注費を給与と判断されたらどうなる?納めるべき税金について
しっかりと処理をしたつもりでも、税務調査において、外注費を給与と認定されてしまうことがあるかもしれません。実際、そうしたケースは決して少なくないのです。ここでは、そうした場合に納めるべき税金について説明します。
さかのぼって納税
もし、外注費を給与と判断されてしまった場合には、さかのぼって納税をする必要が出てきます。しかし、その場合には「ただ不足していた分を払えば終わり」というわけではありません。加算税や延滞税といったものが罰則として加わるので、きちんと納めていれば本来払わなくて済んだ額を支払わなければならなくなってしまいます。また、場合によっては「支払いをした相手に返金してもらう」というとても煩雑な作業が必要になるので気をつけましょう。
外注費が給料と判断された場合の具体的な額例
もし、外注費が給与と判断されてしまった場合「いったいどれだけの金額を追加で支払わなければいけないのか」判例をご紹介します。
たとえば、月40万円の外注費が給料と判断された場合、源泉徴収税額は1年間で約100万円です。税率10%とすると、消費税額は1年間で約44万円となります。これに延滞税や過少申告加算税等を考えると、源泉徴収税額と消費税額の合計額に20〜30万円が加算される計算です。
つまり、1年間分だけでも170万円以上、3年間分で考えると500万円近く支払う必要があります。これは、決して少ない金額とはいえないでしょう。
[PR]未経験・初心者でも安心のビジネス
[PR]自宅開業OK
その他、勘違いしやすい出費「販売促進費」
外注先に報酬を支払った際は支払手数料として経費処理できる一方で、勘定科目の支払報酬の使用もできます。支払報酬を使用して経費計上することにより、経費をわかりやすくまとめられます。
また、販売業務を委託している場合は、支払った報酬を販売手数料として経費計上しているところもあるかもしれません。しかし、販売手数料は直接的な販売促進のために費やした金銭であるため、販売促進費として経費計上するのが一般的です。
外注と雇用、どっちがお得?
外注にすると年末調整や社会保険の手続きをする必要がないので手間を軽減できます。また、消費税の節税や社会保険料の削減などができるので、外注依頼のほうがお得と言えます。利益を高めるには、売り上げを大きくして経費を小さくするのが基本ですから、メリットの多い外注依頼に注目するのが自然でしょう。
しかし、まったく従業員を雇用しなくても良いわけではありません。外注に頼ってばかりいると、業務への理解度が深い従業員が育ちにくくなりますし、情報漏えいなどのリスクもつきまといます。事業が大きくなるに従い、業務内容を熟知して会社のために働いてくれる社員の存在が強みになるでしょう。
たしかに、外注依頼のほうが雇用するよりもお得ではあるものの、雇用には事業そのものやその将来に影響を及ぼす大きなメリットがあるので、2つをバランスよく考えて取り入れることをおすすめします。
[PR]既にお持ちの土地活用型
外注費は税金の取り決めが異なる!正しい申告をしよう
事業主が外注費を支払うときには、税金などの取り決めがあるので注意が必要となってきます。税金は「難しい」というイメージを持たれがちですが、事業主として必要な知識だけであれば、それほど難しいことではありません。「すべて税理士に任せているから大丈夫」といった問題でもないので、しっかり外注費と給与の違いを認識し、関連する知識を身に付け、正しい申告をするように気を付けましょう。