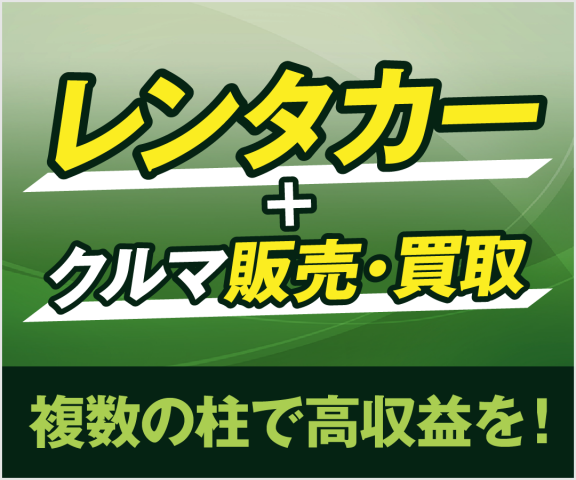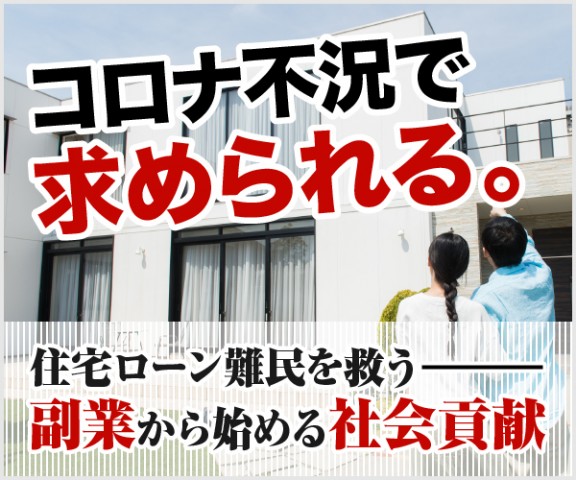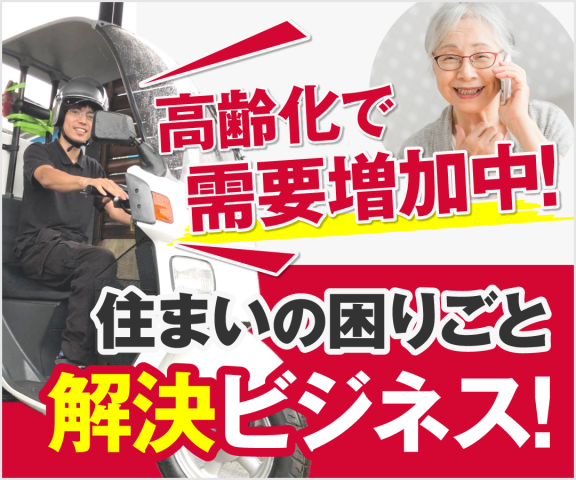業務委託とは?メリットやデメリット、派遣社員との違いを解説

正社員、派遣社員、フリーランス、パラレルワーカー、フランチャイズオーナーなど、個人の働き方の多様化がすすんでおり、フランチャイズWEBリポートでも、フランチャイズを活用した働き方をメインに、現在160以上のビジネスモデルや、独立開業者の成功事例を紹介しています。そうした多様化の一つである「業務委託」も増加傾向にある働き方です。
では、業務委託とは一体どのようなものを指すのでしょうか。ここでは、業務委託の概要やメリット・デメリット、また同じ外部リソースとして混同されがちな人材派遣との違いについて解説します。
業務委託とはどのような働き方なのか?
業務委託とは、企業に雇用されるのではなく「仕事を請け負う」という働き方です。業務内容や流れ、完了時期や報酬などを契約で決めて、その契約に基づいて業務を遂行します。業務委託は委託者と受託者の立場が対等であることが、大きな特徴です。
なお、業務委託という言葉は実務では頻繁に使われていますが、民法上は存在していません。
民法で規定されている業務に関する契約には「委任契約」「請負契約」「雇用契約」という3つの種類があります。そのうち、「委任契約」と「請負契約」の2種類を総称して業務委託と呼んでいるのです。
この2種類の契約には、それぞれ異なる特徴やメリットがあり、業務の遂行や成果に対する考え方が異なります。それでは、業務委託と呼ばれる2種類の契約について詳しくみていきましょう。
委任契約とは
委任契約とは業務上の納品物や成果物などがなく「業務そのもの」の時間や期間に対してに対価が発生するものを指します。たとえば、会社の受付業務や事務業務などがこれに当たります。
決めた期間で業務の遂行を委任されるという契約であり、委託された仕事をきちんと行えば、成果の如何を問わずに契約を果たすことにつながるのです。
請負契約とは
請負契約とは「一定の成果を上げる」のが前提となっている業務委託を指します。たとえば、システムエンジニアのように、期限を決めてプログラムを完成させるような業務などが、これに当たります。
具体的には、請け負った業務に対する納品物および成果物が、対価となるのです。請け負った内容に見合う納品物や成果物を完成させると、契約を果たしたことになります。
[PR]趣味を活かす・好きを仕事に
業務委託の3つのメリット
得意分野を活かして働く
1つ目のメリットには「自分の得意分野を活かして働ける」ことが挙げられます。自分の得意分野やスキルを生かして仕事ができるため、いきいきと楽しく働けます。
それに、業務委託では得意なことやスキルをアピールして、自ら仕事の提案を行えるのも魅力です。提案時に報酬額を提示するのも可能なため、能力ややる気次第では、高収入を狙うこともできます。
比較的自由な働き方ができる
契約の内容によっては「在宅でも仕事が可能」なのもメリットです。業務委託は企業に雇用されない働き方なので、一般的な社員とは業務の進め方が異なります。
基本的には、契約に沿って業務さえ遂行すれば問題がなく、それ以外には縛りがありません。したがって、契約の内容によっては、勤務地にとらわれず、自宅などの好きな場所で業務を行えるのです。
また、勤務時間の縛りもないため、ライフスタイルに合わせてスケジュールを調整しやすいというメリットもあります。
社内の対人関係といったストレスがなくなる
それに加えて「対人関係によるストレスなどがない」のも大きな魅力です。仕事をする際に、上司や同僚など社内の対人関係にの悩みを抱えている人は少なくありません。
その点、業務委託であれば、基本的に取引相手との関係が中心になるため、対人関係のストレスが溜まりにくいのです。対人関係のわずらわしさから解放され、そのぶん仕事に集中しやすくなるのがメリットでしょう。
業務委託の3つのデメリット
労働者ではないため労働基準法に守られない
デメリットには「労働基準法などの適用外になる」ことが挙げられます。
業務委託は会社に雇用されない、いわば事業主となります。労働者を保護する労働基準法などの適用がなく、労働者として守られるものがないのです。そのため、万が一の事態には自分の身は自分で守るという意識を持つ必要があります。
確定申告を自分でしなければいけない
それから「確定申告などを自分で行うことになる」のもデメリットの1つです。基本的な事業主となるため、税金の申告なども自ら行う必要が生じます。
仕事が安定しない
また「仕事が必ずあるとは言い切れない」のもデメリットです。業務委託は、必ず継続的に仕事を受注できるという保証はありません。
継続的に仕事をして安定した収入を得るためには、スキルを磨いたり、自ら仕事を提案したりするなどの努力が必要になるでしょう。
業務委託と派遣社員との違いはなに?
派遣は、派遣会社に雇用される形で登録して、そこから企業などに出向き、業務を行うという働き方です。相手企業との契約は派遣会社が締結しているため、給与なども派遣会社から支給されることになります。
一般的に、派遣会社との雇用関係が成立するのは、派遣先が決まってからです。派遣期間が終了すると、雇用契約も終了となります。なお、雇用主は派遣会社であり、実際に仕事の指示を受けるのは、派遣先である企業です。
業務委託との大きな違いは、「派遣会社が介入している」ことです。派遣は業務を請け負う企業と直接契約をするのではなく、間に派遣会社が入っているため、この点が業務委託の事業主と異なります。
1.業務委託は突発的な異動や出張がない
| 業務委託 | 派遣社員 | 正社員 |
|---|---|---|
| ○(基本的に異動・出張なし) | ○(基本的に異動・出張なし) | ×(あり) |
「会社の事情に振り回されにくい」という点です。業務委託も派遣も契約内容がきちんと定められています。したがって、基本的には会社の事情によって業務内容が大きく変わったり、異動・出張を命じられたりする心配がありません。(ただし契約内容による)
2.業務委託はプライベートな時間の確保できる
| 業務委託 | 派遣社員 | 正社員 |
|---|---|---|
| ○(基本的に残業なし) | ○(基本的に残業なし) | ×(残業あり) |
「自分の時間を確保しやすい」ということです。請負契約であれば成果物の提出なので時間は自分で調整することができます。また、委託業務や派遣であれば勤務時間が決まっているため、無理な残業を頼まれるケースは少ないのです。
企業の事情で自分の時間をつぶされる心配がないため、プライベートを大事にしたいという人にも向いています。
3.業務委託はトラブルを自分で解決しなければいけない
| 業務委託 | 派遣社員 | 正社員 |
|---|---|---|
| ×(基本的には自分で解決) | ○(派遣会社) | ○(労働局) |
「仕事上のトラブルや不満を相談がいるか」ということです。派遣社員であれば、派遣先で何か仕事上のトラブルや不満があったときにも、派遣会社が相談に乗ってくれるので、安心して働くことができます。
しかし、業務委託である場合は、基本的に自分一人で解決することが多いでしょう。
4.業務委託は自分で仕事を取らなければ仕事がない
| 業務委託 | 派遣社員 | 正社員 |
|---|---|---|
| ×(仕事がなくなる可能性がある) | ×(派遣先が紹介されない可能性がある) | ○(会社に行けば基本的にある) |
「仕事が必ずあるとは限らない」という点です。業務委託の場合、自分で仕事を探さなければ、突然なんの仕事もない、という状況になることもあります。
また、派遣は必ずしも希望したときに、すぐ仕事を紹介してもらえるとは限りません。業務委託であっても、自分で仕事を取ってこれなければ、仕事がないということもあるでしょう。
契約期間が終わってすぐに紹介してもらえる仕事がない場合、ブランク期間が生まれることもあるため、注意が必要です。
5.業務委託は努力次第で収入を増やせる
| 業務委託 | 派遣社員 | 正社員 |
|---|---|---|
| ○(仕事の質と量をいかに上げるか) | △(契約内容によっては掛け持ち可) | ×(副業解禁によって変わっている) |
「収入の増減」です。業務委託の場合は、複数の会社から業務を請け負って数を増やしたり、誰にもできない仕事といった質をあげたりすれば、その分収入を増やすことも可能です。
派遣は仕事内容・スキル・経験などにより、給与が決定するケースが多く見られます。自分で給与を自由に決められるというわけではあるません。
6.業務委託は福利厚生がない
| 業務委託 | 派遣社員 | 正社員 |
|---|---|---|
| ×(契約によるが基本的にない) | △(派遣会社によって変動) | ○(あり) |
「退職金など備えになるようなものがない」ことです。業務委託の場合、給与所得ではないので退職金やボーナス、福利厚生はありません。
また、派遣の場合は退職金やボーナスなどの有無や、福利厚生については派遣会社によってそれぞれ異なります。しかし、退職金やボーナスの支給制度がある派遣会社は、少ないのが現状です。そのため、退職金やボーナスなどの備えになるようなものは、もらえる可能性が低いのがデメリットです。
業務委託契約書の種類と記載される項目
ここでは、業務委託契約書の種類と、その中に記載される主な項目について紹介します。なお、細かい契約内容は会社によって異なるため、ここで紹介するのはあくまでも一例です。
業務委託契約書の3つの種類
まず、業務委託契約書は報酬の支払い方法によって種類が分かれており、「毎月定額型」「成果報酬型」「単発業務型」の3つがあります。
決まった額の報酬が毎月支払われることを定めるもので、コンサルティング業務や保守業務などで用いられる場合が多いです。
業務の成果に応じて報酬が変動することが定められており、店舗運営業務や営業代行業務などで使用されます。
原則的に一度限りの業務を委託する際に用いられる契約書です。デザイン業務や建設設計管理業務、開発業務などにおいて使用されることが多いでしょう。
収入印紙のコストや手間を削減するために、これらの契約書を電子化する企業も増えてきています。電子契約書を利用すれば、従来の方法よりもスピーディーに契約を締結することができます。また、請負契約の場合は紙の契約書を使うと最大で60万円の印紙税がかかりますが、電子契約書であればそのコストをカットすることができるのです。
契約書に記載する項目
契約書の内容としては、業務内容や成果物、報酬、損害賠償などの項目について記載するのが主流となっています。
業務内容の項目では業務の具体的な内容や工程が明記され、専門的な業務や特殊な業務の場合は追加資料が添えられることもあります。報酬の項目に記載されるのは、報酬の金額や内訳、支払い時期、支払い方法といった内容です。
損害賠償については、委託者あるいは受託者が契約に違反した場合などを想定して記載されます。損害賠償に関する取り決めがない場合、委託者が契約解除した際に損害賠償が生じる可能性があります。
委託者と受託者の間でトラブルが起きないように、記載項目については事前にしっかりと確認しておくことが大切です。例えば、業務遂行の成果物がどの時点で誰に帰属するのかということを確認しておかないと、所有権などを巡るトラブルに発展する可能性があります。「受託者は無体性の成果物の情報を利用できるか否か」といった内容を細かく確かめておきましょう。
[PR]趣味を活かす・好きを仕事に
業務委託契約の注意点
委任契約の場合、受託者が負うべき責任の範囲は「善管注意義務」にとどまります。「善管注意義務」とは、一般的に注意を払うべき常識的な義務のことです。
一方、請負契約の場合は受託者が「瑕疵担保責任」を負うことになります。「瑕疵担保責任」があると、受託者の仕事に欠陥やミスがあったときに瑕疵修補や損害賠償を求められる可能性があります。
また、委任契約では仕事をすれば成果物の有無にかかわらず報酬請求権が発生します。しかし、請負契約の場合は成果物が完成しなければ報酬請求権が発生しないという相違点もあります。このように、契約形態によっては成果物に対して重大な責任が生じる場合もあるため、契約内容はしっかりと確認しておきましょう。
その他に、業務委託契約を交わす際は「偽装請負」にも注意が必要です。「偽装請負」とは、契約上は業務委託でありながら実態が労働者派遣に該当する場合のことで、委託者と受託者の双方がペナルティの対象となります。
独立後の選択肢としての業務委託
業務委託は企業に雇用されない仕事を「請け負う」ものであり、派遣は派遣会社に雇用される形で「企業に出向いて業務を行う」ものという違いがあります。それぞれの働き方によって、メリット・デメリットが異なるため、きちんとポイントを理解しておくのが重要です。
業務委託のメリットには、得意分野を生かして仕事にできることや、契約によっては在宅でも仕事が可能なことなどが挙げられます。一方、デメリットは基本的には労働基準法などの適用がされないことや、仕事が必ずあるとは言い切れないことなどです。
独立の選択肢の一つとして業務委託で仕事を請け負うというのもよいでしょう。
フランチャイズWEBリポートでは、未経験でも店舗運営や販売のノウハウなどを提供をしてくれるフランチャイズビジネスを紹介。それだけでなく、業務委託の募集も紹介しています。
なかでも、「スーパーホテル」のスーパードリームプロジェクトは、ホテルの支配人・副支配人の業務を請け負うことで、スーパーホテルの経営ノウハウを学びつつ、4年間2人で4560万円の報酬が手に入るため、独立開業の資金を貯めながら経営を学べます。
独立に興味がある人は、業務委託、フランチャイズのどちらも視野に入れてみてはいかがでしょうか。
[PR]1人で独立開業できる仕事