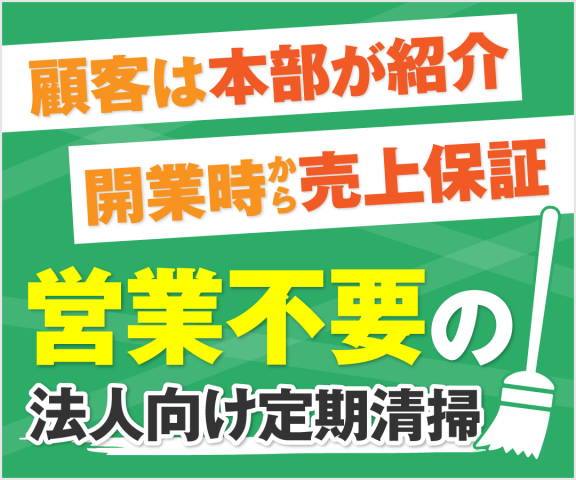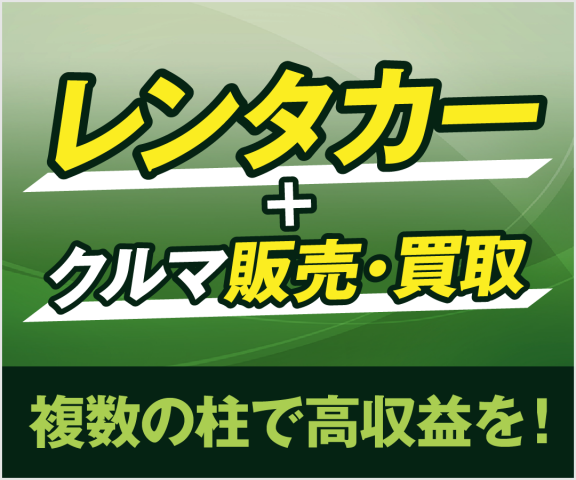年収と所得は何が違う?自分の年収や所得を把握する時のポイントを紹介

これまで会社員として働いてきた人のなかには、「年収」「所得」「手取り」などの給与にまつわる用語を、なんとなく理解している人も少なくないでしょう。
しかし、独立開業した場合、自分の年収や所得が税金の計算にも関わってくるので、それぞれの意味の違いをしっかり理解しておく必要があります。そこで今回は、年収と所得の違いや所得税の計算の仕方など、知っておきたいポイントを解説します。
年収・所得・手取りの違いとは?
ここでは、まず、混同されやすい「年収」「所得」「手取り」の3つの用語の意味をそれぞれ解説します。サラリーマンと個人事業主で意味合いが変わってくるものもあるので、しっかり理解しておきましょう。
年収
まず、年収」というのは、1年間の収入の合計のことです。「会社員の場合、給与明細には「総支給額」と「差引支給額」の2つの金額が記載されているため、そもそも収入とはどちらの合計を指しているのかと疑問に思う人もいるでしょう。答えは、税金や社会保険料などが引かれる前の総支給額のほうです。毎月の総支給額に加えて、ボーナスの総支給額を合計した金額がその人の「年収」ということになります。具体的な金額は、年末に配られる源泉徴収票の「支払金額」の項目に記載されているため、手元にある場合は確認してみるといいでしょう。
一方で、個人事業主の場合はその事業だけで入ってきたお金を、年収ではなく「年商」といいます。年収と年商は特に混同されがちですが、2つの言葉には明確な違いがあるのでしっかり覚えておきましょう。まず、年収というのは、年間の「給与や利益」を指す言葉で、事業の売上以外にも家賃収入や利息などがあれば、これらも年収に含まれます。これに対して、年商が示すのは個人事業主や会社の年間の「売上」です。
所得
「所得」というのは、年収や年商から経費を引いた金額のことを指します。ちなみに、1年に1度支払う住民税や所得税は、この所得金額をもとに計算されています。サラリーマンの場合は、年収から「給与所得控除」を引いた額が所得です。
一方で、個人事業主の場合は年間の売上から経費を差し引いた金額が所得として計上されます。両者の異なる点は、個人事業主の場合は、経費の金額によって所得金額も大きく変動するということです。
たとえば、ある個人事業主の年商が1000万円だとしましょう。ただし、この数字はあくまでも売上金額であるため、利益を計算するためにはここから仕入れなどの経費をマイナスする必要があります。1年間の経費の合計が500万円だとすれば、所得は500万円という計算になるでしょう。
手取り
「手取り」というのは、年間の売上または収入から、税金や社会保険料などを差し引いた金額のことを指します。サラリーマンの場合であれば、給与明細にある「差引支給額」がこれにあたります。つまり、実際に銀行に振り込まれる、もしくは手渡しされる金額が手取りということです。ちなみに、ここで差し引かれる税金の金額や社会保険料は、年間の所得金額に応じて変動する仕組みになっています。
これに対して、個人事業主は源泉徴収はされないので、確定申告の際に税金や保険料を納める必要があります。1月から12月分の確定申告は翌年に行なわれるため、手元に残ったお金から税金として納める分を残しておかなければいけません。
[PR]赤字補填・収入保障・黒字保証があるフランチャイズ
個人事業主と会社員の年収の意味合いは?
会社員の場合、年収から引かれる経費は必要経費である「給与所得控除」です。給与所得控除は実際の経費に関わらず、1年間の収入額に応じて一定の金額が引かれることになっています。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 180万円以下 | 収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円) |
| 180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
| 1000万円超 | 220万円(上限) |
これに対して、個人事業主の場合の経費は、実際に事業を行う際にかかった費用のことを指すため、年商からその経費が引かれることになります。
独立開業したら年収や所得の金額はどんなシーンで必要になる?
ここでは、独立開業したら年収や所得の金額はどのような場面で必要になるかを紹介します。
賃貸契約などの審査の時
賃貸契約やローンなどの審査時は、年収が1つの審査基準となります。個人事業主は会社員よりも信用が低くなることが多いので、開業後にローンなどを組む予定がある人は、自分の年収を把握しておく必要があるでしょう。
確定申告をする時
個人事業主として開業した場合、1年に1度自分で確定申告を行う必要があります。この確定申告の際には、年間の所得金額を計算し、所得に対して税金を支払わなければいけません。ちなみに、確定申告の時期は例年2月16日~3月15日(土日祝と重なる場合は変更あり)です。確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、基本的には白色申告ですが、希望者のみ、さらに特別控除が受けられる青色申告ができるようになっています。
年収や所得から所得税や住民税はどう計算するの?
所得税
「所得税」は、1年間の所得に応じて、国に対して支払い義務が発生する税金です。納付時期は、基本的には毎年3月15日までですが、銀行振替の場合は4月中頃の振替になります。
(年間の売上-経費-各種控除(社会保険料など))×税率-課税控除額
ちなみに、この計算式の税率は5%~45%と決められていて、どの税率が適用されるかは1年間の所得金額によって異なります。
所得金額が高くなればなるほど、適用税率も上がっていき、「課税控除額」も税率同様、所得金額に応じて増えていきます。具体的な税率・課税控除額は国税庁のホームページに記載されているため、確認してみるといいでしょう。
なお、確定申告の手段として青色申告を希望した場合は、青色申告特別控除も適用されるようになっています。
住民税
住民税」というのは、「都道府県民税」と「市町村民税」を合わせたもののことを指します。「つまり、一言で住民税といっても、その税金の行き先は居住している都道府県と市町村の2カ所に分かれているのです。個人事業主の場合、所得税は確定申告時に自分で計算することになりますが、住民税はその確定申告をもとに自治体によって計算されるという違いがあります。
ちなみに、住民税の計算方法は「均等割」と「所得割」です。均等割は、所得金額に関係なく均等な金額で課税されるのに対して、所得割は所得金額に応じて収める金額が決定するという特徴があります。
(所得金額-所得控除)×税率-税額控除額
税率は原則として10%ですが、均等割も所得割も、地域によっては独自の税率や税額が採用されている場合があるため、事前に確認しておく必要があるでしょう。住民税は所得税が決まってから計算されるため、毎年6月ごろに通知が届きます。
[PR]趣味を活かす・好きを仕事に
個人事業主が年収や所得を把握するときの3つのポイント
口座は個人用とプライベート用で分ける
1つ目のポイントは、「口座を個人用とプライベート用で2つに分ける」ということです。最初のうちは、一緒にしていてもそれぞれの内訳を覚えていれば問題ないと思うかもしれません。しかし、後から見直したときのことを考えれば、事業用の口座とプライベート用の口座が混同していることで、どちらの支出だったのか把握しづらくなるというデメリットがあります。最初から事業専用口座を用意しておけば、確定申告の際も年間の所得の計算がしやすいでしょう。
確定申告書類は必ず保管しておく
2つ目のポイントは、「確定申告書類は必ず保管しておく」という点です。確定申告書は税務署に提出するもの以外に、控え分も必ず用意しておく必要があります。なぜなら、控えがあれば、必要なときにすぐに所得を把握することができるからです。
また、確定申告書の控えは、ローン契約などの審査時に所得の証明として必要になるケースも多いため、大切に保管しておきましょう。なお、控えの書類を有効なものにするためには、確定申告書提出時に、窓口で受付印をもらっておく必要があるので注意が必要です。
年途中で開業した場合は源泉徴収票を用意しておく
3つ目のポイントは、「年の途中で開業した場合は源泉徴収票を用意しておく」という点です。たとえば、年の途中で会社を退職して開業する場合、会社員の給与と個人事業主としての売上を合算して年収や所得を計算する必要があります。その際、サラリーマンのときの給与は源泉徴収票で把握することができるので、退職時には必ず会社から受け取っておきましょう。
年収や所得の金額は正確に把握しておこう!
年収や所得の意味の違いを知ることは、自身の収入を正確に把握するために欠かせないことです。特に、これから独立開業して個人事業主になる場合には、最低限の知識として押さえておきましょう。年収や所得の金額は、1年に1度の確定申告をはじめとして、ローンなどの審査時にも必要になることがあります。いざというときのために、自分の年収や所得を把握しておくことが重要です。
[PR]高収益・高利益が狙えるビジネス