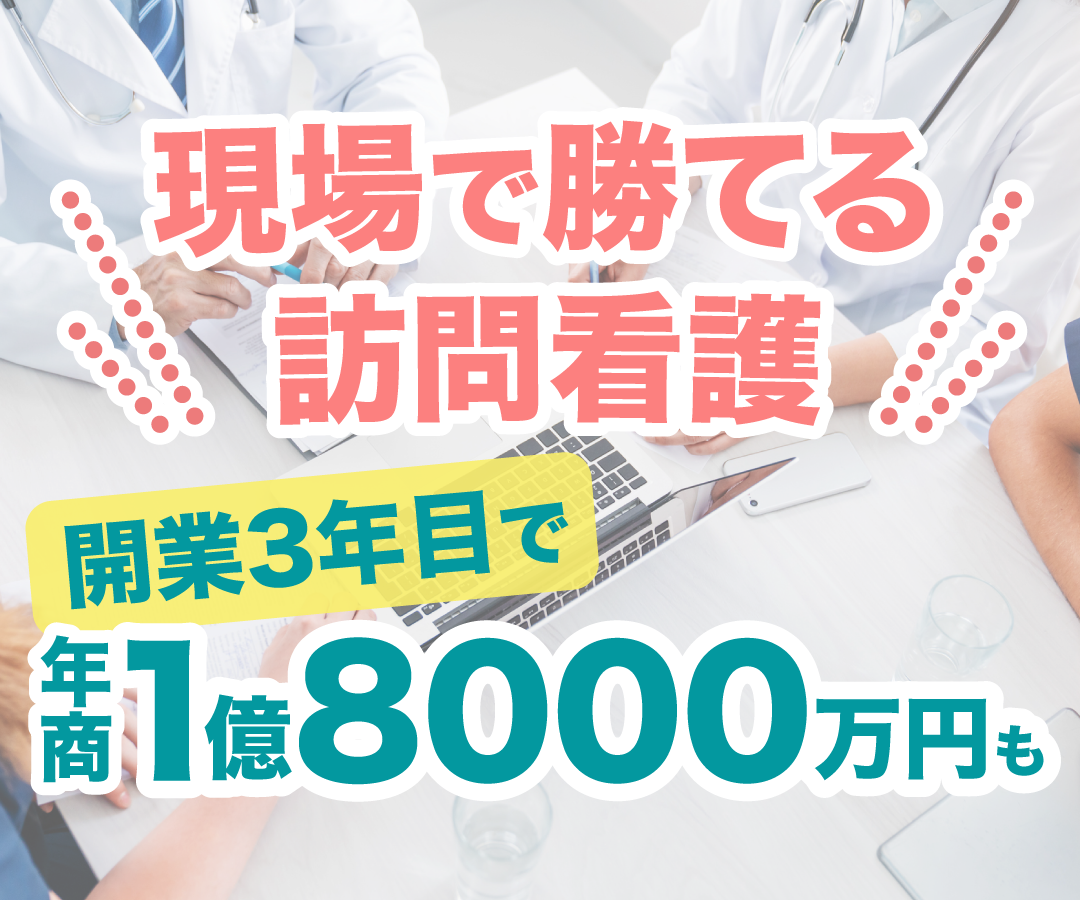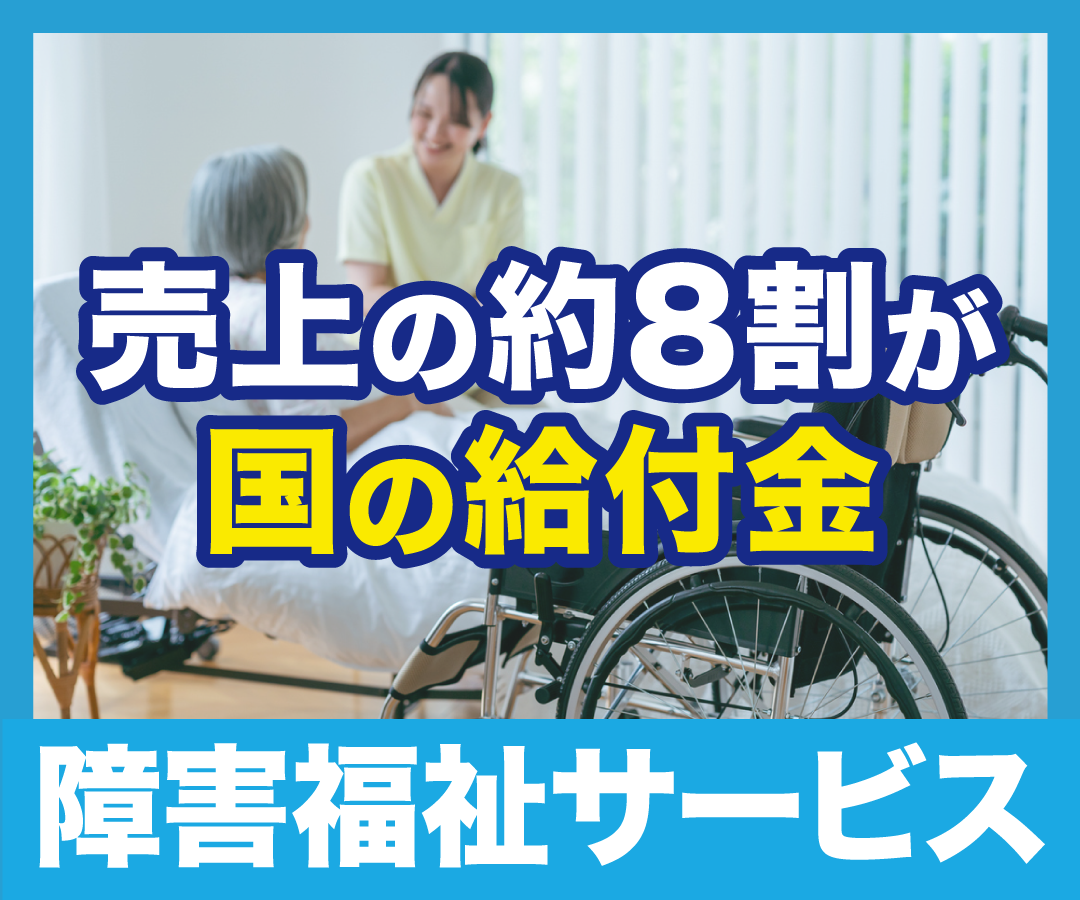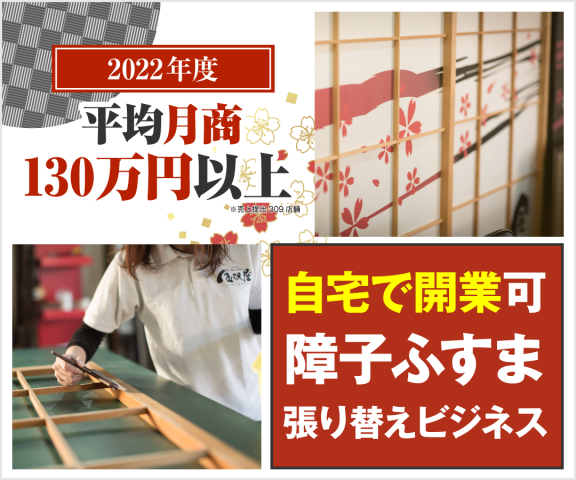個人事業主と法人の違いとは?社会的な信頼性と個人事業主ならではのメリットを比較

「個人事業主と法人、どちらの事業形態を選べば有利か?」と開業時に迷う人は多いのではないでしょうか。 個人事業主と法人の大きな違いは、税金のかかり方や対外的な信用力です。そのため、自分自身の事業に合っていない形態を選んでしまうと、後悔することになりかねません。 今回は、個人事業主と法人それぞれの基礎知識やメリット・デメリット、事業形態を選ぶときのチェックポイントについて解説します。
個人事業主と法人の違い
個人事業主とは、継続する意思を持って営利を目的とした経済活動を行なう人で、「自営業」「フリーランス」と呼ばれることもあります。登記手続きは不要なので、商材と開業する意思があればその場で開業できるのが特徴です。決算期は毎年12月31日で、3月15日までに所得税の申告(確定申告)を行ないます。
一方、法人とは、法律によって組織や団体に人格が付与され、人間と同様に権利・義務の主体として認められる存在です。株式会社や合同会社といった営利法人と、NPO法人などの非営利法人に区分されています。法人の代表者による登記手続きが必須で、本社(本店)を管轄する法務局に登記申請書を提出した日が開業日です。決算月は自由に決められ、決算月の末日(決算日)から2ヶ月以内に法人税の申告を行ないます。
個人事業主の基礎知識
個人事業主とフリーランスともに、税務署に開業届を出せば税法上の事業者として取り扱われますが、事業の進め方は別です。
個人事業主とフリーランスは別もの?
個人事業主とフリーランスの大きな違いは、1つの業務が継続する可能性と税務署への開業届提出の有無です。
個人事業主は、法人を設立せずに個人の責任のもとで商品やサービスの提供を繰り返し、かつ継続的に行なう人のことです。特定の顧客と契約を締結して業務を進める場合と、店舗での販売のように不特定多数の顧客を受け入れる場合があります。商品・サービス内容によって変わる可能性はあるものの、継続的な収入が見込まれるため開業届を提出するのが一般的です。
一方、フリーランスは個別の案件ごとに契約を結んで業務を遂行する人のことをいいます。プログラマーやフォトグラファーなど、専門的な技術やスキルを提供する場面が多いのが特徴です。一時期、フリーランスの麻酔科医が話題となったこともありました。技術・スキルの提供そのものは継続的ですが、案件としては単発的なものです。そのため、開業届を提出していないフリーランスも少なくありません。
なお、個人事業主・フリーランスともに、経済活動で得た収入について確定申告を行ない、所得額に応じた所得税を納税する義務があります。
開業届を出すメリット
個人事業主・フリーランスとも、税務署に開業届を出すと3つのメリットがもたらされます。節税効果を高めるために「青色申告承認申請書」との同時提出がおすすめです。
(1)屋号で銀行口座を開設できる
開業届の控があれば、屋号付きの銀行口座を開設できます。銀行によっては、屋号のみの銀行口座の開設も可能です。個人と事業の収支を明確化できる上、取引先からの信頼性が高まるでしょう。
(2)節税効果を高められる
複式簿記により記帳していれば、最高55万円の青色申告特別控除を受けられ、所得税額を節減できます。e-Taxで確定申告を行なえば、控除額が最高65万円に拡大します。会計ソフトを使って記帳すると集計や帳簿作成がスムーズです。
(3)赤字は最長3年間繰り越せる
仮に業績が赤字になった場合でも、最長3年間赤字額を繰り越せます。黒字となった年に赤字分の所得を差し引けるので、節税にも効果的です。
個人事業主のメリット・デメリットは?
個人事業主のメリットとデメリットを紹介します。メリットだけでなくデメリットも押さえておけば、個人事業主を選んだとしても後悔を防げるでしょう。
個人事業主のメリット
まずは、個人事業主ならではの3つのメリットを紹介します。
手続きが簡単
税務署に開業届を提出するだけで、個人事業主として開業できます。マイナンバーカードなど個人番号がわかるものと本人確認書類(運転免許証など)の持参は必須ですが、その他の添付書類は必要ありません。税務署に行けば1時間程度で手続きは終了しますが、郵送で提出しても大丈夫です。手続きをするための費用も無料で、気軽に事業をスタートできます。
自分で確定申告ができる
個人事業主として事業を開始すると1年に1度、毎年3月15日までに確定申告を行わなければなりません。確定申告の書類を税務署に提出して、所得税や住民税を確定するため、1年間の収支を計算する必要があります。そう聞くと、税理士を雇わなければならないと思うかもしれませんが、会計ソフトを使えば自力で確定申告を行なえます。ただし、最低限の複式簿記の知識を学び、帳簿付けを忘れないようにしましょう。なお、確定申告の書類は電子申告(e-Tax)での提出も可能です。
あとから法人にできる
個人事業主として事業をスタートしたからといって、その後も継続して個人事業主として事業を営まなければならないということはありません事業が軌道に乗ってきたら、法人化にすること(法人成り)も可能です。ただし、法人成りするには、資金が必要になるうえ、法人登記や開業届・青色申告承認申請書の再提出などの手続きを行う必要があります。
税金の負担が小さい
事業を開始したばかりで利益が少ない段階では、個人事業主の税金は法人よりも安くなります。課税所得が600万円の場合における、所得税と法人税の税額を比較してみましょう。なお、課税所得が600万円となる人は、年収約1,000万円の給与所得者が目安となります。
| 所得税 | 法人税 | |
|---|---|---|
| 税率 | 20% | 15%※ |
| 控除額 | 427,500円 | なし |
| 税額 | 772,500円 | 900,000円 |
※資本金1億円以内の法人の場合の税率。課税所得が800万円を超えた部分の税率は23.20%。
住民税の均等割は課税所得がゼロ、すなわち赤字であっても課せられます。金額は個人世帯で年5,000円、法人だと年70,000円です。
したがって、開業初年度から年商1,000万円を超える見込みがなければ、個人事業主の選択が税金の負担面で考えると有利かもしれません。具体的なシミュレーションについては、税理士への相談をおすすめします。
個人事業主のデメリット
次に、個人事業主のデメリットを2つ紹介します。
社会的信用度が低い
個人事業主は法人と比べて社会的信用度が低いため、事業展開に支障をきたす恐れがあるのがデメリットです。
法人の場合は、登記事項証明書を取り寄せれば法人の存在や事業目的を客観的資料で確認できます。一方、個人事業主の場合は事業目的の確認が自己申告にとどまり、事業主としての活動実態の確認が難しいのが実情です。
そのため、法人企業との取引や銀行融資を受ける場面を中心に、個人事業主が不利になることが多いといわれています。
利益が多いと税金の負担が大きい
利益が少ない段階では税金の負担が少ない反面、利益が多くなると税金の負担が大きくなります。所得税は5%~45%の7段階の税率が定められており、課税所得が増えるほど高い税率が適用されるからです。
一方、資本金1億円以内の法人などの法人税の場合は、課税所得800万円以下の部分は15%、800万円を超える部分は23.20%で税率が一定です。税率だけをみても、課税所得が900万円を超えると法人のほうが軽い税負担となるでしょう。
[PR]地方移住・田舎暮らしができる
法人の基礎知識

法人を設立する前に、法人格ごとの特徴を確認しておきましょう。
設立には資本金が必要
株式会社や合同会社を設立するためには、資本金が必要です。
資本金とは会社の純資産にあたるお金で、会社が確保している現金の最低額という意味合いもあります。かつては、会社の債権者保護を目的としたお金でした。資本金が1円でも会社を設立できますが、資本金の額が対外的な信用度を示すバロメーターとして機能する場面があるため、事業の規模に合わせた額を用意しているのが実情です。
法人には種類がある
法人格とは、法律の手続きに基づいて与えられた人格のことです。法人の名前で権利の行使や義務の履行が認められる存在で、営利法人と非営利法人の2つに分けられます。
営利法人は、ビジネスで得た利益を株主や出資者などの構成員に分配する目的で運営される法人です。役員や従業員に対する株式報酬型ストックオプションの付与も、利益分配の一つの方法です。
一方、非営利法人は団体の活動で得た収益を構成員に分配せずに、社会福祉や教育振興など法人の事業目的を達成するための費用に充当します。なお、給与や賞与の支給は利益分配に該当しません。
株式会社
株式会社とは、株式を発行して調達した資金を使って事業を展開する法人組織で、株主が選任した取締役が経営上の意思決定を行ないます。
債権者に対する責任の範囲は出資した金額が上限ですが、代表取締役は個人として債務の連帯保証を求められるケースが多いです。設立には2週間ほどかかり、25万円前後の費用がかかります。
かつては設立するために1,000万円以上の資本金が必要だった経緯もあり、営利法人の代表格として社会的信頼性が高いとされています。
合同会社
合同会社とは、出資者がお金を出しあって事業を展開する法人組織です。出資者と経営者が同一人物で、出資額にかかわらず経営に関する意思決定権を等しく持つことから、意思決定が速い組織だといわれています。
株式会社と同様に、債権者への責任は出資額に限定されます。一方、利益配分は出資額にかかわらず自由に決定可能です。
設立費用は6万円前後と安く、3日~7日ほどで設立できるため、個人事業主が法人化する際に選択されるケースが増えています。西友やアマゾンなどの大手企業が合同会社として運営されている実態もあり、知名度も上昇傾向です。
合資会社
会社の債務に直接責任を負う無限責任社員と、出資額を限度に責任を負う有限責任社員が各1名以上で構成される会社です。無限責任社員には現金による出資の他、信用力や労務の提供を金銭換算した形での出資も認められています。
合名会社
無限責任社員のみで構成される会社で、複数の個人事業主による共同事業の展開が想定されています。合同会社制度の普及もあり、2019年の新規設立数は48件(法務省「登記統計」)と減少傾向です。
非営利法人
営業活動は行なうものの、構成員への利益分配は法律で禁止されている法人です。ただし、職員へのボーナス支給は利益分配に含まれません。
社会貢献活動を行なうNPO法人をはじめ、各種団体が法人化した一般社団法人、集めた財産に法人格を付与する一般財団法人などの形態があります。
設立に必要な人数や資産に条件が設定されていたり、一般社団法人を除いて展開できる事業が限定されていたりするのが特徴です。
法人のメリット・デメリットは?
法人のメリットとデメリットを紹介しましょう。メリットと共にデメリットも知っておけば、「こんなはずじゃなかった」などと悔やむことがなくなります。
法人のメリット
まずは法人のメリットを4つ紹介します。
社会的信頼性が高い
法人の場合、個人事業主よりも社会的な信用力が高いと言えます。事業を大きく展開するためには、資金が必要なることもありますが、その際に法人のほうが金融機関などの審査に通る確率が高く、資金も調達しやすいでしょう。
また、求人募集をした場合も法人には、多くの応募者が集まります。事業を拡大していきたいと考えるのであれば、法人のほうがよいがしれません。
個人より節税しやすい
節税を考えているのであれば、法人をおすすめします。個人事業主の場合は累進税率で課税されるため、所得が増えるにつれて税率が高くなり、高収入の場合は最大で45%の税率になり、収入の半分近くを税金として支払わなければなりません。一方、法人の場合は原則一定税率で課税されます。たとえば、所得金額が800万以下の場合は15%、最大でも約24%で済みます。一定以上の売上が見込める場合は法人にしたほうが節税ができるでしょう。
加えて、事業主(役員)の自宅を社宅扱いにすると、家賃の一部を法人の経費として計上できます。社宅を使用する役員が家賃の一部を支払うことが、経費化の条件です。
役員名義の住宅を法人が買い取り、役員から家賃収入を得る方式に切り替えると、固定資産税など住宅の諸経費だけでなく減価償却費も経費として計上でき、節税効果が大きくなります。
決算月を自分で決めることができる
個人事業主の場合、決算月は12月に固定されています。そのため、12月が繁忙期の場合、会計処理に追われて、より忙しさが増すことになるでしょう。一方、法人の場合は、自由に決算月を定めてよいことになっています。そのため、繁忙期を避けて会計処理を行なうことが可能です。また、キャッシュが多い月を決算期にすることで節税対策を行なうことができます。
従業員である家族に対して法人が給与を支払う場合は、税務署への事前届出が不要です。
個人事業主の場合は、あらかじめ「青色事業専従者」として仕事内容や給与・賞与の支払予定額を税務署に届ける必要があります。一方、法人が給与を支給する場合は、業務実態に応じて給与・賞与額を自由に設定可能です。ただし、法人経営に関する意思決定に関与する家族については、役員報酬扱いとなるため金額の調整が不可となるので注意しましょう。
法人のデメリット
法人のデメリットについても紹介します。
設立と運営にコストと手間がかかる
法人を設立するには費用がかかります。たとえば、株式会社にする場合は約25万円必要です。定款の作成や登記申請を司法書士へ依頼する場合は、所定の報酬が別途かかります。定款の作成は、行政書士登録を行なっている税理士に依頼しても差し支えありません。設立には手間や時間がかかるため、事業を始める日が決まっているのであれば、あらかじめ準備をしておくとよいでしょう。
社会保険の加入義務がある
個人事業主の場合、一部の業種を除いて社会保険の加入が義務化されておらず、加入するかどうかは個人事業主の判断に委ねられています。一方、法人の場合は従業員数に関係なく、事業主・従業員共に必ず社会保険に加入しなくてはなりません。そのため、従業員が増えるほど社会保険料の負担が大きくなります。
赤字でも税金が発生する
法人化したものの、利益が出せず赤字になる場合もありますが、赤字だとしても法人住民税を支払わなくてはなりません。法人住民税とは、会社の所在地にある都道府県や市区町村に支払う税金のことです。資本金が1000万円以下・従業員数50人以下の小規模事業者であったとしても、法人税額は年額7万円かかってしまいます。税金を支払えないという事態を防ぐためにも、毎年、税金のための費用を用意しておきましょう。
[PR]高収益・高利益が狙えるビジネス
【個人事業主と法人】どっちを選ぶ?

個人事業主・法人それぞれのメリット・デメリットを紹介しましたが、結局個人事業主・法人を選ぶときに何を基準にしたらよいのでしょうか。ここでは、事業形態を選ぶ際のポイントを2つ紹介します。
独立後の売り上げの見込みで判断する
年間の売上が多くなる予定であれば、法人として開業するとほうが税金を節約できます。法人にする目安は、独立後に課税所得が800万円以上見込めるかどうかです。経費の額にもよりますが、事業主単独で課税所得800万円を得るには、年間売上1,200万円前後が目安といえます。所得税・法人税それぞれの税率と金額を比較してみましょう。
| 所得税 | 法人税 | |
|---|---|---|
| 税率 | 23% | 15% |
| 控除額 | 63万6,000円 | なし |
| 納税額 | 120万4,000円 | 120万円 |
所得税の場合は控除額が設定されているため、単に税率だけで比較しづらい一面があります。しかし、課税所得が多い場合は開業時の手間や時間がかかったとしても、最初から法人として開業するのが金銭面で有利といえます。
信用力の違いで判断する
今後、事業をどのように展開するかによって、法人化するかどうかが決まります。一般的に個人事業主に比べて法人のほうが社会的な信用力は高いので、金融機関などから融資を受けたり、人材を集めたい場合は法人にしたほうがよいでしょう。
優先順位と目的をはっきりさせる
個人事業主と法人のどちらを選択するかを決める前に、優先順位と目的を確認します。ここが曖昧だと、誤った選択をしてしまう恐れがあるので要注意です。たとえば、1人で小規模な事業をスタートさせたいのであれば個人事業主がいいでしょう。逆に、人を集めて大きく事業を展開したり、節税したりしたいなら法人がおすすめです。
個人事業主と法人どっちが多い?
平成28(2016)年経済センサス活動調査の結果によると、2016年6月時点での企業数およそ385万6千社のうち、個人経営の企業は約197万9千社(51.3%)でした。
同じサービス業でも、飲食業や生活関連サービス業、教育・学習支援業では個人経営の割合が75%を超えています。一方、職業紹介事業や警備業といったその他サービス業では、約80%が法人経営の企業です。
どっちで起業する人が多い?
2019年「全国新設法人動向」調査(株式会社東京商工リサーチ)によると、2019年に新設された法人数は13万1,292社でした。
個人事業の開業・廃業届の提出数に関する公式な統計は存在しないものの、個人経営の企業数が全体の約51%であることを考えると、個人事業主としての開業が多いという見方も可能です。
フランチャイズのオーナーの場合
フランチャイズチェーンに加盟する場合、加盟金や月々のロイヤリティといったチェーン本部に支払うお金は、個人事業主・法人とも経費として計上可能です。法人経営の場合は、家族分の社会保険料・給料や社宅の費用も経費化できるなど、節税の可能性も広がるでしょう。
フランチャイズチェーンによっては、法人でなければ加盟できない場合や、別法人との兼業を不可とする場合もあります。加盟を検討する場合は、加盟資格を十分に確認しましょう。
個人事業主と法人の選択は目的を明確化して決めよう!
起業するにあたっては、個人事業主・法人どちらの形態を選択するかが重要なポイントです。それぞれにメリット・デメリットがあるので、事前にきちんと把握することが大切です。その上で自分自身の目標や規模を考えて、どのような事業をスタートさせるのかを明らかにすれば、個人事業主と法人どちらを選べばよいのか見えてくるでしょう。なお、個人事業主として開業した後に、法人化することも可能です。
[PR]リペア・リフォームビジネス