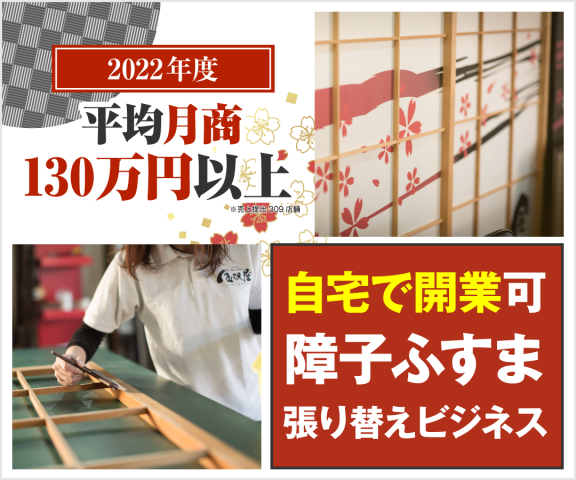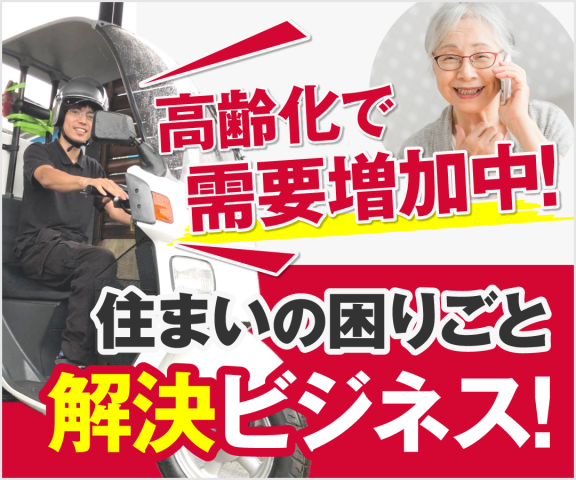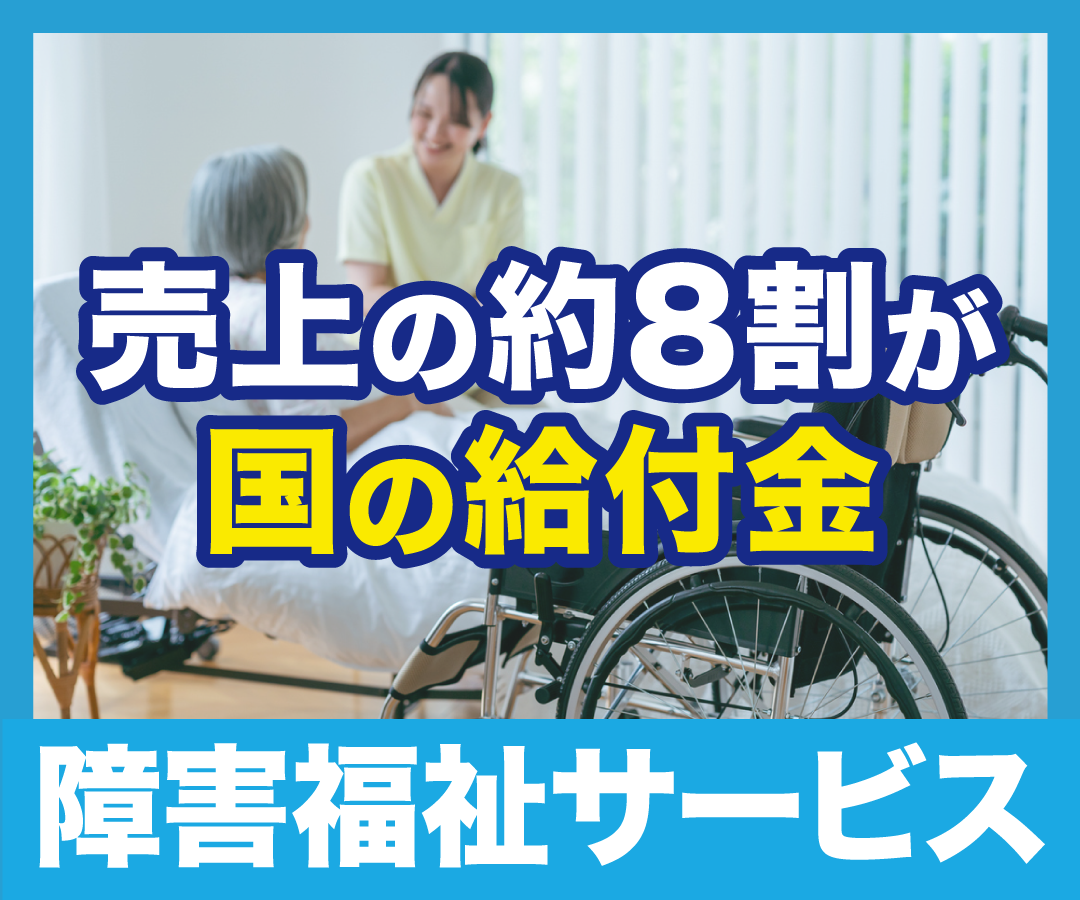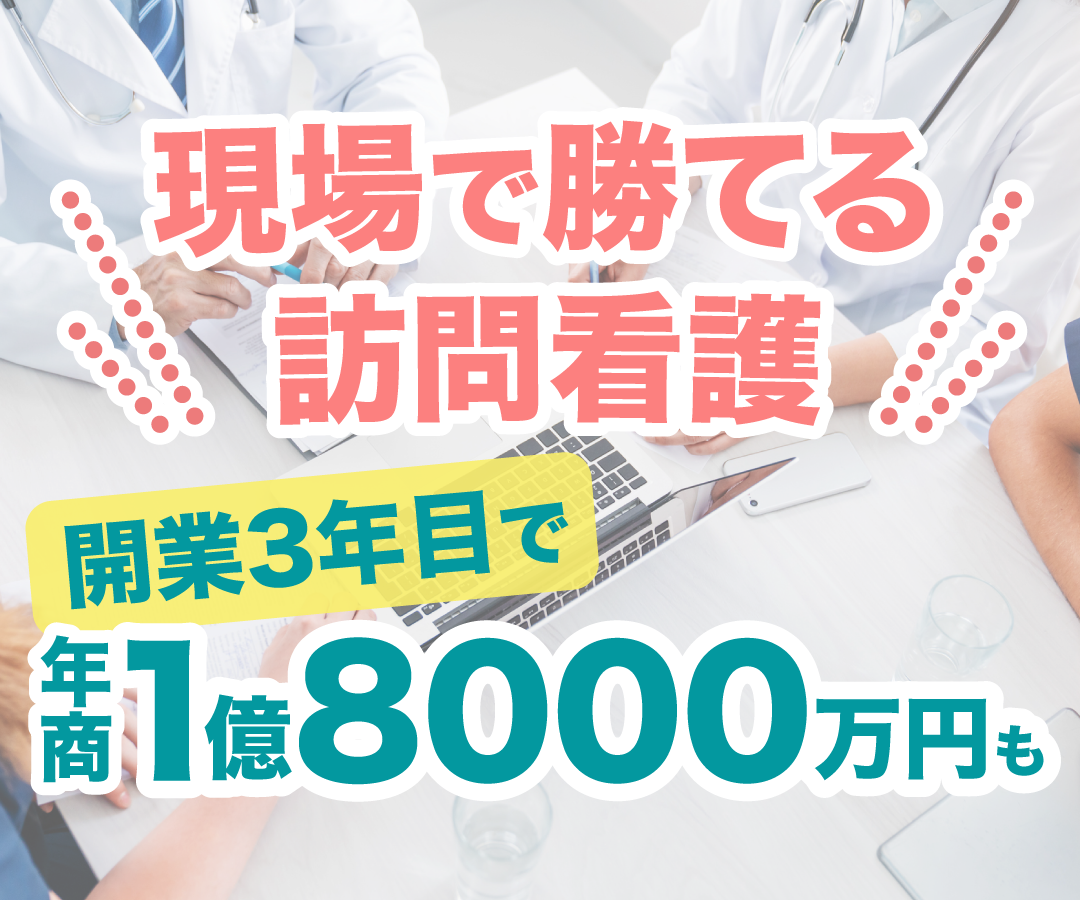開業費用は500万円で十分?業種別の開業費用目安と資金調達の方法を紹介

独立開業する際は、事業が運営できるようになるまでの準備金を含めた開業費がどれだけ必要になるのかを事前に把握しておく必要があります。開業する業種や業態によっても費用が異なるので、まずは開業費の相場を知るところから始めましょう。
開業の準備にかかる費用は経理上、開業費として計上することができますが、計上するためには開業前にかかった費用の帳簿付けについても知識が必要になります。この記事では、開業費の相場と資金の調達方法に加え、開業費の概要や会計処理の方法について紹介します。
開業資金はどれくらい?業界の開業資金を紹介
独立開業を目指す人にとって、最も気になるのが開業費用ではないでしょうか。資金調達を円滑に行なうためにも、まずは開業費の目安を押さえておきましょう。
開業資金は500万円未満?
日本政策金融公庫総合研究所によると、2019年度における開業費用の平均値は1,055万円ですが、500万円未満の開業費で独立した経営者が最も多く、その割合は40.1%です。また、開業資金の調査が開始された1991年から見ると開業費の平均値は右肩下がりの傾向にあり、開業費を抑えて起業する人が多くなっています。
とはいえ、開業費のすべてを自己資金で賄うのが難しい場合は、融資を受けなければなりません。借入先は金融機関をはじめ、親族や友人、知人などにお願いするのが一般的です。開業費に不安を抱えている人は、自己資金以外にどうやって開業資金を調達するのか考えておく必要があります。
業界別の開業資金相場
開業資金は起業する業界によって大きく変わります。ここでは、業界別に開業費用の目安を紹介するので相場を押さえておきましょう。
| 飲食(カフェ) | 100万円〜1,500万円 |
|---|---|
| 飲食(居酒屋) | 500万円~2,500万円 |
| 美容サロン | 800万円~5,000万円 |
| 学習塾 | 100万円〜1,000万円 |
| 介護 | 400万円~1,000万円 |
各業界で開業費用に大きな開きがありますが、低いほうの金額は居抜き物件(内装や設備機器、什器などが残っている物件)を利用した場合の開業費用です。実際には、紹介した金額の中央値付近が目安になります。物件に強いこだわりがなく、コストを抑えて開業するには居抜き物件を契約したほうが良いでしょう。また、フランチャイズに加盟した場合の開業費用の目安は以下のようになります。
| 飲食(カフェ) | 300万円~1,200万円 |
|---|---|
| 飲食(居酒屋) | 100万円~5,000万円 |
| 美容サロン | 50万円~4,000万円 |
| 学習塾 | 150万円〜1,000万円 |
| 介護 | 200万円~3,000万円 |
| コンビニエンスストア | 100万円~350万円 |
フランチャイズは費用を抑えて開業できるケースが多く、開業後は経営のサポートを受けられるのが一般的です。経営の自由度に制限があるとはいえ、コストだけでなく、経営ノウハウの面でも大きなメリットがある点は見逃せません。
開業資金の調達方法は?
開業費用が自己資金だけで間に合うケースは少ないのが一般的で、何らかの手段により資金を調達して開業にこぎつけます。そこで、資金集めの方法について紹介します。
開業資金は自己資金と金融機関の借入から
先に紹介した日本政策金融公庫総合研究所の調査では、2019年における開業時の資金調達額は平均で1,237万円となっており、1991年の調査開始後最も少なくなっています。内訳は、金融機関等からの借入が平均847万円で最も多く、次いで自己資金が平均で262万円、以下は家族や親類の平均53万円、友人・知人の平均39万円、その他が平均36万円と続きました。金融機関等からの借入は68%以上を占めていることから、自己資金のみで開業できる人は少ないようです。
なお、開業するための融資を受けるには、開業の3割ほどの自己資金を用意していなければ難しいといわれています。同研究所の調査でも、開業資金のうち約6割は金融機関などで借入、自己資金を約3割以上用意している人が多いようです。一般的に、自己資金の割合が多いほど融資を受けやすくなりますし、借金の少ない健全な経営につながります。融資の審査をスムーズに通過するためには、開業資金に占める自己資金を3割程度は用意しておきたいところです。
自己資金
開業費の準備で優先順位が高いのは自己資金の用意です。前述したように、自己資金の比率が高いほど借金に頼る割合を減らせますし、創業資金の3分の1を自己資金で用意できれば融資を受ける際も有利に働きます。もちろん、開業費用の全額を自己資金でカバーできるなら自己資金を用意する方法として多いのは、地道に貯金をしたり投資商品の売却や保険の解約をしたりするケースです。
注意したいのは、金融機関等から融資を受けるのを目的に親族や友人からお金を借りて自己資金の比率を高めようとする行為です。そもそも、融資は自己資金としては認められないので、出資や贈与をしてもらうことが前提条件になります。ただし、出資や贈与を受けた場合も自己資金として認められない可能性がある点には注意が必要です。
金融機関からの借入
自己資金で足りない資金は金融機関からの借入を検討する必要があります。創業融資として活用できるのは、主に以下のようなものがあります。
新創業融資制度
日本政策金融公庫による融資制度のひとつで、新規に事業を始める人や事業を始めて間もない人を対象にしています。担保や保証人を必要としない融資であり、条件付きではあるものの、開業費に対して10分の1の自己資金があれば融資を受けられます。融資限度額は3,000万円で、返済期間は設備資金の場合は20年以内、運転資金の場合は7年以内です。
中小企業経営力強化資金
政府系の融資制度で、主に地方自治体、銀行などの金融機関、信用保証協会が連携して融資を実施します。信用保証協会付の融資のため、実績のない新規創業者でも借りやすくなっているのが特徴で、金利が1.0~3.0%と低いなどのメリットがあります。一方で、融資が実行されるまでに3カ月程度の期間がかかるほか、自治体によっては連帯保証人が必要などのデメリットもあります。
銀行融資
銀行は返済能力がない人に融資を行なうことはないので、独立開業しようと考えている人が融資を申込んでも審査に通過するのは難しいでしょう。日本政策金融公庫の融資や制度融資の利用を検討するのが無難です。
補助金や助成金
開業費を十分に用意できない人は、国や自治体の補助金や助成金の活用も視野に入れましょう。補助金とは、店舗の借入費用や事業を円滑に進めるためにシステム導入費用など、事業に対して支給される制度です。審査があるので、すべての事業者が受け取れる仕組みではありません。
助成金は、福利厚生や雇用など従業員に関する施策に対して支給される制度です。要件を満たせば支給され、審査はありません。
国が行なっている補助金や助成金は厚生労働省や中小企業庁のホームページで案内されていますが、各地方自治体が行なっているものについては違いがあるため、開業予定の地域の役所に確認が必要です。
出資の受け入れ
株式会社として開業するなら、株式を売却して資金を調達するのも方法のひとつです。開業前の資金調達はできないものの、開業後の運転資金に困るようなら株式を売却することで資金を得られます。
ただし、借金ではないため返済する必要はないものの、手放す株式が多くなれば経営権を失ってしまうおそれがある点には注意しましょう。特定の出資者の持ち株比率が創業者よりも多くなってしまうと、経営権が出資者に移ってしまうため、計画性のある売却が必要です。
クラウドファンディング
クラウドファンディングとは、インターネット上で取り組む事業内容を発表し、共感した人から資金を得る手法です。資金を集めるための種類は、購入型・寄付型・株式型・融資型など複数の種類がありますが、多くのクラウドファンディングで使われているのが購入型です。
購入型では、事業に共感した出資者が金銭を提供し、事業者がリターンとして商品やサービスを提供します。確実に資金を集められる方法ではないものの、魅力ある事業内容なら開業費を得られるうえに開業前にファンを獲得できる可能性もあります。
会計上の開業費とは?

開業を目指す人たちが覚えておきたいのが「開業費」です。この開業費という言葉は何度か耳にしたことはあっても、それが何を指すのかよく理解できていない人も多いのではないでしょうか。 開業費とは、開業前の準備から営業開始までにかかった費用のことです。法人の場合、会社設立後の営業開始までに掛かった費用を指し、法人設立前のものは含まれません。会社設立のために支出した費用で開業費とは微妙に異なり、「創立費」にあたります。
いつまでのものが大丈夫?開業費に含むことができる期間
開業費は「営業開始までにかかった費用」と定義されていますが、「営業開始までに」というのがいつからの期間を指すのかが不明瞭で、どこまでの費用を開業費として計上すれば良いのかが分かりにくいです。
実は、開業費として認められる期間は明確にされていないため、開業のためにかかった費用であれば何年前に遡っても開業費にすることができます。開業準備が長期に渡った人、もしくは準備に時間がかかりそうな人も安心して準備できるようになっています。
[PR]手に職をつけられるフランチャイズ
把握しておこう!開業費に含まれるものと含まれないものの費用例
まずは開業費として含まれるものから紹介していきます。開業には欠かせないものばかりなのでしっかりと確認しておきましょう
広告宣伝費
最初に挙げられるのが広告宣伝費です。事業を開始するためには、自社の商品やサービスを宣言して多くの人に知ってもらわなければなりません。宣伝活動として挙げられる代表的なものにパンフレットやポスター、フライヤーの配布がありますが、現代では SNSでのプロモーションも盛んに行なわれています。それらにかかった費用は全て広告宣伝費になるので開業費に含まれます。
名刺作成費
名刺作成費も立派な開業費用として成立します。ビジネスシーンでは取引先など多くの人と接する機会がありますが、そのような場で自分の名前や会社を簡潔に紹介するためには名刺の準備が必要不可欠になります。名刺は通常、印刷会社に作成を依頼することが多いので、そのときにかかった費用もきちんと記帳しておきましょう。
市場調査費
続いて紹介するのが市場調査費です。例えば、店舗を開業する場合、立地調査や他店調査などをする必要がありますが、より綿密な調査を行うとなると各部門の専門家やコンサルタントに依頼することがあるかもしれません。そのときにかかった依頼費用はもちろん、移動の際の交通費なども市場調査費として認められるので開業費として計上することができます。
接待費
開業は、いろいろな人の協力がなければなかなか成り立たないことも多いので、他の企業と関わり合いながら事業を運営することもあるでしょう。打ち合わせを重ねながら準備を進めたり、食事などで接待したりする必要も出てくるため、その際かかった飲食代や贈答品は接待費になるので、開業費に含まれます。会計の際は領収書を発行してもらうのを忘れないようにしましょう。
開業費に含まれないもの
ではここで、開業費に含まれないものにはどのようなものがあるのか紹介していきましょう。自分では開業費に含まれると思っていても計上できないものがいくつかあるので確認が必要です。
10万円以上するもの
まず注意が必要なのは、「10万円以上するものは開業費にならない」ということです。開業準備の際はいろいろなものに出費が伴いますが、その額は細かいものから大きなものまでさまざまです。大きな出費を伴うものとして挙げられるものに設備や機械がありますが、1回につき10万円以上出費することも珍しくないでしょう。しかし、10万円以上するものは、固定資産として計上することになるので、開業費として認められることはありません。
敷金・礼金
店舗を運営する場合、多くの場合テナントを借りることになります。そのとき、敷金・礼金が発生することが多々ありますが、これらも開業費として計上することはできません。敷金は将来的に返却されるものになるため開業費の扱いにならないうえ、礼金は20万円以上になる場合、繰延資産として計上しなければなりません。礼金が20万円以下の場合は、開業費ではなく支払手数料として扱われることになります。
仕入れ費用
販売業や飲食業など、事業内容によっては商品の仕入れを行なう場合もあります。そのような事業において、仕入れ費用は開業に必要不可欠な支出ですが、それを開業費にすることはできません。なぜなら、それらの費用は後に販売することで利益に変えることができるためです。
開業費の会計処理の方法

ここで、開業費の会計処理の方法を紹介していきます。開業費が帳簿上どのように扱われるのか一通り確認しておきましょう。
会計処理の方法
経費ではなく繰延資産として償却
まず押さえておくこととして、会計処理において開業費は経費ではなく繰延資産として計上されることを覚えておきましょう。繰延資産とは、数年にわたって償却される費用のことを指します。開業費は経費のイメージが強いですが、初年度以降も事業に影響を与え続けるものとして一旦資産の科目で計上し、その後少しずつ経費として計上していきます。 償却方法には「均等償却」と「任意償却」の2種類があります。それらがどのように違うのか次の項目で解説していきましょう。
均等償却
「均等償却」とはその名の通り、費用を60カ月で均等に割り、毎月同じ額を経費として計上する方法です。均等に償却されるため、収支を正確に把握することができるという特徴があります。計算が簡単なので帳簿ミスを少なくすることができるのがメリットといえるでしょう。固定資産には有形・無形とありますが、無形固定資産はこの方法でしか償却することができません。
任意償却
「任意償却」とは、納税者が自由に経費にする金額を決めながら償却していく方法です。時期によって償却を0円にしたり、全額経費にしたりすることもできるのが特徴です。事業の調子が悪く赤字になりそうなときは償却額を0円にし、黒字になりそうな時は一気に全額経費として計上するなどといった自由な償却が可能なので、多くの人が採用している方法でもあります。
任意償却
「任意償却」とは、納税者が自由に経費にする金額を決めながら償却していく方法です。時期によって償却を0円にしたり、全額経費にしたりすることもできるのが特徴です。事業の調子が悪く赤字になりそうなときは償却額を0円にし、黒字になりそうな時は一気に全額経費として計上するなどといった自由な償却が可能なので、多くの人が採用している方法でもあります。
開業費の会計処理をする時のポイントは?
開業費の計上をする際は、押さえておくべきポイントがあります。それは、「開業費は任意償却で会計処理を行うと節税につながることもある」ということです。先ほど、任意償却は黒字の際に一気に経費として計上することもできると述べました。利益が多く発生すると、その分税金も高くなるため、償却する金額を多くするなどして節税を図るという人はたくさんいます。
[PR]40代以上のキャリア設計
気をつけよう!開業費の4つの注意点とは?
開業費を計上するうえで気をつけておかなければならないことがいくつかあります。注意点が理解できていないと、確定申告の際にトラブルになる可能性があるのでしっかり確認しておきましょう。
領収書や請求書は必ず保管しておく
申告を適切に行いたいのであれば、領収書や請求書は大事に保管しておきましょう。税務調査の際、領収書や請求書など証拠となるものがない場合、開業費として認められない可能性が出てきます。領収書や請求書は捨てずに必ず保管しておくのはもちろんのこと、日頃から書類の発行をしっかり行なうようにしておきましょう。
可能な限り開業費の帳簿付けは明細ごとに記載する
忙しい日々を過ごしていると、帳簿をつける時間をとるのが難しくなります。しかし、まとめて集計していると記憶も曖昧になるため、何にお金を使ったのか把握がしづらくなってしまいます。なるべく明細ごとに記載することを心掛けるようにしましょう。
固定資産に該当するものは耐用年数で経費にする
価格が10万円以上する備品や機械は固定資産として扱われますが、それらは年々劣化していくもので減価償却していく必要があり、耐用年数を基準に毎年経費として計上していかなければなりません。耐用年数は国税庁のHPから調べることができるので、帳簿付けの際は各備品の耐用年数が何年になっているのか調べておきましょう。
法人と個人事業主では開業費の対象が異なる
開業費は法人と個人事業主とで扱い方が変わってきます。法人の場合、開業のために特別に支出した費用しか開業費として計上できませんが、個人事業主の場合は開業前に支払った従業員への給料や事務所の家賃なども開業費として計上することができます。法人の場合は「創立費」と「開業費」をしっかり分けて申告しなければならないので今一度確認しておきましょう。
開業費は正確に計上して節税につなげよう!
いざ開業準備を始めると、想定していたよりも多くの資金が必要になるということもありますが、開業準備にかかった開業費は、申告の方法によっては節税につなげることができます。いつから準備を始めたのか、どのような項目があったのかを把握して正確に会計処理するためにも、領収書など証拠となるものを日頃から発行・保管しておくようにしましょう。
資金を無駄にしないために、フランチャイズという選択肢もある
開業資金の相場や調達方法、会計上の「開業費」について説明しました。開業するための大切な資金を有効活用し、事業を成長させるひとつの方法としてフランチャイズという選択肢があります。自己資金が0円~500万円程度で始められるフランチャイズビジネスもあるので、開業資金を心配している人にもおすすめです。業種や業態も豊富にあるので検討してみてはいかがでしょうか。
[PR]未経験・初心者でも安心のビジネス