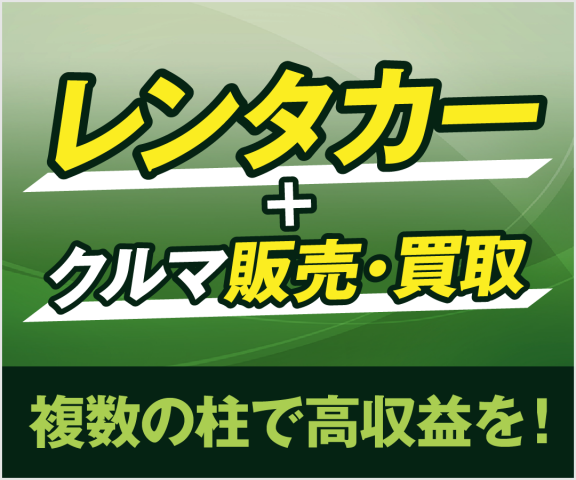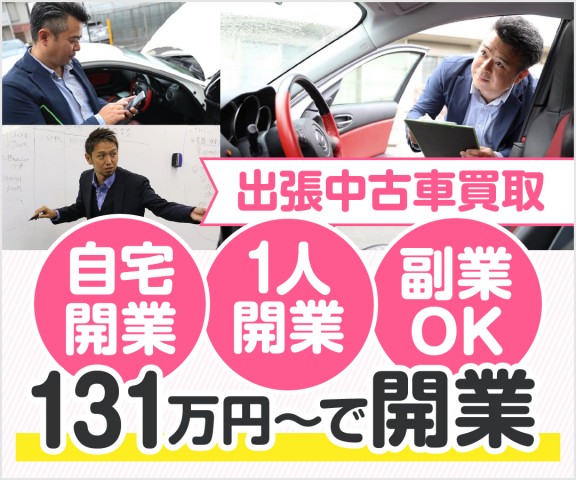個人事業主のための領収書の発行の仕方!書き方やルールまとめ

個人事業主でも商品を売ったり、サービスを提供して代金を受け取ると、領収書の発行が必要になってきます。支払いの証明となる領収書は記載方法が決められているので、その形式に従わなければなりません。
しかし、書く内容はなんとなく知っていても、正確な書き方を知らない人は多いのではないでしょうか。そこで今回は、領収書の正しい書き方や印鑑、印紙について説明します。
領収書とは?経費の裏付けとなる大事な書面
そもそも領収書とは、商品やサービスを提供する者が、その対価として代金を受領したことを証明するために、支払者に対して発行する書類のことです。領収証とも言われ、英語にするとレシート(receipt)になります。しかし、日本では会計の際にレジなどで機械的に印字されたレジシートをレシートと呼び、手書きで日付、金額、宛名、但し書きなどを書き入れたものを領収書と呼んで区別している場合がほとんどです。
また、お金を支払った側にとって領収書は支払証明書であり、必要経費の裏付けとなる大事な書面です。税法上はレシートでも必要事項(日付、金額、支払先、支払内容)が記載されていれば領収書の代わりになりますが、会社に経費を請求する場合はレシートでは認められない場合があります。宛名が記載されていないため、誰が支払ったのか不明瞭だからです。
[PR]1人で独立開業できる仕事
領収書の役割とは?領収書が必要な理由について
では領収書にはどんな役割があるのでしょうか。 ここでは、領収書の3つの役割や必要な理由について説明します。
過払いや二重請求を防ぐ
領収書には過払いや二重請求を防ぐ役割があります。領収書を発行することにより、代金の受け渡しが確実に実行され完了したという証拠となり、商品やサービス提供側の二重請求や、支払側の過払いを防ぐことができます。領収書がないと代金を支払ったことを客観的に証明することができません。
代金を受け取った側のミスで、支払ったはずの代金が二重に請求される可能性もあります。二重請求に気が付かずに支払ってしまうことや、気が付いたとしても支払い済であることを証明するのが困難な場合もあるでしょう。領収書があれば金銭授受の証拠が残るので、このようなトラブルは避けられます。
売上金や経費を証明する
領収書には売上金や経費を証明する役割もあります。売上のためにかかった経費は領収書があれば必要経費と認められ、その分を所得税から減額することができます。確定申告では領収書の提出は必要ありませんが、税務調査で提出を求められた場合は速やかに提出する必要があります。個人事業主の領収書の保存期間は、白色申告なら5年、青色申告なら7年となります。
内部での不正を防ぐ
領収書には内部不正を防ぐという役割もあります。従業員が会社へ経費を請求する際に、領収書の提出を義務付けていないと、内部不正につながる恐れがあります。たとえば、私的な飲食費を接待費として申請することや、金券ショップなどを利用して安く手に入れたチケットで出張時の交通費をまかない、会社には正規の料金を交通費として申請して差額分を着服することなどが挙げられます。
領収書はルールがある!個人事業主が発行する領収書の書き方とは
領収書の記載方法にはルールがあります。必要な項目と書き方が定められているので、項目や書き方に不備があると信用を失いかねません。ここでは個人事業主が発行する領収書に必要な6つの項目とそれぞれの書き方を解説します。

書類名
まず、書類名を記載する必要があります。中央上部、または上部左側に大きな文字で「領収書」と記載するのが一般的です。誰が見ても領収書だとわかることが重要なポイントです。
宛名
宛名には支払者の会社名(屋号や商号)と氏名を記載します。株式会社は(株)、有限会社は(有)などと略さずに正式名称で記載する必要があります。また、改ざんや不正が起きないように、空欄や「上様」を記載することは避けます。支払者から求められた場合は「領収書は上様や空欄では発行できません」とお断りしましょう。
金額
金額の記載方法には、改ざんを防止するために以下の3つのルールがあります。
・金額の数字の前に「¥」または「金」を記載する
・金額の末尾に「-(ハイフン)」または「也」を記載する
・金額の3桁ごとに位取りの「,(カンマ)」を記載する
それぞれの記号と金額の数字は間隔が開かないように詰めて記入する必要があります。間隔が開いてしまうと、後からそこに数字を書き足すことができてしまい、改ざんや不正につながるからです。なお、金額の前と末尾の記号は「¥」には「-」、「金」には「也」が対応します。
但し書き
但し書きには、どんな商品やサービスに対して支払われた代金なのかを記載します。「品代」というあいまいな表記は避けて具体的に記載しましょう。たとえば、本や参考書を購入した場合は「書籍代として」、食事や飲み代にかかった費用であれば「飲食代として」という書き方が一般的です。
なお、クレジットカード払いの場合は、支払者と受取人の間で金銭授受が発生するわけではないので領収書を発行する必要はありませんが、支払者から求められた場合は「クレジットカードにてお支払い」と記載すれば良いでしょう。
発行日
発行日(受領日)には領収書を発行した日付(代金を受け取った日付)を年月日で記載します。支払者に「空欄で」と言われるケースもありますが、実際に受領した日を必ず記載するようにしましょう。
受領人
受領人(発行者)は代金を受け取った個人事業主の氏名(屋号があれば屋号と個人名)、住所、連絡先を記載します。ゴム印でも手書きでも問題ありません。受取人を記載した部分に少しかかるように屋号印または個人印を押印します。

[PR]安定した集客力がある
便利な手書き領収書テンプレートの活用
領収書のテンプレートを活用する方法
領収書を1から手作りするのは相当な手間がかかります。そこで、オススメなのがテンプレートで作成する方法。なかでも、MISOCAが提供している無料テンプレートが使いやすいので、こちらをぜひ参考にしてみてください。
無料領収書エクセルテンプレート- Misoca(ミソカ)
また、テンプレート作成ツールなどもありますので、どちらのほうが活用しやすいか実際に試してみて、自分にあった方法を探すのが重要です。
領収書作成アプリやソフトウェアの使い方
テンプレートのほかにも、アプリケーションを活用して簡単に作成することもできます。有料であれば、マネーフォワードといったアプリケーションは有名でかつ便利に活用できそうです。無料版も探すと多く存在していますが、使ってみてご自身がいいと思うものを選んでみてください。
有料:見積書・納品書・請求書作成ソフト | マネーフォワード クラウド請求書
無料:領収書.net | 無料の領収書作成ツール
領収書が本物であることの証明!領収書に必要な個人事業主の印鑑
領収書には印鑑を押印するのが通常で、押印した者が領収書を発行したことの証明になります。個人事業主の場合は個人印、屋号印、署名のいずれかが無難です。シャチハタでも問題ありませんが、領収書が本物であることを証明するためにも避けた方が良いでしょう。
なお、税法上は領収書に必要事項が記載されていれば印鑑は必要ありません。しかし、会社の経理上、領収書には印鑑が必要としているところが多いので、はじめから印鑑を押印しておいたほうが親切ですし、後から要求された場合の手間も省けます。
領収書の金額によって異なる!収入印紙について
領収書の金額が5万円を超えている場合には、必ず収入印紙を貼る必要があります。収入印紙は、課税対象である文書を作った人が該当する金額の印紙税という税金を支払ったことの証明になるものです。領収書に貼る収入印紙の税額は、領収書の金額により以下のように規定されています。
| 領収書の金額 | 収入印紙の税額 |
|---|---|
| 5万円未満 | 非課税 |
| 5万円以上~100万円以下 | 200円 |
| 100万円超~200万円以下 | 400円 |
| 200万円超~300万円以下 | 600円 |
| 300万円超~500万円以下 | 1000円 |
| 500万円超~1000万円以下 | 2000円 |
| 1000万円超~2000万円以下 | 4000円 |
| 2000万円超~3000万円以下 | 6000円 |
| 3000万円超~5000万円以下 | 1万円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 2万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 4万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 6万円 |
| 3億円超~5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超~10億円以下 | 15万円 |
| 10億円超~ | 20万円 |
| 受取金額の記載のないもの | 200円 |
なお、収入印紙は領収書を発行する側がその税金を負担します。規定額の収入印紙を貼って割印を押すと納税が完了したことになります。
領収書の発行は義務?発行の必要性と再発行について
個人事業主にも領収書の発行義務があります。領収書は民法486条において「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。弁済とは代金の支払いを意味します。
したがって、個人事業主でも代金を受領したら、支払者から領収書の発行を求められた場合に、領収書を発行する義務があるということです。領収書の発行は代金の受領と同時に行なわれることが原則なので、領収書を発行しないと代金の支払いを拒否される場合もあります。
ただし、領収書の再発行については応じる義務はありません。領収書を紛失した場合などに再発行を求められるケースがありますが、領収書は支払証明書として代金の支払いと同時に発行することが原則なので、拒否することができます。領収書の再発行に応じること自体は問題ではありませんが、経費の水増しなど不正に利用される可能性もあるので注意が必要です。
個人事業主も領収書のルールを理解して正しく発行しよう!
個人事業主も代金を受領したら領収書の発行義務が発生します。正しい形式の領収書が発行できないと領収書と認められなかったり、不正に利用されたりするケースもありえるため、取引先の信頼を失ってしまうことにもなりかねません。余計なトラブルを避けるためにも、ルールに従い、正確な領収書を発行できるようにしておきましょう。
[PR]買取ビジネス