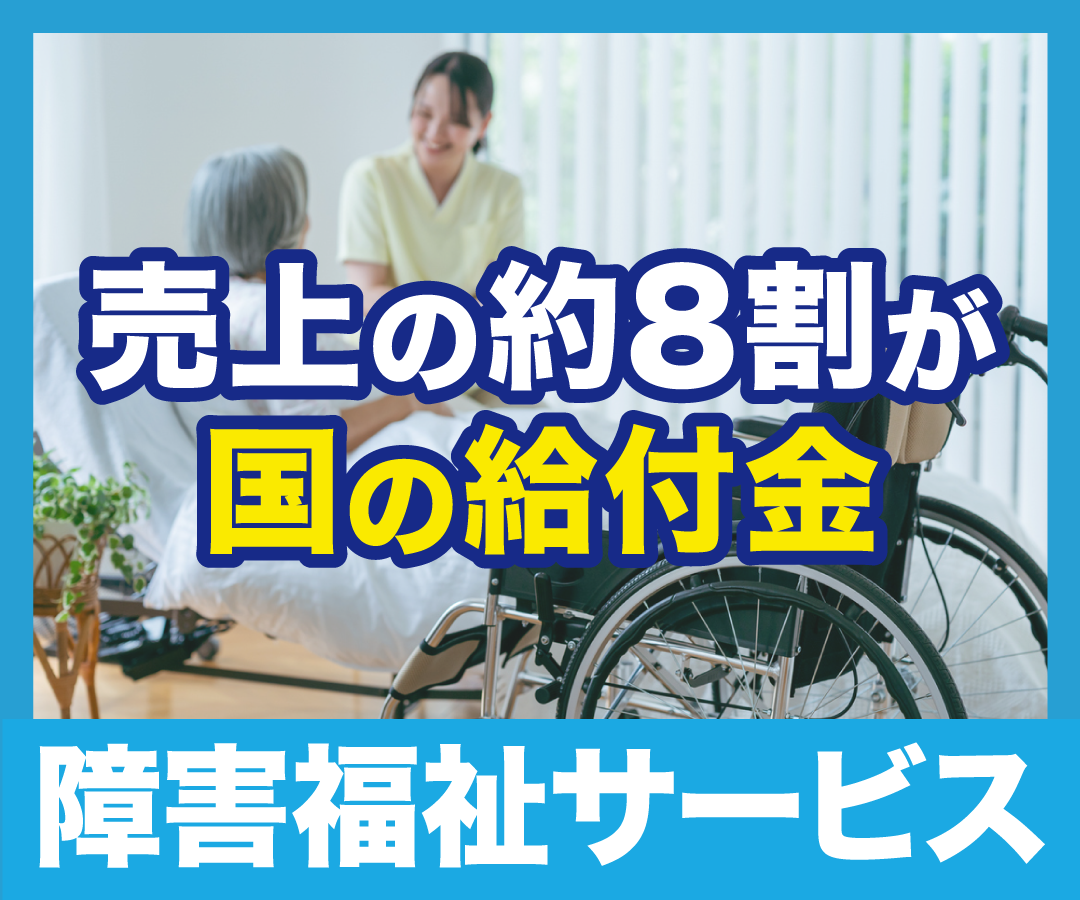個人事業主の老後は?会社員との年金額の違いや保険・投資での老後対策を紹介

会社員が加入する厚生年金は国民年金の上乗せ部分として、毎月の給与から保険料が天引きされています。企業によっては退職金制度も設けられており、定年後などにまとまった現金を受け取れるので老後の生活設計も立てやすいでしょう。
一方、個人事業主が加入する年金は国民年金だけで、保険料は自分で納付するのが原則です。保険料を納付しなければ将来の年金額が少なくなったり、年金そのものを受け取れなかったりする可能性があります。
そこで今回は、個人事業主が国民年金の上乗せとして加入できる公的制度や、老後に向けた資金作りに有効な保険・投資商品の概要、国民年金保険料が払えない場合の対処法を紹介します。
会社員と個人事業主の老後の違いは何か?
個人事業主・会社員ともに働いてお金を得ていますが、組織に属しているかどうかで仕事の環境や責任は大きく変化します。加入する年金も異なるため、老後の経済面にも差が生じがちなのも現状です。具体的にどのような差が生じるのでしょうか?
なお、厚生労働省では公的年金について漫画で解説したサイト「いっしょに検証!公的年金」が開設されています。この記事を読みながら参考にしてみるとよいでしょう。
定年のあり・なし
会社員の場合は勤務先のルールで働ける年齢の上限が定められているのに対し、個人事業主の場合は年齢にかかわらず働き続けられます。
会社員の場合は、会社の就業規則(ルール)で定年制度や再雇用制度が設けられています。2021年4月からは高年齢法雇用安定法が改正され、少なくとも65歳までは同じ会社で働き続けられます。また、70歳以上も働き続けられる制度を設けたり、定年制度を廃止したりする企業も増加傾向にあります。
一方、個人事業主の場合は引退する年齢を自分自身で決めます。従業員の定年・再雇用制度を設定していたとしても、オーナーである事業主には適用されません。したがって、体力と気力が続くまで働き続けることができますが、健康状態によっては突然の引退を余儀なくされる場合がある点に留意が必要です。
働く時間と賃金の考え方
働く時間や賃金も、会社員の場合は雇用契約で定められているのに対し、個人事業主は自分の裁量で決められます。
会社員の労働時間は基本的に1日8時間・週40時間の範囲内で、残業時間も1年あたり360時間(一部企業では720時間)に規制されています。人事評価制度が普及しているとはいえ、必ずしも成果が給与に反映されるわけではありません。ただし、出社さえしていれば遂行するべき仕事がなくても給与はもらえます。
それに対して、個人事業主は1日に働く時間を自由に決められます。経営者なので、労働基準法による労働時間や休日の規制対象外です。仕事の成果(顧客の評判)は売上、すなわち個人事業主の収入にすべて反映される反面、仕事を獲得できなければ売上は得られません。
年金や退職金の額
会社員と個人事業主とでは、老後に受け取れる年金の額が大きく異なります。
2019年度の年金の全国平均受給月額は厚生年金が146,162円、国民年金は56,049円です。人事院が公表している標準生計費と比較すると、国民年金だけでは生活費をまかなうのが非常に難しいことがわかります。
| 世帯人員 | 標準生計費 |
|---|---|
| 1人 | 110,610円 |
| 2人 | 153,040円 |
| 3人 | 176,230円 |
会社員で退職金制度の対象になる場合は、勤続年数などを基準に決定された金額が退職時に支払われます。ちなみに、東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」によると、同一企業にずっと勤め定年退職した場合のモデル退職金は、1,118万9千円(月給24.7ヶ月分)です。
個人事業主の場合は自分自身への退職金として、何らかの形で老後資金の確保の検討が必要です。すでに、定期預金などで老後対策をしている個人事業主もいるのではないでしょうか。
[PR]新着フランチャイズ
老後には一体いくらいるの?
では実際に老後にかかるお金がどのくらいになるのか、その額について調べてみました。
政府の試算では75歳以上で月23万円
総務省が実施している家計調査報告によると、老齢年金を受給できる年齢(60歳以上)の2人以上世帯における2020年11月時点での月間の消費支出は次のとおりでした。
| 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 |
| 297,629円 | 275,996円 | 252,090円 | 236,545円 | 197,152円 |
一方、65歳以上の夫婦世帯が受け取れる年金の額は、正社員中心の経歴と自営業中心の経歴とで倍近い差があります。厚生年金保険料の会社負担分が、ほぼそのまま年金額の差に反映されているといっても過言ではありません。
| 経歴 | 年間の平均年金額 | 月額に換算 |
|---|---|---|
| 正社員中心 | 3,493,000円 | 約291,100円 |
| 自営業中心 | 1,951,000円 | 約162,600円 |
自営業中心の経歴でも必要最低限度の生活は送れるものの、老後のゆとりある生活を送りたい場合は個人年金や投資商品などで資産を形成しておくと安心です。
会社員時代と違う!個人事業主の年金とは
個人事業主が納める年金と会社員が納めている年金には違いがあることを、ある程度は知っている人もいるでしょう。ただ、詳細までは把握していないという人も多いかもしれません。そこで、個人事業主と会社員の納める年金の違いを再確認してみましょう。
個人事業主が加入できる公的年金は国民年金のみ
日本の公的年金は、国民年金と厚生年金の2種類に分かれています。
国民年金
国民年金は基礎年金制度として運営されており、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入を義務づけられています(第1号被保険者)。一方、厚生年金は企業に勤める会社員や公務員が主な加入者です(第2号被保険者)。厚生年金に加入している配偶者は、一定の条件を満たせば追加保険料なしで国民年金の被保険者になることができます(第3号被保険者)。なお、2015年10月に、公務員を加入対象にした共済年金が厚生年金と統合されました。
厚生年金
厚生年金は「被用者年金」とも呼ばれ、基礎年金の上乗せ部分として支給されます(詳しくは後述)。個人事業主は経営者であって被用者には該当しないため、厚生年金には加入できません。そのため、個人事業主の所得に応じて老後の保障を充実できるよう、付加年金制度や国民年金基金といったオプションが用意されています。また「iDeCo(個人型確定拠出年金)」では個人事業主の掛け金が最大68,000円までで、厚生年金の加入者より幅広く設定できるのが特徴です。
将来受け取れる年金が少ない
国民年金だけでは将来の年金額が少なく、老後の生活に不安が残ります。前述したように、会社員だった人の厚生年金受給額が月平均146,000円ほど、国民年金だけだと月平均56,000円です。標準的な生活水準とかけ離れているのが現状で、特に国民年金だけでは厳しい生活が予想されます。
国民年金で受け取れる金額
国民年金(老齢基礎年金)は加入期間の長さで受給額が決まる仕組みで、2020年4月時点での満額は781,700円(月額65,141円)です。「満額」とは、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)にわたって国民年金保険料を毎月欠かさず支払った場合の金額で、免除・未納期間がある場合は満額を下回ります。また、国民年金の加入期間が10年に満たない場合は、老齢基礎年金を全く受給できません。
個人事業主に厚生年金の加入期間がない(国民年金の加入期間のみ)場合は、他に受給できる年金はありません。なお、日本年金機構の「ねんきんネット( 利用登録が必要)」で年金の加入実績に応じた受給額のシミュレーションを行えるので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
厚生年金で受け取れる金額
厚生年金(老齢厚生年金)は、会社員時代(被保険者期間)に受け取った給与や賞与の額に応じて受給額が決まります。基本的に定額部分と報酬比例部分で成り立っており、配偶者や子の年齢によっては加給年金を受けられる場合があります。なお、65歳以降は厚生年金の定額部分を老齢基礎年金(国民年金)として受け取る仕組みです。
1946年4月2日以降に生まれた人の、報酬比例部分の受給額は次の(1)と(2)を合算した額です。
(1)2003年3月以前の月数×平均標準報酬月額×(7.5/1000)
(2)2003年4月以後の月数×平均標準報酬額×(5.769/1000)
「平均標準報酬月額」と「平均標準報酬額」の概算は、それぞれ次の計算式で求められます。
(a)平均標準報酬月額=被保険者期間の月給の総額÷被保険者期間の月数
(b)平均標準報酬額=被保険者期間の月給と賞与の総額÷被保険者期間の月数
厚生年金の加入年数と給与・賞与額に応じた、老齢厚生年金(報酬比例部分)の年間受給額の概算も紹介します。この表では賞与額は考慮せず、2003年4月以後の年数を用いて計算しています。
| 加入年数 | 平均標準報酬額 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15万円 | 26万円 | 32万円 | 38万円 | 44万円 | 50万円 | 56万円 | 65万円 | |
| 1年 | 1.0万円 | 1.8万円 | 2.2万円 | 2.6万円 | 3.0万円 | 3.5万円 | 3.9万円 | 4.5万円 |
| 5年 | 5.2万円 | 9.0万円 | 11.1万円 | 13.2万円 | 15.2万円 | 17.3万円 | 19.4万円 | 22.5万円 |
| 10年 | 10.4万円 | 18.0万円 | 22.2万円 | 26.3万円 | 30.5万円 | 34.6万円 | 38.8万円 | 45.0万円 |
| 15年 | 15.6万円 | 27.0万円 | 33.2万円 | 39.5万円 | 45.7万円 | 51.9万円 | 58.2万円 | 67.5万円 |
| 20年 | 20.8万円 | 36.0万円 | 44.3万円 | 52.6万円 | 60.9万円 | 69.2万円 | 77.5万円 | 90.0万円 |
| 25年 | 26.0万円 | 45.0万円 | 55.4万円 | 65.8万円 | 76.2万円 | 86.5万円 | 96.9万円 | 112.5万円 |
| 30年 | 31.2万円 | 54.0万円 | 66.5万円 | 78.9万円 | 91.4万円 | 103.8万円 | 116.3万円 | 135.0万円 |
| 35年 | 36.3万円 | 63.0万円 | 77.5万円 | 92.1万円 | 106.6万円 | 121.1万円 | 135.7万円 | 157.5万円 |
| 40年 | 41.5万円 | 72.0万円 | 88.6万円 | 105.2万円 | 121.8万円 | 138.5万円 | 155.1万円 | 180.0万円 |
例えば、月給32万円の会社員の場合だと、勤続1年ごとに約2万2千円ずつ厚生年金の受給額が上乗せされることがわかります。より正確に厚生年金の受給額を見積もりたい場合も、自分の年金加入歴をもとに年金額のシミュレーションを行える、日本年金機構「ねんきんネット」を利用するとよいでしょう。
会社員の厚生年金保険料は会社と従業員が半分ずつ支払っています。一方、個人事業主は国民年金保険料だけでなく、国民年金基金やiDeCoの掛金も全額自己負担です。そのため、厚生年金に加入するのと同レベルの年金を受け取りたい場合は、支払いが増えることがほとんどでしょう。
中には会社員時代に支払っていた厚生年金保険料よりも、個人事業主として支払う国民年金保険料安くなる人もいます。そのため、単純に負担する保険料が安くなったことで喜ぶ人もいるかもしれません。しかし、実際には国民年金に上乗せされる厚生年金分がなくなるため、将来受け取れる年金額が下がってしまいます。
[PR]代理店契約型ビジネス
受け取る金額を増やしたい!個人事業主が加入できる年金一覧

国民年金だけでは、個人事業主が将来受け取れる年金の受給額は十分とはいえません。そこで、個人事業主が国民年金以外に加入できる年金や制度がいくつか用意されています。個人事業主が加入できる年金や制度を詳しく確認してみましょう。
国民年金基金
国民年金基金は、個人事業主が国民年金にプラスして加入できる公的制度です。厚生年金に加入している人と同様に、2階建ての年金制度で将来に備えられます。
国民年金基金は、終身年金と期間を限定して受け取る確定年金を組み合わせることができ、国民年金に上乗せすることが可能です。自由なプランで加入できるほか、掛け金は全額所得控除の対象となるので、税金面でのメリットももたらされます。
個人型確定拠出年金(iDeCoイデコ)
「iDeCoイデコ」と呼ばれる個人型確定拠出年金は、毎月掛け金を積み立て、そのお金を元に用意された金融商品で運用するシステムです。
途中で現金化することはできず、60歳以降に受け取ることになりますが、一度始めれば途中で転職・退職しても積み立てを継続できます。利子や分配金などの運用益が非課税で、掛け金自体も全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になるというメリットもあります。
付加年金
付加年金は国民年金の加入者が月額400円の付加保険料を上乗せして支払うことで、将来受け取る年金額に上乗せして増やすことができる年金です。年金を受け取るときは、毎月「200円×付加保険料を納付した月数」の金額が上乗せされて支給されます。なお、国民年金基金に加入している人の場合は、この付加年金を利用できません。
小規模企業共済
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員が、廃業や退職するときに備えて積み立てる共済制度です。退職金制度の個人事業主版という見方もできる制度です。個人事業主も加入することができ、廃業や退職時に生活資金などに充てることができます。月々の掛け金は500円単位で1000円から7万円まで自由に設定することができ、全額所得控除の対象です。また、掛け金の範囲内ではあるものの、事業資金の借り入れに利用できるのも小規模企業の事業者にとっては安心感につながります。
受け取る金額を増やすために民間でできる老後対策
保険会社の個人年金商品をはじめ、将来の資産を増やす仕組みは多数用意されています。証券会社や金融機関を通じた資産運用や、不動産の収益物件で家賃収入を得る方法もあります。資産運用では元本割れや損益発生のリスクが伴うので、十分な情報収集を行なった上で運用方法を決めるのが重要です。
個人年金
生命保険各社が提供する私的年金制度で、運用実績に応じて給付額が変動する「変動年金保険」と、加入段階で給付額が確定する「定額年金保険」に分かれています。保険料の払込み期間が終了した後は、一時金あるいは定期・終身年金として保険金を受け取る仕組みです。
不動産投資
購入した不動産(土地や建物)を他人に賃貸して、賃料収入を得る方法です。事務所(本社)と賃貸マンションを併設させた自社ビルを建築する事例もみられます。周辺の大規模施設の移転などにより、賃料相場が急落したり借り手を見つけるのが困難になったりするリスクの考慮が必要です。
FX
「外国為替証拠金取引」とも呼ばれ、外国の通貨を売買して差益を得る投資方法です。少ない資金でスタートでき、24時間好きなタイミングで取引を行なえます。国内・海外の経済情勢を十分に分析した上で取り組むことをおすすめします。
外貨預金
金融機関を通じて、日本円ではなく外国の通貨で預金する仕組みです。保険会社では「外貨建て貯蓄型保険」として販売されています。FXと同様に金利差による利益を得るシステムですが、入金・出金それぞれに為替手数料が発生する点に留意が必要です。
資金繰りが厳しい!国民年金の保険料が払えない場合の対処法
個人事業主は開業したすぐの時期は資金面で余裕がないことも多く、国民年金の保険料を支払うことさえ大変なこともあるかもしれません。そこで、万一、国民年金の保険料が払えない状況の場合にどうなるのか、そして対処法について詳しく解説します。
未納のままでは受給できない可能性がある
年金の保険料は一定の期間以上納めていなければ、将来年金を受け取ることができません。年金の受給権を取得するためには、10年以上の受給資格期間(加入期間)が必要です。保険料が支払えないからといって未納の状態を続け、その結果10年以上の受給資格期間に満たなければ将来年金を受給できなくなります。
保険料免除制度や保険料納付猶予制度を利用する
年金の保険料を支払うことができないような収入の減少や失業があった場合、保険料を免除されたり猶予されたりする制度があります。国民年金の保険料を納めることが困難なくらい所得が少ない場合、保険料の支払いを免除されるのが保険料免除制度です。前年の所得が一定以下のケースや失業したケースなどで、全額または4分の3、半額、4分の1という4パターンの免除があります。申請書を提出して承認されると保険料の納付が免除されます。
一方、20歳から50歳未満の人で前年所得が一定額以下の場合、保険料の支払いが猶予されるのが保険料納付猶予制度です。保険料免除制度と同様に、申請して承認されると納付が猶予されます。
保険料を免除された期間がある場合は、免除の割合に応じて将来受給できる年金額が少なくなるため注意が必要です。保険料納付猶予制度の場合は、猶予期間も受給資格期間にカウントされるものの、受給額は増えません。いずれの場合も、免除あるいは猶予された保険料を納めると、将来の年金額を増やせます。
個人事業主は受け取る年金が減る!国民年金の上乗せを検討しよう
会社員から個人事業主になると国民年金のみの加入となるため、厚生年金の加入者と比べると年金の受給額が少なくなりがちです。前述のとおり、年金の平均受給額は厚生年金で月146,000円、国民年金だけの場合は月平均56,000円で、国民年金だけの加入では最低限度の生活にも事欠くことになります。2020年11月時点での60歳~64歳世帯の消費支出は297,629円、ゆとりある老後の暮らしを送るためには、資産の「上乗せ」が必要不可欠です。
「iDeco」なら会社員時代から老後に向けて資産形成に取り組めるほか、個人事業主になった後は小規模企業共済をはじめ国民年金基金などを活用して、年金額の上乗せを目指せます。早い段階から保険会社の個人年金に加入したり、不動産投資などに取り組んだりするのも一つの方法です。独立を検討している場合、老後の経済状態が困窮しないよう、会社員時代から計画性を持って資産形成に取り組みましょう。
[PR]未経験・初心者でも安心のビジネス