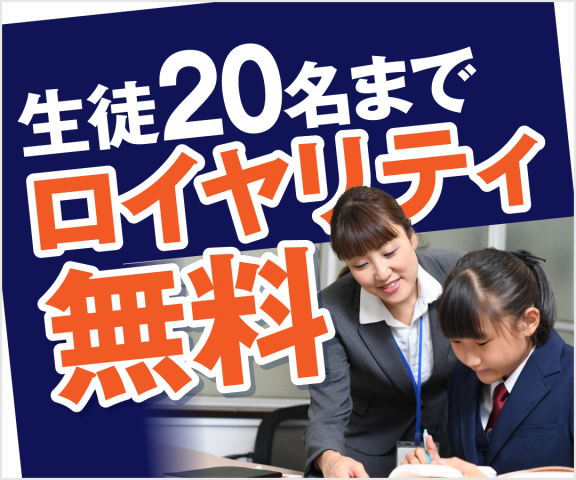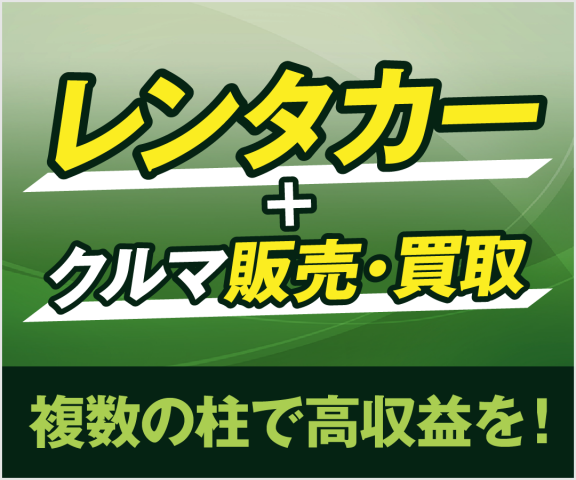自己資金なしでも起業できる?資金を集める方法と注意点について

基本的に、起業するためにはある程度の自己資金が必要です。しかし、資金はないものの、今すぐ起業したいという人もいるでしょう。たとえ十分な自己資金が用意できなかったとしても、開業に必要な資金を調達する方法はあります。
そこで、起業を目指す人のために、自己資金がない状態でも起業できる方法や注意点について紹介します。
起業とは
そもそも「起業」とは、新しく事業を起こすことをいいます。起業には大きく2つの形態があり、目的や業種、将来の成長戦略などによって向いている形態を選択します。
自営業者として起業する形態です。起業にあたっては「開業届(個人事業の開廃業届出書)」を税務署に提出するだけでよく、個人事業主が起業することを「独立・開業する」とも言います。たとえば、「ラーメン店を開業する」「古着屋を開業する」「弁護士が独立する」「開業医になる」などがこれに当たります。
個人ではなく、株式会社や合同会社などの法人を設立して起業する形態です。こちらはの場合は開業と言わず、一般的に「会社設立」などという表現をされます。法人を設立すると、税制面や社会的信頼性が高まるというメリットがありますが、定款作成や登記が必要など費用面のデメリットもあります。個人事業主として数年経過してから法人化する場合は「法人成り」と表現されます。
みんなの起業・開業資金はいくら?
起業を考えるようになると、気になるのは開業資金です。日本政策金融公庫が公開している資料(※)によると、起業時に苦労したこととして「顧客・販路の開拓」と並び、「資金繰り、資金調達」あげている人が半数近くにのぼっています。
では、具体的な開業資金がいくらだったのかと言うと、これも同資料によると平均1,237万円となります。資金調達先の内訳は、約7割の847万円を「金融機関等からの借入」、残り約2割の262万円が「自己資金」となっており、この2つで約9割を占めています。配偶者や親族などからの借入・出資という方法もありますが、主たる資金調達法として考えておくべきはこの2つと言えるでしょう。そのうち、自分で計画的に増やすことができるのは自己資金となるため、起業を考えだしたら計画的な自己資金作りも同時に考えた方がよさそうです。
※ 日本政策金融公庫『「2019年度新規開業実態調査」~アンケート結果の概要~』
そもそも自己資金とはどんな資金?
自己資金がなくても開業できる方法を知る前に、まずは自己資金がどのようなものかを理解しておきましょう。ここでは自己資金として認められるものと、認められないものの違いについて紹介します。
自己資金として認められるもの
まず、自己資金として認められるものの基準として、可視性が挙げられます。代表的なのは銀行や郵便局に預けている現金です。
日本政策金融公庫の場合は預貯金に限らず、事業者本人が保有する国債や株式といった証券や、解約返戻金のある生命保険、医療保険なども自己資金と見なされます。預貯金は記帳すれば1円単位まで金額の確認が可能です。生命保険や証券も、保険会社や証券会社の明細を見れば明確に価値がわかります。
なお、配偶者が持つ資金は事業者本人の自己資金ではなく余剰資金です。配偶者が融資に協力する場合、融資による借金は事業者と配偶者の二人で返済することになります。そのため、事業者が単独で融資を受けるよりも、有利に審査が受けられるのです。
自己資金として認められないもの

自己資金として認められないものとして、タンス貯金や、事業者本人または配偶者が保有する不動産、車などが挙げられます。
自宅で保管している貯金については、確認が難しいことから、自己資金とは認められません。たとえば、事業者本人が自宅に1千万円の貯金があると申告しても、融資を行う金融機関が実際に事業者の自宅を訪れて、金額を確認するのは難しいでしょう。ただし、融資を受ける前に自宅の貯金を銀行に預けて記帳を行えば、自己資金と見なされます。
[PR]ロイヤリティ無料のフランチャイズ
起業するのに必要な資金

起業するために必要な資金は、業種によって大きく異なります。準備資金を計算する際は、「設備資金」と「運転資金」に分けて考えなければいけません。そこで、設備資金と運転資金の意味や違いについて詳しく解説します。
設備資金
設備資金とは、事業を維持したり拡大したりするために、一時的に必要になる資金のことです。
たとえば、事務所や店舗を借りるための初期費用や内装など、設備投資のための資金も含まれます。また、電話やパソコン、机などの事務用品を買うためのお金も、設備資金の一つです。店舗によっては業務に必要な機械や自動車を購入したり、ホームページを作成したりするための費用が必要になる場合もあるでしょう。
運転資金
運転資金とは、事業を運営するために必要なお金のことです。運転資金は設備資金とは異なり、継続的に発生するので、事業が軌道に乗るまでの運転資金は事前に用意しておかなければいけません。
たとえば、従業員の給料や商品の仕入れに必要なお金は運転資金です。また、毎月の地代家賃外注費や消耗品費、広告や宣伝にかかる費用なども、事業を続けるために継続的に発生する資金なので運転資金に含まれます。
1人で独立開業する場合にかかる費用
所属していた組織(会社やお店など)を離れて、自分で新たに事業を起こす独立開業。弁護士や税理士、コンサルタントなどの資格系だけでなく、こじんまりとした美容サロンや個人の学習塾など、比較的初期費用をかけなくても起業できる職種が多いです。では、従業員を雇用せず、1人で起業する場合の最も規模の小さいパターンで必要な初期費用について紹介します。
| 事務用品(名刺や印鑑、文房具など) | 3千円~2万円程度 |
|---|---|
| オフィス機器(プリンター、ソフトウェアなど) | 1万円~3万円程度 |
| HP製作費 | 15万円~25万円 |
| 広告費(チラシやネットなど) | 月1万円~ |
| 打ち合わせ費用(交通費やコーヒー代など) | 月5千円~ |
上記は自宅を事務所として利用した場合であり、オフィスを借りて事務所・店舗を構えるのであれば、この他に契約にかかる諸費用として、数10万円~数100万円かかります。
店舗を構える場合の費用
これまでの経験を活かしたり、夢をかなえるために店舗を構えて起業するケースも多いでしょう。たとえば、「ラーメン好きが高じてラーメン店をOPNEした」とか「夢見ていたカフェを開く」などです。飲食店経営の場合、一般的に2,000万円前後の開業資金が必要と言われていますが、ここでは最低限かかるであろう費用について紹介します。
| 店舗取得費(20坪程度) | 200万円〜300万円 |
|---|---|
| 内装・看板設置費用 | 100万円~ |
| 厨房機器 | (ラーメン店)製麺設備を含む300万円~ (カフェ)オーブンやエスプレッソマシーンなどを含む120万円 |
法人設立の費用
何人かで起業するにあたり会社設立をする、という場合には法人登記をする費用が必要になります。ただし、法人の種類によってその費用は幅があり、もっともコストを抑えたいのであれば「合同会社」となります。合同会社の場合には、新株発行などの資金調達が行なえないというデメリットもありますが、節税が主目的で法人化するのであれば十分です。反対に、「短期間で上場を目指す」というベンチャー企業を設立するなら、初めから株式会社化することも考えられます。
| 合同会社 | (電子定款)約7万5千円〜/(紙定款)約11万円〜 |
|---|---|
| 株式会社 | (電子定款)約21万5千500円~/(紙定款)約25万1千500円~ |
すぐに独立したい!自己資金なしで起業する方法

起業するときは、必ずしもまとまった自己資金を用意しなければいけないというわけではありません。ここからは自己資金が少ない状態で起業する方法について説明します。
共同事業主を見つける
一つ目の方法は、共同事業主を見つけることです。事業主が多いほど、自己資金の総額も増えます。
ただし、意見が合わない事業者同時が集まっても、ビジネスがうまくいくことはないでしょう。資金を提供してくれるだけではなく、自分がやりたいビジネスを理解し、賛同してくれる人を見つける努力をしましょう。
投資家に出資してもらう
また、エンジェルと呼ばれる個人投資家から出資してもらうという選択肢もあります。エンジェルとして活動するのは元起業家や経営者などの富裕層が多く、事業の規模や自己資金の金額よりも、事業内容や将来的なビジョンを重視したうえで投資を行うのが特徴です。
資金の提供はもちろん、経営についてアドバイスをくれたり、精神的なサポートまでしてくれたりする投資家も少なくありません。ただし、中には投資をするかわりに、経営にも口を出そうとする投資家もいるので、望んでいない場合は注意しましょう。
助成金を利用する
もう一つの方法は、助成金や補助金を利用する方法です。どちらも国や地方自治体が、小規模事業者の起業や運営を推進する目的で作られた仕組みで、一部例外もありますが基本的に返済不要な資金です。要件を満たしていれば、国の機関や自治体に経費の一部を支給してもらえることがあります。
支給額は募集している内容によって幅がありますが、中小企業支援サービスを行なう「Jマッチ」が調査したところによると、従業員規模が9人以下の企業が申請した助成金の額は平均251万円(※)でした。※ ライトアップラボ『 Jマッチラボ 調査レポート「中小企業の助成金申請状況」』
また、優れた事業成果をあげている企業に対しては、最大1億円の助成金が支給される「ものづくり助成金」という制度もあります。これは、革新的な商品やビジネスモデル開発などを行なった企業に対して支給されるものです。もちろん、採択される基準は簡単なレベルではありませんが、採択されることによってその企業が持つ技術力などが裏付けされると考えれば、目標として目指すのもいいでしょう。
こうした助成金や補助金の情報は、厚生労働省や各主管の機関によって公開されていますが、それらをもれなくチェックするのは大変なので、中小企業やこれから起業する人を対象にしたサポートを活用するのがよいでしょう。
たとえば、情報取得という点では独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」や中小企業庁が運営する「ミラサポPlus」が有名です。どちらも全国の助成金や補助金の検索や電子申請ができたり、経営・企業・資金調達などに関するおすすめの情報や各種ツールを提供していたりしますので、参考にするとよいでしょう。
さらに、実はこうしたサービスは中央機関だけではなく、地方自治体でも行なわれています。
たとえば、東京都産業労働局では、東京都創業NETというポータルサイトを設立し、積極的に企業支援を行っているのが特徴です。特に、23区は起業者に向けた支援施設が豊富で、クラウドファンディングを活用した資金調達支援の方法を指導したり、電話相談窓口を設けたりしています。また、東京都中小企業公社では、創業助成金や東京都中小企業融資を受けることも可能です。
融資を受ける
銀行などの金融機関から融資を受けるのも、資金調達の方法の一つです。
起業する人や起業後間もない人などが融資を受けられる金融機関として、日本政策金融公庫の公庫融資や信用金庫が挙げられます。日本政策金融公庫は民間ではなく、政府が出資を行っている政策金融機関です。また、政府の政策に即した融資を行なっており、代表的なものとして次のような融資があります。
・新規開業資金…新規起業をするもしくは事業開始後7年以下の事業者向け
・女性、若者/シニア起業家支援資金…女性または35歳以下か55歳以上で、新規起業をするもしくは事業開始後7年以下の事業者向け
・中小企業経営力強化資金…外部専門家のサポート、または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用などにより経営力強化を図る事業者向け
また、信用金庫では個人や中小企業との取引を中心に行なっています。株主の利益よりも、地域社会の繁栄を目的としているため、比較的融資を受けやすいのが特徴です。
地方で起業する
最近は、出身地や気に入った地方に移住したい、という方も増えています。それならばいっそ、地方で起業し、公的支援を受けるという選択肢もあります。
国が進めている地方創生事業の一環として、地方へのIターン・Uターンかつ起業を行なう場合、起業支援金として最大200万円、移住支援金として最大100万円の最大合計300万円の支給がされます。ただし、東京在住もしくは東京へ通勤している方で、なおかつ東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)以外の地方で起業し、移住する方が対象となります。
地方でのんびりと子育てをしたい、通勤時間を短くしてプライベートを充実させたい、という方にはおすすめの制度ではないでしょうか。
[PR]趣味を活かす・好きを仕事に
自己資金なしで起業するときの注意点
自己資金が少ない状態で起業する場合、気を付けたいのは融資で借りられる金額です。
一般的に、融資で借りられるのは自己資金の2倍の金額までとされています。融資の審査は、事業の業種や将来性、物件の立地など、さまざまな要素を考慮したうえで決定されるものです。そのため、自己資金が少ない状態でも融資が通る可能性はあります。
また、日本政策金融公庫で融資を受ける場合には、原則として融資額の1/10の自己資金があれば融資を受けることが可能です。ただし、自己資金は多いほうが融資にも通りやすいので、一般的に融資額の3割は自己資金を用意しておいたほうが良いといわれています。ビジネスモデルや事業計画書次第ではありますが、必要な融資額が1,000万円なら100~300万円の自己資金を貯めれば審査に通ることもあるので、ぜひ活用したいところです。
しかし、自己資金が全くない場合は、融資が受けられない可能性が高いです。事業を始めるにあたり、初期費用が高額になると予想される場合は、会社員やアルバイトを続け、ある程度の自己資金を貯めてから起業したほうが良いでしょう。
自己資金が少なくても開業しやすい業種
自己資金が少ない状態でも、開業しやすい業種もあります。
たとえば、ビジネス系コンサルタントのようなコンサルタント業務は、商品を仕入れたり在庫を持ったりする必要がなく、少ない資金で開業できます。さらに、コンサルタントは肩書きよりも実績のある支援力が求められる仕事なので、個人が起業しても参入の余地がある業種です。
また、Webシステムの開発やコーディングを行うシステムエンジニア、Webデザイナー、Webライターやイラストレーターなど、Webを媒体としたクリエイティブな業種で開業している人も多く見られます。スキルがあれば仕事を受けられるので、少ない資金で開業が可能です。
具体的な資金調達方法を無料で相談できるところがある
開業資金や運転資金など、経営者は資金調達について常に考える必要があります。実際、既出の日本政策金融公庫のアンケート結果でも、起業後に苦労していることとして資金調達をあげている人が最も多くなっています。
会計士や税理士などが資金調達のアドバイスをしてくれることもありますが、ここでは経営に関するあらゆる相談を無料で行なってくれる「よろず支援拠点」を紹介します。
経済産業省により各都道府県に設置されたよろず支援拠点では、地域の支援機関と連携しながら企業のサポートを行なっています。起業の相談はもちろん、資金調達や起業後の雇用に関する労務、売上拡大、生産性向上など、あらゆる経営課題に対して専門家チームが無料でワンストップサービスを行っているのが特徴です。
事業に集中するためにも、ある程度の自己資金は用意しておこう
自己資金が少ない状態で起業する方法はいくつかあるものの、必要なのは準備資金だけではなく、当面の生活費も用意しておかなければならないでしょう。融資を受けるにしても、自己資金がある程度なければ、借りられる額が少なくなってしまいます。
また、資金に余裕がない状態だと、経済的な不安から事業に集中できなくなってしまう可能性があるでしょう。起業を目指すのであれば、ある程度の資金を確保しておいたほうが安心です。
[PR]未経験・初心者でも安心のビジネス