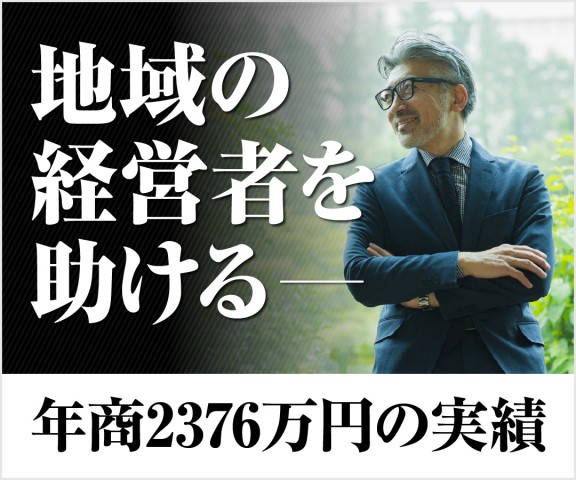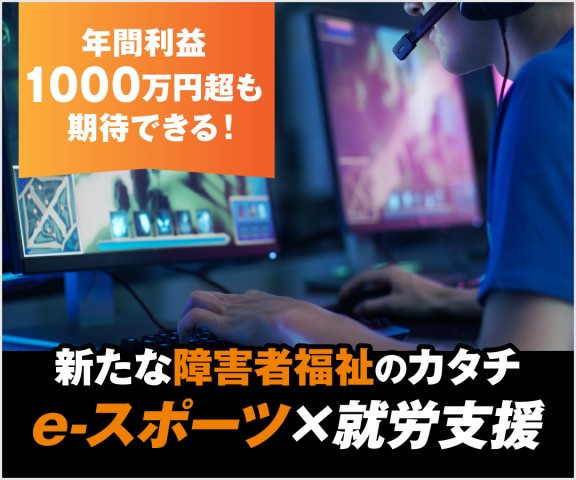無申告のリスクを回避!赤字決算でも確定申告するメリットや3つの節税方法をチェック

新型コロナウイルスの影響で、2020年度の事業所得が赤字となった事業主が少なくありません。そのため、確定申告を行なうべきかどうか迷う人もいるでしょう。 青色申告の場合は、確定申告によって赤字決算時の損益通算・損失繰越が可能になるなど、節税面で大きなメリットを得られます。同時に、無申告のデメリットも複数潜んでいます。
2021年1月に申請を終了した持続化給付金制度では、確定申告を行なっていなかった人が申請に苦慮する事例が続発しました。 黒字・赤字にかかわらず、確定申告を行なったほうが良いということです。 この記事では確定申告のメリットと共に、新型コロナに伴う納税特例についても紹介します。
コロナの影響で納税が困難な場合
2021年2月現在、コロナに関する納税特例として国税の納期限猶予(原則1年間)や延滞税の軽減措置(年1.6%)が実施されています。
次の4つの要件をすべて満たせば特例が認められますが、事業主本人や事業の運営状況に応じた柔軟な対応が取られているようです。また、2020年2月以降の収入が前年同期に比べて20%以上減少した場合や、事業主本人や家族の病気に伴う申請の場合などでは延滞税が免除されます。
(1)納税により、事業の継続や生活維持が困難になる恐れがある
(2)納税への誠実な意思がある
(3)猶予を受けようとする国税以外の滞納がない
(4)本来の納期限より6ヶ月以内に申請している
特例申請にあたっては収支の状況を申告しますが、自力での申告が難しい場合には税務署職員のサポートを受けられます。特例に該当しない場合でも、既存の納税猶予制度の提案を受けられるので、迷ったときは「国税局猶予相談センター」への電話相談をおすすめします。
「国税の納税の猶予制度に関するFAQ」も参考にするとよいでしょう。
赤字で納める税金がなければ確定申告の義務はない
確定申告とは、1年間で発生した所得税額を確定して納税あるいは還付を受けるために必須の手続きで、課税所得の金額や小規模企業共済をはじめとする各種控除額を計算します。個人事業主の場合は毎年1月1日から12月31日までの1年間を事業年度として、翌年の3月15日(土日の場合は翌開庁日)までに手続きを行ないます。
所得のある人は確定申告を行なうのが基本ですが、次のいずれかに該当する人は確定申告の義務はありません。
(1)事業所得が赤字で、納税額がゼロの場合
(2)諸経費を引いた年間所得が38万円以下の場合
(3)1ヶ所の勤務先で給与所得を受けていて、他の所得が20万円以下の場合
(4)公的年金の受給額が400万円以下で、他の所得が20万円以下の場合
「赤字」とは、売上から必要経費を引いた金額がマイナスである状態をいいます。所得がある場合でも、基礎控除や医療費控除といった所得控除額を下回れば、やはり赤字状態です。
また、確定申告を行なえば住民税の申告を行なったものとみなされる他、所得額に応じて国民健康保険料が自動的に減額される場合があります。前述のコロナに関する納税特例や国や自治体の各種制度の申請にも確定申告書の控が必要なので、赤字でも確定申告を行なうようにしましょう。なお、青色申告の承認を受けている場合は、確定申告を2期(2年)連続で行なわないと承認が取消される場合があります。
万が一、所得がある人が確定申告を怠ると、本来の所得税額の他に無申告加算税や延滞税が加算されます。税務調査により確定申告が済んでいないことが発覚した場合には、重加算税が課せられる恐れもあるため要注意です。
[PR]1人で独立開業できる仕事
白色申告と青色申告の赤字の取扱の違い
赤字の場合は確定申告が義務づけられていませんが、白色申告と青色申告では赤字に関する取扱いが大きく異なります。
白色申告では赤字を翌年度以降に繰り越せませんが、青色申告では最大3年間繰り越せます(詳しくは後述)。1年目に300万円の赤字決算だった個人事業主が2年目・3年目で150万円ずつ黒字決算だった場合の課税所得は、次のとおりです。
| 1年目の課税所得 | 2年目の課税所得 | 3年目の課税所得 | |
|---|---|---|---|
| 白色申告 | 0円 | 150万円 | 150万円 |
| 青色申告 | 0円 | 0円 | 0万円 |
青色申告だと赤字を繰り越した結果、2年目・3年目も課税所得はゼロで所得税の支払いは発生しません。一方、白色申告では赤字を繰り越せないため、黒字分がそのまま課税所得とされます。ちなみに、課税所得が150万円のときの納税額は7万6575円(税率5%+復興特別所得税)です。
前年度が黒字で今年度が赤字だった場合は、前年度の黒字分から今年度の赤字分を相殺する「純損失の繰戻し還付請求」の手続きもできます。ここで、赤字でも確定申告を行なうメリットが生じるわけです。
課税所得の算定についても、青色申告では白色申告よりも優遇されています。白色申告の場合は事業所得に関する特別控除がなく、売上から必要経費を引いた収益はそのまま課税所得となります。一方、青色申告の場合は白色申告時の課税所得から最大65万円の特別控除を受けられ、節税効果が生まれます。
| 特別控除額 | 記帳方法 |
|---|---|
| 10万円 | 簡易簿記または現金式簡易簿記 |
| 55万円 | 複式簿記 |
| 65万円 | 複式簿記+e-Taxでの申告 |
白色申告の場合
白色申告の場合は所得の特別控除を受けられませんが、収支内訳書(法定帳簿)だけで確定申告を行えるので記入項目が少なく、計算も楽です。ただし、2014年1月からは帳簿の作成・保管が義務づけられているため、売掛帳など経理処理に必要な補助簿を作成し、納品書・請求書・領収書といった関連書類(エビデンス)は保管します。
青色申告の場合
一方、青色申告では白色申告と異なり複式簿記で記帳した上で、総勘定元帳や仕訳帳の作成が必要です。簡易簿記での記帳も認められていますが、特別控除額は10万円に減ります。そのため、会計ソフトで記帳したり税理士が関与したりするのが一般的です。
青色申告を受けるためには、あらかじめ事業所の住所地を管轄する税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。開業から2ヶ月以内に提出するルールですが、開業届と同時に提出する人が多いようです。
また、白色申告から青色申告に変更したい場合は、確定申告の期限までに青色申告承認申請書を提出しますが、確定申告書と同時に提出するとスムーズでしょう。青色申告の承認を受けることで、家族に支払った給与を経費化できたり(専従者控除)、家事按分の幅が広がったりするという節税特典を受けられます。
赤字でも確定申告をするメリットとは
青色申告を行なっている事業者なら、確定申告の手続きを取れば赤字を繰り越したり、他の黒字所得と通算して課税所得を減らしたりできます。ここからは確定申告を行なうことで得られるメリットを具体的に紹介します。
損益通算
損益通算とは、所得が赤字の場合に他の黒字所得と通算して、赤字と黒字を相殺する手続きです。課税所得を減らす効果が生じるため、事業主にとっては確定申告で得られるメリットが大きいとされています。青色申告・白色申告ともに損益通算は認められており、対象となる所得は次の4種類です。
事業所得:農業や漁業、建設業、飲食店の経営などの事業で得た所得
不動産所得:所有する土地や建物など、不動産の貸付により得た所得
譲渡所得:不動産や株式、ゴルフの会員権などの資産を譲渡した際に発生する所得
山林所得:山林を譲渡した際に発生する所得
ただし、山林所得は50ヘクタール未満の山林の場合、所有してから5年以内に譲渡または伐採してしまうと、雑所得に分類されます。また、山ごと譲渡した際、山林以外の土地から得た所得は譲渡所得となるので注意が必要です。
損益通算が認められる具体例も確認してみましょう。
(1)個人事業主がアルバイトをした場合の給与所得を、赤字の事業所得と損益通算
(2)個人事業主が不動産投資で赤字を出した場合に、黒字の事業所得と損益通算
(3)個人事業主が事業所得で赤字を出した場合に、黒字の不動産所得と損益通算
(4)雑所得の黒字で、事業所得や不動産所得の赤字を埋め合わせる
(5)マイホームを売却したが赤字(売却損)が出た場合に、他の黒字所得と損益通算
(6)上場株式Aの売却損を、上場株式Bの配当所得や利子所得Cと損益通算(申告分離課税を選択している場合)
雑所得の赤字を他の所得の黒字で埋め合わせることはできませんが、事業所得と複数の所得と損益通算して節税につなげられるのが特徴です。
赤字の場合の繰越損失赤字額(純損失)を最大3年間繰り越せるのも、確定申告で得られるメリットです。ちなみに純損失とは、損益通算をしてもなお相殺できなかった赤字のことをいいます。
先述の例のとおり、今年度の純損失を翌年・翌々年の黒字と相殺することで節税効果を発揮します。繰越控除によって適用される所得税の税率が変わったり、個人事業税(最大税率5%)の課税有無の分かれ目になったりするからです。
青色申告の場合は、後述の計算方法で確定した純損失なら全額繰り越せます。白色申告の場合は、次の場合に限り繰越控除が認められます。
(1)災害により、事業用の資産が被害を受けた場合
(2)変動所得に関する損失(原稿料や著作権使用料、漁業や養殖など)
繰越損失額の計算の仕方
当年度の純損失を翌年以降に繰り越すことで所得税はもちろん、住民税の節税にも直結します。国民健康保険料の所得割に反映されたり、総所得額によっては保険料そのものの減額を受けられたりします。青色申告をする個人事業主ならではのメリットです。
繰越損失額の計算にあたっては、次の順位で損益通算を行ないます。
(1)「事業所得・不動産所得」と「利子所得・配当所得・給与所得・雑所得」の中で損益通算する
(2)「総合譲渡所得」と「一時所得」の中で損益通算する
(3)(1)と(2)で控除できなければ、山林所得と損益通算する
(4)(3)でも控除できなければ、退職所得と損益通算する
(5)当年度の純損失、すなわち繰越損失額が確定する
確定申告によって還付金が受け取れる可能性も!
個人事業主は報酬を受け取る際、源泉徴収税額が差し引かれている場合が多いです。ただし、源泉徴収された税金には、所得控除や必要経費は含まれていません。そのため、報酬から源泉徴収された金額が本来納めなければならない税額よりも多い場合は、還付金として受け取れる場合があります。
ただし、還付を受けるためには、確定申告が必要です。還付金の申告は、過去5年間にさかのぼって請求できます。なお、源泉分離課税とされる所得は、受け取る時点で納税されているため確定申告の必要がなく、還付の対象にはならないので注意しましょう。
[PR]他のオーナーの成功事例を共有できる
赤字の場合に確定申告をしないとどうなる?
確定申告をすることによるメリットもあれば、確定申告をしないことによるデメリットも存在します。赤字の際に確定申告を行わないと、どのようなことが起きるのかを詳しく見ていきましょう。
ローンが組めない恐れがある
赤字でも確定申告を行なわないと、住宅ローンなどの各種ローンが組めなくなる恐れがあります。
ローンを組む際には所得の証明が必要ですが、個人事業主の場合は所得を証明する書類として、数年分の確定申告書の控の提出を求められることがあります。直近2期分・3期分の確定申告書の控えを求められるケースが多いです。しかし、赤字だからといって確定申告をしていないとその年の所得を証明できないため、ローンが組めなくなる可能性が高くなってしまうのです。
また、事業の融資を受ける際にも、同様の理由から融資を断られてしまうケースがあります。たとえ今すぐに困ることがなかったとしても、数年後に確定申告をしなかったことが痛手になるケースも考えられるでしょう。将来のためにも赤字か黒字かに関わらず、毎年確定申告をしたほうが無難です。
非課税証明書の発行ができない
確定申告を行なわないと、非課税証明書の発行ができません。非課税証明書とは、所得の状態や所得控除などにより、住民税が課せられてないことを証明する書類です。非課税証明書は、児童手当を申請する際や、公営住宅の使用料を減免する際など、あらゆる場面で必要になります。そのため、無申告だと自分だけではなく、子どもの生活にも影響を与えかねません。
なお、確定申告で所得税を申告すれば、住民税の申告も同時に行なわれます。所得税が発生しない場合は、住んでいる自治体に住民税だけを申告することも可能です。自身の所得や生活の状況を考慮したうえで、最適な方法を選びましょう。
国民健康保険料において不利な条件になる
個人事業主の場合、国民健康保険に加入し、保険料を支払う人が多いでしょう。国民保険料は所得金額を基準として決定されます。そのため、収入が少なかったり、無収入だったりする場合は、保険料の減額を受けられる場合があります。
しかし、確定申告をしていないと、自治体に所得に関する情報が届かないため、収入を公的に証明できません。そのため、保険料の軽減措置を受けられなくなってしまうのです。さらに、所得証明書が発行できないと、保険料に限らずさまざまな場面で不利になるケースがあるので注意しましょう。
赤字が続いた場合どうなる?
個人事業主の赤字が続いた場合、事業の運営や日常生活にも支障を来たすことが考えられます。金融機関からの融資が得られないために、ノンバンクのビジネスローンで資金を調達したり、個人事業主の資産を処分したりして運転資金を確保する事例もあるようです。
特に、国民年金保険料を納付できなければ老後の生活にも影響を及ぼすため、早めに保険料の免除申請を行なうことをおすすめします。申請にあたっては所得審査があるため、確定申告が済んでいることが前提です。前年度の所得に応じて4段階の免除割合が定められており、保険料の免除が認められた期間については次の割合で年金額に反映されます。
| 免除割合 | 年金への反映割合 |
|---|---|
| 全額 | 2分の1 |
| 4分の3 | 8分の5 |
| 半額 | 4分の3 |
| 4分の1 | 8分の7 |
ただし、世帯主の収入が高い場合には保険料の免除ではなく、保険料の納付猶予が承認されることがあります。この場合は、納付猶予を受けた月から10年以内に保険料を納めなければ、年金額が増えないので注意が必要です。
法人が赤字を繰り越した場合
法人が赤字を繰り越す場合、毎年欠かさず確定申告書(法人税申告書)を提出していれば最大10年間にわたって繰越欠損金として損金算入(会計上の費用計上)が認められます。繰越欠損金が発生した年度に青色申告を行なっていることが繰り越しの条件で、その後10年の中で白色申告の年があったとしても、継続して損金算入が可能です。
繰越欠損金とは、法人税の所得計算における赤字額のことで、個人事業主の「繰越損益」に相当するものです。中小企業や特定の法人以外の場合は控除限度額が設けられており、繰越控除前の所得額に、開始事業年度によって定められた率を掛けて限度額を算出します。
| 開始事業年度 | 限度額 |
|---|---|
| 平成24年4月1日~平成27年3月31日 | 100分の80 |
| 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 100分の65 |
| 平成28年4月1日~平成29年3月31日 | 100分の60 |
| 平成30年4月1日以降 | 100分の50 |
赤字でも確定申告をして節税しよう
納める所得税がない場合は、基本的に確定申告をする義務は発生しませんが、確定申告をすることで損益通算が認められたり、青色申告者の場合には特別控除が受けられたりと、節税につながるさまざまなメリットがあります。
反対に、確定申告をしなければ所得証明書(非課税証明書)の発行を受けられないだけでなく、国民健康保険料が正しく計算されないなどの不利益が生じる可能性があるので要注意です。新型コロナなどの不測の事態における特例を受ける際にも、確定申告書の控を求められる場合があります。事業が赤字だったとしても、忘れずに確定申告を行いましょう。
[PR]新着フランチャイズ