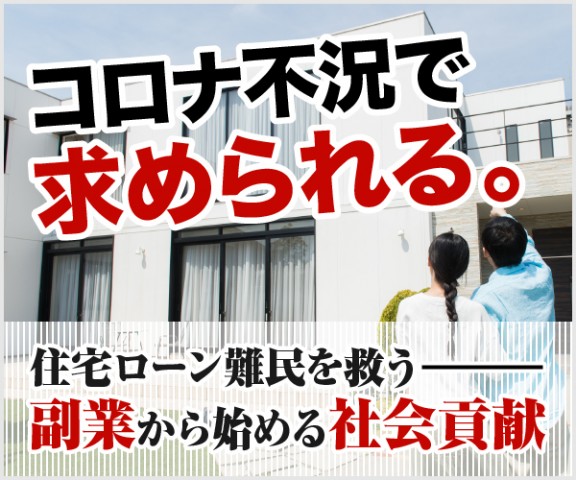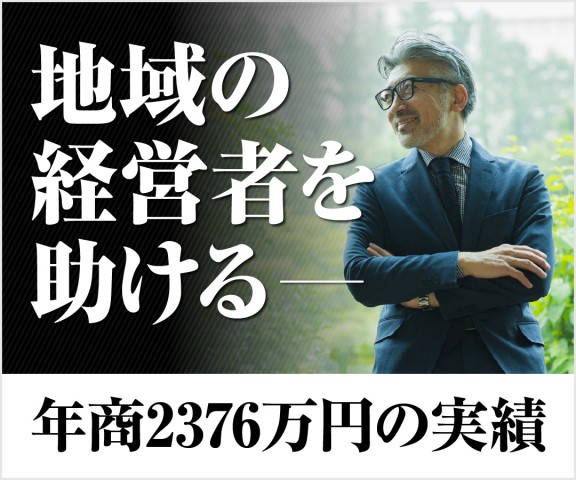民泊を開業するには?3つの運営形態や開業費用・アフターコロナの需要見込みを紹介

コロナ禍によってインバウンド需要が激減し、民泊業界も収益減など大きな影響を受けました。
一方、国内旅行分野ではワーケーションや「3密を避けた旅」といった新しい行動様式によって、民泊需要が回復する兆しもみられています。空き家を民泊として活用する動きも見られますが、民泊の運営にあたっては旅館・ホテルやシェアハウスとの違いを理解しておくことが重要です。
そこで今回は、民泊の運営形態や収益性、民泊事業の魅力を紹介します。
民泊とはどんなもの?

最初に、民泊とはどのようなものかを紹介していきます。民泊営業に関する規制や、利用客からみた民泊と旅館・ホテルとの違いについても確認しておきましょう。
民泊について
民泊とは、一戸建ての住宅やアパート・マンションといった共同住宅の一室を宿泊施設として、旅行客に有償で提供するサービスです。住人の善意で旅人を無償で泊める人もみられますが、現在では、宿泊施設の運営ビジネスの一つとして認知度が高まっています。近年では「エアビーアンドビー」など民泊の仲介サービスを通じて、国内・国外の観光客の利用も増加傾向です。
民泊ビジネスが始まった当初は、運営に関するルールが不明確だったこともあり、予約や決済などに関するトラブルが少なくありませんでした。宿泊客の出入りに伴う、近隣への騒音や衛生面での問題も明るみに出るなど、民泊に関する法的な規制を求める声も上がり出しました。
そのため、2018年6月からは「住宅宿泊事業法(民泊新法)」により、民泊を営業する前に行政機関への許可または届出が必要となりました。民泊の運営形態や営業する自治体によって必要な手続きが異なり、無許可で営業すると刑事罰の対象となっています。適正に民泊を運営するために、民泊の運営形態を十分に理解しておきましょう。
現在の民泊に関する規制
民泊新法の施行後は、民泊の運営方法が以下の3通りから選べるようになりました。
| 種類 | 営業日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 旅館民泊 | 制限なし | 管理スタッフの常駐が必要 |
| 特区民泊 | 制限なし | 2泊3日以上での提供が必要 |
| 新法民泊 | 年間180日以内 | 営業開始までの手続きが簡単 |
それぞれの運営形態の特徴を解説します。
手続きの簡単な新法民泊
新法民泊は、台所・トイレ・洗面所・風呂が備わっている住宅であれば都道府県知事等への届出だけで営業できるタイプの民泊です。営業できる日数が年間180日以内という制限はありますが、建築基準法上の用途変更が不要なので、民泊へ参入するハードルが低くなっています。また、工業専用地域以外の場所であれば、どの住宅でも営業が可能です。
家主には、宿泊者に対する騒音防止に関する説明や近隣住民からの苦情に対する適切な対応などが求められます。1軒の住宅で5部屋以上の宿泊室を設ける場合や、家主が同居しない住宅で民泊を運営する場合は、住宅宿泊管理業者へ管理業務の委託が必要です。
年間営業日数に制限のない旅館民泊
旅館民泊は、旅館業法の「簡易宿所営業」または「旅館・ホテル営業」の許可を管轄の保健所から得た上で運営するタイプの民泊です。アパートなどの共同住宅を活用した運営が想定されており「サテライト型民泊」と呼ばれることもあります。1年を通じて営業できるため、季節に応じた運営戦略を立てやすい点が民泊運営にとってはメリットです。
都市計画法で宿泊施設を営業できる場所が規制されている他、建築基準法で旅館・ホテルに用いる建物の構造などが細かく決められています。そのため、民泊の営業許可が取れる場所かどうかを開業計画段階で確認しておく必要があります。
外国人を対象とした特区民泊
特区民泊は、外国人旅行客の滞在に適した施設であれば都道府県知事の認定を受けて旅館業法の適用を受けずに営業できるタイプの民泊です。日本人旅行客の受け入れも可能ですが、最低でも2泊3日以上の旅程で宿泊申し込みを受ける必要があります。
新法民泊と同じようなスタイルで運営できる上、年間営業日数の制限も受けないため長期滞在の旅行客やビジネスユースを対象にした運営方法も考えられます。なお、2021年7月現在では次の自治体が特区の対象です。
・東京都大田区
・千葉市
・新潟市
・北九州市
・大阪府(大阪市・八尾市・寝屋川市を含む)
利用者にとっての民泊と旅館・ホテルとの違い
2018年の旅館業法改正によって、旅館・ホテル営業における最低客室数の基準や、ホテルに設ける洋室の構造設備の条件が撤廃されました。一定の条件を満たせばフロント(帳場)の設置も必須でなくなったため、民泊とホテル・旅館の違いはプライベート性の高さ程度にとどまってきています。そのため、今後は旅館・ホテル営業の許可を得た上で、通年で民泊事業に乗り出す個人事業主や法人が増える可能性もあります。
一方、宿泊客にとっては民泊を通じて観光先でも自宅に近い雰囲気を味わうことができ、ホテルや旅館に比べると敷居が低い印象をもたらすでしょう。民泊では宿主が同じ空間で生活していることもあるので、異文化のコミュニケーションをとりたいと考えている外国人観光客には非常に人気が高いといわれています。
また、自分が知らない国内の魅力を知りたいという日本人観光客にとっても、民泊は気軽に地方の特色や文化を知ることができる宿泊施設として注目されています。
民泊の開業にかかる費用と開業後の収益
民泊の開業にかかる費用は、内装工事やサービス提供用の設備・備品代だけで約300~350万円が目安です。民泊用の建物を賃貸契約する場合は、月額賃料の6~12ヶ月分の費用が別途かかります。3LDKの住宅で民泊を運営する場合を例に、必要な費用の内訳を簡単に紹介します。
リフォームをせずに現状のまま民泊運営を始める場合は、開業費用を抑えることができます。
・客室(6畳間3室)と浴室のリフォーム…約250万円
・布団8組…約25万円
・エアコン3台…約30万円
・客室内の設備(冷蔵庫やポットなど)…約20万円
物件の場所や築年数によって、家賃は大きく異なります。不動産業者によっては、賃貸契約時に退去時のハウスクリーニング代や鍵交換費などを請求される場合もあります。
・3LDKの一戸建て家賃…月10万円~20万円
・敷金…家賃の1~3ヶ月分
・礼金…家賃の1ヶ月分が目安
・仲介手数料…家賃の1ヶ月分が目安
・前家賃…最大で家賃の2ヶ月分
民泊の収益性は?
民泊の運営で得られる収益の大部分は宿泊料で、宿泊人数や稼働室数に応じて変動します。民泊予約を仲介するサイト「Airbnb」を使って予約した場合の、1泊あたりの宿泊料金(1名分)の相場を確認しておきましょう。
| 地域 | 1泊あたりの料金相場 |
|---|---|
| 東京23区 | 3,000円~15,000円 |
| 大阪市 | 2,500円~12,000円 |
| 那覇市 | 1,500円~12,000円 |
| 札幌市 | 2,000円~8,000円 |
民泊の運営で得られる利益は、稼働率が8割の場合だと売上の2~3割といわれています。運営にかかる経費としては水道光熱費や清掃料、予約仲介サイトへ支払う手数料が代表的です。客室が5室以上ある場合には、住宅宿泊管理業者への管理料も必要となってきます。ちなみに、Airbnbを利用した場合に民泊の運営者が支払う手数料は、宿泊客が支払う宿泊料の3%です。
収益アップを狙うには
客室やアメニティの質を高めるのが、民泊の収益アップを目指す第一歩です。例えば、内装の素材にこだわったり、グレードの高いアメニティを取り揃えたりすると他の民泊やホテル・旅館との差別化につながるでしょう。インターネット経由での集客が一般化しているため、客室・共用設備の写真や360度ビューを活用して、民泊の魅力もアピールしましょう。
ホテル業界で一般化している「レベニューマネジメント」の手法を用いて、周辺でのイベント開催日や週末・連休など集客見込みに応じて宿泊料を柔軟に設定するのも収益を高める方法の一つです。
[PR]物件取得費が抑えられる居抜き物件
民泊運営の注意点
住宅の面積の半分以上を民泊として活用する場合は、避難誘導灯や客室部分への自動火災報知設備などの防火設備の設置が必要です。カーテン・じゅうたんなど燃えやすい内装には、防炎性能を持つものか不燃・準不燃材料を用いたものを使う必要があります。
また、民泊の運営者には2ヶ月に1度、国土交通省の「民泊制度運営システム」を使って宿泊客の人数・国籍や滞在日数などの報告が義務づけられています。自治体によっては、定期的に運営状況や苦情対応に関する報告を求められる場合もあります。各種報告を怠ると、業務停止などの処分を受ける場合があるのでご注意ください。
どうしてインバウンド事業で民泊がねらい目になるか
民泊がどのようなものかはお分かりいただけたでしょうか? ここからは、なぜ民泊がインバウンド事業で狙いやすいのか、現在の情勢も踏まえてご紹介いたします。
アフターコロナのインバウンド需要の見込み

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、2020年の訪日外国人旅行者の数は激減し、インバウンド業界に大きな影響を与えています。
しかし、2020年8月に実施された政府系金融機関の日本政策投資銀行が公益財団法人日本交通公社とインターネットを通して実施したアンケートによると、新型コロナウイルス感染症が終息した後に海外旅行をしたいか、という問いに対し「そう思う」「どちらかといえばそう思う」が全体の82%を占めたことが分かりました。さらに、旅行したい国や地域の選択では、日本が46%でトップとなりました。その理由として、「買い物」「食事」「治安の良さ」などに加え、「清潔さ」が高く評価されているようです。
この結果から、コロナ禍が終息したあと、日本のインバウンド業界では更なる賑わいを取り戻す可能性は大いにあるでしょう。
宿泊施設不足の日本
日本政府は経済の発展を目指して、日本を観光立国にするという方針を掲げています。一方、コロナ禍の影響で宿泊施設の廃業が相次いでおり、インバンド需要を含め今後の観光需要が回復したとしても、宿泊施設の不足が懸念されます。そこで、日本の空き家や民家を宿泊施設として活用する方法が考えられています。
平成30年(2018年)住宅・土地統計調査(総務省)によると、国内にある住宅のうち約850万戸(全体の13.6%)が空き家状態となっています。この数値は過去最高になっており、今後もどんどん空き家問題は増えていくと考えられています。特に農村・漁村や山間部といった地方の空き家軒数が多いため、空き家を民泊として利用することで地方を活性化させる戦略を立てる自治体もみられます。あわせて、空き家を減らすことで地域の治安悪化を防ぐという狙いもあるようです。
シェアリングエコノミーの推進について

民泊の活用は、総務省が提唱する「シェアリングエコノミー」の取り組みとしても注目されています。簡単に言えば、自家用車の相乗り(ライドシェア)やレンタサイクルといった、資産を有効活用するシステムの一つです。自治体との協働によって地域のコミュニティを再構築する動きもみられます。
徳島県阿南市では、普段は民泊として営業する一方で災害時の避難所に活用する協定を結んでいる事例もみられます。観光客を迎えるだけでなく、地域の安全を確保する戦略がとられているのが特徴的です。一部の自治体ではスキルシェアによって観光体験プログラムを提供するなど、未来の発展に向けた取り組みも始まっています。
民泊事業に参入するなら、フランチャイズがおすすめ

旅館業法の緩和や民泊新法の施行によって、民泊を開業するハードルは下がりつつあります。しかし、既に民泊を運営している人も多く、開業にあたっては客室や共用部分の設備を充実させるなどの差別化が必須です。そのため、民泊に参入しようか悩んでいる人もいるのではないでしょうか。
これから民泊事業に参入しようと検討している人には、フランチャイズの活用もおすすめです。苦戦しがちな観光需要の予測や物件探しなどもフランチャイズ本部から手厚いサポートを受けられるので、スムーズな開業を目指せます。フランチャイズだけでなく、民泊に特化した開業支援サービスも多数あるので自分に合った形で民泊参入を目指してみてはいかがでしょうか。
[PR]ニッチビジネス特集
低リスク、低投資の民泊ビジネスでインバウンド需要に参入しよう

民泊はインバウンド需要だけでなく、国内旅行での宿泊先としても注目されています。空き家や普段使っていない部屋を、収益物件として有効活用する方法としても魅力的です。ホテルや旅館と比べて初期投資が少なめで、既存の住宅を活用する場合には自治体に届け出た後に運営をスタートできます。そのため、新規参入のリスクが低い点もメリットといえます。
開業支援サービスを活用したりフランチャイズチェーンに加盟したりして、サポートを受けながら参入に成功している事例も少なくありません。コロナ禍が過ぎた後の観光需要拡大を見据えて、民泊事業下の参入を考えてみてはいかがでしょうか。
民泊開業についてのよくある質問
民泊開業に関するよくある質問を紹介します。
簡易宿所と民泊とはどう違うのですか?
簡易宿所は通年での営業が可能ですが、都市計画法で定める商業地域や第1種・第2種住居地域などに設置場所が限定されます。一方、民泊は工業専用地域以外ならどこでも営業可能ですが、年間の営業可能日数は180日以内となります。接客設備については、簡易宿所・民泊とも大きな差はありません。
仕事で日中不在となってもいいのですか?
家主の不在時間が2時間を超える場合は、住宅宿泊管理業者への管理委託や非常用照明設備の設置が必須です。住宅宿泊事業者として登録していない家族による留守番は認められていません。住宅宿泊管理業者のリストは国土交通省ホームページに掲載されているので、参考にしてみてください。
宿泊者の人数の制限はありますか?
施設の規模によって宿泊者の人数制限は設けられていませんが、宿泊客が占有できるスペースとして1名あたり3.3平方メートル(1坪)以上の確保が必要です。6畳間だと定員3名まで、10畳間だと定員5名までとなります。宿泊客の占有スペースには、廊下やトイレ・洗面所などの共用部は含まれません。
消防用設備はどうすればいいのですか?
客室や共用部に煙感知器または熱感知器を設置した上で、自動火災報知設備と連動させる必要があります。客室や共用部から20メートル以内の位置に消火器の設置も必要です。宿泊客が見やすい位置に避難経路図を設ける他、2階以上には非常用照明装置の設置も必要となります。
[PR]新着フランチャイズ