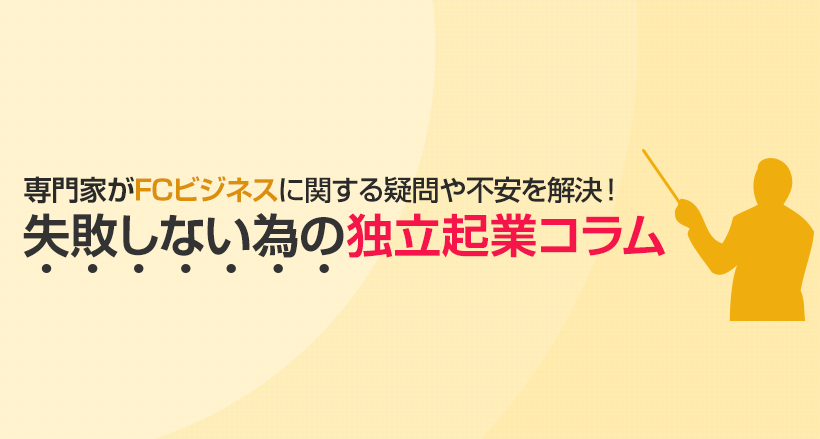|
2016-02-09 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム
株式会社フォーナレッジ 代表取締役
加藤 綱義 |
M&Aのタイミングとフランチャイズ×M&Aを活用した企業の事例

このコラムのポイント
フランチャイズ業界では、コンビニや塾、飲食業界などでM&Aをしているフランチャイズ本部が見受けられます。そもそも、こうしたM&Aとはいくらで?、どのようなタイミングでM&Aが為されるのか?ということに着目してください。また、執筆者である加藤綱義が在籍していたジー・コミュニケーションという企業(フランチャイズ+M&A活用)の事例にもご注目を。
フランチャイズWEBリポート編集部
M&Aのタイミングは?自社はいくらで売れるのか?計算法を紹介
前回はM&Aの概要と後継者不在問題について書かせて頂きましたが、フランチャイズのコラムにも関わらず、ほとんどフランチャイズのことにふれていないと一部の方(決して編集当局ではありません)からお叱り?を受けました。
性懲りもなく、もう少しM&Aの概要的なことを触れながら、フランチャイズに絡めていければと思います。
この仕事(M&A関連のコンサルタント)をしていると知人経営者からよく頂く質問は二つ。
「自分の会社はいくらで売れるか?=企業評価」「いつ売れば良いか?=タイミング」です。
まず、企業評価(バリュエーション)の方法ですが、DCF(ディスカウントキャッシュフロー)法があります。
この手の教科書には「将来、会社が稼ぐであろうキャッシュフローを現在価値に割引計算して算定」と書いてあります。この方法は、将来生む利益(キャッシュフロー)の見積もり、いわゆる事業計画を使って算出されます。
つまり、恣意的なものが入りやすく、数字の信ぴょう性は買主側でしっかり精査が必要です。ただし、足元の売上がなく先行投資が多いベンチャー的な業種には必要な方法です。

現在、一番使われているのが「時価純資産額+のれん代」で算出する方法だと思います。
時価純資産額は清算価値で、のれん代は、EBITDA(税引前利益+特別損益+支払利息+減価償却費を加算した値)が本来ですが、M&Aでは、ざっくり営業利益+減価償却費+M&A後に不要となるオーナー報酬・経費で使われることが多く、ここではその意味で使います)の3~5倍を加算します。
株式譲渡価額の算出
(例)時価純資産5000万円、営業利益3000万円、オーナー報酬1500万円、節税対策1000万円、減価償却費500万円の場合
株式評価額(企業価値)
5000万円+(3000万円+1500万円+1000万円+500万円)×5倍
= 3億5000万円
EBITDAの3~5倍は、あくまでも全業種の目安です。
つまり、売主は5倍で売りたいし、買主は3倍で買うことができればお値打ちということです。
実際に私が株式会社ジー・コミュニケーション(以下、ジーコム)時代に経験した飲食M&Aは概ねこの枠内に収まっていたと思います。しかし、業種や状況によってはこの枠外で評価されることがあります。
飲食店関連のM&A事情と判断方法で気をつけるべきポイント
特に、最近の飲食においては、1倍から3倍ぐらいが実感です。私がこの4年間で成約した21件のM&Aの内、11件が飲食でしたが概ね1倍から3倍で取引されています。
飲食は将来の成長性・安定性が読みにくいということもありますが、飲食の買主は同じ飲食業界の場合も多く、人材の採用及び労務問題等で自らの業界を悲観し評価を下げている(慎重になっている)とも言えます。
逆に、直営店しかなくても、その業態がフランチャイズ展開できるようなものであれば、M&A後の収益の伸びが大きく期待できます。このような場合には、5倍を超える評価がつくかもしれません。

最後にジーコムの時に判断基準の一つにしていた方法を紹介します。
飲食10店舗を運営する会社(事業)が売却希望価額1億円だったとします。
つまり、1店舗あたり1000万円です。これを高いとみるか安いとみるか。
シンプルですが、経営者・人材・業態・立地・物件・収益性・将来性などを総合的に判断します。正直、飲食に関してはこの方法が正しいのではないかと感じています。
先述したEBITDAの方法は数字だけをみて誰でも評価できるものです。言い方を変えれば、事業そのものを見ていません。M&Aを数字だけで扱うことは極めて危険です。特に、中小零細企業は、経営者含めた人材そのものが事業であり価値であることが多いことを理解しておく必要があります。
売却時のタイミング=業績が右肩上がり時(経営悪化してからでは遅い)
次に、「いつ売れば良いか?=タイミング」です。前回で後継者不在問題を解決するためのM&A(事業承継)のことを書かせていただきました。後継者不在に迫られて焦って売却することが良くないことは誰でも分かります。
これは後継者不在を理由としないM&Aでも同様です。
譲渡(売却)の理由には、将来への不安、選択と集中(本業回帰、不採算事業の清算等)、事業発展、大手傘下での安定した経営、ハッピーリタイア、新規事業への参入・挑戦などがあります。多種多様な時代の変化に耐えうるだけの体力が大企業のようにない中小零細企業の経営者は、いつも将来への不安を抱えています。

かつて、事業拡大の一環で新規事業として加盟したフランチャイズ事業を売却したり、大手傘下に入ることで経営の安定化を図ろうとします。創業者利益(売却益)を得てのハッピーリタイアや、それを元手に新規事業に挑戦できるのはとても幸せなM&Aの形です。
それでは、いつ売るかのが一番良いか?売るタイミングは少なくとも経営が悪化してからでは遅いです。高く売るという観点だけで言えば、黒字の時であり、それも最高利益をたたき出す手前が一番評価されやすいです。しかし、利益のピークに何時なるかは神のみぞ知るです。そのため、少なくとも業績が右肩上がりの内に売却をするのがセオリーとなります。
買収側の企業がM&Aをする理由は「リスク軽減」と「事業構築時間の短縮」
一方で譲受(買収)をする側の企業のねらいは、既存の経営資源(人材・物件・技術・ノウハウ・販路・顧客・仕入先等)の獲得、スピーディーな事業拡大、規模拡大による安定などです。つまり、自ら新規事業を立ち上げるよりも時間を短縮し、リスクを軽減するためにM&Aを使います。
これは、フラインチャイズに加盟する理由によく似ています。昨年11月2日にフランチャイズWEBリポートで掲載されたコラムにて、筆者の川上健一郎氏がフランチャイズに加盟する加盟希望者側のメリットとして下記を挙げております。
1.直営店でビジネスモデルが検証されている
2.システム、マニュアル等が整備されている
3.商品開発等もブラッシュアップされている
4.他店舗での成功事例などの情報がある
5.時代の変化に対応しやすい
このままM&Aをするメリットと言い変えても良いです。
決定的な違いを言えば、フランチャイズに加盟することはあくまでも加盟店(ジー)になるだけです。M&Aの場合は、自らがいきなりフランチャイズ本部(ザー)になる可能性を秘めています。これがM&A(買収)の醍醐味です。
フランチャイズとM&Aを活用したジー・コミュニケーションの成功事例
フランチャイズとM&Aは共通点があることはご理解いただけたと思います。この二つを活用してジーコムグループは、2000拠点を超えるまで発展しました。その発展の過程を少し具体的に説明したいと思います。
ジーコムは稲吉正樹氏(現NOVAホールディングス代表取締役)が1994年に創業。愛知県岡崎市に「かんばる学園」というオリジナルの個別指導塾を起業したのがきっかけです。
創業当初は生徒がなかなか集まりませんでしたが、教室の周辺の草取り・清掃はもちろん、生徒がいないのに電気を煌々とつけたり、自転車を買って並べたりする等の努力をしながら、敢えて2校舎目、3校舎目と立て続けに開校したと聞いております。
その勢い・積極性が功を奏して生徒が増えアルバイト講師も増え、更に、そのアルバイト講師の何人かからのれん分けの希望があり、フランチャイズ展開が始まりました。

ジーコムの外食事業も岡崎市周辺に学習塾が増えていき、業務終了後にスタッフとのミーティングを兼ねた会食が多くなり、いっそ自社の飲食店を持った方が都合が良いとしてオープンしたのが「高粋舎(はいからや)」で、2000年のこと。その高粋舎も個室感と創作料理が受け、大繁盛しました。
そして、評判を聞いた学習塾のフランチャイズオーナーの多くが加盟して多店舗展開が進みました。
このように、ジーコムのフランチャイズビジネスは、当初からフランチャイズ展開を目的としてできた訳ではなく、自然発生的にできたものです。
フランチャイズ本部に必要な3つのポイント(黒川孝雄氏説より)
当時はジーコム監査役になって頂いていたフランチャイズの専門家、黒川孝雄氏にフランチャイズ本部に必要な3つの要件を教えて頂いたことがあります。
1.ブランド
2.ノウハウ
3.SV(スーパーバイジング、継続的な経営指導)
ただ、この3つの要件よりも重要というか当たり前のこととして、“直営店が儲かっていること”、が絶対条件と力強く仰っていたことを今でも鮮明に覚えております。昔も今も直営店の実績もままならないのに、加盟金欲しさに安易にフランチャイズ本部を立ち上げる例はなくなりません。
この点、ジーコムのフランチャイズビジネスの成り立ちは極めて理にかなっており、加盟店の増加とともに制度も組織も整備されていきました。
そして、このことこそが、M&Aで傘下に加わった事業の再生及び業績の改善に大きく関わっていくことになりますが、何とか今回の必要な文字数を超えたので次回とさせて頂ければ幸甚です。