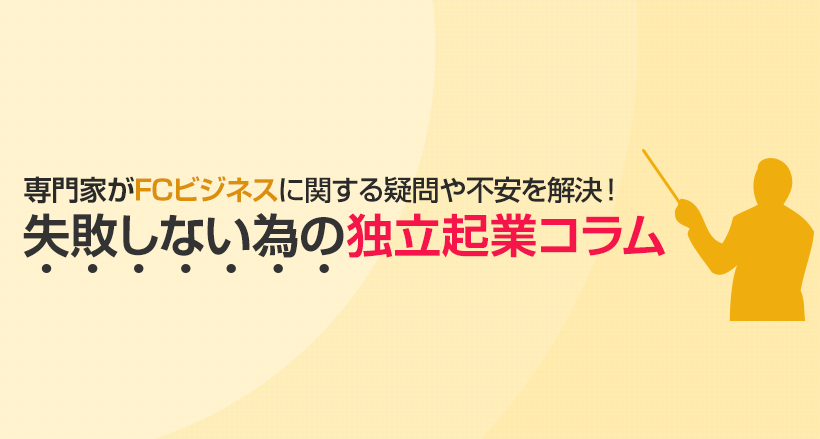|
2016-03-14 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム
合資会社マネジメント・ブレイン・アソシエイツ 代表
中土井 鉄信 |
塾経営の年収を変える!?授業料設定でおさえておきたい計算方法と授業回数への意識

このコラムのポイント
学習塾オーナーの収入源とは生徒の月謝、授業料です。 授業料の設定方法としては、講師に払う人件費や生徒1人あたりの負担額を加味する必要があります。そこで授業料を決めていくのですが、月の授業回数をどうするかでオーナーの収入にも関わってくるのです。 ここではそんな「授業料設定」のポイントについて解説します。
フランチャイズWEBリポート編集部
学習塾経営における「授業料設定」の仕方とは?
前回は、授業料における相場観でしたが、今回は更に細かく掘り下げ、授業料の設定についてお伝えしたいと思います。
講師人件費から割り出す
まず、授業料の設定は講師人件費から設定していきます。
たとえば、講師時給が1,200円であれば、この時給が、売上げに対して何%の経費比率でよいのかを考えて作ります。個別指導塾における講師人件費比率は、30%が最大ですから、この数値を利用して計算をすると以下のようになります。
講師人件費比率を30%に設定の場合の1時間あたりの売上げ
1,200円÷30%=4,000円
これが1コマ1時間あたりの売上げです。この4,000円を一人の講師が売り上げてくれれば、その講師の人件費比率は、30%になります。90分であれば、4,000円×1.5=6,000円。
逆に50分ですと、4,000円×50/60=3,333円となります。
生徒1人あたりの負担を考える
次に生徒1人の負担額を考えます。
先生1人が何人の生徒を指導するかで、生徒1人当たりの負担額が決定されます。
たとえば、1コマ90分として、生徒2人であれば、6,000円÷2人=3,000円になります(実際の設計の際は、2人では割りませんが、今はそうしておきます)。
60分では、2,000円。50分であれば、1,667円ということになります。
この1コマあたりの負担額に月の授業回数をかけたものが月謝です。
人件費率をおさえれば授業料も下がる実例
下の表は、時給を1,200円に固定し、人件費率を細かく変え、指導人数も変えた時の一人あたりの授業料単価(60分)を表したものです。
※指導生徒数が2人以上の場合は、組み率が完全にならない場合もあるので、組み率を90%前後で本来は計算します。下の表は、便宜上90%で計算を行っています。
| 生徒数\人件費率 | 人件費率 15% |
人件費率 20% |
人件費率 25% |
人件費率 30% |
人件費率 35% |
| 1人 | 8,000円 | 6,000円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,429円 |
| 2人(1.8人) | 4,444円 | 3,333円 | 2,667円 | 2,222円 | 1,905円 |
| 3人(2.7人) | 2,963円 | 2,222円 | 1,778円 | 1,481円 | 1,270円 |
| 4人(3.6人) | 2,222円 | 1,667円 | 1,333円 | 1,111円 | 953円 |
この表から分かるように、人件費率を上げ利益率を抑え、指導人数を増やすと授業料もどんどん下がっていきます。
月の授業回数で年間の売上に差が出ることを意識すること
最後に、月の授業回数(週)を設定します。これは、年間の授業回数(週)から考えるのが筋です。通常の授業と季節講習の授業が行われるのが学習塾ですから、年間の授業回数(週)から考えます。
従来の個別指導では、季節講習という考え方が乏しかった為、年間授業回数(週)が48回(週)になっていました。年間の授業回数(週)が48回(週)であれば、毎月4回(週)の授業をすることになります。授業料も1回当たりの料金に月の授業数をかけたものになります。
1回の授業料×月の授業回数=授業料
月の授業回数(週)は、4回(週)のところが多いようですが、私どもマネジメント・ブレイン・アソシエイツでは、授業回数(週)を年間42回(週)という授業設計を考案しています。
月に直せば、授業回数(週)は、月平均3.5回(週)で通常授業を行います。授業回数は、納得性があれば、4回(週)でなくても良いのです。ぜひ、色々と考えてください。
ちなみに、月4回と月平均3.5回は、小さな差ですが、実は、非常に大きな差を生みます。年間の売上が大幅に変わってきます。

次回は、連載の最終回として、この小さな差が大きな差になることを説明します。経営は、小さな差から大きな結果が生まれるものです。こういう差の意味を知れば、塾経営も実に面白いものです。