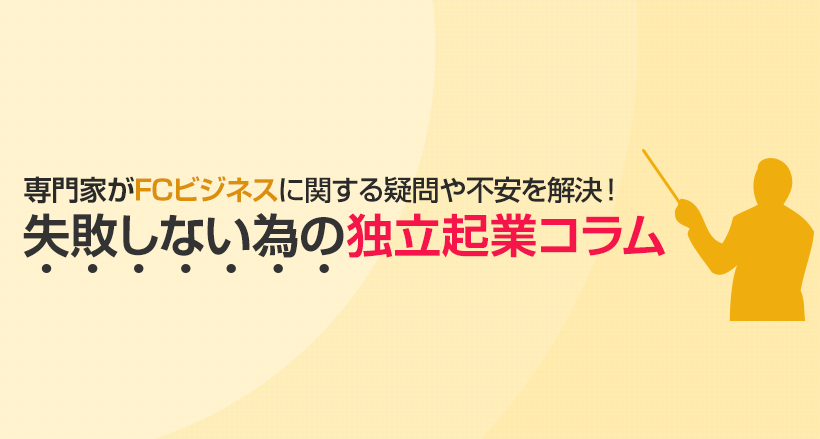|
2016-03-19 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム
コンビニ研究家
田矢 信二 |
「1冊のノート」でスタッフは変わる!元大手コンビニ店長が実践した秘策とは

このコラムのポイント
人手不足といわれるコンビニ業界。今ある人材を最大限戦力化することで、この問題も解決することができるのです。店舗経営者ひとりで悩むのでなく、当事者意識の強いスタッフを育てる。これによって店長やオーナーの負担も楽になり、体力的に無理なく働けることでしょう。 今回はそのために有効な「1冊のノート」を活用する意義と人材育成のコツについて、コンビニ研究家で元大手コンビニ店長をつとめた田矢信二氏に解説いただきました。
フランチャイズWEBリポート編集部
人材配置のミスマッチは、コミュニケーションの希薄化で生まれている!
店舗経営者の皆様。店舗運営のため、働いてくれているスタッフは千差万別、それぞれ得意分野が違うものです。誰にでも同じ仕事を振っていいものではないということをまず肝に免じておいてください。
私がコンビニ研究家として販売スタッフの育成に携わる時、店舗経営者がしばしば、スタッフの素質を理解せずに役割を与えている場面を目にすることがあります。。例えば「売ることが得意なタイプ」なのか「人を育てることが得意なタイプ」なのかという見極めです。
店舗ビジネスやコンビニなどの接客業では、ローテーション勤務(シフト制)のために、経営者や店長とスタッフ間のコミュニケーションが希薄であることが原因といえます。時間的余裕も持てていないといった理由もあるのでしょうが。
人材育成・配置に有効な「ノート活用」という手段
商売を通じた適材適所が「可視化するノート」でスタッフの成長レベルを把握
先にあげたようなコミュニケーションの希薄化によって生じた人材配置のミスマッチ―これを解決するのにいい方法をご紹介します。
日々の対面コミュニケーションを効率よくするため、ノートを活用することです。
店舗で一冊の大学ノートを用意し、全員で業務の振り返りや伝達事項を記入しながら情報共有を行うというシンプルなものです。たかがノートですが現場の「成功事例・失敗事例」を全員で積み重なることにより、やがて自社らしい生きたマニュアルになります。
ノートを定着させるポイントは、まず新入社員やアルバイトに感想文など簡単な内容の記入を徹底し、先輩スタッフがフォローするという流れをつくることです。
スタッフたちの日々の成長を捉えやすく、接し方が分かり、理念に沿った育成が可能になります。さらにはテーマやスローガンなどを設定し、スタッフに仮説⇒実施⇒検証の考え方が身に付くよう、書く習慣で促すことです。
店舗スタッフがノートを書き続け“最強チームのメンバー”になる
スタッフによって「売れる人」なのか「育成できる人」なのかがおのずと見えてくると、戦力を適材適所に投入でき、長所を見つけほめる育成が可能になります。あるコンビニエンスストアで時間帯毎に売れる人を育成した結果、おでんの販売は300個を30日連続で売上げ、昨年比1000%と以上にもなりました。
また育成できる人は「人」の心理を捉えやすい傾向があるため、予約活動で貢献してくれます。恵方巻き寿司の予約では、前年50本程度から500本以上を獲得したケースなどもありました。
いずれも、単品での地域一番化が実現できたのです。ノートの活用によって全員が商売意識を持つようになり、フォロー体制もできますから、現場で頻繁に起こる「言った言わない」「知らない」といった悪い現象がなくなります。
そして新入社員・アルバイトを巻き込んだ、売上に直結するチームを作り上げます。顧客満足や良いお店の雰囲気はデジタルの中では生まれません。IT・スマホの効率化追求時代の今こそ、アナログな手法で商売人を育てるべきなんです。

アルバイトに仕事を任せる方法は「仮説検証」と「見える化」
ただ作業をするのでない「考える」スタッフを育成し他社と差別化
ここで、人材採用への意識についてもお話ししておこうと思います。
大手企業に比べて資金も採用人数も少ないのに、同じような採用方法、求人広告を打ち出しても、大手企業に優秀な人材を確保されてしまいます。採用難時代に、大切なのは既存戦力での地域一番化なのです。
一般的なサービス業では、パート・アルバイトは作業に集中して時給をもらうことが多いでしょう。この考えはある意味で正しいと思います。
しかし同じ時給800円でも、時間単価で「作業」をするスタッフと、自分で「答え」を出して「仕事」をするスタッフでは、その後のお店の差別化という点で圧倒的に違ってきます。結論からいえば、学生や主婦のスタッフに業務をまかせる組織風土があるお店は強いのです。
スタッフに「もし私がお客なら」の視点を仮説・検証の上、可視化させる
ではどのようにスタッフを戦力化すればよいでしょう。例えばコンビニエンスストアでは、明日はどんな商品が売れ筋になりそうか、スタッフに「仮説」を立ててもらい、発注まで任せます。
そうすると翌日、実際に発注した商品が売れたかどうかが気になるものです。そこで販売結果をデータでチェックします。これが「検証」になります。このように毎日の仮説・検証をノートに書いて、全店で可視化するのです。
同時に、お客様の立場でどんな対応をしてもらえると嬉しいかを考えることを促し、アイデアが出るように仕掛けをします。仮説というと一見むずかしい言葉に感じますが、「もし自分がお客様だったら・・・」という視点は、誰でも持っています。
学生や主婦のスタッフでも、仮説ができるようになれば従来の発想に疑問を持つようになり、お店の現状のメリット・デメリットを顧客視点で考えることができるようになるのです。一方、単に作業をするスタッフは、その作業に何も疑問を持ちません。
スタッフに顧客視点を持たせることでお店は変わる!
このように、目線を変えて仕事をすることができるようになると、学生や主婦のスタッフも自己成長し、新人スタッフの中からでもすぐに輝ける居場所を見つけることができるのです。今日から「パート・アルバイトは決められた時間、決められた作業をしてもらうのが当たり前」という考え方を、育成する側は忘れていただきたいと思います。

スタッフ戦力化には「当事者意識」と「ほめられる経験」が効く
3か月で商売を語り始める「アルバイト学生・パート主婦」にするための劇的作戦
店長ひとりでお店を運営していては、必ず限界がやってきます。人材採用が難しい今、スタッフを認める環境をつくることで経営参加意識を高め、どう戦力化するかということに商売思考をシフトさせるべきなのです。
売れる仮説を立て、発注した商品の販売結果を検証することを繰り返すと、失敗もあれば成功もします。ポイントは自分のためではなく、お店・お客様視点で考えた発注なのかどうかの見極めです。
曖昧な考えの場合は私もコンビニのプロとして経営者様に厳しく注意していますが、そこに感情論は必要ありません。データと仮説が基本となります。
このようにして取り組むと、3か月もたてば、学生でも主婦でも商売、経営について自分なりの意見を話せるようになります。そのときこそが、育成の最大のチャンスです。
パート・アルバイトが戦力になるのは「ほめられる経験」をしたとき
「当事者意識」が芽生えているため、そのスタッフの強みの部分のみを見てほめるように心がけます。このときに絶対にやってはいけないのは、怒る行為と「まだまだ」というマイナス発言です。
指導者が気づいていないこのようなマイナス発言は、スタッフの成長を促したい指導者によくありがちですが、むしろ逆効果で、成長を止めてしまいます。「ありがとう」「がんばってね」とひと声添えて、ほめてあげてください。
ほめられた経験をしたスタッフから良い風土が新しいスタッフへとつながり、自己成長意欲の高い組織が継続していきます。仮に、あまりモチベーションの上がらないスタッフや、一見ほめる要素がないように思うスタッフには、例えばイベントや催事企画のリーダーや清掃・整理作業のリーダーを任せると、ほめる要素が見つかってきます。
スタッフを育てるためにはメンバーの目線に立ち、彼らの考え方や情報を読み解く力を備えたいものです。それだけで、どんな高額なノウハウよりも貴重な、お客様から自社に直結した売上情報が現場から手に入るのです。