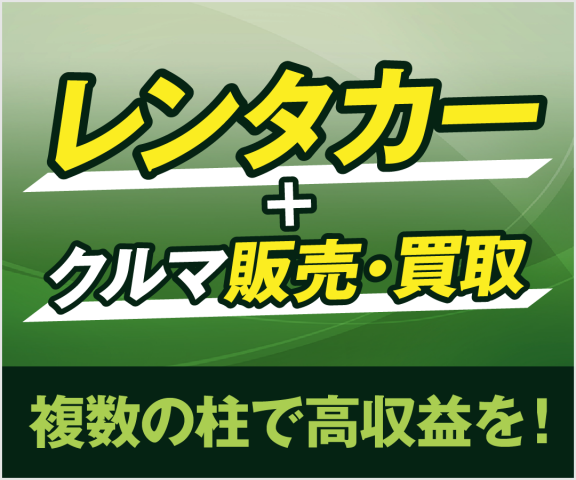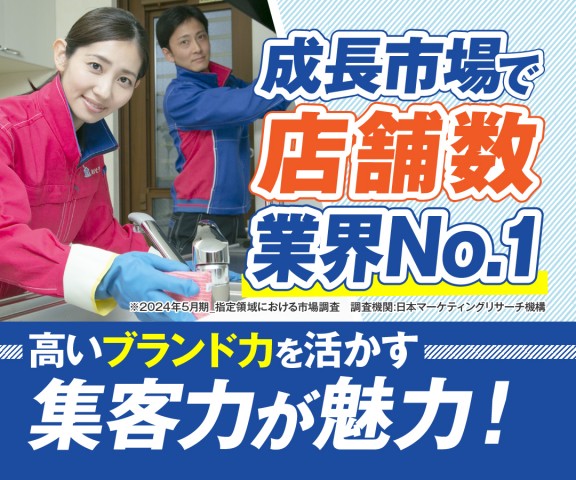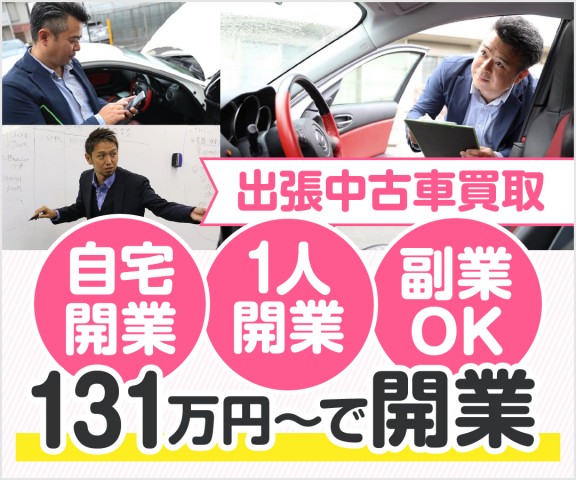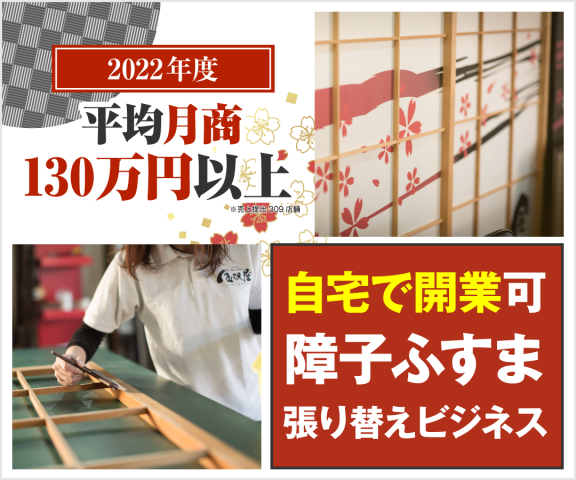開業10年後の生存率は?独立成功に向けた目標設定や資金調達方法を解説

副業解禁の流れや起業支援制度の充実などもあり、独立開業しやすい環境が整ってきています。税務署に開業届を出すだけで簡単に個人事業主として新たなスタートを切れますが、自分の夢を叶えるチャンスを最大限に活かすには念入りな開業計画が欠かせません。 そこで今回は、独立開業に成功して最低10年は生き残るために必要な目標設定や、資金調達など独立前後の動き方について事例を含めて解説していきます。
どうすれば開業できる?開業する際に必要なこととは
独立しようと思い立ったら、所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出すれば、その瞬間から個人事業主として開業が可能です。独立開業すると、事業者として国税である所得税や地方税である住民税、事業規模によっては自治体へ個人事業税や固定資産税(償却資産分)の納税義務が生じます。
課税売上高が1,000万円を超える場合は消費税の納税義務も生じますが「消費税課税事業者届出書」の提出は、事業が軌道に乗ってからでも差し支えありません。また、せっかく税務署に出向くのなら「所得税の青色申告承認申請書」も一緒に提出しておきましょう。白色申告と比較して認められる経費の幅が広がるなど、青色申告は節税対策に有効だからです。
また、店舗型の事業を開業するにあたっては資金調達や物件探しをはじめ、内装・外装の工事、人材の採用、店舗の宣伝などが必要となってきます。初期費用の調達や立地などのリサーチ、店のコンセプトを考えるなど、開業にあたってやるべきことは盛りだくさんです。
[PR]副業からスタート
開業自体は簡単!事業を続け成長させられるかどうかが重要
開業そのものは開業届を1枚提出するだけで完了するので、誰でも簡単にできます。しかし、独立開業においては「事業を拡大していかに成長し続けられるか」が重要な課題です。個人事業所の生存率は創業1年後で62.3%、5年後で25.6%、10年後で11.6%と年数が経つほど数が減っているのが現実です。事業を存続させることがいかに難しいのかが、数値上でも理解できます。(中小企業白書2006年版第1-2-21図開業年次別 事業所の経過年数別生存率より算出)
生存率の求め方は、前年の生存企業数にその年の生存率をどんどんかけあわせていくことで算出可能です。たとえば、1年後の生存率なら「1×1年次の生存率」ですが、5年後の場合は「1×1年次の生存率×2年次の生存率×3年次の生存率×4年次の生存率×5年次の生存率」となります。経過年数別生存率は、1〜5年目でそれぞれ「0.623」「0.759」「0.795」「0.813」「0.838」です。これらをすべてかけると0.256となり、5年後の生存率が25.6%とわかります。
開業1年目で廃業を余儀なくされる個人事業主が約4割に上るため、事業を続けていくにはまず明確な目標を立て、日々の努力や変化をし続けることが大事な要素です。生存率に関する最近のデータも確認してみましょう。
起業後の国際比較
2017年版中小企業白書(中小企業庁)によると、日本では開業5年経過後の生存率が81.7%です。アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスでは半数以上の企業が撤退しているのと比較すると、日本の企業生存率の高さが際立っています。一方、諸外国と比べると日本では開業コストが高いため、慎重なプロセスを踏んで起業した結果、多くの企業が何らかの形で生き残りを果たしているという見方も可能です。
なお、中小企業庁のデータは帝国データバンクに収録された情報を基にしていることから、実際の生存率は多少前後する可能性があります。
中小企業庁の起業・廃業の数値から
また、国内企業における2017年度の開業率は4.4%・廃業率は3.5%と諸外国より低い水準です。日本では、勇気を持って開業に踏み切れば高い割合で生き残れる状況にあると考えられます。
また、国内の開業率は雇用保険の適用事業所数、すなわち従業員を雇う意思のある企業をベースに集計されています。保険の加入手続きを取って真剣に起業したと考えれば、廃業率の低さもうなずけます。では、真剣に起業するとはどのようなことなのでしょうか。
開業で成功するために、事業を始める目的を明確に!

開業において重要なのは、自分がその事業を行ないたい目的を設定することです。目的が明確になっていれば、事業展開に向けた目標設定をスムーズにできるだけでなく、事業の方向性に迷ったときに経営方針を決める指針にもなります。目的を決めるうえで何が大切かを再確認しておきましょう。
自分のやりたい仕事を実現する目的で独立
自分のやりたい仕事をするために独立する人が少なくありません。こちらを事業の目的にする人の場合は「自分のやりたいことを今いる会社では実現できない」「独立して会社のルールにとらわれずに仕事がしたい」という動機が強い傾向が見られます。具体的にどのようなことをやりたいのか明確にすることが、開業を成功させるためのポイントです。
もしも独立の動機が、「今の会社はノルマがきついから嫌だ」というような現状から逃れることが目的なら、消去法でやりたくないことを消していきましょう。自分が心の底からやりたいと思えるところへ行き着くまで、消去法を繰り返しながら目的を見つけるのも成功を目指す一つの方法です。
ただし、ネガティブな理由を回避するのだけが目的だと、モチベーションが上がらず事業をやる意味を見失う恐れもあるので注意が必要です。
お金を稼ぐことを目的として独立
独立する理由に「お金を稼ぐこと」を挙げる人もいるでしょう。一見ネガティブな意味にとらえられがちですが、立派な目的の一つです。お金を稼ぐためには、どの事業を行えば効率が良いかを考えるようにしましょう。
不動産経営のように少ない労働で所得を得られる事業を始める場合も、少なからず勉強や調査が必要となります。どのような方法であれお金を得るのはそう簡単ではないため、地道に努力できないと事業を長続きできない可能性が高いです。「今年までに資格を取る」というように目標に期限を設けると、より努力しやすい状況を作ることができます。
[PR]法人の多角化に最適
開業する前に確認!目標設定をするうえでの注意点
目標設定をするうえでは、知っておきたい注意点があります。誤った目標を持ってしまわないように、気をつけるべきポイントを確認していきましょう。
生存率の高い業種を選ぶ方法もアリ
「絶対にこの業種」というこだわりがないのであれば、比較的生存率の高い業種で起業するのも賢い選択です。
2020年度小規模企業白書(中小企業庁)のデータでは、「電気・ガス・熱供給・水道業」と「運輸業・郵便業・情報通信業」の企業数が増加しています。しかし、許認可などの関係から運輸業・情報通信業を除いて個人事業主の参入は困難と言わざるを得ません。
一方「金融業・保険業」と「その他サービス業等」は廃業率が比較的低いので、これらに属する業種を選択する道もあります。生存率が低めの業種でも、独立開業した人の頑張り次第で長期にわたって事業を継続しているケースも少なくありません。市場の動向なども踏まえつつ、自分に合った業種で独立を目指しましょう。
経営理念に関する目標や売上目標
やりたい仕事を決めると同時に、経営理念を定めることを忘れてはいけません。
経営理念とは事業の存在意義を明文化したもので、経営の方向性を示すコンパスのようなものです。コンパスが狂うと誤った方向に舵を切ってしまう、すなわち経営が迷走してしまう恐れがあるため、経営理念を明確化しておくのが企業の生き残りにおける必須項目です。また、経営理念が明確であれば経営者と従業員が同じ価値観を共有して事業を推進できるようにもなります。
取引先や顧客にとっても企業像をイメージづける効果があるため、経営理念には大きな意味があるのです。有名企業の経営理念をいくつか見てみましょう。
・全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること(京セラ株式会社)
・「人と地球の健康」への願いを実現する(株式会社島津製作所)
・住まいの豊かさを世界の人々に提供する(株式会社ニトリ)
各社ならではの思いが込められていることがわかります。こうあるべきだという縛りはありませんが、大切にしたい言葉を簡潔につなげるのが経営理念を形作るポイントの一つです。さらに適切な売上目標を設定して、達成に向けて取り組むことも重要です。立派な理念を掲げたとしても、内実が伴っていなければビジネスとして成功とはいえません。高すぎない、しかし低すぎない数字を見極めることも、経営者として求められる能力の一つなのです。
目標設定の次に!具体的な計画を立てて生存率をアップさせよう
企業が廃業する3つの理由
企業が廃業を余儀なくされる最大の原因は、売上の低迷です。優れた商品・サービスを取り揃えていても、顧客に選ばれなければ売上が立たず事業を継続できなくなります。ある程度の売上を確保できていても、支出をはじめとする事業の状態を把握できていなければ、資金繰りが苦しくなって廃業に至ってしまいます。黒字経営でも運転資金不足によって廃業に追い込まれる事例もあるため、十分な現金を確保しておくことも企業が生き残る上では大切です。
事業の存続に必要な営業利益を割り出す
独立の目的や経営理念が明確になったら、具体的な数値目標を設定しましょう。数値目標の設定にあたっては、最低でも確保したい営業利益や事業運営に必要な諸経費の額を知っておく必要があります。
売上の算出方法は「来店客数×客単価」の他にも、以下の式で算出できます。
・商品の単価×販売個数
・サービス案件の単価×顧客数
売上から材料費などの原価を引いたものが、売上総利益(粗利益)です。粗利益から家賃や水道光熱費・人件費などの固定費を差し引くと、本業での稼ぎを示す営業利益になります。また、営業外での収入・支出を加減したものが経常利益です。さらに支払った税金などを差し引くと最終的な利益、すなわち当期純利益がわかります。
適切な売上目標の決め方
売上目標を高めに設定するとモチベーションの維持・工場につながりますが、達成不可能な金額を設定するとやる気が下がってしまうので要注意です。頑張れば達成できる可能性が高い、やや強気な数字を目標として設定するとよいでしょう。
開業当初の売上目標を設定する際は、同業他社の動向や業界特有の事情を踏まえながら、稼働で得られる売上と営業活動とのバランスも考慮するようにしましょう。開業当初は自分ひとりで商品・サービスを提供しながら営業活動も推進していくことになります。そのため、フル稼働の状態を作ってしまうと営業活動の余力を作れず、売上が未達になる可能性があります。
売上目標を設定する際は、長期的に達成し続けられる数字かどうかも深く考えておく必要があります。繁忙期・閑散期のように売上が大きく変動する時期はありますが、経営は基本的に長期戦で、マラソンのようなものです。スタートアップで頑張りすぎて失速し、売上低迷に陥らないよう注意しましょう。
[PR]注目のフランチャイズを比較
計画を立てたら開業に向けていよいよ行動

計画を立てたら、早速行動に移しましょう。「何年後、あるいは何カ月後にはここまで達成する」という目標に対して、着実に進むよう努力することが大切です。時には、事業の目標を達成するために他の仕事をしながら資金を確保することも必要となります。
絶対に開業した事業のみで食べていくというプライドは大切ですが、せっかく個人事業主という柔軟な働き方を選んだのですから、必要であれば副業を行なうこともできます。ただし、具体的な目標を達成するために行動を起こしつつも、軸である目的を見失うことのないようにすることがポイントです。
状況を常に俯瞰するようにし、近視眼的なアクションを控えることも経営者には求められます。
個人事業主の場合のスタートアップ
個人事業主が開業当初から従業員を50名以上雇うケースは考えられないため、中小企業を立ち上げるのと同じ流れでスタートアップします。新しいビジネスモデルを考える、あるいは商品・サービスの価値を高めるといった行動から、事業の認知度を高めて売上アップにつなげていきます。事業のスピード感から考えるとベンチャー企業に通じる部分もありますが、事業主単独で仕事の方針を決定できるので柔軟性の面では個人事業主が有利です。
資金調達について
自治体によっては、創業補助金や開業当初の家賃補助といった形で資金支援を受けられる場合があります。中小企業庁が運営する「ミラサポplus」では、国や自治体が提供する補助金・助成金制度を検索できるので、開業後も積極的に活用しましょう。また、日本政策金融公庫から融資を受ける場合に利子補給制度を設ける自治体も少なくありません。融資を希望する際は、事業計画を立てた上で相談してみてはいかがでしょうか。
開業は全て自己責任!そのリスクを負えるだけの目標設定をしよう
独立開業で成功するためには、モチベーションを保ち続けることのできる目標設定が大切です。目標は自由に設定できますが、仮に売上が未達だと毎月の固定費の支払いに苦しむリスクが伴います。企業の経営責任はすべて自分にあると意識して、利益が残せるように売上目標を立てるようにしましょう。開業できても、経営を維持していくことは決して簡単ではありません。
特に開業当初は顧客の認知度が低いため、売上が低迷しがちです。最初に出会った10名の顧客には、信頼関係の基盤を構築することを念頭に置いて徹底的に対応するとよいでしょう。顧客の生の声を広告で伝えることで、商品・サービスの強みをアピールできます。集客が増えれば売上にも反映し、事業も徐々に成長・成熟していきます。開業当初の顧客とは長い付き合いとなるケースが、意外と多いものです。
しっかりとした目的と目標達成への意欲をもって、事業を継続・成長させて、自分がやりたかったことを世に発信していきましょう。
[PR]脱サラした先輩が選んだビジネス
副業についてのよくある質問
独立、生存率に関するよくある質問を紹介します
10年後の生存率はどの程度なのでしょうか?
A1. 企業の10年後の生存率は1割未満という意見もありますが、実際には半数以上の企業・個人事業主が10年以上事業を継続しています。開業資金の確保が不十分だったり経営理念が曖昧だったりすると、早期に事業が頓挫する恐れがあるので要注意です。一方、用意周到に起業し、事業の状況によって経営方法の改善を繰り返していけば生き残れる可能性は高まるでしょう。
個人事業主はなにか優遇されますか?
A2. 個人事業主として起業した場合、利益が少なければ支払う税金が少なくて済みます。仮に赤字だったとしても、青色申告の承認を得ておけば最大3年分赤字の繰越ができるため、次年度以降が黒字だった際は節税効果を発揮するでしょう。なお税金以外の面では、法人企業・個人事業主とも同じフィールドで切磋琢磨していくことになります。
起業の意思はあるものの、どこから始めたらいいかわかりません
A3. まずは独立の動機と開業後に展開する事業について検討することをおすすめします。中小企業庁が全国各地に設置している「よろず支援拠点」では経営課題に関するあらゆる相談に対応しています。女性が起業する場合は、自治体に設置された女性起業・経営相談窓口の活用も有効です。多くの意見を参考にしながら、起業の方針を決めるとよいでしょう。
生存率の高い業種を教えてください
A4. 飲食サービス業や生活関連サービス業は競争率が高いため、差別化戦略がない状態で安易に開業すると早期廃業に陥る恐れがあるので要注意です。反面、需要自体は高く顧客から高い支持を得られれば成功できる可能性が広がるため、チャレンジする価値があるといえます。低リスクで開業できるフランチャイズの活用も一つの方法です。