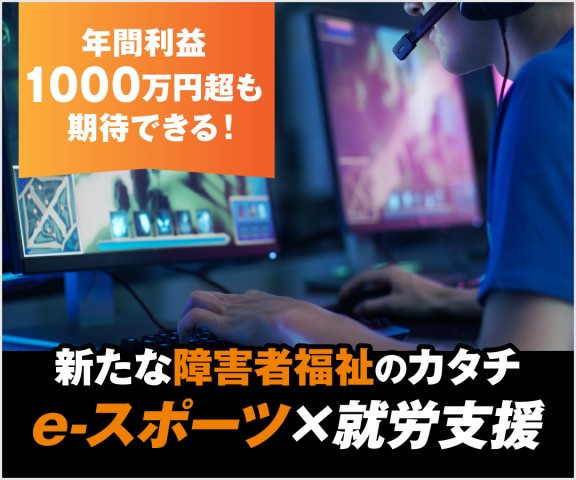補助金と交付金の違いを解説!用途や条件、申請・受け取りの手続きを知っておこう

事業を展開するためにはある程度の資金を用意しなければなりませんが、誰でもまとまったお金をすぐに用意できるわけではありません。そこで重要なのが資金調達ですが、起業を目指す人や事業の拡充を目指す人に向けた補助金制度があるのをご存知でしょうか。 この記事では、補助金の種類や申請手続きの流れ、助成金・交付金との違いについて紹介していきます。
国や自治体からの支援金を知ろう
補助金とは
補助金とは、ビジネスにおける特定の目的を実現するために国や自治体から支給される、返済不要の資金です。ICTシステムの導入を支援する「IT導入補助金」や、新事業を展開する際の設備投資を支援する「ものづくり作り補助金」が知られています。申請期間が限られており、目的の実現可能性を中心に書類審査が実施されます。複数の申請期間がある補助金の場合は、後の回になるほど難易度が上がる傾向なので、第1回での申請がおすすめです。
助成金とは
助成金とは、雇用環境を維持・改善するために厚生労働省や自治体から支給される資金です。返済が不要なだけでなく、受給条件を満たせば支給を受けられる可能性が高いため事業者にとって使い勝手が良いのが特徴です。休業手当の一部を補填する「雇用調整助成金」や、一定の条件を満たす労働者を雇った際に受けられる「トライアル雇用助成金」などが知られています。年間を通じて募集している助成金が多いですが、労働基準法が守られていることが受給の前提条件です。
交付金とは
交付金とは、国や各自治体が特定の目的を持って支給する、返済不要の資金です。自治体あるいは公的機関が受給対象なので、民間企業にとっては縁が薄いかもしれません。交通違反の反則金が信号機の設置など交通安全対策として自治体に交付される「交通安全対策特別交付金」が有名です。地域活性化を目指す地方自治体がプロジェクトを立ち上げるときなどは、国から地方自治体に向けた交付金を利用して計画が進められることが多いです。
補助金・助成金・交付金の共通点と違い
補助金・助成金・交付金とも。特定の目的を実現するために国や自治体が出してくれるお金で、返済が不要である点は共通しています。しかし、補助金・助成金や企業や団体に対して支給されるのに対し、交付金は地方自治体に対して支払われるものです。
また、補助金は目的を実現する前に交付申請を行うのに対し、助成金は何らかの目的を達成した後に支給申請を行う流れが主流です。支給審査についても、補助金の場合は目的の内容に関して過去の事例や他の申請者と比較されますが、助成金の場合は支給要項に合致しているかどうかの審査です。どちらにせよ、補助金・助成金を受ける目的を明確化することが大切なのです。
補助金・助成金を探すには
補助金・助成金を探す公式ツールとして、以下の2つが提供されています。
(1)J-Net21(独立行政法人中小企業基盤整備機構機構)
(2)ミラサポplus(経済産業省・中小企業庁)
また、厚生労働省ホームページでは、雇用関係助成金に関する情報提供ページが設けられています。
補助金・助成金に関する情報を提供するサイトは多数ありますが、情報が古かったり審査機関と見解が異なったりするケースがあるので参考程度にご利用ください。補助金・助成金を申請する際は、必ず公式サイトで最新の情報を確認するようにしましょう。
給付金とは
給付金は、企業の運営や国民の生活を支援する目的で国や自治体から給付されるお金ですが、何らかの事情で受けた損失を補填する色合いが強いのが特徴です。新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、事業者向けの「持続化給付金」や、国民全員に支給された「特別定額給付金」が知られています(いずれも支給手続きは終了)。したがって、起業や独立を支援するお金とも意味合いが異なるのでご注意ください。
[PR]法人の多角化に最適
補助金・助成金の受け取り方法は
補助金・助成金を受け取るためには、決められた申請書類や参考資料を提出した上で審査を受ける必要があります。補助金・助成金を申請する流れを簡単に説明します。
補助金を受け取れるまで
申請したい補助金を決めた後、申請書や添付書類を用意して郵送またはオンライン申請で事務局に提出します。オンライン申請には「gBizID」が必要となるため、申請手続きを済ませておきましょう。
補助金の種類によっては、補助対象となる品物・サービスの購入先と共同で申請する場合もあります。補助金の交付決定が出た後、実績報告書や経費明細書を事務局に提出すると補助金が受け取れます。
なお、経済産業省「ミラサポplus」では、補助金を受け取るまでの流れがチャート形式で紹介されています。補助金申請の参考にしてみてください。
助成金を受け取れるまで
厚生労働省の雇用関係助成金を受け取る際は、申請書や必要書類を用意して最寄りのハローワークまたは助成金申請センターに提出します。雇用調整助成金以外は電子申請に対応していないため、紙での書類作成が必要です。就業規則の内容など細かいルールが設定されている場合があるので、申請前にハローワークなどへの相談をおすすめします。
厚生労働省の「雇用関係助成金検索ツール」では、取り組む内容や対象となる労働者に応じた助成金の情報が一覧形式で掲載されています。
補助金申請のポイント
補助金を申請する際は、支給目的に応じて申請理由や必要事項を申請書に明記することが大切です。例えばIT導入補助金の申請では、業務の弱みを明らかにしつつ、ICTツールの導入で得られる効果や将来性をわかりやすく説明するようにします。
税理士・中小企業診断士などの専門家などが補助金申請のコンサルティングを提供していますが、料金がかかる場合がある他、内容も多種多様です。国が設置する支援機関のひとつ、東京都よろず支援拠点では補助金の活用方法を申請時のポイントを30分動画で紹介しています。公的機関が提供する中立的な情報なので、ぜひ参考にしてください。
新型コロナ関連の補助金・助成金
コロナ禍に伴い、飲食店の休業に対する協力金や融資時の利息補給制度など事業継続に向けた補助金・助成金制度が全国各地で設けられています。「J-Net21」では、新型コロナウイルス感染症に関連する補助金・助成金情報が掲載されています。申請期限や受給条件を十分確認した上で活用を検討してみてはいかがでしょうか。
[PR]未経験・初心者でも安心のビジネス
交付金の主な種類
交付金が国から地方自治体に支給されるものであることは分かりましたが、ひと言に交付金といってもその種類はさまざまです。ここでは、交付金にはどういったものがあるのかをいくつか紹介します。
地方創生推進交付金
はじめに紹介するのは、内閣府の「地方創生推進交付金」です。地方創生推進交付金とは、地域活性化を目的とする事業に対して国から支給されるお金のことで、2014年から制度が施行されました。「まち・ひと・仕事創生交付金」と呼ばれることもあります。
この支援金の特徴として、事業に対して複数年にわたって支援するということが挙げられます。地域活性化事業は、結果が出るまである程度期間を見据える必要があるため、そのような仕組みになっています。
主な活用事例としては、道の駅の建設や設備拡張、特産品を充実させるための商品加工費、さらには交通弱者が自由に街を行き来できるような交通網の整備などが挙げられるでしょう。
都市再生整備計画事業(社会資本整備総合交付金)
続いて紹介するのが、国土交通省の「都市再生整備計画事業」です。都市再生整備計画事業とは、地域の個性にあふれるまちづくりを支援するためのお金で、駅周辺設備の充実を図ったり、その地域の文化や自然環境などの特性を生かしたまちづくり事業に活用されたりします。
支給対象となる主な事業は、市街地再開発事業や土地区画整理事業などが挙げられます。支給期間は約3~5年と長期間のサポートが得られるのが特徴で、配分された交付金は住宅・社会資本の整備目的であれば自治体の裁量で活用できる仕組みです。防災・安全交付金として、架線や道路の安全対策にも活用されています。
農山漁村振興交付金
農林水産省の「農山漁村振興交付金」も、政府が支給する交付金のひとつです。農山漁村振興交付金は、農村・山村・漁村の活性化や維持発展を支援するという目的のもとに生まれたサポート制度です。

たとえば、農山漁村の雇用増大を図るための施設の整備を支援するときに活用されますが、農山漁村においては、人口の減少や高齢化などのさまざまな問題が取り沙汰されており、地域経済の低下や過疎化の歯止めがきかなくなっているような場所があります。
しかしその一方で、都市部では農山漁村の価値が見直されてきているという現状もあり、都市部から移り住むことを望む若者などが増えてきています。このような移住者の雇用を促したいときには、農山漁村振興交付金が非常に大きな役割を果たすため、地域活性にはなくてはならない重要なサポート制度となっています。
交付金の申請の流れ
交付金を受け取るには準備や申請が必要になります。どのような手続きをしなければならないのか、順を追って確認しておきましょう。
まず必要なのは、国のホームページなどで交付金に関する情報収集をすることです。自分の事業がどの交付金に該当するかなどきちんと調べたうえで申請するようにしましょう。
調べ終えたら、次は事業に関する計画書や提案書など必要書類の準備をしなければなりません。交付金を受け取るには、それに相応しい事業であるということを証明しなければなりません。より訴求力の高い書類を作るためにも、読んでもらう人の目線に立った分かりやすい書類を作ることを心掛けましょう。
書類の提出が終われば、あとは交付金が交付されるのを待つだけですが、そのためには審査を通らなければなりません。本当に必要な事業であると認めてもらうことができれば、晴れて交付金が交付されます。
交付金を検討する際の注意点
交付金を検討する際には、いくつか気をつけておかなければならないことがあります。ポイントが押さえられていないと交付金を受け取ることができなくなるかもしれないので、どのようなことに注意する必要があるのかいくつか例を紹介していきましょう。なお、企業や団体が受給できる補助金や助成金の申請でも注意点は同様なので参考にしてください。
提出期限に遅れないようにする
まず、一番に気をつけるべきこととして、計画書の提出期限を守るということが挙げられます。期限に遅れてしまうと計画書を受け取ってもらえず、申請することができません。郵送で提出する場合は「必着」「消印有効」のどちらなのかも確認が必要です。
計画書の内容は審査の結果を左右するため入念に作らなければならないのは確かですが、どれだけ優れた計画でも目を通してもらえなければ意味がないので、計画書の作成は時間に余裕を持ってする必要があります。
交付金の内容にあった提案をする
交付金は、交付されるにふさわしい事業でなければ受け取ることはできません。交付金の計画書や提案書を作成するときは、交付金の交付要綱に書かれている目的や対象事業などをよく読んで、内容に合った形で必要事項を記載するようにしましょう。
申請書や事業計画はわかりやすく書く
提出書類をわかりやすく作成するよう、十分に配慮しましょう。申請書や計画書の内容が抽象的だと、審査を行なう担当者にどのような事業なのか理解されず、審査で不利になってしまいます。
そのため、どんな事業を行うのか具体的に記載する必要があるのはもちろんのこと、読みやすい文章を書くことなどにも気を配らなければなりません。
目標の達成状況を報告する必要がある
交付金の申請は、審査に通って交付することができればそれで終わりというわけではありません。計画書には事業の目標を記載する必要がありますが、交付期間が終了すれば、記載した目標に対しての達成状況を報告する必要があります。
達成状況は数値化して報告することになるので、事業を運営中も収益金や動員人数などを細かく控えておかなければなりません。
私人や1つの民間企業に交付するお金ではない
交付金制度は、国が地方自治体に対して行うサポート制度という意味合いが強いです。支給されるお金は基本的に地方自治体のためのものであり、私人や1つの民間企業が支給対象でないことが多いため、交付金の対象でない場合は、補助金や助成金も検討してみましょう。
サポート制度を活用するときは、自分の事業内容と制度の内容を照らし合わせて、きちんと適合しているのか確認することが大切です。
[PR]複数店経営がしやすいフランチャイズ
応募要件を確認してから交付金を申請しよう!
起業後に新たな事業を始めたり、現在取り組んでいる事業内容を充実させたりする時は、資金調達が必須です。国や自治体では事業の目的に応じた補助金・助成金制度を設けていますが、支給を受けるためには審査があります。そのため、補助金や助成金の目的に合わせて事業者が取り組みたい内容を具体化する必要があります。
取り組み内容が補助金・助成金の目的にふさわしいものであっても、公表されている審査項目に合致していなければ受給できません。補助金・助成金を申請する際は、あらかじめ応募条件・支給要項などを十分に調べるようにしましょう。
補助金と交付金についてのよくある質問
補助金や交付金に関する、よくある質問を紹介します。
若者向けの起業支援はありますか?
日本政策金融公庫では、35歳未満の若者やシニア・女性の開業に特化した「女性、若者/シニア起業家支援資金」を提供しています。融資額は最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円)、開業から2年以内に返済を始めればよいため、スタートアップ期の資金繰り改善にも効果を発揮します。融資以外でも、若者の起業を支援してまちづくりを促進する目的で補助金制度を設ける自治体もあります。
研究開発でも支援がありますか?
新しい商品や技術を研究開発する中小企業に対する、さまざまな支援制度が用意されています。補助金の支給だけでなく、研究開発にかかった経費の税額控除制度(研究開発税制)や特許の出願審査請求料の減免といった制度も用意されています。自治体が定める条件に合った研究開発を進めることで助成金の支給を受けられる場合もあります。
販促用のチラシを作成して送付したいのですが、補助金は使えますか?
販促用チラシの作成・郵送には、販売ルートの拡大に必要な経費が補助される「小規模事業者持続化補助金<一般型>」を活用できます。業務の効率化を進める什器類の購入や生産性を向上させるICT機器の導入など、幅広い用途で活用できるのが特徴です。イベント会場の利用料や専門家のコンサルティング料金も補助対象なので、普段の業務でも補助金を活用できる可能性があります。
業績転換や業態転換向けの補助金はありますか?
コロナ禍で売上が減ったため、業態・業種を変更したり新事業を展開したりして事業継続を目指す企業を対象に「事業再構築補助金」が用意されています。税理士や公認会計士などの「認定経営革新等支援機関」と新たな事業計画を立て、付加価値額(営業利益・人件費・減価償却費の合計)を3%以上の増加を目指すのが条件です。申請時期が限られているので、詳しい情報は事業再構築補助金公式サイトをご確認ください。
[PR]新着フランチャイズ