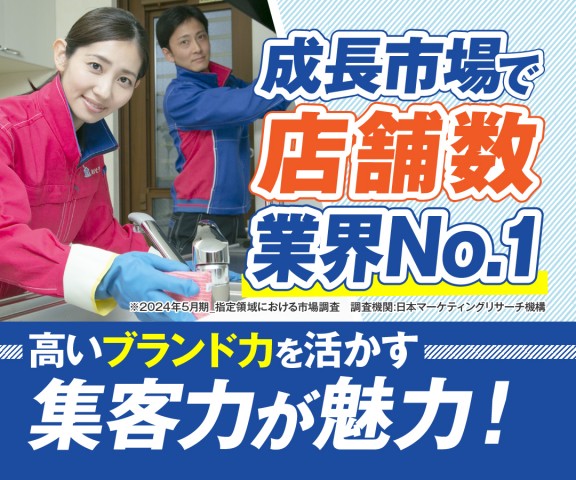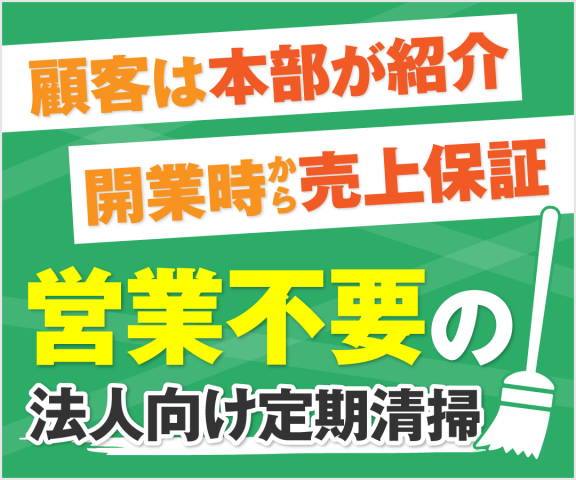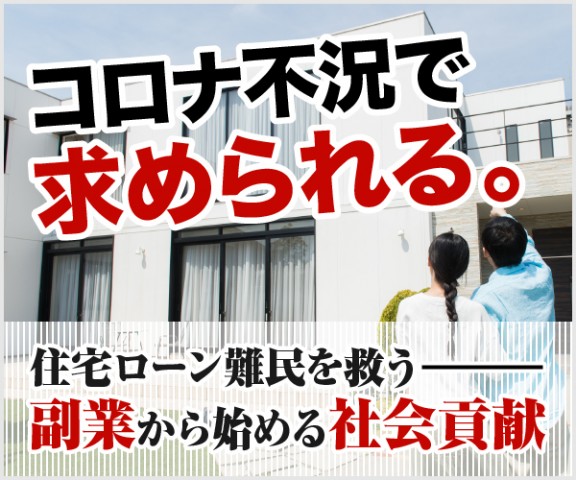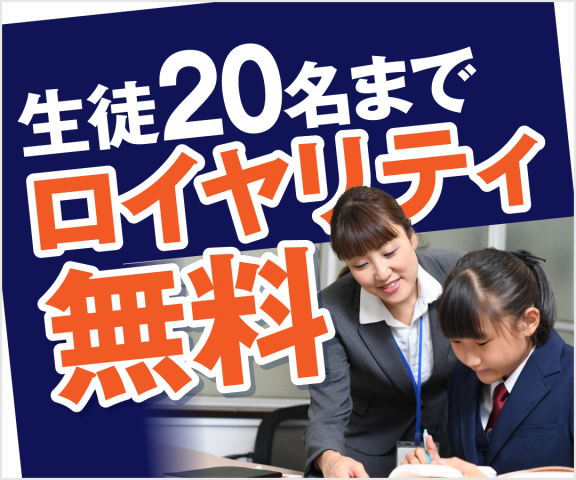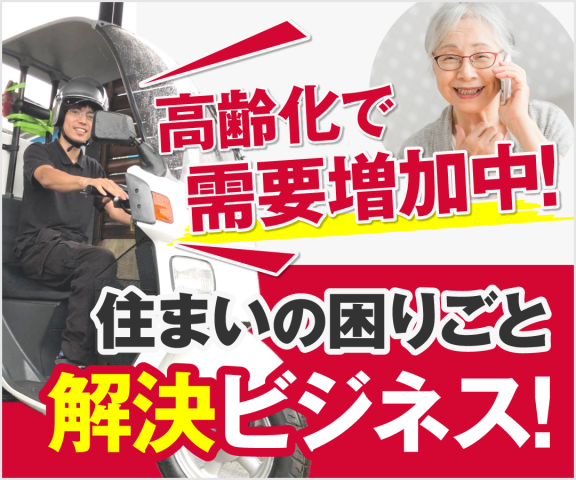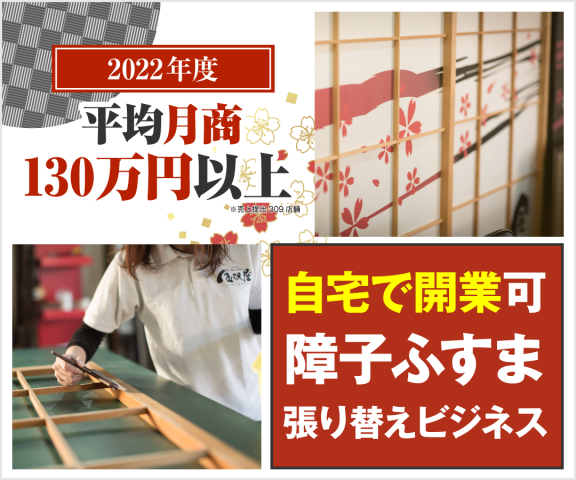個人事業主でも労災保険は加入できる?特別加入制度の基礎知識と注意点

労災保険は、労働者がケガをしたり病気になったりした場合に保険給付を受けられる制度です。有名な制度ですが、対象者になる条件などはよく知らない場合もあるでしょう。
独立開業を検討しているなら、個人事業主と保険制度の関係を押さえておくことが大切です。そこで今回は、個人事業主が労災保険に入れるかどうか詳しく解説します。
個人事業主でも労災保険に加入できる?
労災保険とは労働者が安心して働くための公的な保険制度であり、正式名称は「労働者災害補償保険」です。基本的には、労働者が業務災害や通勤災害が起こった場合に、被災者である本人や遺族に対して保険金の給付が行なわれます。
一般的な民間保険の加入者は被保険者ですが、労災保険の加入者は保険金を受け取る側の労働者ではありません。雇用している事業主が加入して、保険料も負担するという規則になっています。それにもかかわらず、事業主自体は保険給付の対象にならないので注意が必要です。
したがって、個人事業主も本来は労災保険の適用を受けられませんが、特別加入制度を使って加入すれば保険給付を受けられるようになります。具体的には、個人事業主を含む「中小事業主」「1人親方」のほか、「特定作業従事者」「海外派遣者」も特別加入制度の利用が可能です。
個人事業主が加入できる労災保険の特別加入制度とは
本来は対象外となる個人事業主などにも加入を認める仕組みとして、労災保険の特別加入制度は用意されています。ただし、個人事業主だからといって必ずしも利用できるわけではなく、業種や業務の実情などを考慮したうえで、労働者に準じて保護するのが妥当だと判断された場合のみ認められます。
たとえば、労働者を使わずに建築や土木を行っている場合は利用が可能です。貨物の運搬や廃棄物の収集なども対象となる可能性があります。
個人事業主が労災保険に特別加入するメリット
個人事業主に対しても、労災保険はとても重要な役割を担います。しかし、具体的にどんな点が良いのかイメージできない人もいるでしょう。ここでは、個人事業主の労災保険への特別加入について、代表的なメリットを3つ挙げます。
業務中に怪我をしたときに保険金が給付される
業務中に怪我をする可能性があることは、個人事業主も他の労働者と変わりません。一般的な会社の事業主とは異なり、経営に専念するのではなく、現場で自分のスキルを活かして働く必要があるからです。
怪我をしたときに労災保険に加入していなければ、治療費を自己負担で用意しなければならず、大きな負担になる場合もあるでしょう。一方、事前に労災保険に特別加入していれば、治療に使える保険金を給付してもらえるので安心です。
休業補償給付や遺族補償給付も受けられる
個人事業主が怪我や病気で働けない状態になると、事業による収入は途絶えてしまいます。貯蓄を切り崩しながら暮らす必要があるため、復帰まで長期化すると生活水準が著しく下がりかねません。
しかし、労災保険に特別加入しておけば、休業補償給付を受けられるので、そのようなリスクを小さくできます。また、障害が残ってしまったときは障害補償給付の対象になりますし、もし死亡してしまったら残された家族は遺族補償給付を受けられます。
国が運営している制度のため安心できる
民間保険は保険会社が営利目的で用意した商品であり、加入者が支払う保険料には保険会社の利益が上乗せされています。それに対して、労災保険の特別加入制度は国が用意しているものであり、営利を求めていないため、個人事業主は充実した補償を少ない負担で受けられるのです。
また、労災保険は一企業が支えているわけではなく、国が運営する社会保障制度に含まれているので、加入するときに安心感があるのも大きなメリットと言えます。
個人事業主が加入する労災保険特別加入の保険料の計算方法
労災保険に特別加入した場合の保険料は個人事業主によって異なり、その違いの要因となっているのは給付基礎日額というものです。
給付基礎日額とは、その名のとおり労災保険の給付額を算定するために設けられていますが、保険料の計算においてもベースになるのです。個人事業主から申請を受けた労働局長が決めるのがルールで、決定後に変更を希望する場合なども労働局長あての申請書を提出することになります。
また、給付基礎日額が定まるのと同時に「給付基礎日額×365」という計算式によって保険料算定基礎額も自動的に決定します。この保険料算定基礎額に保険料率を乗じて求められる金額が、個人事業主が1年間に支払う必要のある保険料です。
個人事業主が労災保険に特別加入する際の手続き方法
個人事業主の労災保険においての注意点
労災保険への特別加入は個人事業主にとってメリットが大きいですし、必要な手続きも決して難しくはありません。とはいえ、勘違いなどが原因で十分な恩恵を受けられない場合もあります。ここでは、そのような事態を避けるための注意点を挙げていきます。
業種によっては健康診断を受ける必要がある
個人事業主が一人親方などで、健康への影響が大きいと見なされる業務に従事している場合は、特別加入するときに健康診断を受けなければなりません。業務の種類によって具体的な条件や健康診断の種類は異なります。
たとえば、粉じん作業を行う業務を通算で3年以上実施している場合は、じん肺に関する診断が必要です。また、有機溶剤業務に従事する個人事業主は、通算期間が6カ月以上あると有機溶剤中毒の診断の対象になります。
労災保険料は経費として扱えない
売上と経費の差額である事業所得が大きいほど、所得税や事業税、住民税などの納税額も高くなります。そのため、労災保険に特別加入して支払う保険料も、経費として計上したいと思う人が多いでしょう。
しかし、消耗品や通信などの費用とは異なり、保険料は経費として扱えないので注意が必要です。ただし、国民年金や健康保険の保険料などと同様に、確定申告の際には社会保険料控除として扱えるので、納税額を下げるのに役立たないわけではありません。
また、事業用資金を保険料の支払いにあてた場合、会計処理では事業主貸という勘定科目を使用します。
1つの事業のみが対象になる
個人事業主のなかには事業をいくつか手掛けている人もいます。最初は1つからスタートした場合でも、経営が好調で増やしていくケースも珍しくありません。しかし、労災保険の特別加入は1つの事業を対象にするのが基本なので、複数の事業を運営している個人事業主は要注意です。
承認を受けていない事業に従事していて怪我を負った場合は保険給付を受けられないため、複数の事業を展開している場合は、すべての事業について個々に申請しておくのが理想です。
個人事業主として人を雇う場合は加入義務がある
保険料を節約したいなどの理由で、労災保険の加入を希望しない個人事業主も見受けられます。もちろん自身のための特別加入であればしないという選択肢もありますが、従業員を1人でも雇った時点で労災保険に加入しなければなりません。
従業員であれば雇用形態や労働時間などは問わず、アルバイトやパートなども対象になります。従業員を雇っていない場合とは異なり、業種や業態に関係なく、すべての事業において加入義務が生じることもポイントです。
未加入のままで営業を続けてしまうと、未払いの保険料の支払いに加えてペナルティが発生するので気を付けましょう。