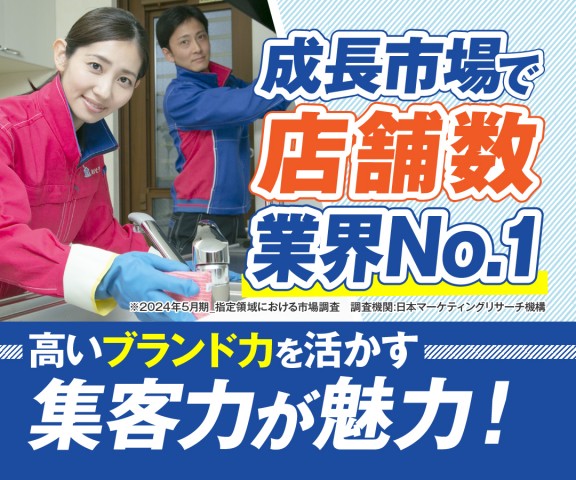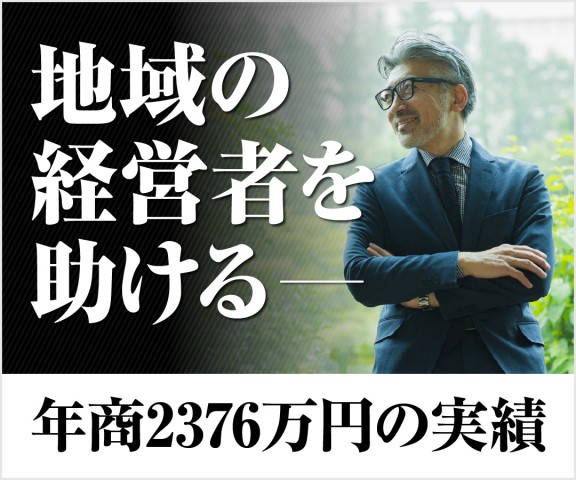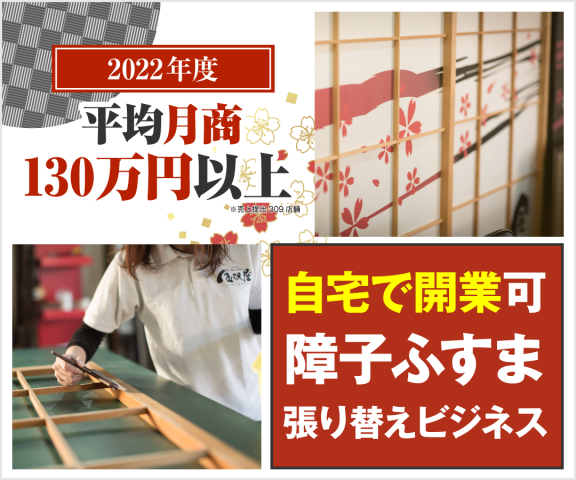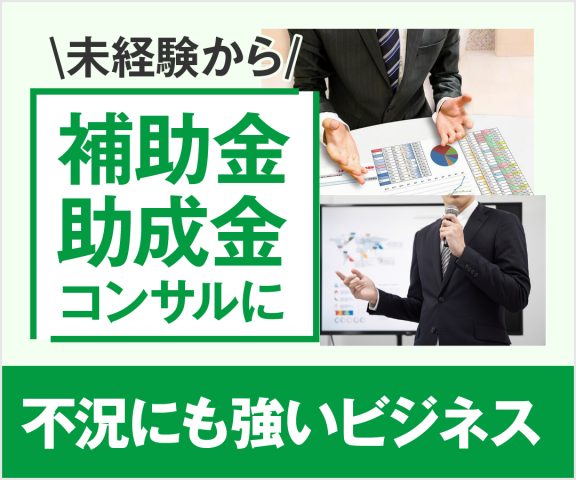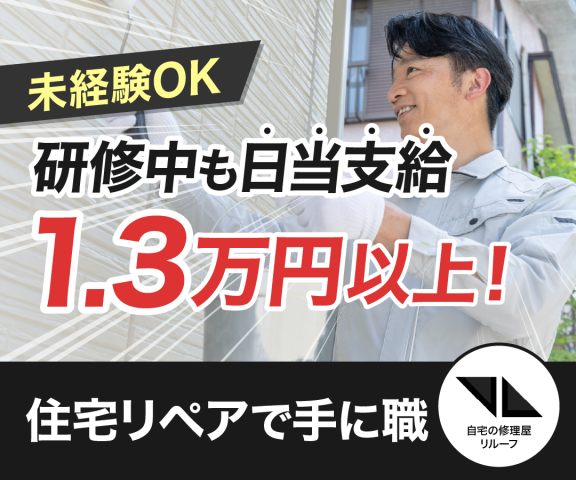家賃は経費として計上できる?個人事業主が知っておきたい家事按分とは

事業を行なうために必要な費用は経費として計上でき、売上から差し引くことができます。経費の金額が大きいほど納税額を減らせますので、該当するものは漏れなく計上したほうがいいでしょう。
そこで気になるのが、自宅で仕事をしている場合に家賃を経費として扱えるかということではないでしょうか。今回は、家賃を経費として計上するときの考え方などを紹介していきます。
家賃は経費として計上できる?
個人事業主として仕事をするときは、オフィスなどを借りず、自宅を事務所として使用するケースはよく見られます。自宅が賃貸住宅で毎月家賃を払っているのであれば、経費として計上することは可能です。
ただし、自宅の家賃を100%経費として計上することはできません。なぜなら、経費として認められるのは「事業を行うために必要な費用」だからです。当然ながら、生活にかかる費用を経費として計上することはできません。
自宅兼事務所の場合、家賃は事業として必要な費用ですが、生活にかかる費用でもあります。そこで、事業で使う割合と個人で使用する割合を考え、その割合に応じた金額を計算することが必要です。これを「家事按分」といいます。
[PR]自宅開業OK
家賃を経費として計上する際に知っておきたい家事按分とは
家事按分とは、自宅兼事務所でかかった家賃や光熱費などを、事業用として使った分と個人で使った分のそれぞれの割合に応じて振り分けることです。
事務所として利用している割合で計算する
たとえば、自宅が30平方メートルのマンションで、そのうち15平方メートルを事業用として使用していたとしましょう。月々の家賃が12万円だった場合、事業スペースは全体の50%ですので、家賃12万円のうち6万円を経費として計上できるのです。
事業用スペースをどこまでとするかは、事業で使用しているかどうかで判断します。例えば、実際の作業部屋や在庫を保管している場所などです。
共用部分の計算方法
仕事中に使うトイレや廊下などの共用部分の一部も、事業用スペースとして計算できます。ただし、共用部分の面積をすべて事業用スペースに含めることはできません。
たとえば、共用部分を除いた自宅の面積に対して、事業用スペースが30%を占めるとすると、その比率を共用部分にもあてはめて計算します。共用部分が10平方メートルの場合、3平方メートルを事業用スペースとして計算できます。
自宅の家賃を経費として扱うときの考え方
家事按分をするときは、自分で仕事に使う割合を算出して計算しなければいけません。そのためには、家賃を経費として扱うときの基本的な考え方をよく理解しておくことが必要です。ここでは、経費をどのように考えればいいかを紹介していきましょう。
駐車場代や光熱費も経費として扱う
自宅で仕事をしている場合、経費として扱えるのは家賃だけではなく、光熱費も按分できます。なぜなら、仕事をしているときは、ほぼ電気も使用しているからです。ただし、経費として計上できるのは事業用に使った分だけです。
電気代の場合は、使用時間やコンセントの数の割合に応じて比率を算出することが一般的です。たとえば、自宅全体に12個のコンセントがあり仕事部屋に3個あるなら、電気代の25%を経費にできます。また、配達で車を使うなど、事業上の必要があって駐車場を借りているというときは、駐車場代も経費として計上可能です。
事務所が別にあっても経費として扱う
自宅とは別に店舗や事務所を借りている人のなかには、在庫を自宅に保管していたり、自宅で作業することもあるでしょう。その場合、自宅の家賃も按分して経費として計上できる可能性はあります。
ただし、自宅を仕事でどの程度使っているのか、事業とどの程度関わりがあるのかなどによって、経費として認められるかどうかは変わってきます。可能性はゼロではないので、経費として扱えるケースもあることを知っておくといいでしょう。
区別が難しい場合家賃の5割程度を経費にする
家賃を経費として按分するときは、自宅全体に占める事業用スペースを割り出す必要があります。しかし、仕事をするスペースと生活スペースがはっきり分かれていなくて、どう按分していいかわかりづらいという人もいるでしょう。
判断が難しいときは、家賃の5割程度にするのもひとつの方法です。ただし、5割というのはあくまで目安であり、実態にできるだけ即した割合にする必要があります。税務署から計算の根拠を求められたとき、合理的に説明できるようにしておきましょう。
[PR]カフェや喫茶店を開業・経営
自宅の家賃を経費として計上するときの注意点
経費をどれだけ計上するかによって、納税額は変わってきます。しかし、どのようなものでも経費として認められるわけではありません。ここでは、家賃を経費として計算する場合に注意すべきポイントについて紹介していきます。
事務所兼自宅の場合は全て経費にしない
納税額を減らすためには、経費にできるものはできるだけ計上する必要があるので、自宅を事務所として使用しているのであれば、家賃は経費として計上することが望ましいです。
しかし、家賃の全額を経費にすることは基本的にできません。按分計算が面倒だったり、よくわからなかったりしても、100%を経費として計上するのは避けましょう。税務署からの指摘が入る可能性が高いです。
青色申告と白色申告ではルールが異なる
確定申告には、青色申告と白色申告があります。どちらで申告するかで、家賃を経費として計上する際のルールが異なりますので、注意が必要です。
青色申告の場合
青色申告の場合、事業に必要であることが証明できれば、適切な基準で按分した家賃を経費としてあげることができます。これは、事業用として使っているスペースが全体のどの程度の割合であっても構いません。
白色申告の場合
一方、白色申告の場合は、事業に関わる部分が50%を超えている場合にしか経費とすることはできません。たとえば、自宅の40%を事業用スペースとして使っているとしましょう。このケースでは50%を超えていないために、按分した家賃を経費として計上することはできないのです。
敷金は計上できない
自宅を借りるときは、敷金や礼金を払うことが一般的です。このうち、敷金を経費とすることはできず、「資産」として処理する必要があります。なぜなら、敷金は支払ったものではなく、退去時に手元に戻ってくるものだからです。
礼金は、経費とできる金額の基準が定められています。20万円未満のときは、地代家賃として処理することが可能です。20万円以上のときは資産として扱い、減価償却しましょう。
賃貸借契約書など資料を保管しておく必要がある
家賃を按分するときは、適当な数値で計算してはいけません。必ず、根拠のある数値で計算し、その際に使用した資料は保管しておきましょう。なぜなら、適当な計算をして不自然な数値で経費を計上してしまうと、税務署から指摘が入ることがあるからです。
税務署から按分計算の根拠を問われたときに、合理的な説明ができるように、計算した根拠がわかる資料を手元にそろえておきましょう。たとえば、賃貸借契約書や支払いを証明できる通帳記録などです。また、作業しているスペースがわかる自宅の間取り図などもあると説明しやすいでしょう。
持ち家の住宅ローンは必要経費にならない
賃貸住宅に住んでいて月々家賃を払っているのであれば、経費にすることができます。しかし、持ち家に住んでいる場合は家賃を払っていませんので、経費とすることは当然できません。仮に住宅ローンを払っていたとしても、月々の返済額を按分計算して経費とすることもできませんので注意しましょう。ただし、建物自体を減価償却することは可能です。
住宅ローン控除を受けられないケースもある
住宅ローンを利用して住居を購入したとき、一定の要件を満たすと住宅ローン控除が受けられます。所得税が還付もしくは軽減されますので、利用すべき制度です。
しかし、住宅を事業用として使用している場合、この住宅ローン控除が受けられなくなることがあります。なぜなら、住宅ローン控除を受けるには、「床面積の2分の1以上が自己の居住の用に供するもの」という条件を満たす必要があるからです。そのため、事業用の割合を50%以上で設定すると、住宅ローン控除が受けられなくなります。住宅ローン控除を受けたほうが、経費として計上するより節税になる可能性も高いため、十分な注意が必要です。
家賃は按分して賢く経費計上しよう
自宅を事務所として使っているなら、家賃も積極的に経費として計上しましょう。経費にすることで課税対象額が減り、節税できるからです。
ただし、家賃を100%経費とすることはできず、事業用として使用している割合に応じて按分する必要がありますので注意しましょう。また、税務署の調査が入ったときにきちんと説明できるように、按分計算した根拠がわかる資料を保管しておくことも大切です。
[PR]自宅開業OK