事業多角化に今こそ取り組むべき理由!多角化のメリットとリスク、成功事例を紹介
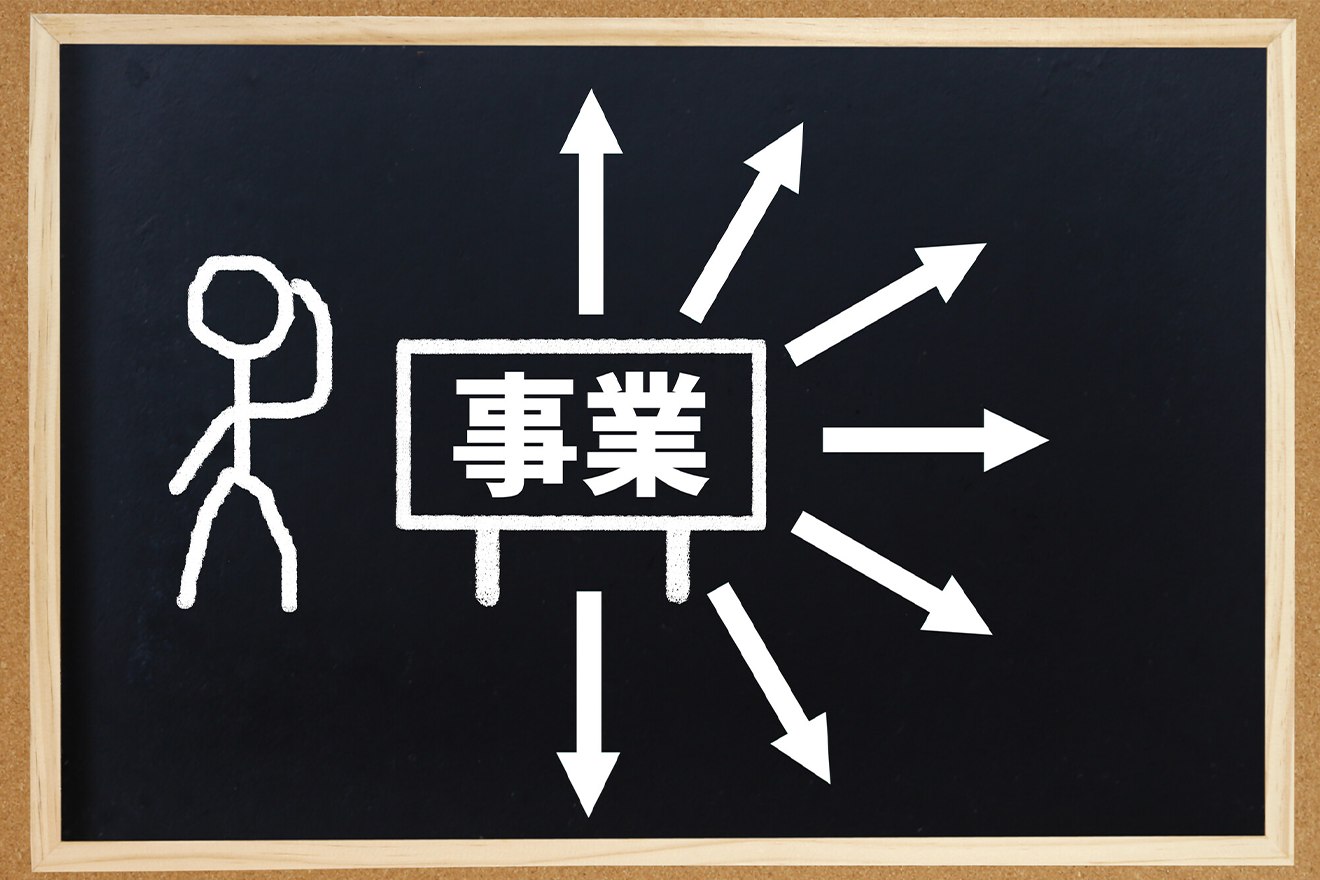
事業経営を行なっていると上手くいっている場合も、ひっ迫している場合も対応策として事業多角化を考えることがあるのではないでしょうか。近年、事業多角化が注目されるようになり、実際に取り組む企業も多くなっています。この背景にあるのは、コロナ禍や米中の新冷戦などの社会情勢の変化。従来の経営戦略だけでは将来的に不安がある時代だからこそ、収益の柱を増やす事業の多角化は重要な経営戦略です。
そこで今回は、事業多角化が必要な理由や多角化に成功した企業の事例とともに、事業多角化のメリットとリスクなど、事業多角化を進める前に知っておきたい重要なポイントを紹介します。
なぜ事業多角化が必要なのか
まずは本当に事業多角化が企業にとって必要なことかを考えていきましょう。最初に日本の企業の廃業数からご紹介します。
年間の廃業数
まずは帝国データバンクから年間の廃業数について見てみましょう。全国「休廃業・解散」動向調査」2019年版によると、2019年の年間廃業数は2万3634件にもなることが発表されており、2018年に比べると2.6%の増加になります。このうち、経営者側が自ら事業をたたんだケースは1万2764件で、7年ぶりの増加です。
2020年分に関しては新型コロナウイルスの影響により、さらに増加を見せると考えられます。帝国データバンク内では倒産速報のデータもあり、新型コロナウイルスの影響による倒産が既に多く寄せられています。掲載されていない個人事業などを含めると非常に多くの企業・店舗が経営難に立たされていると考えられるでしょう。
東京新聞では新型コロナウイルスの影響による倒産は2020年に1万件を超え、自主的な休廃業数は2万5000件にのぼると報道しています。
多角化経営の必要性とは
こういった廃業を回避する手段の一つが事業の多角化です。多角化経営にリスクがないとは当然言い切れません。しかし、多角化経営をすることによって複数の事業や会社・店舗をもてれば収益を安定化させることに繋がり、時代の変化に柔軟な対応がしやすくなります。
収益の柱となる事業を1つに絞るのではなく、複数持つことで、どれか1つが欠けても他の事業によるカバーが可能になるということです。
ビジネスには終わりがある
今現在は好調で業績も右肩上がりに成長していたとしても、それが未来永劫続くわけではありません。ビジネスモデルのほとんどは、黎明期から成長期、成熟期を経て衰退期へと向かっていきます。どれだけ市場のニーズがあっても、いずれは人気が衰えて過去の遺物になってしまうというのは歴史を振り返ってみても明らかでしょう。
ひとつのビジネスモデルだけにしがみついていると、市場の衰退とともに企業経営も右肩下がりになるのは避けられません。だからこそ、成長分野への事業多角化が必要なのです。
[PR]法人向けフランチャイズ
事業多角化の基礎的な考察

企業が生き残るためには、歩みを止めずに成長を続けなければなりません。事業多角化は、企業が成長するために欠かせないものの、リスクを伴う施策です。そこで、事業多角化の基礎的な部分について少し考えてみましょう。
事業の成長とは
企業が成長するための方法として、多角化戦略以外の成長戦略を導入する場合も少なくありません。たとえば、既存市場で既存商品の販売を強化する市場浸透戦略や、既存市場で新製品の販売を強化する新製品開発戦略があります。
また、既存の商品を新たな場所や顧客層をターゲットにして販売する新市場開拓戦略もありますが、いずれも既存市場または既存製品をベースとした戦略です。一方、多角化戦略は新しい市場で新しい製品を販売する戦略という点で異なります。
多角化が注目される理由
事業多角化が注目されているのは、独自の技術を活用したイノベーションの創出や、デジタルトランスフォーメーションなど、新規事業に取り組みやすい時代の流れがあるからです。事業多角化は、本業との関連性が小さい事業への参入よりも、関連分野への参入を進めたほうが収益の向上を実現できる可能性が高いという研究結果が出ています。
つまり、事業多角化を進めるにあたっては、本業で培った技術を応用できる分野に参入したほうが大きなメリットを得られやすいというわけです。実際に多角化している多くの企業では、自社のノウハウや技術を「横滑り」させる形をとっています。全く新しい分野にチャレンジするよりも、データやデジタル技術を活かした取り組みが事業多角化を成功させるポイントになりそうです。
事業多角化によるメリット・デメリットとは?

では具体的に多角化経営を行なうことでどのようなメリット・デメリットがあるのかをご紹介いたします。これから多角化経営を考えている方は是非、参考にしてみてください。
事業多角化によるメリット
まずは事業多角化のメリットをご紹介いたします。
(1)経営基盤が安定する
これは先述した通り、収益の柱が複数あることでどれか1つの柱が欠けても他の柱でカバーできるということです。収益の柱が複数あることで経営にも柔軟性が生まれやすく、時代やユーザーのニーズに合わせて企業戦略がとりやすくなります。
いわゆるリスク分散となるため、一極集中して運営している企業よりも経営破綻リスクは小さいです。1つの事業が失敗しても経営資源の振り分けが可能で、たとえば人員整理による企業イメージの失墜も避けられます。
(2)相乗効果の期待
ただ闇雲に複数の事業に手を出すのではなく、強い収益の柱となる事業から関連性のある事業を行なうことで、両方に相乗効果が生まれることが期待できます。
事業多角化によって相乗効果が生まれると、知識や人材、経験、技術などの経営資源をフル活用できるので、リスクを低減することが可能です。
(3)多様性が身につく
複数の事業を経営することによって、新たな発見が得られます。内容によっては経営資源を分割して他の事業に活かすこともできますし、今後の改善点として課題が見つかるかもしれません。
たとえば、1つの事業で発生した廃棄物が、ほかの事業では原料として利用できる場合もあります。今までは必要なかった・気が付かなかったことも、多角化経営によって必要な知識やノウハウとして企業の実力を上げるために役立つようになります。
(4)従業員の成長が見込める
多角化経営によって成長するのは企業だけではありません。従業員も今までより多くの知識やノウハウが身につくことでスキルアップし、今まで以上に企業に貢献してくれる人材としての成長が見込めます。
事業多角化によるデメリット
(1)コストがかかる
新たな事業を始めようとすると、当然初期費用などのコストが必要になります。初期費用は会社や店舗の運営費用だけでなく、広告費用や研究開発、人材確保といった費用もかかります。短期的とはいえ、各方面に投資をして事業を育てていくことになりますが、新規事業が頓挫するリスクは考慮しておく必要があるでしょう。
(2)損害リスクについて
事業が上手くいけば初期費用などの回収もできるうえ、新たな収益の柱となります。しかし失敗した場合、初期費用も全て無駄になってしまうということがあります。特に自社による投資だけであればまだ負債額も少なく済みますが、M&A(企業の合併や買収)を行なって失敗をした場合、負債額は億を超えるほどの損失になる可能性があります。
(3)経営の非効率化
これまでひとつの事業でスケールメリットを活かした事業を営んでいた企業の場合、事業多角化によって個別発注に切り替えるケースもあるので非効率な経営状態に陥る可能性があります。また、多様性が身につくメリットがある一方で、分割した事業同士で似たような商品やサービスを開発するなど事業が重複するリスクも懸念点と言えるでしょう。
多角化経営の成功が見込みやすい企業とは
どのような企業であっても必ず成功するとはいえませんが、成功見込みがある企業の特徴はあります。それは「成功を収めている収益の柱となる事業が1つ以上ある」ことです。既に1つの事業で成功している場合、余裕を持って事業展開でき、今までの知識やノウハウを活かした経営が行なえるため、新たな事業もスムーズに運営しやすいといえるでしょう。反対に、まだ成長段階の企業は単一事業に専念し、まずは主力となる収益の柱を1つつくることが重要といえます。
また、本業との関連性を重視し、本業と関連した事業の多角化を目指すことも重要です。本業で培った技術が確かなものであり、付加価値が高いほど多角化によって業績アップする可能性は高くなります。たとえば、競合他社に比べて自社の主力事業で手掛ける商品やサービスのほうが高い付加価値を提供できていれば、事業多角化が成功しやすいでしょう。そのため、まずは競合他社と自社の事業を見比べ、自社の優位性を判断することが大切です。
多角化の成功例
これまで、多くの企業が事業多角化に成功しています。代表的な企業にソフトバンクがあります。展示会事業や出版事業を行なっていたのが、ソフトウェア開発・提供やYahoo!などのインターネット情報発信、通信事業、モバイル通信キャリア事業など、IT関連で次々と事業を多角化し、現在では巨大な投資会社となっています。また、富士フイルム株式会社は、主力事業だった写真フィルム事業の需要減をきっかけに、化粧品や素材系などの事業多角化に舵を切って成功しています。
海外ではYouTubeを買収したGoogleや、Instagramを買収したFacebookもM&Aによって事業多角化をしているわかりやすい例です。Appleもパーソナルコンピューター市場からiPodで音楽プレイヤー市場に参入し、iPhoneを提供以降は、デバイス・ソフトウェアメーカーでありながら、自ら音楽や映画、アプリなどのコンテンツを提供し、なおかつマーケットのオーナーとしての事業も展開しています。いずれも市場の変化を見逃さないフットワークの軽さが生んだ成功例です。
一方で、株式会社すかいらーくのように、業態はそのままでブランドの異なる飲食店を次々と展開していく多角化経営もあります。本業を軸にした関連多角化として見習うべき成功例でしょう。
中小企業の成功例
事業多角化は何も大企業だけが成功しているわけではありません。中小企業でも多角化に成功している事例があります。たとえば、運送業者が引っ越しサービスへ参入し、不用品の処分も請け負うなどの関連多角化で成功しています。
また、日経ビジネスでとりあげられていたこちらの企業では、イベント機材の運搬後に会場の設営や運営サポートを行ったり、貸し切りバスの事業を多角化して旅行のツアー企画を始めたりするなどの多角化にも成功しているようです。中小企業の場合は新規事業に費やせる資源は限定されやすいことから、本業に関連する事業に注目して多角化を目指すのが成功への近道と言えそうです。
多角化戦略を考える際に知っておきたいこと

多角化戦略を考える際に、事前に知っておくべきことがあります。今後の経営戦略を考える際には是非これからご紹介する3つのことを覚えておいてください。
多角化戦略の4つの分類とは?
多角化戦略は大きく分けて4つの展開方法に分類されます。この4つは主軸となる事業の関連性・関係性以外に、事業の方向性から考えられたものです。
(1)水平型多角化戦略
既存の顧客と同じ客層に対して、別商品やサービスの投入を行なうタイプです。例を挙げると、家庭用自動車メーカーが事業用のトラックや特殊車両を販売するケース、陶器製の食器を専門に作っているメーカーが金属製の食器を販売するケースがあります。
(2)直角型多角化戦略
直角型では今までの市場と同じ市場で従来品と同じような製品やサービスを提供しますが、技術による差があるタイプです。例えば万年筆メーカーがボールペンの販売を行なうようなケースです。また、飲食チェーンが食品の生産や流通を行うといった、複数の事業を1つの企業が担うケースも直角型に該当します。
(3)集中型多角化戦略
集中型は既存製品やサービスと関連性の高い生産技術を要する商品などを提供するタイプです。例として、化粧品メーカーがアルコール消毒液を販売するケース、テレビの製造会社がカーナビを製造するケースなどが挙げられます。
(4)コングロマリット型多角化
コングロマリット型はこれまでの3つの分類とは異なり、全く別の分野に事業を広げるタイプです。例えば飲食企業がアパレル進出をするケース、不動産会社がペット販売事業に進出するケースなどが挙げられます。
本業から遠いコングロマリット型多角化はハイリスクハイリターン
既に事業多角化によるメリット内でご紹介しましたが、コングロマリット型は高い収益を見込めると共に、非常にリスクが高い戦略です。今まで全く違う業界で活躍していた企業が別の業界に進出することは注目度を高めることができ、宣伝効果も期待できます。しかし、これまで培ってきたノウハウや知識が全く通用しなくなることも考えなくてはなりません。
非関連型の多角化ならフランチャイズがおすすめ
コングロマリット型多角化でも、リスクを抑えて参入する方法があります。その方法が「フランチャイズ加盟」です。非関連型の多角化によるフランチャイズ加盟のメリットは沢山あります。
人材資源を使いこなせていない場合でも、フランチャイズ本部の適切な指導により、戦力として働いてもらうことが可能です。雇用を継続しながら業績向上を目指せるので、企業と従業員の双方にメリットがあります。また、フランチャイズ加盟は事業計画が立てやすい点もメリットです。馴染みのない分野に新規参入する場合、事業計画を立てるのは困難ですが、フランチャイズなら過去のデータと実績で適切な事業計画を立てることができます。マニュアルが整備されているため事業拡大が容易だったり、運営に必要な最適な設備を利用できたりするのもフランチャイズのメリットです。
法人加盟が可能なブランドが多数
フランチャイズの場合、個人加盟だけでなく法人加盟が可能なブランドが沢山あります。業種業態も幅広く、コンビニや飲食店、塾などの教育系、介護、理美容、買取など、さまざまブランドから選ぶことができます。
ノウハウの共有、サポート体制の充実
本部からの指導やノウハウを得ることができ、開業地域や経営についての相談も行なえるため、非関連型の多角化であっても成功しやすいというメリットがあります。
安定の収益が見込める「ストック型ビジネス」や加盟後本部が運営や営業を代行してくれる「投資型ビジネス」もあるので、多角化のための人件費を削減することが可能です。
事業多角化におすすめのフランチャイズビジネス

さまざまなフランチャイズビジネスや代理店募集がありますが、特に事業多角化におすすめなブランドをいくつかご紹介しましょう。
ブルースカイランドリー
投資型ビジネスの中でも特に注目なのが「コインランドリー経営」。中でもブルースカイランドリーは災害対応型のコインランドリーで、他社と差別化を図ることも可能です。出店の要となる出店場所については、ノウハウのある本部からのアドバイスを受けることができます。
スマートフィット100
24時間小型スポーツジムは、従来の大型ジムと比べ、会員が通いやすい工夫がされているので安定した収益が見込めます。スマートフィット100は「完全運営委託プラン」もあるので、投資型のビジネスとして本部に運営を任せることも可能です。
まいぷれ
地域情報ポータルサイトの運営を行なうビジネスです。まいぷれは地域密着型ビジネスなので、地域活性化に貢献することが可能。地域のネットワークを利用し、既存の事業に繋げることもできるので、さまざまな多角化経営に向いています。
ハウスドゥ!
メディアでもひっぱりだこの「ハウスドゥ!」は、法人限定のフランチャイズ募集を行なっています。異業種から加盟して成功を収めている法人も多く、景気に左右されないビジネスは事業多角化にぴったりです。
多角化経営を考えるならフランチャイズも1つの選択肢

事業多角化は4つの分類があり、特に非関連型のビジネスは自社展開では失敗のリスクが高くなっています。
本業とは別の非関連型のビジネスを検討するのであれば、未経験でもノウハウが手に入るフランチャイズ加盟を利用するという方法も戦略として考えてみてはいかがでしょうか。紹介したように、フランチャイズ加盟はメリットが豊富にあります。過去の実績やデータから成功に繋がりやすい事業計画を立てられますし、人材の戦略化を短期間で実現することが可能です。加えて、多店舗展開もスムーズにできたり、スケールメリットを活かした仕入れができたりするメリットもあります。
事業多角化についてのよくある質問
ここでは、事業多角化に関するよくある質問を紹介します。
多角化とM&Aの違いなんですか?
多角化は、既存の事業を活かして取り組むケースがあるものの、多くは新規事業としてゼロから立ち上げる戦略です。一方、M&Aは企業買収によって新規事業を手に入れる戦略です。どちらも事業の幅を広げるという面では同じですが、M&Aは企業同士の相乗効果によって企業価値を高めることを目的にしています。多角化よりもM&Aのほうが「新たな分野への挑戦」という意味合いは薄いと言えるでしょう。
多角化する前に注意する点はありますか?
多角化で業績を上げるためには、本業のブランディングが成功している状態であることが重要です。社会的に影響力のある企業が新規事業を立ち上げると、話題性もあり成功する確率が上がります。そのためにも、本業の社会的価値を高めることが先決です。多角化は経営資源と経営基盤が整っていることが前提になるので、これ以上ないほどに本業の価値が高まっているのかを再点検しましょう。
多角化せず、ある事業に集中する戦略はだめですか?
ある分野に特化した集中戦略は中小企業ほど大事な戦略です。多角化は多大な経営資源が必要になるので、企業規模が小さいほど不利になります。狭い市場のなかで自社の優位性を高めることができれば、あえて多角化する必要はありません。集中戦略を進めることでコスト削減が可能になるうえに、差別化が可能になるメリットもあるので、中小企業の課題解決に適しています。
消費者ニーズはどのように調査しますか?
経済産業省が発表した「消費インテリジェンス研究会」の報告書では、消費者ニーズに関する情報が詳しく掲載されています。消費経済市場の変化や消費行動のタイプ、消費者と企業の関係性の変化など、消費ニーズに関わる内容が詰まっているのでチェックすることをおすすめします。また、中小企業庁の「よろず支援拠点」で相談するのも良いでしょう。相談者の9割以上が満足したと評価しているだけに、課題の解決に繋がる可能性が高いです。
[PR]新着フランチャイズ


























