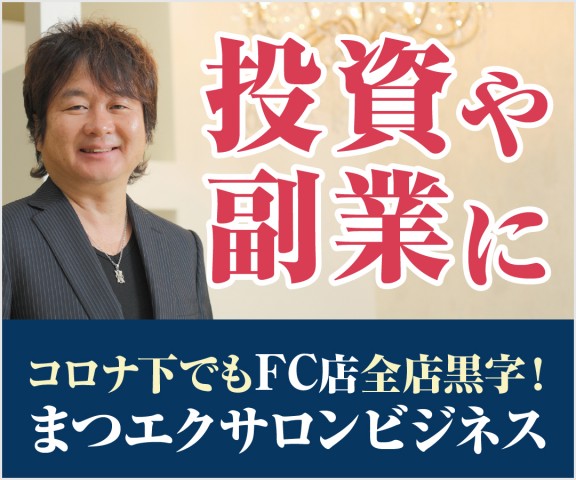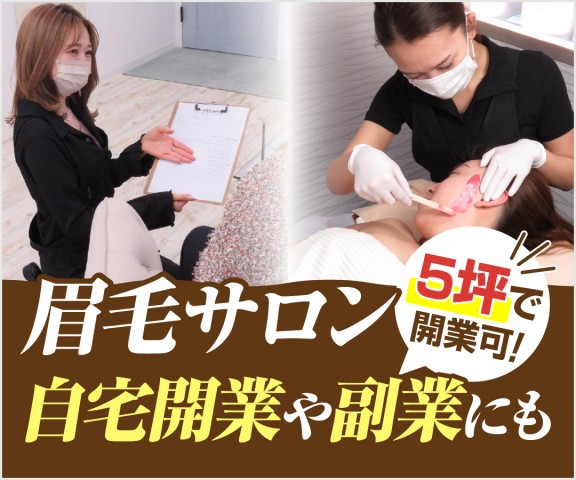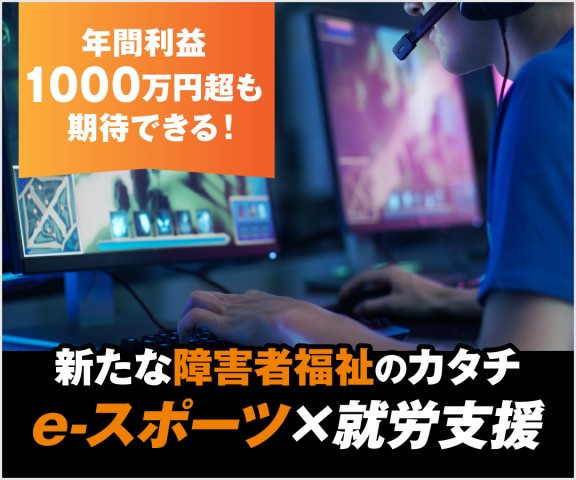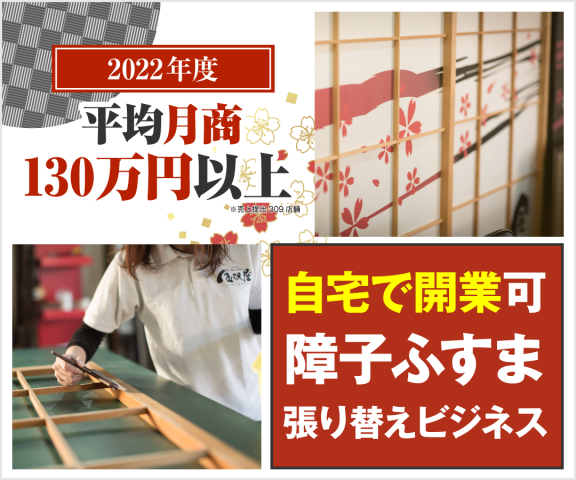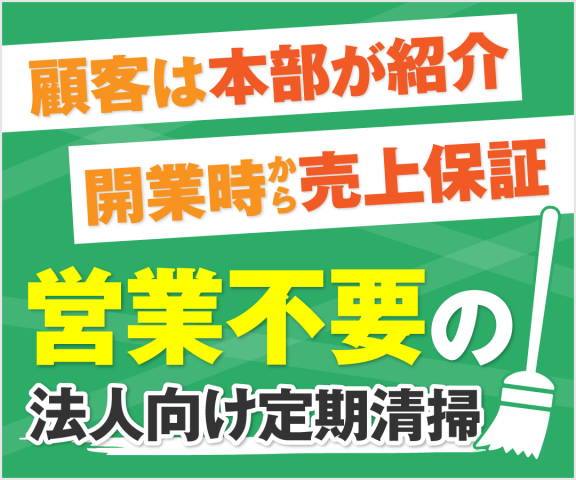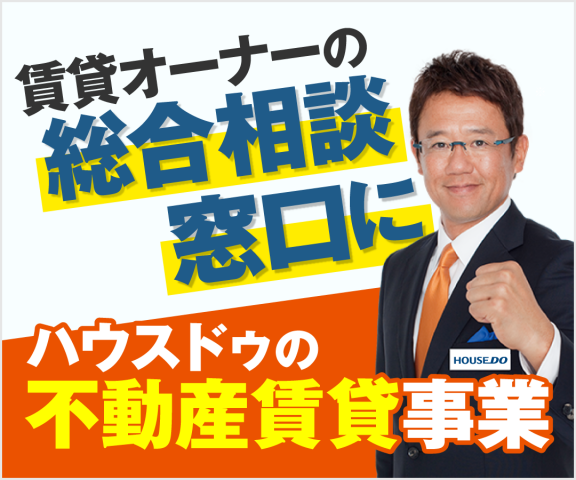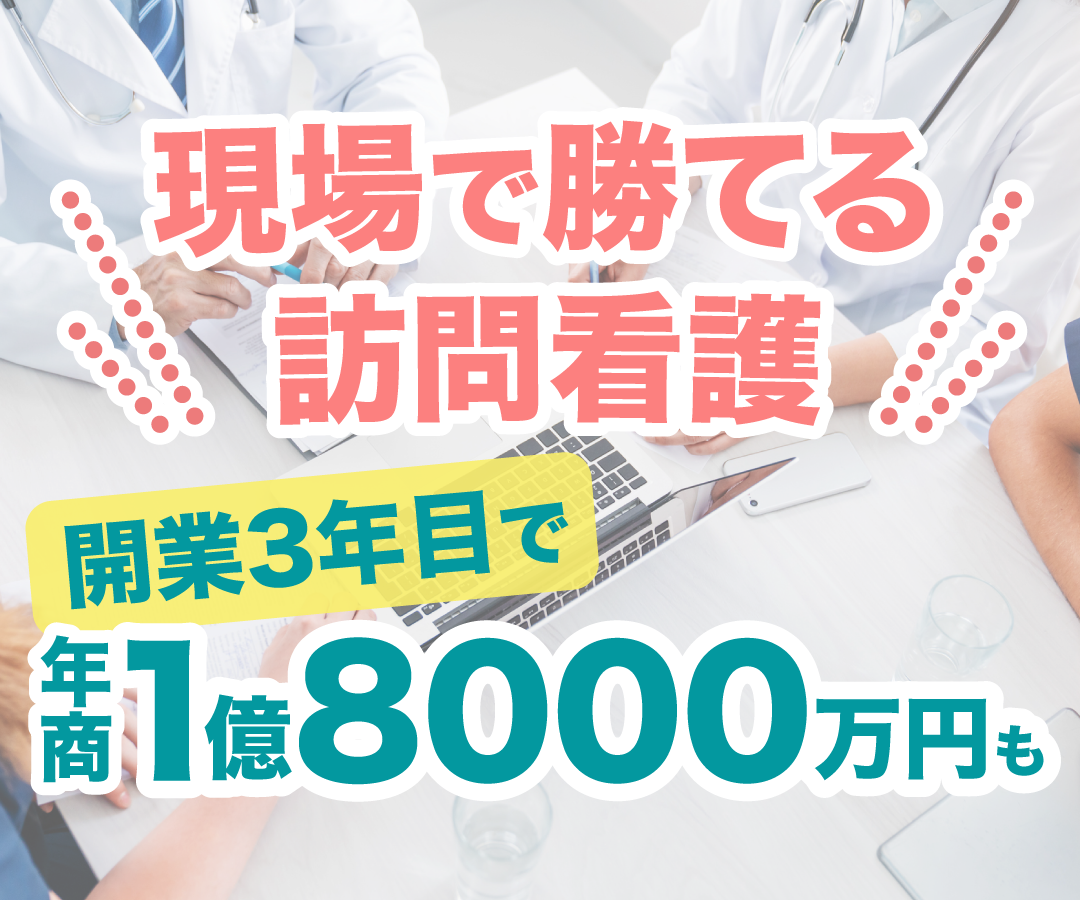個人事業主も福利厚生の利用ができる!福利厚生の種類と導入の条件や方法を解説

個人事業主として開業すると、節税対策として「経費」を計上することになります。そのうちの一つである「福利厚生費」は、会社員として働く人にとっては馴染みのある項目ですが、 個人事業主で利用できるのか分からないという方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、福利厚生費と個人事業主の関係や、利用するための条件について解説していきます。
そもそも福利厚生費って何?給与とは異なるので注意!
最初に、福利厚生費の意味を解説します。個人事業主であっても、福利厚生費の定義をしっかり把握しておくほうが、経費計上のときに迷うことがなくなります。
福利厚生費の考え方
「福利厚生費」とは、会社が従業員の生活向上を意図して拠出する費用を指します。従業員への報酬という点で給与とは似ていますが、同じ項目には入りません。福利厚生費には従業員のモチベーションアップという側面があり、余暇を楽しむため、生活を支援するために支給されるお金です。
なお、福利厚生費は「法定福利費」と「法定外福利費」の2種類があります。法定福利費は、法律により定められた「社会保険」や「労働保険」など、会社・事業主が法律で費用負担を義務付けられた費用を指します。一方、法定外福利費は、従業員の生活向上や労働環境改善のための費用で、適応される項目や内容は会社の意向に委ねられています。
たとえば、財形貯蓄や健康診断、従業員の結婚祝い金、短時間勤務制度、リフレッシュ休暇などが法定外福利費に該当します。
給与と福利厚生費の違い
まず、給与は従業員の行なった労働の対価として支払われるお金です。そのため、従業員の能力やキャリア、労働時間に応じて大きく差が生まれることもあります。一方、福利厚生費は従業員の福利厚生のために平等に割かれるお金です。ただし、細かく定義しようとすれば複雑になるケースも少なくありません。
基準としては、福利厚生費はあくまで福利厚生のためだけに使われるお金だという点でしょう。福利厚生費は、役員を含めた全従業員に対して、平等に利用できる機会が設けられています。
また、給与は課税対象となるため、従業員には所得税がかかり、会社は源泉徴収をする必要があります。従業員は給与額の増加に比例して住民税や社会保険料が増える傾向にあります。一方、福利厚生費は非課税です。
どんなものが福利厚生費になる?福利厚生費として計上できる種類
どの範囲を法定外福利費に含めるかという明確な基準はなく、「社員の生活や労働環境を向上させるため」の費用と条件を満たせば計上できるので、会社によって内容が大きく変わってきます。
そこで、福利厚生費として計上できる条件と費用について解説します。また、法定外複利費は、内容によって福利厚生費として非課税扱いにすることが可能である一方で、内容によっては福利厚生費として認められないケースもあります。福利厚生費として認められなければ課税対象になってしまうので、ここで計上できるものを確認しておきましょう。
福利厚生費として計上できる条件
会社ごとに内容を決められる福利厚生ですが、経費として計上するためには3つの条件があります。その1つ目が「全社員が平等に利用できること」です。一部の従業員や役員のみを対象にしている場合は経費に計上できません。2つ目は「常識の範囲内の金額」であること。福利厚生費に上限はありませんが、だからといってなんでも福利厚生として計上できるわけではなく、妥当な範囲と金額であることが認められなければいけません。そして最後の条件が「非金銭的支出」であることです。直接金銭で授与することはできません。
なお、福利厚生制度があることは社内規定にしっかりと記載しておきましょう。口頭で福利厚生制度について説明しても、社内規定に書かれていなければ誤解を招きますし、会社と従業員の間にトラブルが発生するおそれがあります。
福利厚生費の種類
一般的に福利厚生として計上される事例をご紹介します。従業員の慰労を目的としたさまざまな催しに使われたお金も、福利厚生費に含めることができます。
・通勤費
・慶弔見舞金
・健康診断費用
・忘年会、新年会、歓送迎会
・社員旅行
・制服費用
・食事代の補助
・社宅
・健康増進のためのジム利用料
・育児、介護支援
限度がある福利厚生費
通勤手当、社宅や寮の家賃負担、食事の現物支給は一定額まで非課税ですが、全額が非課税になるわけではありません。まず、交通機関や有料道路を利用している人や、通勤用定期乗車券を購入している人に支給する通勤手当は、15万円までが非課税の対象です。また、自動車や自転車を使用している人に対する通勤手当は、距離に応じて4,200円~31,600円が非課税の対象となっています。
社宅や寮の家賃負担は、会社が契約している物件であり、社宅手当として支給していることが前提です。そのうえで、従業員が家賃相当額の50%以上を支払っていれば非課税となります。食事の現物支給は、従業員が食事代の半額以上を負担しているうえで、1人あたり月額3,500円(消費税及び地方消費税抜き)以下が非課税対象です。
個人事業主は福利厚生費を計上できる?ケース別に解説
原則として、福利厚生費は会社から”従業員”に対して支給されるお金です。そのため、「個人事業主でも福利厚生費は計上できるのか」と迷ってしまうでしょう。結論から言えば、個人事業主が福利厚生費を計上できるかどうかは、従業員雇用の有無によって異なります。以下、パターン別に経費計上の可否を説明していきます。
1人で事業を行なっている場合
自分以外に従業員のいない1人経営の個人事業主であれば、福利厚生費は計上できません。福利厚生とは、”従業員”のために用意する制度なので、経営者が自分で自分の生活を補助したとしても福利厚生費の条件を満たしません。例えば、個人事業主が仕事の疲れを癒すためにテーマパークを利用したとしても、旅費は単に「個人の消費」とみなされます。
従業員を雇用している場合
個人事業主が従業員を雇っている際、条件を満たせば福利厚生費は認められます。すなわち、全従業員が利用できる福利厚生制度として企業で設けているのであれば、その制度を社長や役員が一緒に利用することは可能です。ただし、「ベテラン社員しか利用できない」「役職がついていないと支給しない」といった条件がついていると、福利厚生費として認められず、給与と同等にされてしまうので、経費として計上できません。
家族で事業を行なっている場合
福利厚生費は、家族経営の会社でも問題になるテーマです。もしも個人事業主と専従者(事業に従事していて、個人事業主と生計をともにする配偶者や親族)以外に従業員がいないなら、福利厚生という概念はあてはまりません。売上から生活費を補助したり、医療費にあてたりしても福利厚生費とはならないので注意しましょう。また、個人事業主と専従者が「慰安旅行」と称して出かけたとしても、単なる家族旅行とみなされてしまいます。生活費の一部だったという認識になるので、会社の経費としては計上できないのです。
[PR]健康・美容関連ビジネス特集
福利厚生費を計上するときの注意点
福利厚生費の計上には、細かい条件がたくさんあります。そのうえ、個人事業主には独特のルールが適用されることもあるので注意が必要です。よくある間違いを知った上で、正しく計上できるようにしましょう。
事業主と役員のみの場合は対象外になる
福利厚生費はあくまで従業員のために支払われるお金です。そのため、経営者本人と役員など一部に対して使われた生活補助、食事費などは福利厚生の対象外です。例えば、経営者が従業員を食事に連れて行った場合は福利厚生費に計上することが可能です。しかし、経営者と役員だけで食事に行ったケースでは、福利厚生費として認められません。経営陣ではない従業員のために使われている費用なのかどうかが、福利厚生の判断基準の一つです。
常識的に認められる範囲内の金額で計上しなければならない
福利厚生費は、上限が定められていないわけではありません。しかし、「一般常識で許容される範囲」との目安が設けられているため、その中に収まるように計上することが必要です。原則として福利厚生費は、全従業員に対して支払われるもののですが、誰もが無限に利用できるシステムではありません。例えば、対象外になるケースとして、全社員を海外旅行に連れて行って高級ブランド品をお土産として買い与えたときなどは福利厚生と呼べません。生活や環境向上と、贅沢は別物です。
経団連が2019年に発表した福利厚生に関する調査結果では、従業員1人あたりの福利厚生費は1カ月約108,000円となっています。このうち、法定福利費は約84,000円、法定外福利費は約24,000円です。福利費厚生費がどんなに多くなるとしても、この金額を目安に計上するのが無難と言えます。
現金支給だと福利厚生費とみなされない

福利厚生とは、従業員を物やサービスで支援するシステムです。つまり、現金を渡してしまうと給与や接待費に変わってしまい、福利厚生費の対象外になるので注意しましょう。福利厚生だと思って現金支給をしたことにより、かえって会社の負担が大きくなる危険も出てくるので適切な支給方法を徹底しましょう。
ただし、現金支給でも慶弔費はルールを定めておくと福利厚生費として計上できるので、社内規定に慶弔見舞金に関する条項を明記しておきましょう。そのうえで、規定通りに慶弔見舞金を支給します。なお、常識の範囲内であることが前提となっているので、従業員の結婚祝い金に数十万円を渡すなどは経費計上できません。また、支給した旨を確認できる書類などを従業員から提出してもらい保管しておくことも忘れないようにしましょう。
交際費との違い
交際費は取引先や協力会社などの他社に対する行為にあたる費用で、贈答や接待などの費用が該当します。これに対し、福利厚生費は社内にいる従業員向けの費用ですので、交際費とは別物です。ただし、特定の従業員のために支出した場合は、福利厚生費ではなく社内交際費となるので注意しましょう。
新年会、忘年会の場合
会社が従業員を集めて忘年会や新年会を行った場合、その費用の一部を食事補助として福利厚生費に計上できます。ただし、食事補助をした費用を経費計上するには、従業員1人当たり1カ月の会社負担額は税抜き3,500円以下で、しかも従業員本人が飲食代の半分以上を負担することがルールです。いずれか一方の要件しか満たせない場合は経費計上できません。
間違いやすい経費との違い
普段から支出している経費の中には、福利厚生費と間違いやすい経費があります。消耗品費は、業務に直接関り、日常的に使用する物品の費用であるため福利厚生費には該当しません。また、従業員にプレゼントを贈る場合、社内規定でプレゼントについてルールがあるうえで、花束やケーキなどの常識的な範囲内のプレゼントであれば福利厚生費として計上できます。しかし、現金や高額な品物を渡す場合は課税対象です。
似たようなケースで、永年勤続者へ記念品を贈る場合は、常識的な範囲内で収まる金額の記念品であり、対象となる従業員の勤続年数が10年以上あることが要件です。記念品を対象者が選択できる場合や現金を支給する場合は課税対象となります。また、従業員の資格取得費用も一定要件を満たすと福利厚生費として計上できます。
適切な経費計上をしなかった場合にリスクがある
個人事業主は発生した経費を適切に計上していかなくてはいけません。もしも経費計上を間違えたり、ごまかすなどの行為をおこなうとペナルティが科せられるため注意しましょう。ちなみに、福利厚生費には源泉徴収の必要がなく、支給された額を経費として計上すれば通ります。ただし、給与や接待交際費は源泉徴収が必要となる項目なので、給与や接待交際費を福利厚生費として計上した場合、あとから不納付加算税が課せられます。結果的に会社の支出が大きくなるので、最初から正しく計上するほうが賢明でしょう。
福利厚生を導入できる条件と方法
ここまで説明してきた福利厚生費に関する情報について、簡単に理解できるように箇条書きで紹介します。
導入できる場合
■福利厚生費の条件…従業員が平等に利用できる。常識の範囲内の金額。現金でないこと。
■福利厚生費扱いになるもの…社宅費・通勤費・忘新年会・健康診断費用など。
■福利厚生費の上限…従業員1人あたりの福利厚生費は1カ月約108,000円が目安。
■現金が福利厚生費扱いにできる条件…慶弔見舞金は、社内規定で定め、常識の範囲内の金額であれば福利厚生費扱いにできる。
■個人事業主の場合…従業員を雇用している場合に限り、条件を満たすと福利厚生費が認められる。
導入できない場合
■事業主と役員を対象とした経費…従業員のために支払われるお金ではないため。
■現金支給…一部例外を除き、給与や交際費扱いになる。
■交際費…社外の人間に対して使用する費用のため。
■消耗品費…業務に直接関わる費用のため。
■個人事業主の場合…1人で事業を行なっている場合。家族で事業を行なっている場合。
福利厚生費は個人事業主も計上できる!適切な経費計上をしよう
個人事業主でも、家族以外の従業員がいるなどの条件を満たしていれば、福利厚生費を計上することは可能です。福利厚生費にできる範囲は広いですが、不正が発覚するとペナルティが発生するので、経費の計上は適切におこなうべきです。正しく福利厚生費を計上していけば節税効果もあるので、計上できる事例や注意点を知って、正しく利用しましょう。
経費処理で困った場合は、あれこれと情報を探し回るよりも国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)を確認してみましょう。科目別に分かれていますし、キーワード検索を使って知りたい情報を素早く見つけることが可能です。福利厚生費をはじめ、税金についてわかりやすく解説されているので、再確認という意味でも利用する価値は大いにあります。
[PR]法人の多角化に最適
福利厚生費についてのよくある質問
福利厚生に関するいくつかの質問にお答えします。
社員旅行は高額になりがちです。福利厚生費になりますか?
2つの要件を満たすと福利厚生として計上できます。1つ目は、旅行の期間が4泊5日以内であることです。海外旅行の場合外国での滞在日数が4泊5日以内でなければ認められません。2つ目は、従業員の50%以上が旅行に参加していることです。複数の支店がある場合は職場ごとに50%以上の従業員が参加していることが条件です。なお、自己都合で社員旅行に参加しなかった従業員に対して現金を渡してしまうと、給与や接待交通費の扱いになるため気をつけましょう。
去年、創業記念を行い、今年、売り上げ倍増記念をしたら、両方とも福利厚生になりますか?
国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)によると「創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。」との記載があるので 福利厚生扱いにするのは難しいと考えられます。詳しくは国税庁のタックスアンサーを確認してみてください。 国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)
制服は福利厚生費、消耗品費のどちらでしょう?
制服と一口に言っても、業界によっては業務に欠かせない制服とそうではない制服があります。たとえば、医療従事者の白衣や警備会社の制服などは、職場だけで着用するものですし、業務に欠かせないものであるため福利厚生費として経費計上することが可能です。なお、福利厚生費は従業員向けの費用であるため、個人事業主が自分のために制服を購入しても福利厚生費にはならず、消耗品として計上しなければなりません。
個人事業主が福利厚生を用意するのに、いい方法はありますか?
個人事業主向けの福利厚生サービスを提供する団体も増えていますので利用を検討してみてはいかがでしょうか。一般財団法人 あんしん財団では、福利厚生・災害防止・ケガの保障などのサービスを提供していて、福利厚生事業では職場環境改善や健康管理のための補助金制度などがあります。また、全国中小企業勤労者福祉サービスセンターでは、全国200カ所以上のセンターがあり、幅広い福利厚生サービスを低コストで受けられるのが魅力です。そして、商工会議所でも個人事業主向けの福利厚生サービスのサポートを行なっています。サービスの内容は都道府県ごとの商工会議所で異なるので、最寄りの商工会議所を確認してみましょう。 商工会議所名簿
[PR]新着フランチャイズ