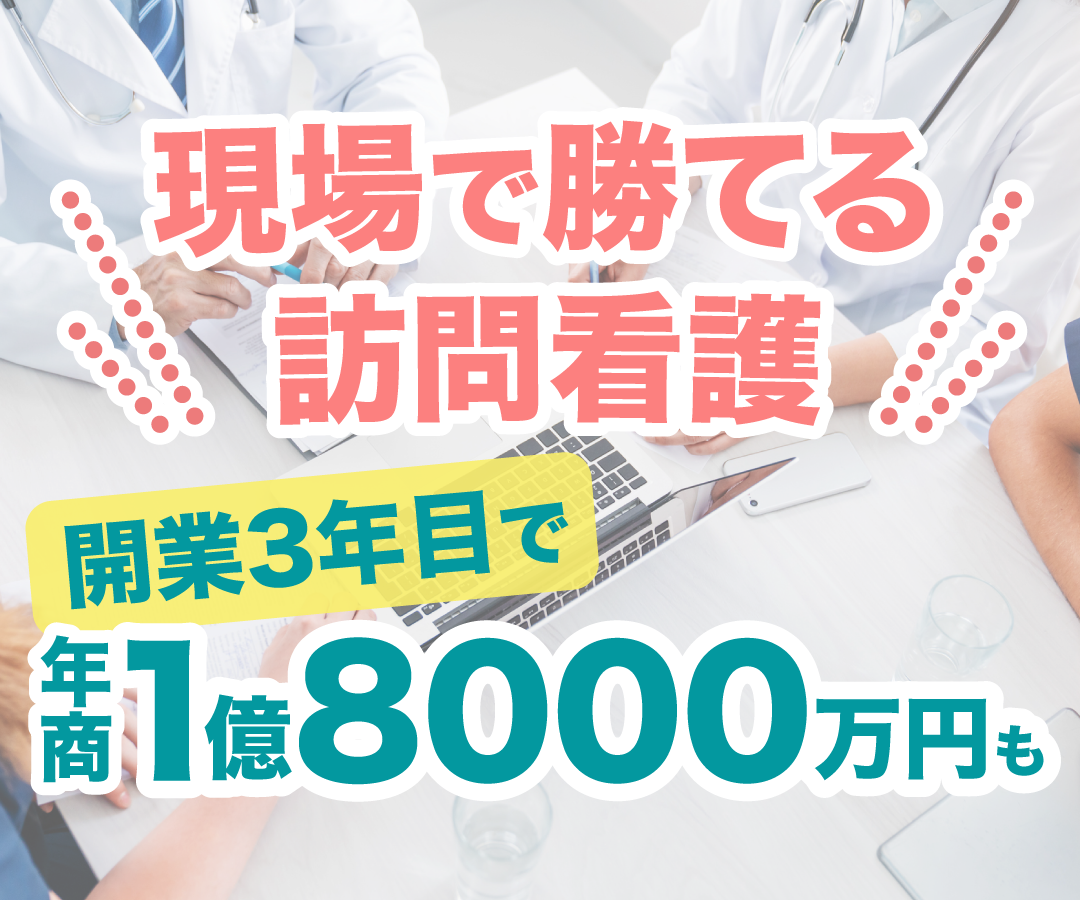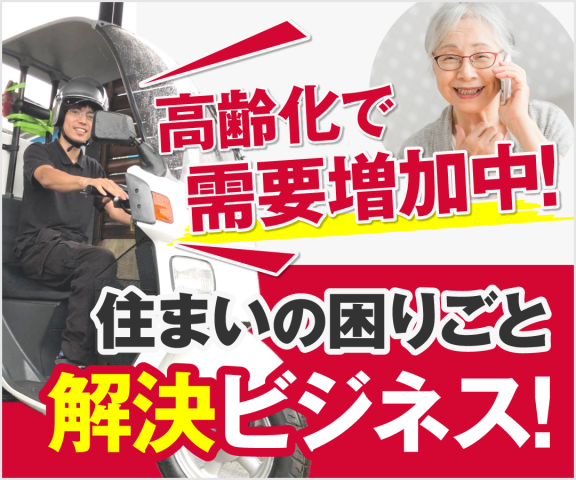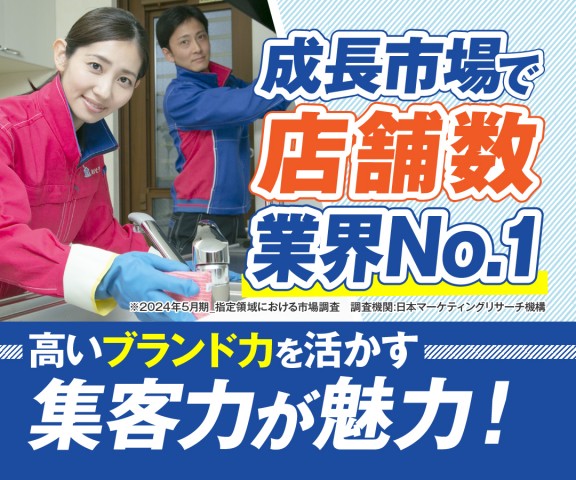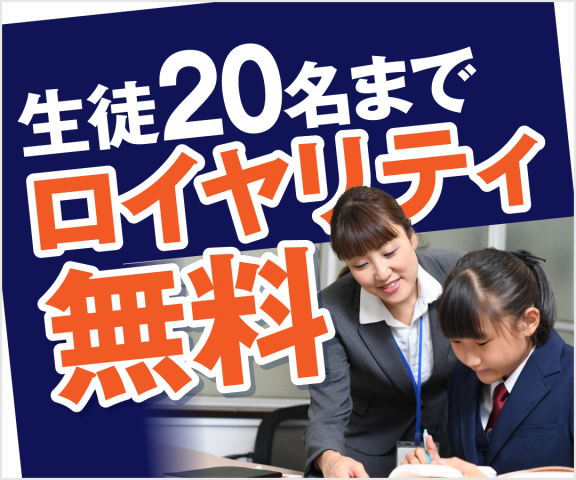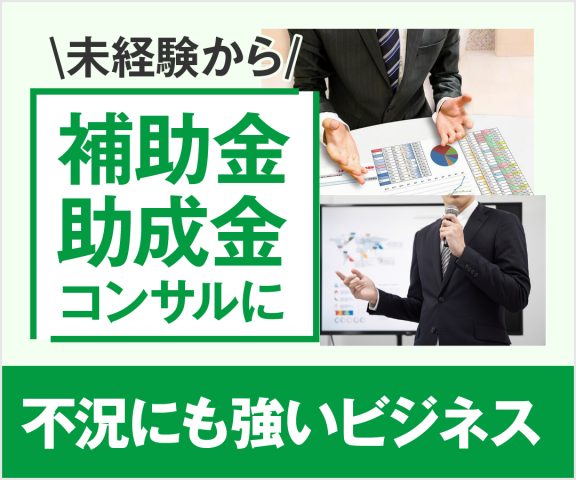個人事業主は給与が0円!お金の管理はどうしてる?生活費を経費計上する方法や節税対策を解説

個人事業主は給与が発生しないという話を聞いたことがある人は少ないかもしれません。企業に雇用されて働いている場合、労働の対価は雇用主から給与として受け取ることになります。そのため、会社員の経験しかない人などは、個人事業主がどのように事業の利益を生活費に回しているのかイメージできない場合もあるでしょう。
そこで今回は、自分自身への給与の支払いが可能なのか、個人事業主はどのように生活費を管理していくと良いのかを紹介し、会計処理の方法についても詳しく解説します。
個人事業主に給与はない!経費にできないので注意
個人事業主はいくら働いても、給料という形で報酬を受け取ることはありません。会社員とはまったく異なる方法で、生活費として使うお金を口座や財布などに収めているのです。これを理解するには、両者の働き方に関する根本的な違いも把握しておかなければなりません。その違いも含め、個人事業主に給与がないことに関して以下で説明します。
会社員との違い
会社員は文字どおり会社に所属しながら働いており、雇用主との間に雇用契約が成立しているという特徴があります。毎月一定の給与をもらえるのは、その雇用契約によって支給がしっかりと規定されているからです。
それに対して、個人事業主はどこかに所属して働いているわけではありません。もちろん、誰とも雇用契約を結んでいないので、給与を受け取るという概念自体も存在しないことになります。したがって、自分自身に報酬を支払って、それを経費に計上することも不可能です。
事業で得た収入から経費を捻出するのと同様に、生活費も引き出して暮らしていくことになります。
事業所得をすべて使えるわけではない
個人事業主が事業によって得た所得は事業所得に分類されます。給与所得はすべてを生活費に回すことも可能ですが、事業所得はそういうわけにはいきません。事業所得は、事業で必要となる経費の支払いも、そのなかから行なうことになるため、資金を確保しておく必要があるからです。
また、確定申告の後に納税する資金も事業所得から工面するのが一般的となっています。事業所得の金額が大きくなれば、所得税や事業税の課税額も増えていくので、事業が順調なときも先を見通しておくことが大切です。たくさん稼げたからといって、油断して生活費に回しすぎると、納税できなくなるので気を付けましょう。
[PR]高齢者向けビジネス特集
家族には給与を支払える!
事業主の生活費は経費になりませんが、家族関連のお金を経費として扱えるケースも存在します。それは配偶者やその他の家族に事業を手伝ってもらっている場合です。
そういった家族従業員は専従者と呼ばれており、個人事業主が給与を支払った場合はその支出を経費として処理できます。ただし、個人事業主は青色申告を行なっていることが条件であり、さらに「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出していなければなりません。
一方、白色申告の場合も、専従者に支払った給与は節税に役立ちますが、こちらに関しては控除という形になります。確定申告書に控除額を記載できる欄があり、定められた上限までの範囲内で事業所得に応じて対象となる仕組みです。
給与を支払うときの注意点
「青色事業専従者給与に関する届出書」(以下、届出書)とは、青色事業専従者給与額を必要経費にするための届出書であり、事業主が申告する必要があります。届出書は3月15日までに提出しなければなりませんが、新規に青色専業専従者になった人がいるケース、新たに事業を始めたケースでは2カ月に提出する必要があります。届出書の内容と異なる給与規定がある場合は、写しの提出も必要です。
なお、届出書の提出により家族への報酬を控除できますが、一定の条件をクリアしていることが前提です。まず、ほかに仕事をしていない15歳以上であることと、事業主である青色申告者と生計を一にする親族であること、そして6カ月を超えて申告者の事業に専従していることの3つが条件になります。
事業のお金と生活費はどう区別する?
法人は事業に関する収支と生活費は明確に分かれているのに対し、個人事業主はそれらが一緒になっているケースも多く見受けられます。事業用と生活費用の通帳を個々に用意すれば、ある程度の区別は可能になりますが、それでも入金や支払いの都合により完全に独立させるのは困難です。
たとえば、自宅の一部を事務所として使用している場合、電気代や通信費などの支払いのなかには、事業と生活の両方で使用した分が含まれていることになります。そのため、事業用の口座から引き落とした場合、生活費の一部もそこから支払ったことになるのです。
このような現象が起こるのは、個人事業主にとって仕方がないことなので特に問題ではありません。同様に、事業用口座に入っている事業所得から生活費を引き出すのも自由ですが、いずれにせよ帳簿に記入して管理しておく必要があります。
事業のお金と生活費は帳簿で管理
個人事業主の収支の管理は基本的に帳簿で行なうことになります。生活費に関する記載に間違いがあると、全体の計算が合わなくなり、確定申告の時期に困ることになりかねかません。とはいえ、コツさえ知っていれば決して難しくはないので心配しなくても大丈夫です。ここでは、個人事業主の生活費の帳簿の付け方に関して方法や事例を紹介していきます。
生活費は事業主貸
帳簿上の生活費の処理においてポイントになるのは、事業に関係がない支出を意味する「事業主貸」です。生活費を引き出したり支払ったりするなど、事業の収支計算に影響しない支出の場面では、勘定科目として事業主貸を使うというルールになっています。
また、事業主貸の特徴として、個人事業に特有のものであり法人会計には存在しないことが挙げられます。事業に関係のない収入を意味する「事業主借」とともに、個人事業主の帳簿付けにおける使用頻度はとても高いのが一般的です。

事業用とプライベート用で口座を分けよう
事業主貸という勘定科目を使えば、事業用の口座しか持っていなくても生活費の支払いを行なえますが、プライベートで出費するたびに、記帳をしなければならないのが大きな問題です。そのため事業用とは別にプライベート用の口座を用意しておき、定期的に生活費を移すようにすれば、記帳するのはそのタイミングだけで良くなります。
また、口座以外もできるだけ分けておくと、さらに手間が減って生活費も使いやすくなるでしょう。クレジットカードを別にしておけば、請求が混じらないので処理しやすいですし、交通系電子マネーのカードも個々に用意しておくと、プライベートで使った分を間違えて経費に計上するリスクを小さくできます。
生活費を経費に計上できない
個人事業の会計で生活費の処理をする際、最も注意しなければならないのは経費として処理しないことです。課税額を不当に下げる行為なので、うっかりミスをしないように気を付けましょう。
事業主貸として処理するなら課税額に何の影響もありませんし、プライベートなお金の用途は個人の自由なので、いくら計上することになっても基本的には問題ありません。ただし、売上と比べて生活費が多すぎると見なされた場合、税務調査の対象になってしまう恐れがあります。
たとえば、売上が300万円以下であるのに対し、生活費に500万円以上もかけているようであれば、申告していない収入の存在を疑われるケースもあるでしょう。事業主貸の金額が常識的な範囲に収まっていれば、そのような疑いは受けずに済みます。
家賃・光熱費はどうする?
生活に関する費用を経費計上することはできないとお伝えしましたが、生活するうえで必要な経費の一部を計上できる方法があるので押さえておきましょう。たとえば、自宅兼事務所として仕事をしている場合、家賃や光熱費、通信費などの費用が発生します。このような事業用とプライベートの両方で使用していて、まとめて支払っている費用を家事関連費と呼びます。
家事関連費は事業用にも使っているので経費扱いにできると考える人もいるかもしれませんが、そのすべてを経費として計上することはできません。経費計上できるのは、プライベート用部分の費用を除いて事業に使ったお金だと認められる場合だけです。これを家事按分と言います。また、事業経費を経費計上できるとしても、概算で算出して計上できるわけではなく、きちんと計算する必要があるので気をつけましょう。
なお、事業経費に使った分の金額を経費計上できるのは青色申告者のみで、白色申告の場合は家事関連費がおよそ50%を超えなければ経費計上することはできません。
家事按分の目安と算出方法
ここでは、家賃と電気代を例にして家事按分の目安を見ていきましょう。大事なポイントは、申告者自身の主観によるものではなく、客観的かつ合理的に説明できる判断基準によって計算されていることです。
| 家賃 | 延べ床面積に占める作業スペースの割合から算出 |
|---|---|
| 1日の在宅時間に占める業務時間の割合から算出 | |
| 電気代 | 作業スペースにあるコンセント数の割合から算出 |
| 1カ月の電気代に占める業務時間の割合から算出 |
では、1つずつ計算方法を見ていきましょう。いずれの場合も家事按分比率を先に計算した後で事業経費と生活費を算出します。
【家賃】延べ床面積に占める作業スペースの割合から算出する例
家賃が15万円で、延べ床面積が50平米の自宅のうち、8平米を作業スペースとして使用していると仮定
8平米 ÷ 50平米 = 16%
15万円 × 16% = 2万4,000円(事業経費)
15万円 - 2万4,000円 = 12万6,000円(生活費)
【家賃】1日の在宅時間に占める業務時間の割合から算出する例
家賃が15万円で、在宅時間が20時間のうち、業務時間が6時間と仮定
6時間 ÷ 20時間= 30%
15万円 × 30% = 4万5,000円(事業経費)
15万円 - 4万5,000円 = 10万5,000円(生活費)
【電気代】作業スペースにあるコンセント数の割合から算出
1カ月当たりの電気代が1万5,000円の住戸で、コンセントの数が10個あり、そのうちの2個を事務所スペースのコンセントに使用していると仮定
2個 ÷ 10個 = 20%
1万5,000円 × 20% = 3,000円(事業経費)
1万5,000円 - 3,000円 = 1万2,000円(生活費)
【電気代】1カ月の電気代に占める業務時間の割合から算出
1カ月当たりの電気代が1万5,000円の住戸で、1カ月あたりの業務時間が132時間と仮定
132時間 ÷ 720時間 = 18.3%
1万5,000円 × 18.3% = 2,745円(事業経費)
1万5,000円 - 2,745円 = 1万2,255円(生活費)
以上のように、家賃の経費計上可能額には2万円以上もの差が出ました。客観的かつ合理的な説明ができる経費計上のやり方であれば認められるので、経費額が最も大きくなる方法で申告しても問題ありません。ご自身の状況に照らし合わせて算出してみましょう。
事業と生活のお金はしっかり記帳を!
個人事業主は雇われていないので給与という概念は存在しません。生活費は事業用の口座から自由に引き出して問題ありませんが、事業主貸という勘定科目を使って、きちんと帳簿で管理していくことが条件となります。
いい加減に記帳していると、いざ税務調査を受ける際にとても困ってしまうので要注意です。堂々と提示して説明できるように、生活費の処理の仕方を決めたうえで、日頃から正確に帳簿をつけておきましょう。
事業主貸はいくらまで可能?個人事業主の生活費に関する注意点
個人事業の会計で生活費の処理をする際、最も注意しなければならないのは経費として処理しないことです。課税額を不当に下げる行為なので、うっかりミスをしないように気を付けましょう。
事業主貸として処理するなら課税額に何の影響もありませんし、プライベートなお金の用途は個人の自由なので、いくら計上することになっても基本的には問題ありません。ただし、売上と比べて生活費が多すぎると見なされた場合、税務調査の対象になってしまう恐れがあります。 たとえば、売上が300万円以下であるのに対し、生活費に500万円以上もかけているようであれば、申告していない収入の存在を疑われるケースもあるでしょう。事業主貸の金額が常識的な範囲に収まっていれば、そのような疑いは受けずに済みます。
[PR]ロイヤリティ無料のフランチャイズ
生活費を経費として計上するなら法人化を検討

個人事業主のままでは事業所得になるので手取り分を経費にできない一方で、法人化によって自分に支払った給料を経費として計上できるようになります。専従者として働いている家族に支払った給料も経費扱いです。ただし、経費扱いにするためには、以下に挙げる給料の支払われ方のいずれかに該当しなければなりません。
・定期同額給与…月に1回など、一定期間に同じ金額が支給される給与体系
・事前確定届出給与…所定の日に所定の金額を支給する給与体系で税務署に届け出が必要
・業績連動給与…法人の業績に連動して支給される給与体系で、金額は事前に確定していない
法人なら自宅を社宅扱いにできる
個人事業主が賃貸物件を事務所とする場合、家事按分により一定の割合を経費扱いにできます。ただし、常識の範囲内でなければ経費として認められないのがデメリットです。ところが、法人化をして賃貸物件の自宅を社宅扱いにすると、家賃の5割程度、最大では9割程度を経費扱いにできます。
仕組みは、賃貸借名義を会社に変更して会社が社長に社宅を貸し出します。そして、社長は会社に、会社は貸主にそれぞれ家賃を支払う形です。この場合、地代家賃は経費計上できるので会社は節税につながります。社長としては家賃負担額が軽減するので生活費に余裕ができるでしょう。
しかも、1カ月あたり一定額の家賃が支払われている場合は給与として課税されない社宅にできるというルールもあるので、社長個人の負担割合を減らし、会社の負担割合を増やすことによって経費を最大化できます。
法人成りの目安
個人事業主のなかには、どれだけの年間利益があると法人成りしたほうが良いのかと悩んでいる人も多いかもしれません。法人成りへの一般的な目安は、600~800万円程度の年間利益を得られるようになったときだといわれています。たとえば、年間700万円の利益がある個人事業主の場合、所得税が23%、住民税が約10%なので、トータルで33%ほどの税金を納めなければなりません。しかし、法人成りをすると税率が合計で25%ほどになるため、およそ8%も節税できるのです。金額にすると約56万円にもなるので大きな違いになります。
法人成りするには会社を設立するための登記手続きが必要であるため費用がかかりますし、個人事業主時代よりも複雑な税務申告書の作成もしなければなりません。しかし、デメリット部分を考慮しても、法人成りするメリットのほうが大きいので、利益額が大きくなった際は検討することをおすすめします。