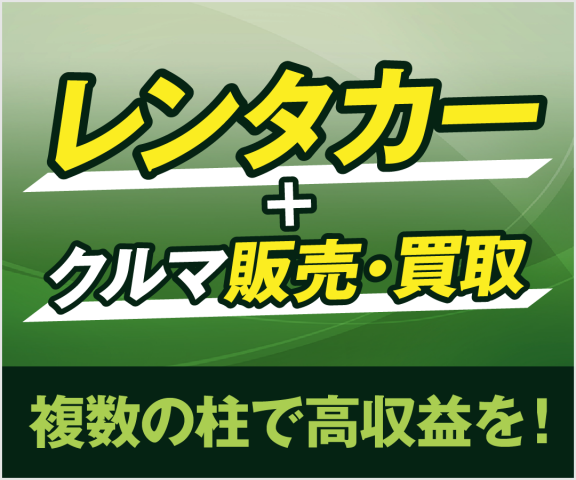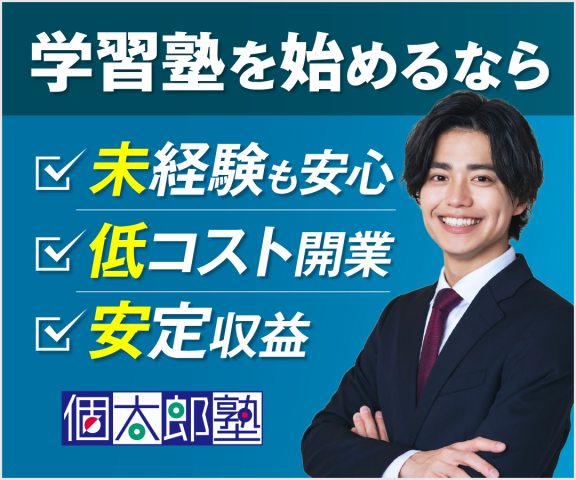納税証明書はどこで発行する?入手方法や手続きの際の注意点とは

独立開業を検討している場合、融資などで必要になってくる納税証明書。発行場所や入手方法について知りたいという人もいるでしょう。
納税証明書はさまざまな場面で必要になるので、この記事では、納税証明書の種類や入手方法を紹介していきます。納税証明書について知ってから、安心して開業準備を進めましょう。
国税の納税証明書の種類
国税の納税証明書というのは、きちんと納税をおこなっていることを証明するために提出するものです。納税証明書には、納付すべき税額、実際に納付した税額、未納・滞納となっている税額が記載されていますが、細かく分けると「その1~その4」までの4種類が存在していて、それぞれ証明する内容が異なっているのが特徴です。
「その1」—— 納付すべき税額や納付した税額と未納税額の証明
「その2」—— 所得金額を証明する書類
「その3」—— 未納の税額がないことの証明
「その4」—— 滞納処分を受けていないことの証明
納税証明書の提出先がどのような情報を知りたいのかを確認し、その指定に合った納税証明書を用意しなくてはいけないので、提出を求められたときには、どの証明書を提出すべきなのかを確認しましょう。
[PR]物件取得費が抑えられる居抜き物件
国税の納税証明書の入手方法について
国税の納税証明書を手に入れるためには、いくつかの方法があります。ここでは、その入手方法について、窓口、書類送付、オンラインの3つに分けて紹介していきます。
税務署窓口
国税の納税証明書を税務署窓口で直接受け取りたいという場合には、所轄の税務署に、納税証明書交付請求書を提出することで、納税証明書を入手することができます。本人が行く場合は、納税証明書交付請求書以外に、手数料の金額に相当する収入印紙または現金、本人確認書類、印鑑を持参してください。
しかし、場合によっては本人ではなく代理人が行くということもあるかもしれません。代理人が行く場合も納税証明書交付請求書を持っていく必要がありますが、作成せずに行くと代理人の印鑑が必要になるので気を付けましょう。また、本人の委任状、手数料の金額に相当する収入印紙または現金、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑も持参してください。
書類送付
国税の納税証明書は郵送でも受け取ることができます。郵送の場合は、納税証明書交付請求書と手数料に相当する収入印紙、返信封筒を送付するようにしましょう。郵送では収入印紙を送るという点がポイントです。
郵送の場合は、手数料の現金納付はできないので注意が必要になります。収入印紙は、納税証明書交付請求書の所定の場所へ貼り、消印を押さないように気を付けます。なお、納税証明書は、請求した本人もしくは法人、代理人本人の住所と事務所以外の関係のない住所に送ることはできません。
オンライン
オンラインで交付請求した場合には、税務署窓口で直接受け取るか、もしくは郵送で受け取る方法があります。税務署窓口で受け取る場合は、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を使い、必要事項を記入するだけで請求ができます。電子証明書を用意する必要はありません。
受け取りの際には、本人確認書類を持っていきましょう。また、法人の場合は不要になりますが、個人の場合は個人番号カードまたは通知カードなどの番号確認書類の提示が必要です。代理人が取りに行く場合は、委任状や代理人の本人確認書類が必要となるので、事前に確認してから行きましょう。
一方、郵送で受け取る場合も、請求は窓口受け取りと同様にe-Taxで行ないます。なお、郵送での受け取りをする場合は、e-Taxの請求に加えて、電子証明書を添付する必要があるので気を付けてください。
国税の納税証明書の発行手数料
国税の納税証明書を発行してもらうには発行手数料がかかります。ここでは、納税証明書はどのくらいの発行手数料がかかるのかを紹介していきます。
納税証明書「その1」・「その2」の場合
納税証明書「その1」と「その2」の場合に関して、受け取り方法によって金額が変わります。
窓口と郵送の場合:税目数×年度数×枚数×400円
オンラインの場合:税目数×年度数×枚数×370円
収入印紙または現金で用意するようにしてください。なお、収入印紙の場合は、消印があると無効になるので、消印をしないように気を付けましょう。
納税証明書「その3」・「その4」の場合
納税証明書「その3」と「その4」の場合も、納税証明書「その1」・「その2」の場合と同様に、受け取り方法によって金額が変わります。
窓口と郵送の場合:枚数×400円
オンラインの場合:枚数×370円
納税証明書「その1」・「その2」と異なり、税目数と年度数は計算に入らないので注意してください。
[PR]趣味を活かす・好きを仕事に
事業税や住民税の納税証明書はどこで発行できるか
事業税や住民税の納税証明書は、管轄の都道府県税事務所や市区町村役場で発行が可能です。
発行においては、納税証明書交付請求書を提出しなくてはいけません。なお、証明書には、事業税や住民税の納税証明書のほかにも、滞納がないことへの証明書や未納のないことに対する証明書などさまざまな種類があるので、どの種類が必要なのかを確認してから発行するようにしましょう。
納税証明書が必要な場面とは
納税証明書は、融資や住宅ローンの審査の際に必要になることが多くなっています。そのため、これから独立開業を考えている人は、発行しなくてはいけない機会が増える可能性があります。なお、納税証明書にはいくつか種類があるため、必要になった際は事前にどの証明書が必要なのか確認しておくようにしましょう。
[PR]未経験・初心者でも安心のビジネス
納税証明書の発行時の注意点
納税証明書を発行するときには、いくつかの注意点があります。ここでは、納税証明書の発行時の注意点を紹介するので、発行時の参考にしてみてください。
開業・会社設立直後は発行されない
まずは、開業・会社設立直後は発行されないという点を挙げることができます。納税証明書は、基本的に納税したことを証明する書類になります。そのため、納税を行なっていない開業・会社設立直後は発行できない仕組みなのです。
会社設立後、少なくとも第1期の決算と税務申告・納税が終われば取得できるので、その時期まで待つ必要があります。ちなみに、納税証明書が発行されるまでの期間は法人設立届の控えや直近の試算表が、会社の実績を表す書類になりますが、効力が弱いので気をつけましょう。
発行枚数が多い場合時間がかかることもある
発行枚数が多い場合は時間がかかることもあるという点も気を付けなくてはいけません。場合によっては納税証明書の必要枚数が多くなる可能性もあり、発行枚数が多くなるほど発行されるまでに時間を要することもあるため、時間に余裕を持って請求するように心がけましょう。
代理人が手続きする場合は必要なものが異なる
納税証明書を発行する場合、本人や会社の代表者が行くのであれば問題ありませんが、代理人が手続きを行う場合は、本人の場合と比べて必要なものが異なるので気を付けてください。
本人が手続きをする場合は、印鑑や納税証明書交付請求書が必要になりますが、代理人が申請する場合は、委任状も必要になるため注意が必要です。委任状がないと本人に電話で確認をしなくてはいけないこともあるので、手間がかかってしまいます。
納税証明書はどこで発行するか事前に把握しておこう!
国税の納税証明書は金融機関から融資を受けたりする際に必要な書類になるため、発行方法を確認しておく必要があります。また、納税証明書にもいくつかの種類があるので、それぞれどのような内容を証明するものなのかを確認して、必要な場合は事前に提出先に聞くなどしてから発行手続きをすると、スムーズに発行ができるでしょう。
[PR]居酒屋・BARビジネス特集