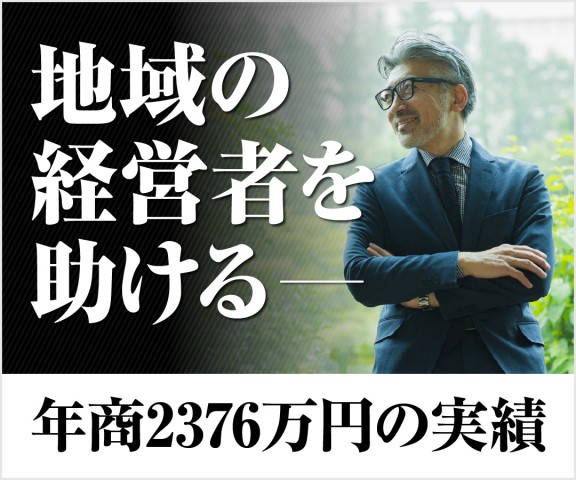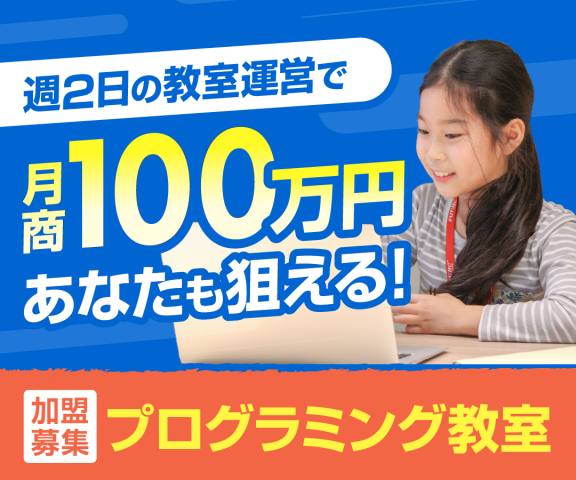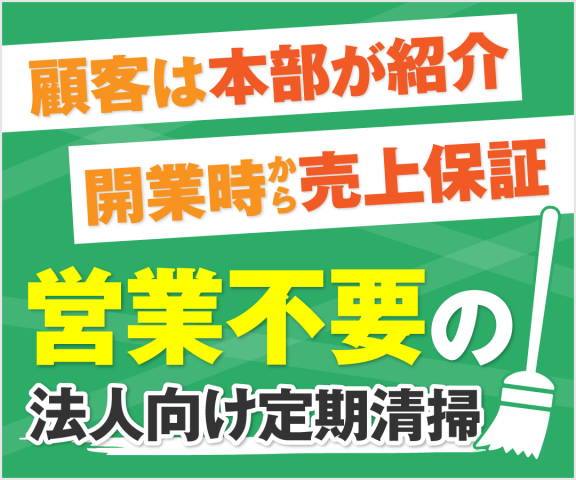源泉徴収は必要?源泉徴収義務者に該当するケースや計算方法を徹底解説

独立起業して人を雇ったり、仕事を外注する際には、源泉徴収の仕組みや手続きについて把握しておく必要があります。しかし、これから起業を考えている人のなかには、ハードルが高く感じている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、源泉徴収をする側である源泉徴収義務者に該当する条件や、納税額の計算方法について例を挙げて紹介していきます。
源泉徴収制度について
そもそも源泉徴収制度とは、給与の支払いをする人が、給与から源泉徴収額を差し引き税務署に納税する制度のことです。給与を受け取る人ではなく、支払いをする人が代わりにこの手続きをすることで、申告漏れを防げるというメリットがあります。
源泉徴収をする経営者や個人事業主のことを、源泉徴収義務者と呼びます。ただし、源泉徴収義務者に当てはまるにはいくつかの条件があるので、自分が該当するかどうかを確認しておくことは非常に重要です。
[PR]自己資金100万円以下で独立可能
源泉徴収義務者となるケース・ならないケース
ここでは、源泉徴収義務者に当てはまるケース・当てはまらないケースを紹介します。該当するかどうかによって必要な手続きが変わってくるので、しっかりとチェックしておきましょう。
源泉徴収義務者となるケース
源泉徴収義務者としては、基本的に従業員がいて給与を支払っている法人・個人事業主が該当します。この従業員には、フルタイムだけでなくパートやアルバイトも含まれるので注意が必要です。
青色申告の個人事業主が配偶者や子ども、親族など青色事業専従者への給与・退職金を支払う場合にも、原則として源泉徴収義務者になります。家族に事業を手伝ってもらい、給与などを支払ったときにも源泉徴収義務者となるのです。
それから、気を付けなければいけないのはホステスやコンパニオンに給与を支払う場合です。こうしたケースでは、源泉徴収義務者でなくても源泉徴収をする必要があるので注意しましょう。クラブやバーを経営する人は、特に気を付けるべきポイントです。
源泉徴収義務者とならないケース
源泉徴収義務者に該当しないケースとして、まず従業員を雇っていない個人事業主が挙げられます。1人で事業を行なっている個人事業主は、基本的に源泉徴収義務者とはなりません。
また、常時2人以下で、家事手伝いをしているような人へ給料を支払っている場合にも対象外となります。それから、税理士や弁護士に対しての報酬についても源泉徴収をする必要はないので覚えておきましょう。
源泉徴収義務者に該当する場合にすべきこと
事業を行なうなかで規模を拡大し、新しく従業員を雇うことがあるかもしれません。もし、それによって源泉徴収義務者に該当する場合には、やらなければならない手続きがあります。
それが、国税庁のホームページからダウンロードできる「給与支払事務所等の開設届出書」という書類を税務署に提出することです。提出には、給与を支払う事務所を開設してから1カ月という期限があるのでくれぐれも注意しましょう。
しかし、すべての人が提出しなければならないわけではありません。個人事業主が事業をスタートさせる際には「個人事業の開業等届出書」というものを提出しますが、この書類の提出をしていれば「給与支払事務所等の開設届出書」を届け出る必要はありません。
[PR]脱サラした先輩が選んだビジネス
給与・報酬においての源泉徴収税額の計算方法
給与に対しての源泉徴収税額
給与に対する源泉徴収税額は「源泉徴収税額表」をもとに算出できる仕組みになっています。源泉徴収税額表は、年度ごとに国税庁がインターネット上で公開しており、誰でも簡単に手に入れられます。
給与の金額と扶養家族の人数によって一目で金額がわかるので、表の見方も簡単です。たとえば、給与が35万で扶養家族が1人の場合、表を見ていくと9350円が源泉徴収税額になります。
報酬に対しての源泉徴収税額
ここでは、報酬に対しての源泉徴収税額を金額別で紹介していきます。報酬の金額によって源泉徴収税額の計算方法が変わってくるので、注意しましょう。
支払金額100万円以下の場合
報酬の支払い金額が100万円以下の場合、計算方法はそれほど難しくありません。
支払金額×10.21%
上記の計算式に当てはめれば、源泉徴収税額を求めることが可能です。たとえば、支払額が80万円の場合には「80万円×10.21%」で8万1680円が源泉徴収税額になります。
報酬の支払い金額が変わっても、100万円以下であればこの計算式を用いて計算できます。計算式は国税庁のホームページに載っているので、覚える必要はありません。
支払金額100万円以上の場合
報酬の支払い金額が100万円を超えてくる場合、源泉徴収税額を求める計算式は変わってきます。
(支払金額-100万円)×20.42%+10万2100円
たとえば、支払金額が120万円だった場合「(120万円-100万円)×20.42%+10万2100円」で、14万2940円になるのです。計算式が少しややこしく、ハードルが高いように感じるかもしれませんが、支払い金額を代入して計算するだけなので心配ありません。こちらの計算式も、国税庁のホームページから簡単に調べられます。
源泉徴収税はいつまでに支払う?
源泉徴収税の納付は「給与支払日の翌月10日に行うこと」というルールがあります。ただし、従業員の人数が10人未満であれば、半年ごとの納付も可能です。この場合、1~6月の分は7月10日まで、7~12月までの分は翌年の1月10日までと、日にちがきちんと決められているので気を付けてください。
また、もし半年ごとに納付をする場合には「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があるので注意しましょう。
[PR]赤字補填・収入保障・黒字保証があるフランチャイズ
源泉徴収を行う際の4つの注意点
ここでは、源泉徴収を行う際の4つの注意点を紹介します。どれも大切なポイントなので、しっかり覚えておきましょう。
源泉徴収義務違反は罰則がある
源泉徴収は、きちんと手続きを行わなかったときや納付が遅れてしまったとき、罰則が科せられることになります。
まず、不納付加算税といって、納付期限に間に合わなかった場合に納付額の5~10%が加算されます。これは加算税のひとつですが、源泉所得税だけに適応されるようになっているものです。
それから、延滞税といって納付期限から実際に納付するまでの日数に応じた利子を支払う必要があります。このような罰則を受けないためにも、期限までにきちんと源泉徴収を行うようにしましょう。
源泉徴収税額表は毎年更新される
源泉徴収税額を算出するために使用する「源泉徴収税額表」は、毎年同じものではありません。場合によっては内容に変更がなく、結果的に前年度と同じ金額になることもあるでしょう。しかし、基本的には毎年更新されるものであるため、きちんと確認する必要があります。
所得税が1月1日から12月31日の所得によって課税されることから、源泉徴収税も1月に更新されるようになっています。源泉徴収税額表は国税庁のホームページから確認できるので、1月に支給する給与の計算をするときには、新しい源泉徴収税額表を使用しましょう。
不明点がある場合は自力で行わない
源泉徴収の手続きや計算をするにあたって、もしかしたらわからないことが出てくるかもしれません。そんなときに「まぁいいか」と考え、そのまま作業を進めてしまう人もいるかもしれませんが、源泉徴収は納税に関わる大切な手続きです。そのため、自力では行わないようにしましょう。
もし、わからない部分や疑問点などがあれば、きちんと税務署に問い合わせをすることが大切です。きちんと自分で理解して、正しく手続きや計算をするようにしましょう。
源泉徴収義務者に該当する人は忘れずに納付しよう
源泉徴収義務者に該当する場合は必要な手続きがあります。ただし、法人や個人事業主であっても源泉徴収義務者に当てはまらないケースがあるので、まずは自分が該当するかどうかの確認をしてみましょう。
源泉徴収義務者は源泉徴収をする必要があり、期限に遅れると罰則が科せられてしまいます。罰則を回避するためにも、忘れずに源泉徴収を行いましょう。