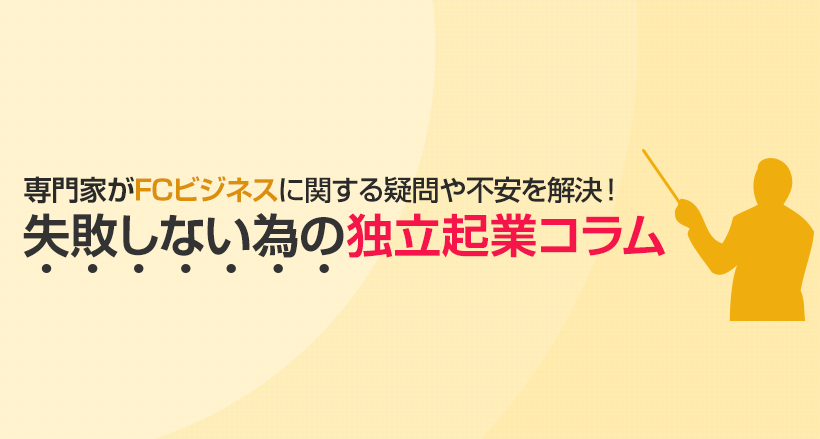|
2016-09-25 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム
株式会社PEOPLE&PLACE 代表取締役
松下 雅憲 |
マクドナルドが実践している『目的』を意識させるスタッフ教育

このコラムのポイント
世の中にはいろんな業種・業態が存在しますが、そこで働く人もまた個性豊かです。性格も気質も、まさに十人十色。新規の人材確保が難しいと言われる今の時代、入ってくれたスタッフ教育が店舗運営において重要なポイントとなるでしょう。 今回のコラムでは、代表的大手チェーン「マクドナルド」の徹底されたスタッフ教育の秘訣を垣間見ることができます。
フランチャイズWEBリポート編集部
ベテランスタッフから新人への問いかけ
「これって、なぜ3種類あるんだと思う?」
スタッフ教育の基本がきちんと出来ているお店では、教育担当者や店長 そしてベテランスタッフ達は、必ずこういう問いかけを新人スタッフに行います。
では、あなたに質問です。
Q. その「必ず使う言葉」とは、一体なんでしょうか?
それは、冒頭のスタッフの言葉の中に隠されています。
そうです。
A.「なぜ?」という言葉です。
A.「何のために?」という言い方も同じです。
この「なぜ?何のために?」と言う問いかけの答えは、そのまま『目的』につながります。
つまり、基本が出来ているお店というのは、新人スタッフを指導するときに、必ず「方法」と同時に『目的』を伝えている、と言うことなのです。
この「なぜ?何のために?」と言う問いかけの答えは、そのまま『目的』につながります。
つまり、基本が出来ているお店というのは、新人スタッフを指導するときに、必ず「方法」と同時に『目的』を伝えている、と言うことなのです。
『目的』を理解させる指導とその効果
冒頭の問いかけは、私が先日、客として利用したマクドナルドで、ベテランスタッフが新人スタッフに「客席でのダスターの使い方」について指導していたときの様子です。
マクドナルドでは、3種類、つまり3色のテーブルダスターを用途に合わせて使い分けています。
食品に触れる場所は「ピンク」、客席テーブルやレジカウンターの上は「グリーン」、そしてゴミ箱や椅子の座面などは「ホワイト」のダスターというふうに使い分けています。
※企業によっては4種類を使い分けているところもありますね。

新人教育をしていたベテランスタッフは、新人に「なぜ?何のために?」という問いかけをしながら、3種類を使い分ける「目的」について考えさせながら指導をしていたのです。
これが、「意識の低い」企業では、単純にルールや方法だけを伝えます。
そういう企業の教育担当者や幹部は、「これは、こういう風に決まっているからね。その通りにやってね」という言い方しかしないのです。悲しいですね。
こんな指導でも、それなりに、なんとか覚えることの出来る新人もいるでしょうけれど、中には勘違いしたり、忘れてしまったりする新人もいるのです。
そういう時に、ただルールや方法だけを伝えていたら、間違いを犯す可能性が高まってしまうのです。
新人に「なぜ?何のために?」と考えさせ『目的』を理解させるような指導方法を採っていると、(1)そこに『目的』があることを深く認識しているので、いい加減な判断をしなくなるのです。(2)もし仮に「方法」を忘れてしまっても『目的』があること解っていれば、先輩に尋ねるという行動を取るようになります。

新人教育をしていたベテランスタッフは、新人に「なぜ?何のために?」という問いかけをしながら、3種類を使い分ける「目的」について考えさせながら指導をしていたのです。
これが、「意識の低い」企業では、単純にルールや方法だけを伝えます。
そういう企業の教育担当者や幹部は、「これは、こういう風に決まっているからね。その通りにやってね」という言い方しかしないのです。悲しいですね。
こんな指導でも、それなりに、なんとか覚えることの出来る新人もいるでしょうけれど、中には勘違いしたり、忘れてしまったりする新人もいるのです。
そういう時に、ただルールや方法だけを伝えていたら、間違いを犯す可能性が高まってしまうのです。
新人に「なぜ?何のために?」と考えさせ『目的』を理解させるような指導方法を採っていると、(1)そこに『目的』があることを深く認識しているので、いい加減な判断をしなくなるのです。(2)もし仮に「方法」を忘れてしまっても『目的』があること解っていれば、先輩に尋ねるという行動を取るようになります。
つまり、「まあ、これくらいは」「こんなもんでも良いだろう」などと、自分勝手にいい加減な判断をしなくなるのです。
間違いや事故を起こさないために
ダスターの間違いならば、まだ取り返しはつくかも知れません。しかし「間違い」の対象が、料理そのものであったり、原材料の使用期限であったりすると、会社として致命的な問題に発展してしまうことさえあるのです。
たとえば、ある企業では…
・フライヤーの油に間違って洗剤を混入させてしまった
・お客様用のドリンクに殺菌液を混入させてしまった
という、とんでもない事故を起こしてしまいました。こうした事故は(私の推測ですが)恐らく、ルールしか教えていなかったことに起因しているのではないかと思うのです。
お店の中のルール、作業手順・方法には、必ず「なぜ?何のために?」という『目的』が存在します。お店でする作業には『目的』がないものは、ただのひとつもないのです。

多店舗展開し、多くの店を運営するチェーン企業においては、その「たったひとつの間違い」がチェーンの存続を大きく揺るがす致命傷にもなりかねません。
事故は、基本的に「人間」が引き起こすものです。その人間を指導・教育するのもまた「人間」です。「人間」は『考える』ことのできる動物です。
『考える』とは、「なぜ?何のために?」と問うことなのです。
そして、その答えが『目的』です。
そして、その答えが『目的』です。
おわりに
あなたのお店にもスタッフがたくさんいると思います。
彼らは、日頃やっている作業の『目的』をしっかりと理解していますか?
彼らがしっかりと「なぜ?何のために?」を理解する事で、リスクやロスが減り、生産性の向上にも繋がります。
ぜひ今いちど、「その作業は『なぜ?何のために?』やっているのか知っていますか?」とスタッフに問いかけてみましょう。