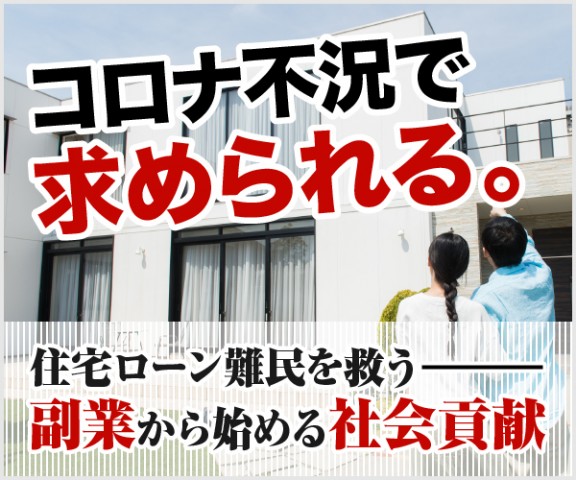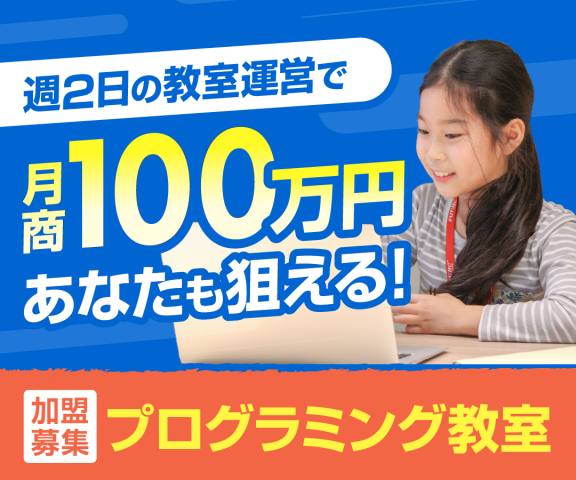経営に必須!キャッシュフローの基礎知識と活用するメリットとは
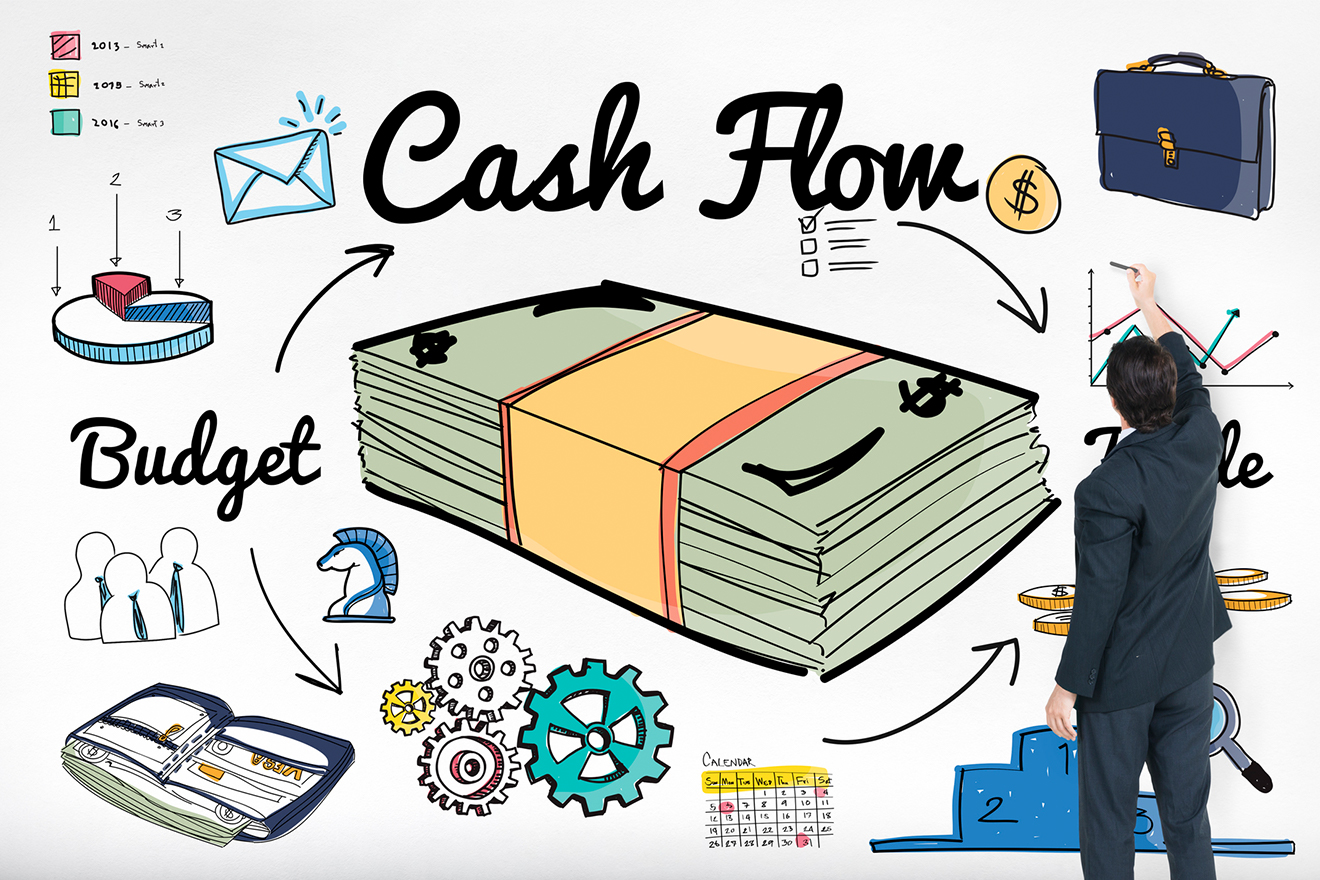
独立開業後は、利益を出すことはもちろん、事業を継続できるかどうかが最大の難所となります。その際に見ておくべきポイントが、お金の流れである「キャッシュフロー」です。
キャッシュフローを正確に把握できているかどうかは社会的信用にも関わるので、この記事では、キャッシュフローの意味や改善するべきポイント、管理方法などを解説します。
キャッシュフローとは
そもそもキャッシュフローとは「お金の出入り」を指す言葉です。事業を始めると、入ってくるお金として利益や融資などが出てきます。それに対し、出ていくお金として経費や配当金などが挙げられます。
これらのお金を正確に計上していかなくては、安定した会社経営は実現しません。そのため、ほとんどの経営者は「キャッシュフロー計算書」を作成してお金の動きを把握しています。キャッシュフロー計算書の精度は事業計画に関わってくることもあります。
キャッシュフローと利益の違い
企業間取引では、現金ではなく「掛け」で売買を行うのが一般的です。「掛け」で売買した場合、売上金が支払われるのは翌月末などになるため、利益が即座に現金化されるわけではありません。
例えば、今月に現金で50万円分の仕入れを行ない、掛けで100万円分売り上げた場合、今月の利益は50万円となるでしょう。しかし、掛け売りした分の現金は翌月以降に振り込まれるので、今月のキャッシュフローはマイナス50万円となるのです。
なお、売り上げが現金化できる早さは業種によって異なります。飲食店などの消費者向け小売業の場合、現金で支払ってもらえば売り上げがそのままキャッシュフローに加算されます。
一方、企業向けに商品やサービスを提供している場合は手形で売り上げを受け取ることが多いので、利益が現金化されるまでに時間がかかります。経営が黒字でも現金がなくなれば倒産のリスクが生じるため、業種ごとのキャッシュフローの特徴を理解しておくことが大切です。
知っておこう!キャッシュフロー経営について
経営者の中には「キャッシュフロー経営」を導入している人が多くいます。キャッシュフロー経営とは、常に利益だけでなく現金終始を意識しながら経営を進めていく方法です。
たとえば、損益計算書では黒字が出ていたとしても、手元に現金がなければ期限内に納税を行なったり、経費を支払ったりできない恐れもあります。キャッシュフロー経営では「実際に会社が使える資金を増やすこと」に焦点をあてているのが特徴で、「現金が増えれば経営も安定する」という考え方が中心にあります。
キャッシュフロー経営の2つのメリット
経営者がキャッシュフロー経営を行なうのであれば、メリットをしっかり押さえておきましょう。何のためにキャッシュフローを意識するのかを理解していれば、経営の考え方も変わっていくはずです。
信用の強化につながる
第一のメリットは「信用の強化」です。お金の流れを曖昧にしか把握していないと、銀行やスポンサーは不安に感じるので、希望額を融資してもらえないでしょう。しかし、キャッシュフロー経営を押し進めていくと、経営状況を堂々と開示できます。銀行などからの信用につながり、事業計画の説得力も増します。その結果、希望した額の融資を行なってもらえる可能性が高くなるでしょう。
想定外の事態にも余裕を持って対応ができる
第二のメリットは「対応力の改善」です。キャッシュフロー経営を導入すると、想定外のトラブルにも冷静に対処しやすくなります。
なぜ対応力が高まるのかというと、売掛や買掛による取引のみを行っている企業よりも現金を大切にできるからです。売掛や買掛の数字だけを信じて経営を行っている場合、取引先が急に倒産すると売掛金を回収できなくなる危険が生まれます。額によっては、経営に大きな痛手を負いかねません。
しかし、キャッシュフロー経営によって手元に現金を置くよう心がけていると、不測の事態にも備えられます。よほどのことがない限り、急激に経営状況が悪化するまでのケースは起こりにくいでしょう。
[PR]1人で独立開業できる仕事
キャッシュフローの3つの種類
一言で「キャッシュフロー経営」といっても、実態はさまざまです。会社経営において、キャッシュフローは3つの種類があるので、それぞれ、どんな場面でどのような考え方に基づいているのかを把握しておきましょう。
営業活動におけるキャッシュフロー
まずは「営業活動のキャッシュフロー」を重要視しましょう。営業活動は、企業の根本的な利益の源だといえます。その営業でどれだけのキャッシュを得られたのかを示すのが「営業活動のキャッシュフロー」です。営業活動のキャッシュフローが黒字であれば、経営状況は良好とみなせます。
反対に赤字の場合は、計上した売上を現金化できていない、利益が出ない商品を販売している、といった原因が考えられます。
営業活動におけるキャッシュフローには多岐に渡る項目があります。その理由は、他の2種類のキャッシュフローに含まれない項目がすべてここに分類されるからです。そのため、金融機関の利息や法人税の支払いなど、純粋に営業活動のキャッシュフローとはいえない項目も含まれています。
売上高に対する営業活動におけるキャッシュフローの割合を「キャッシュフローマージン」といい、数式で表すと以下の通りです。
「キャッシュフローマージン」=「営業活動におけるキャッシュフロー」÷「売上高」×100
キャッシュフローマージンの数値を確かめれば、自社がどれくらい健全にキャッシュフローを回しているのかが分かるでしょう。一般的に、キャッシュフローマージンが7%あれば経営は順調だといわれています。ただし、適切なキャッシュフローマージンは業種によって異なるので一概にはいえません。
投資活動におけるキャッシュフロー
企業が利益を出す方法は営業だけに留まりません。「投資活動におけるキャッシュフロー」も押さえておきたいところです。ここでは、固定資産の取得や売却によって生まれるお金の増減を把握します。なお、基本的に固定資産を取得するとキャッシュはマイナスになるものの、将来的には競争力の糧になる可能性もあります。優良企業の多くは、投資活動のキャッシュフローがマイナスです。
企業が投資活動に力を入れているかどうかは、投資活動におけるキャッシュフローの「固定資産の取得による支出」の金額から判断できます。この「固定資産の取得による支出」が営業活動のキャッシュフローにおける「減価償却費」を上回っていれば、投資活動は活発だといえるでしょう。
「営業活動におけるキャッシュフロー」と「投資活動におけるキャッシュフロー」の合計が、手元に残るお金、すなわち「フリー・キャッシュフロー」となります。フリー・キャッシュフローは有価証券の売買などを含めて計算することもありますが、ひとまず2種類のキャッシュフローの合計だと考えておけば問題ありません。
このフリー・キャッシュフローが多いほど、事業拡大の投資や株主への配当、借入金の返済などの活動が可能となり、順調に経営していくことができます。
財務活動におけるキャッシュフロー
企業が現金を得たり支払ったりする行為として、「財務活動」も挙げられます。「財務活動のキャッシュフロー」では、資金調達や返済で動いたお金の動きを表します。ここでのキャッシュフロー計算書を見れば、どこから資金調達をして、不足分がどのように補填されたのかが確認できます。
設備投資などの資金を工面するために借り入れを行なうと、財務活動におけるキャッシュフローはプラスになります。反対に、借入金を返済して自己資本比率を高めた場合はマイナスとなるでしょう。
すなわち、最終的に資金調達額が返済額を上回れば財務活動におけるキャッシュフローはプラスに、下回ればマイナスになります。
どう計算する?キャッシュフローの2つの表示方法
3種類のキャッシュフローのうち、営業活動におけるキャッシュフローには2つの表示方法があります。それぞれの企業に合ったやり方で計算をしましょう。
直接法
キャッシュフロー計算の「直接法」では、企業に出入りした現金をすべて計算対象とし、あらゆる現金の増減を表示します。直接法は正確性の高い手段ではあるものの、全項目を計算するのが手間です。さらに、現金出納管理を行っている人が計算しなければならないというルールがあります。
間接法
損益計算書を基点とするのが「間接法」です。お金の出入りがあるたびではなく、当期純利益が確定してから各項目を加減し表示させます。直接法よりも手間がかからないので、営業活動におけるキャッシュフローの表示では間接法に頼る企業が多くなっています。
[PR]新着フランチャイズ
間接法によるキャッシュフロー計算書の作り方
間接法では、損益計算書と賃借対照表の項目をもとにキャッシュフロー計算書を作っていきます。営業活動のキャッシュフローは、損益計算書の「税引前当期純利益」の項目を加減して計算します。加減するのは、「減価償却費」「貸倒引当金」「棚卸資産」「売上債権」「仕入債務」「利子利息」「法人税等」といった項目です。
投資活動のキャッシュフローは、「固定資産」または「有価証券」を購入したらマイナス、売却したらプラスで計算していきます。財務活動のキャッシュフローでは、「借入金の増加」「株式発行の収入」「利子利息の受け取り」などの項目をプラスで計算します。
一方、マイナスで計算するのが「借入金の返済」「自社株式の購入」「配当金の支払い」「利子利息の支払い」といった項目です。
このように、キャッシュフロー計算書は記載する項目さえわかっていれば簡単に作成できます。ただし、そのまま転記すべき項目と加減したうえで記載すべき項目があるので、作成の際は注意してください。
キャッシュフロー計算書と損益計算書・賃借対照表の関係
キャッシュフロー計算書と損益計算書、賃借対照表は「財務3表」と呼ばれており、それぞれ密接な関係があります。互いに連動する3つの書類の関係を知ることで、より詳細な経営分析ができるようになるでしょう。ここでは、キャッシュフロー計算書と損益計算書・賃借対照表の関係を紹介します。
キャッシュフロー計算書と損益計算書の関係
損益計算書は、営業活動におけるキャッシュフローと密接な関係がある書類です。前述のとおり、間接法でキャッシュフロー計算書を作成するとき、営業活動の部分は損益計算書の「税引前当期純利益」をもとに記載します。
損益計算書で利益が出ているにもかかわらず、営業活動におけるキャッシュフローがマイナスの場合は早急に原因を調べる必要があるでしょう。在庫が社内に眠っている、売掛金が適切に回収されていない、といった事態が予想されます。
キャッシュフロー計算書が企業の「現金を稼ぐ力」を表すものであるとすれば、損益計算書は「利益を稼ぐ力」を表すものだといえます。このように、キャッシュフロー計算書と損益計算書はお互いを補完し合うことで経営分析の役に立っているのです。
キャッシュフロー計算書と賃借対照表の関係
賃借対照表が「期末時点で企業にある資金」を表しているのに対して、キャッシュフロー計算書は「前期から今期にかけて企業の資金がどのように変動したのか」を表しています。すなわち、前期と今期の賃借対照表を橋渡しする存在がキャッシュフロー計算書だといえるのです。
賃借対照表における資産や負債の増減は、キャッシュフロー計算書におけるプラスマイナスに直結します。営業活動のキャッシュフローは賃借対照表の「流動資産・流動負債」に対応しており、キャッシュフロー計算書の「現金及び現金同等物」は賃借対照表の「現金・預金の合計額」に対応しています。このことからも、キャッシュフロー計算書と賃借対照表の間に深い関係があることがわかるでしょう。
重要なのは、賃借対照表における最終的な数字へと至るまでの経緯が、キャッシュフロー計算書を見れば把握できるということです。前期と比べて保有する現金が増えていた場合、賃借対照表だけでは借り入れによる増加なのか、それとも営業活動による増加なのか判断できません。しかし、キャッシュフロー計算書を参照すれば現金の動きが明確に把握できます。
[PR]新着フランチャイズ
キャッシュフロー計算書と資金繰り表の違い
企業における現金の流れを把握する書類には、キャッシュフロー計算書と資金繰り表の2種類があります。
これまで説明してきた通り、キャッシュフロー計算書は会計期間中の現金の流れを記したもので、過去の現金の流れを可視化することが作成の目的です。決算書の1つでもあり、上場企業などは作成したうえで外部に公表することが義務付けられています。
一方、資金繰り表は将来的な現金の流れを予測するために作成される書類です。会計年度に縛られる必要はなく、期間を自由に設定して作ることができます。あくまでも企業の内部資料なので、当然外部に公表する必要はありません。今後の事業計画などに基づいて現金の動きを予想し、より具体的な経営戦略を立てていく際に資金繰り表が役立ちます。
過去を振り返るためのキャッシュフロー計算書と、より良い未来に向けて作成する資金繰り表は、どちらも健全な経営のために欠かせない書類です。両者の違いを正しく理解し、活用しながら会社を運営することが大切だといえるでしょう。
[PR]既にお持ちの土地活用型
経営に必須!キャッシュフローを管理・改善する際の考え方
キャッシュフロー経営を導入したばかりだと、基本的な進め方もわからないことがあるでしょう。以下、キャッシュフローを管理、改善する際のコツを紹介します。
余裕をもった資金調達をする
営業活動がうまくいっているにもかかわらず、資金不足で各種の支払いが間に合わないと「黒字倒産」が起こります。つまり、キャッシュフロー経営では余裕をもった資金調達が鍵です。融資を受ける際には自社の返済能力を踏まえるようにしましょう。
利益を出すことを最優先に考える
最優先事項のひとつが「利益を出すこと」です。とにかく入ってくる現金を多くするのがキャッシュフロー経営の基本です。具体的には、粗利益を増やしたり、活動原価を見直したりしましょう。売上が一緒なら、原価は抑えたほうが黒字に近づけやすくなります。
売掛金などの売上債権を減らす
キャッシュフロー経営において、売掛金は重要視できません。売掛は手持ちの資金を減らす可能性の高いシステムだからです。そのため、売掛金を減らすための努力を行いましょう。なお、その際も売上は維持したままにすることが肝心です。
入金日と支払い日のバランスを考える
キャッシュフロー経営を行う以上、お金の出入りは徹底的に管理しなければいけません。つまり、入金日と支払い日は忘れないようにしましょう。入金日とは「現金の回収」を意味するので、ここが遅れてしまうと支払い日に間に合わなくなる可能性が出てきます。可能であれば、支払い日は必ず回収日の翌日にするなどの工夫をこらしましょう
在庫削減を行う
いわゆる不良在庫が多くなると、利益の源が眠った状態が続くので、キャッシュフローは悪化し、経営が赤字になる可能性は高まります。逆に、在庫処分を積極的に行えば現金を増やせるのでキャッシュフローは改善されるでしょう。
そのほか、在庫を仕入れるときは販売計画を堅実に立て、時期や数を慎重に設定するようにしましょう。的確な在庫管理とキャッシュフロー経営には密接な関係があるのです。
クレジットカードを活用する
法人用や個人事業主用クレジットカードを使うのも、キャッシュフロー改善に役立ちます。クレジットカードを使って支払いをすると、お金が回収されるのを翌月まで待ってもらえるからです。つまり、その間の現金は増えるので、キャッシュフローを整えられます。
消費税の納税義務の免除
企業経営では消費税の納税額も無視できません。ただし、前々事業年度の課税売上高が1000万円以下ならば、消費税の納税義務は免除されます。そのぶん、手元の資金が多くなるのでキャッシュフローは改善されるといえるでしょう。
キャッシュフローを意識して安定した経営を行なう
経営者として安定した事業展開をしていきたいのであれば、キャッシュフロー経営を学ぶことは欠かせません。キャッシュフローの種類や表示方法など、始めてキャッシュフロー経営をやる場合には知るべき内容が多くありますが、ポイントを抑えておくことが大事です。利益だけでなく現金の収支を意識して、事業を末長く続けていきましょう。
[PR]介護ビジネスへの参入