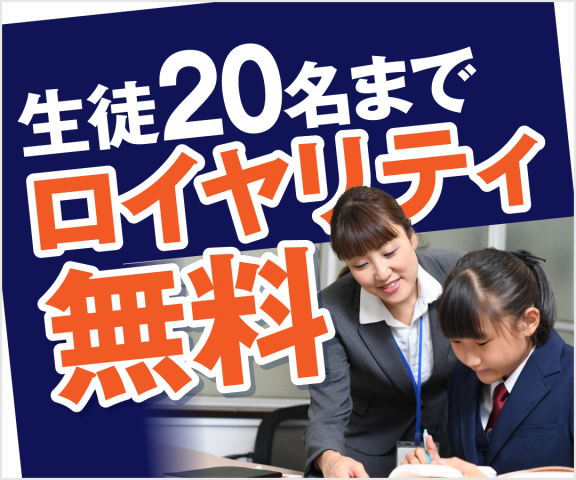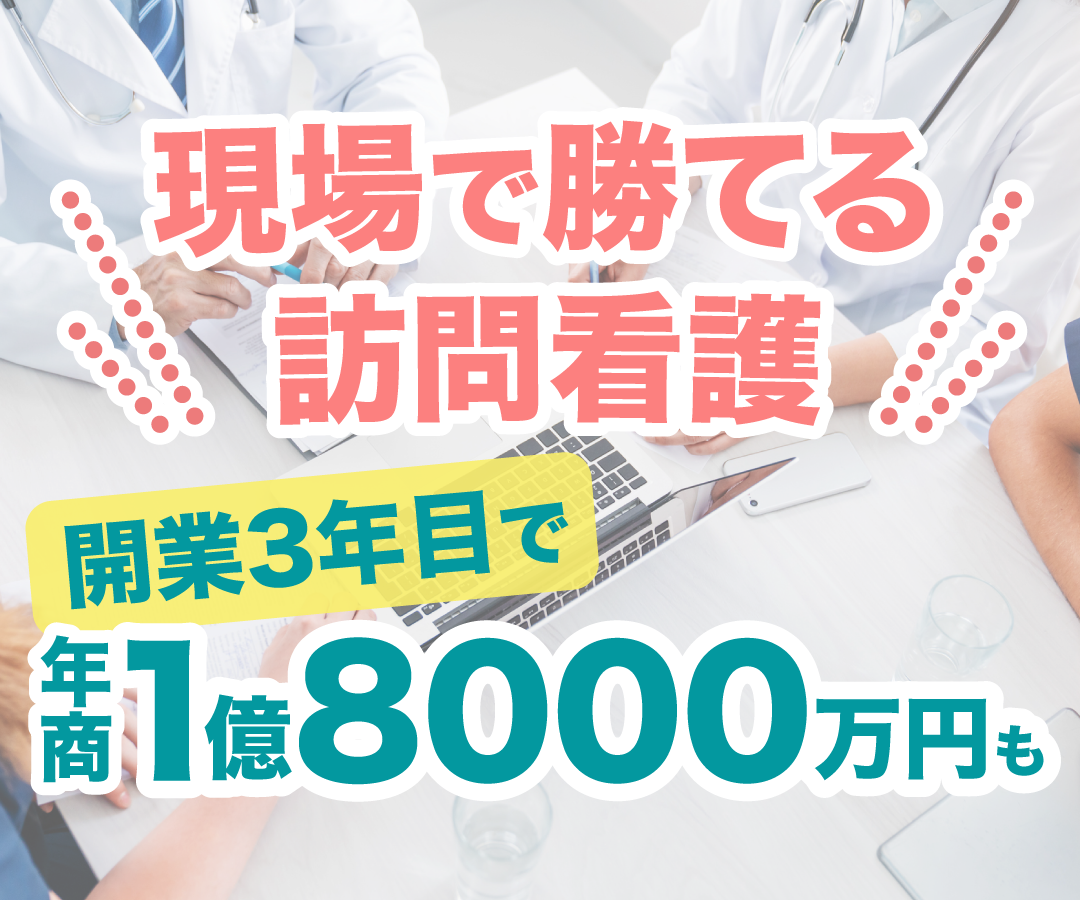会社には4つの種類がある!選択のポイントを押さえて会社を設立しよう

会社の設立にあたっては株式会社または合同会社を選ぶのが主流ですが、組織運営の柔軟性が高い有限責任事業組合(LLP)を設立する事例もみられます。経営する事業に合わせて、最適な会社や組織形態を選びましょう。
今回は、会社や法人格の種類をはじめ、株式会社・合同会社の設立方法について解説します。個人事業主から法人化するメリット・デメリットも紹介するので、法人成りを検討する際は参考にしてください。
会社の種類にはどんなものがある?それぞれの特徴について
会社の種類は多様化しており、株式会社だけでなくさまざまな形で運営されています。有限会社として運営している会社も多いですが、会社法の改正によって現在は有限会社を新規に設立できません。有限会社に代わり、組織を柔軟に運営できる特徴がある合同会社(LLC)や有限責任事業組合(LLP)を設立するケースが増えています。また、特定非営利活動法人(NPO法人)も一般企業と同様に収益を得る活動が可能です。
ここでは、株式会社・合同会社・有限責任事業組合(LLP)と有限会社の特徴を紹介します。なお、合同会社・合名会社という形態もありますが構成員の責任が重くなりがちなこともあり、設立件数はごく少数です(2020年の合同会社・合名会社の設立件数は計75社)。
株式会社
株式会社は第三者から出資を受けることも可能ですが、株式の譲渡制限の有無によって次の形態に細分化されています。
| 形態 | 株式の譲渡制限 | 特徴 |
|---|---|---|
| 株式譲渡制限会社 | あり | 自分1人だけで設立可能 |
| 株式非譲渡制限会社 | なし | 設立には最低4名(取締役3名・監査役1名)以上が必要 |
株式譲渡制限会社として運営するためには、定款(いわゆる「会社の憲法」)に株式の譲渡を制限する旨の記載が必要です。いわゆる「一人会社」の形態も認められることから、会社の設立時点では株式譲渡制限会社とするケースが多いといわれています。
古くからある会社形態のため社会的信用が高く、第三者からの出資を受けやすいのが特徴です。個人事業主よりも節税効果が高く、最終的に利益を残しやすいといえます。一方、法人登記に25万円ほどかかる他、自社のホームページなどを使って決算情報を公開(決算公告)する義務が生じるのがデメリットです。同じ青色申告でも、個人事業と比べて作成する書類が増えるほか、赤字の年でも法人住民税(2020年度の場合は7万円)を納税する必要があります。社長1人で運営する場合でも、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入義務が生じる点にも留意が必要です。
合同会社
合同会社は、2006年の会社法改正で有限会社に代わって設けられた会社形態です。出資者(社員)と経営者が同じで、経営に関する決定権が出資額に左右されないため、社員の意見が経営に反映されやすいといわれています。
役員の任期に制限はなく、決算公告の義務もないことから会社運営に関する事務手続きが簡略化されているのがメリットです。株式会社と同様の節税効果も得られます。
利益配分の自由度が高いことから、西友やGoogle・Amazonといった経営規模の大きい企業が合同会社の形態をとるケースもみられます。組織変更の手続きを取れば株式会社への移行も可能です。
しかし、新しい会社形態のために株式会社ほど社会的な信用度が得られていないのが現状です。経営に関する意見が食い違った場合に社員間の調整がつかない懸念もあります。社員全員の同意がなければ事業承継や権利譲渡ができない点も、運営上のネックになり得るでしょう。
有限責任事業組合(LLP)
有限責任事業組合(LLP)は法人格を持たないものの、法人と同様に「権利能力なき社団」として商業登記が可能な団体です。法人を含め2名以上のメンバーがそろえば設立でき、会社組織と変わりなく事業を展開できます。
組織の運営方法を柔軟に決められるだけでなく、設立の手続きが簡単なので事業のスタートアップに有限責任事業組合を選ぶケースもみられます。収益に伴う所得税や住民税はメンバー個人に課税(構成員課税)されるため、収益が増えた時点で法人化すると節税効果が高まるでしょう。
有限会社
有限会社の制度自体は2006年の会社法改正によって廃止されましたが、現在でも有限会社のまま運営する企業は少なくありません。当時、株式会社の設立には1,000万円以上の資本金が必要でしたが、有限会社だと300万円以上の資本金があれば設立できたため、開業のハードルが低いのがメリットでした。
有限会社制度が廃止された理由はさまざまですが、株式会社の最低資本金制度が廃止されたことや合同会社制度の新設が大きな要因だといわれています。なお、前述した株式譲渡制限会社の形式を取ることで、株式会社でも有限会社と同様の運営形態をとることが可能です。
法人=会社ではない!知っておきたい法人の定義とは
「会社」と「法人」を同じような意味合いで使われることがありますが、会社=法人であるとは限りません。反対に、個人事業主やフリーランスは個人の責任で事業を行いますが、企業として認識されることがあります。
「会社」は会社法という法律に基づいて設立された法人で、株式会社・合同会社・有限会社(特例有限会社)、そして合名会社・合資会社が該当します。営利を目的として運営されるのが基本ですが、行政機関が主要株主となる企業や日本政策金融公庫のように、公益目的を含む会社もあります。
一方「法人」は、人間(自然人)と同じように意思決定や責任の引き受けができ、権利能力の主体性が法律によって認められています。営利を目的とする組織だけでなく、営利を目的としない活動を行なう組織や公共の利益(公益)を目的とする活動を行う組織も含まれるのが特徴です。下記で主な法人の種類を紹介します。
【非営利法人】
・特定非営利活動法人(NPO法人)
・一般社団法人
・社会福祉法人
・医療法人
・学校法人
など
【公益を目的とした法人】
公益社団法人
公益財団法人
独立行政法人
公立大学法人
など
NPO法人は社会貢献活動や福祉に関する活動を行う非営利法人ですが、設立に10名以上のメンバーが必要で、法人登記までに3~4ヶ月かかるため設立のハードルが高めです。一方、一般社団法人だと2名以上のメンバーがいれば設立でき、設立までの期間も短縮できます。収益活動も可能であることから、近年では一般社団法人を選ぶ人が増えている状況です。
[PR]0円開業できるビジネス
個人事業主から法人化するメリット・デメリット
個人事業主が法人化(法人成り)することで、社会的信用が高まるのが大きなメリットです。個人事業主の存在は住民票や戸籍で証明できますが、取引先などの第三者が自由に住民票や戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)の発行を受けることはできません。
一方、法人の存在や事業概要は商業登記簿によって証明されており、商業登記簿謄本(現在事項証明書)は誰でも取得可能です。したがって、事業の実態をつかみやすい点から法人の信頼性は高く、出資者にとっても安心材料となります。そのため、個人より法人が資金調達をスムーズに進めることができるわけです。 税金や社会保険料の負担に関しては、経営者の考え方によってメリット・デメリットが分かれる傾向があります。
法人の場合は社会保険への加入が義務化されていますが、所得によっては国民健康保険税や国民年金保険料の負担より軽くなるケースも少なくありません。所得税・住民税についても、利益が多くなるほど法人化した方が税額面で有利といわれています。
しかし、経営者の家族構成や医療費・社会保険料などの金額によっては法人化せずに、個人として所得・税額控除を受けた方が有利なケースもあるようです。税金面のメリット・デメリットについては、税理士への相談をおすすめします。顧問契約を結べば、経営者にとって負担となりがちな経理事務や決算業務も依頼できるので経営に専念できるでしょう。
会社設立の方法
個人事業主が法人化する際は、株式会社・合同会社のいずれかを選ぶケースが主流です。ここでは株式会社・合同会社の設立方法を紹介します。
株式会社の設立方法
株式会社を設立するには設立手続きを進める発起人を決めた上で、本社(本店)所在地を管轄する法務局に商業登記の申請を行ないます。発起人は、会社の資本金となる出資金を払い込む個人・法人のことで、経営者本人も発起人になることが可能です。株式会社の設立に先立ち、自分の口座に出資金に相当する金額を入金し「払い込みを証明する書面」を作成しておきましょう。
商業登記の申請を行なう前に、以下の内容を定めた上で「定款」として明文化します。その上で、公証役場での定款の認証が必要です。
・会社名
・本社の所在地
・事業の目的
・資本金の金額
・発起人の住所と氏名
登記手続きを含めて司法書士に依頼する人もいますが、「マイナポータル」の法人設立ワンストップサービスを活用する人も増えています。
商業登記と同時に法人の印鑑登録を行うケースがほとんどなので、あらかじめ会社用の印鑑を作成しておきましょう。印鑑登録するのは代表印だけですが、銀行印や取引用の角印とセットで作成するのが一般的です。
合同会社の設立方法
合同会社を設立する場合も、株式会社と同様に出資金の払い込みと法務局への商業登記の手続きが必要です。定款作成も必要ですが、株式会社の設立とは異なり認証手続きは必要ありません。法人としての印鑑登録も必須なので、会社印も作成しておきます。
合同会社として最終的な意思決定を行なう代表社員や、株式会社の取締役に相当する業務執行社員の住所・氏名も登記事項なので、就任予定者の承諾を得ておきましょう。法務局の公式サイトに登記申請書の書き方が掲載されているので、参考にしてください。
[PR]脱サラした先輩が選んだビジネス
株式会社は何が違う?3種類の会社との比較

株式会社・合同会社・有限責任事業組合それぞれの概要や、設立に必要な費用や書類を比較してみましょう。
| 株式会社 | 合同会社 | 有限責任事業組合(LLP) | |
|---|---|---|---|
| 法人格 | あり | あり | なし |
| 構成員の最低人数 | 1名 | 1名 | 2名 |
| 株主総会の記載 | 必須 | 任意(社員総会) | なし |
| 取締役会の設置 | 任意 | なし(業務執行社員が経営に関与) | なし(組合員との合議で経営) |
| 監査役の設置 | 任意 | 任意 | なし |
| 税金の課税 | 法人 | 法人 | 組合員個人 |
| 決算公告義務 | あり | なし | なし |
| 株式会社への組織変更 | - | 可能 | 不可能 |
概要
株式会社・合同会社とも、会社名義の債務に対しては出資額の範囲内で責任を負う「有限責任」という仕組みが取られています。有限責任事業組合も同様です。ただし、会社名義で融資やリース契約を行なう際に、代表者の連帯保証を求められるケースがあります。
経営方針など会社にとって重要な意思決定を行なうとき、株式会社の場合は株主総会での決議が必須です。一方、合同会社では出資者にあたる社員(代表社員・業務執行社員)の話し合いで意思決定を行います。また、有限責任事業組合を設立する際は2名以上のメンバーが必須ですが、株式会社・合同会社は代表者単独での設立も可能です。
設立費用
株式会社を設立する場合は公証役場で定款の認証を受ける必要があるため、合同会社・LLPと比べると設立費用が高めです。
| 株式会社 | 合同会社 | 有限責任事業組合 | |
|---|---|---|---|
| 費用の総額 | 19万円~24万円前後 | 10万円前後 | 6万円前後 |
| 登録免許税 | 最低15万円(※1) | 最低6万円(※1) | 6万円(定額) |
| 定款の認証手数料 | 5万円 | なし | なし |
| 収入印紙代(※2) | 4万円 | 4万円 | なし |
※1 登録免許税の税率は資本金の0.7% ※2 電子定款で手続きする場合は不要
株式会社・合同会社を設立する時の登録免許税は、資本金の額によって決まります。出資額によっては登録免許税が高額になる場合もある点に留意しておきましょう。また、産業競争力強化法に基づく認定を受けた自治体で法人を設立する場合は、登録免許税が半額に軽減される場合があります。詳しい条件は最寄りの経済産業局に確認してください。
必要な書類
株式会社・合同会社の登記申請を行う際は、法務局公式サイトで「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請書」を作成することをおすすめします。申請者本人のマイナンバーカードに電子証明書が搭載されていれば、オンライン申請も可能です。登記申請する際の添付書類は以下の通りですが、書類の写しを持参すれば原本を返還(原本還付)してもらえます。
【株式会社の場合】
・認証済の定款 ・発起人全員の印鑑証明書 ・代表取締役・取締役全員の就任承諾書と印鑑証明書 ・出資金が入金された通帳のコピー(口座番号のページと、出資金額が記帳されたページ) ・出資金の払込証明書(法務局公式サイトに記載例あり)
【合同会社の場合】
・作成した定款 ・代表社員の印鑑証明書と就任承諾書 ・出資金が入金された通帳のコピー(口座番号のページと、出資金額が記帳されたページ) ・出資金の払込証明書(法務局公式サイトに記載例あり)
一部の社員だけを業務執行社員にする場合は、以下の書類も必要です。 ・代表社員・業務執行社員の選任を証する書面 ・業務執行社員の就任承諾書
登記手続きが完了した後は、次の書類を税務署に提出します。控えの書類も作成しておき、提出時に税務署窓口で収受印をもらうようにしましょう。
| 書類の名前 | 備考 |
|---|---|
| 法人設立届出書 | 個人事業主の「開業届」に相当する書類 |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 提出と同時に承認となるケースが大半 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 役員報酬も給与と考えるため、提出が必須 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与・役員報酬に発生する源泉所得税の納期を年2回にしたい場合に提出 |
株式の発行
株式会社は、発行可能株式総数の範囲内で株式を発行できるので、銀行融資を受けるだけでなく第三者からの資金調達が可能です。資金調達が比較的容易で、ビジネスを拡大しやすいのが大きなメリットといえます。
一方、合同会社など株式会社以外の法人は株式を発行できないので、資金調達は経営者や社員からの出資に限られます。
経営に伴う事務
株式会社は、最低でも年1回株主総会を行い、決算後2~3ヶ月以内を目安に決算公告をする義務も生じます。また、役員の任期は取締役が2年・監査役は4年が基本ですが、株式譲渡制限会社の場合は最長10年まで延長可能です。一方、合同会社などでは株主総会や決算公告を行なう必要がなく、役員の任期にも制限がありません。なお、NPO法人など社員総会の開催と自治体への決算報告が義務化されている法人もあります。
株式会社では経営に伴う事務手続きが多いことから、意思決定のスピードが遅くなるなど経営の小回りが利かない一面もあります。デメリットにも映りますが、定期的に経営状況をチェックできる点ではメリットです。経営状況を株主に報告することで、利益分配などのトラブルを回避できるだけでなく、リスクの高い経営に歯止めをかけられる効果も期待できます。
株式会社・合同会社のどちらを選ぶべき?株式会社の設立に向いている場合について
株式会社は社会的信用が高く、株式の追加発行によって柔軟な増資も可能です。保有する株式数に応じて議決権の数が変動するため、経営方針を決定・変更する際の議論の紛糾もある程度防止できます。証券取引所に上場(IPO)して事業拡大を目指すなら、法人の設立当初から株式会社を選ぶのが得策です。
[PR]複数店経営がしやすいフランチャイズ
短期間、低資金で設立できる!合同会社の設立に向いている場合とは
合同会社は登記申請から2週間前後で設立でき、初期費用も安いのがメリットです。すべての社員が対等な立場で法人運営の意思決定ができ、利益配分の方法も柔軟に決められるため社員の功績を反映しやすい一面もあります。
運営方針をめぐるトラブルを防ぐため、社員間との情報共有を密にするとよいでしょう。株式会社と異なり決算公告や役員改選が義務化されておらず、代表社員単独での設立も認められているため、個人事業主にとっては法人化の負担が軽いといえます。
会社の種類を理解して事業に合った会社を設立しよう!
個人事業主が法人化する際は、株式会社あるいは合同会社の形態を選ぶのが主流です。将来的な事業拡大を目指すなら、第三者からの資金調達がしやすい株式会社を選ぶのをおすすめします。一方、柔軟に会社組織を運営したい場合には合同会社も選択肢となるでしょう。
将来の成長戦略を考えながら、自分にふさわしい会社の種類を選びましょう。資金などの関係で合同会社の設立を選んだ場合も、出資者全員が賛成すれば株式会社への移行も可能です。
会社の種類や設立方法についてのよくある質問
会社の種類や設立方法に関する、よくある質問を紹介します。
合同会社から株式会社へ、株式会社から合同会社へと変更はできますか?
合同会社から株式会社への組織変更は、出資者(社員)全員の賛成が得られれば可能です。反対に、株式会社から合同会社へ組織変更する場合には、組織変更計画を作成した上で全株主の同意を得る必要があります。株主に対して出資額の精算を済ませて株式会社を解散し、合同会社としての登記申請を行ないます。会社経営の意思決定権を株主から社員(代表社員・業務執行社員)に移行することで、会社の独自性を高める戦略を推進する企業もみられます。
株式の発行額と件数はどれぐらいが一般的ですか?
かつては1株5万円というルールがありましたが、現在では資本金や出資者の人数・属性に応じて1株あたりの発行額を自由に決定できます。出資の柔軟性を保つため、1株あたり1万円~10万円前後とするのが一般的です。株式の発行数は定款の範囲内で行いますが、定款変更の手続きを経て株式の発行可能数を増減することもできます。
企業組合という形態もあるようですが、どんなものですか?
企業組合とは、4名以上の組合員が出資金や知見を持ち寄って事業を進めるタイプの組織です。設立時の手続きが株式会社や合同会社と比べて多いですが、国や都道府県からの認可を受けられるので社会的信用が高いといわれています。都道府県の中小企業団体中央会から、運営のサポートや補助金などの情報提供も受けられます
定款には何を書けばいいのですか?
定款には会社の名前(商号)や本店所在地をはじめ、法人を設立した当初の出資金額や発起人の住所・氏名を記載します。「○○の製造・販売」「○○の企画・運営」というように、会社の設立当初から行う事業目的も明記します。事業目的の追加・削除は、変更登記の手続きを取れば会社設立後でも可能です。事業の柔軟性を高めるために「前各号に附帯または関連する一切の事業」と事業目的に加えておきましょう。
[PR]新着フランチャイズ