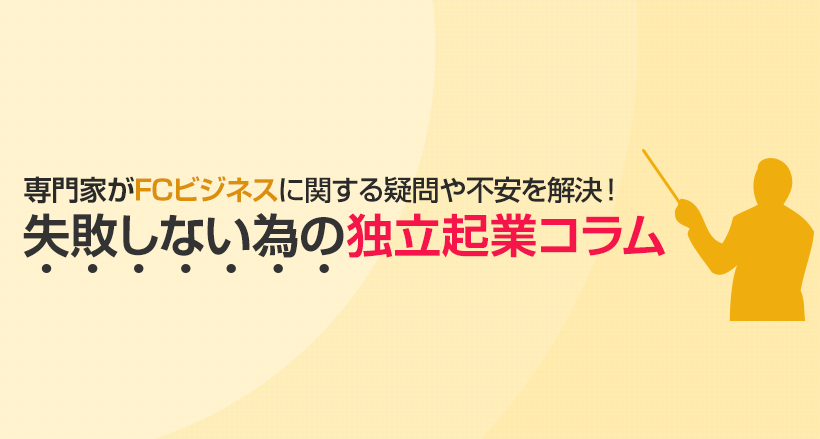|
2017-01-29 専門家が語る。フランチャイズ・独立開業コラム
株式会社PEOPLE&PLACE 代表取締役
松下 雅憲 |
善い提案を育てられる上司になる方法 !やる気を高める「承認」やる気を失わせる「否定」

このコラムのポイント
「もっといい提案はないのか?!俺の周りはデキない奴ばかりだ」と嘆く上司、自分はさも優秀だと言わんばかり経営者…世の中に沢山います。いい考えを持っている新人、会社全体のことを経営者以上に観ているスタッフはどこの会社にも居るのに、それに気付かないのでは『宝の持ち腐れ』というもの。今回のコラムでは、会社を経営する著者自らが普段心がけていることを追いながら、善い意見やスタッフを育てる方法について知ることができます。
フランチャイズWEBリポート編集部
A)「う~ん、それは違うなぁ~ 全然わかってないね、もっと考えてよ」
あなたは、こう言う風に言われるのと、
B)「おぉ、なるほどね~。それ 面白いね〜!で、どうやったら実現できそうかな?」
と言われるのとでは、どちらが嬉しいですか?
また、どちらの方が『やる気』や『責任感』が湧いてきますか?
A)自分の意見やアイデアを一度否定されてから、承認を得るために再び考えるのと、B)肯定された後、どうやったらそれが実現できるかを考えるのとでは、その時点で、すでにモチベーションの種類が変わっているのです。

否定が、説得する対象と結果を変えてしまう
否定から始まると、考えて説得する相手は『上司』です。
一方で、肯定から始まると、考える相手は『お客様』であり『仲間』です。
上司を説得するための方法よりも、どうやったらお客様に喜んでもらえるか、どうやったら仲間に協力してもらえるかを考える方が、より実現に近いと思いませんか?
もちろん、スタッフの意見・提案・アイデアは、必ずしも的を射たものや、優先先順位が高いものとは限りません。実現性が極めて低いものもあります。その場の空気を読み切れていないものもあるでしょう。時には、予算・権限・ブランドイメージ・衛生・法律・モラル… 誰がどう考えても無理なこと、駄目なものもあるかも知れません。
さらに、それをそのスタッフが「不真面目に」「冗談で」「無責任に」そんな意見もあるかも知れません。
それでも『否定』よりも『肯定』の方が、目標達成に対する効果が高いのです。
肯定から得られる4つの効果
では、その『肯定』の効果を4つほど紹介しておきましょう。
一つ目は、先ほども書きましたが、肯定すると、多くの人は実現の可能性を探るようになり、より具体的に目の前の障害を取り除く方法を考えるようになります。その結果、モチベーションや意欲は、必ず高まります。つまり、やる気が出るということです。
二つ目は、改善策やアイデアについて、実現のための障害が大きすぎる場合や優先順位が違うと思われる場合です。こう言う時も、肯定することで、提案者であるスタッフの視野を広げさせることができます。もちろん、ただ「いいね~」ではありません。肯定しつつも、さらに実現に向けた具体的な質問をしていくのです。
他の提案や条件などと比較をしたり、より具体的な質問をしたりすることで、自ら深く考えを巡らせるアプローチをすることが可能になります。しかし、いきなり否定してしまっては、せっかくのアイデアがそこでフリーズしてしまいます。もったいないですよね。
三つ目は、提案者がさほど真剣に考えていなかったり、ふざけていたり、また無責任な提案をしてきたと感じるときです。そんな時でも、頭ごなしで否定をしてしまうとそこで思考が止まるだけになります。こう言うケースでもせっかくの機会ですから、そのスタッフに具体的な実現性を深掘りをさせていくのです。ふざけているようにみえても、ほとんどの場合は、「なんとかしたい」とは思っているのです。なので、その積極姿勢を活かすのです。
自らが意見を言っているのですから、テーマを与えられるよりははるかに考えを深めやすいのです。
最後に四つ目です。それは、肯定することにより、あなた自身の固定概念を打破できる可能性が高まるということです。自分自身が「できない」「無理」と思っていたことでも、一緒に意見を深掘りしていくことで、「あれ?できるかも!」と思えるようなアイデアが出てくることがあるのです。ひらめきが起こりやすくなるのです。

まずは、相手の意思を汲む姿勢に
いかがでしょうか?
私自身は、会議やミーティングでの参加者の発言や意見に対して、ドンピシャではないときの第一声は「うん、それもあるよね」とか「なるほどね」と言うようにしています。
決して「それは違う」とか「何言っているの?」とか「ひとの話聞いているの?」などという言い方はしません。
もちろん、言いたくなることはあります。明らかに今までの話を聞いていないような意見のときは、正直「イラッ」とします。しかし、それでも『否定』はしません。だって、「本当に聞いていないのではなく、言い方が回りくどいだけ」かも知れないのですからね。
相手は、自分と同じではありません。
相手には相手の表現の仕方があるのです。
また、それぞれに立場や思惑があるのです。
そんな彼らを頭から否定をすると言うことは、実は、ただ作戦を自分の思う通りにしたいという自分勝手な想いが強いだけなのです。
さて、あなたはいかがですか?
スタッフの意見をどの様に受け止めて反応していますか?
ちょっと、胸に手を当てて思い出してみましょう。
チクチク痛くなったりしませんか?
次回は「部下の考えを引き出すオープンクエスチョン」というテーマでお話しします。お楽しみに!
- 参考「『これからもあなたと働きたい』と言われる店長がしているシンプルな習慣」松下雅憲著(同文舘出版)
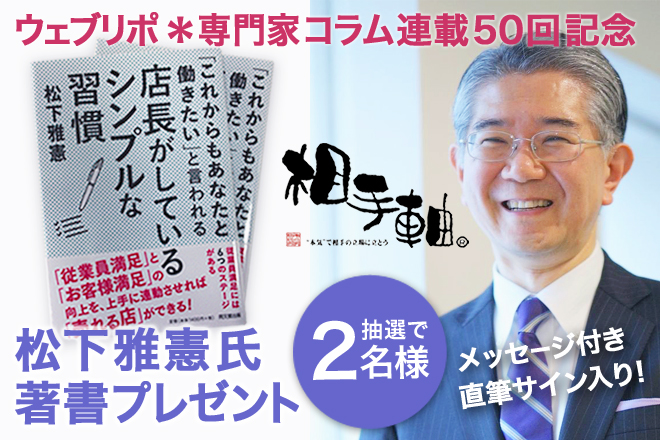
ウェブリポ*専門家コラム連載50回記念!松下 雅憲氏の最新著書プレゼント
▶︎▶︎▶︎ご応募コチラから!【応募締切:2/15まで!】