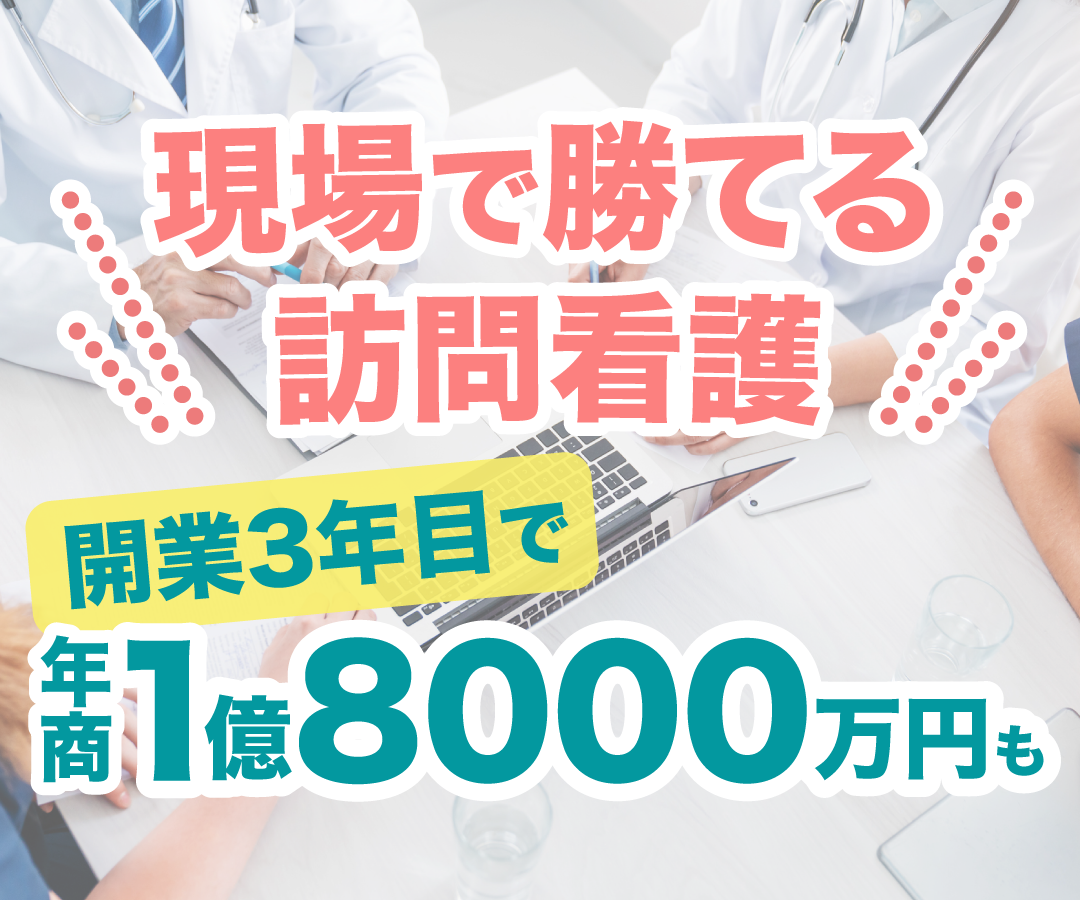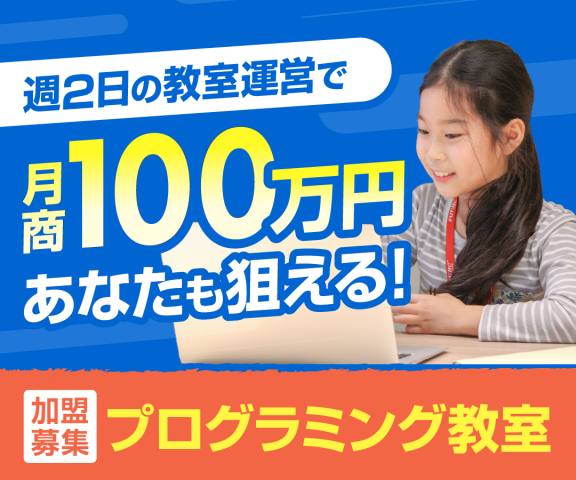コロナ下で中食事業が活況|需要の動向や参入時のポイントを解説

コロナ下で飲食店の営業時間に制約が出る中、中食ビジネスが活況を呈しています。既存の飲食店がテイクアウトに本格参入したり、食事のデリバリーサービスを強化したりする動きも拡大傾向です。自宅で本格的な味を楽しめる中食に魅力を感じる消費者も増えています。
この記事では、中食ビジネスの実態と事業参入にあたってのチェックポイントを解説します。テイクアウトを取り入れたフランチャイズチェーンの事例も紹介するので、中食事業に参入する際は参考にしてみてください。
コロナ下で変わった中食意識、90%以上が中食支持
新型コロナウイルス感染症の収束を見通せない中、テイクアウトやデリバリーといった中食を利用する人が増えています。
フランチャイズWEBリポートが「新型コロナウイルスの流行による中食利用傾向の変化」についてアンケート調査を実施したところ、中食事業への参入を考える人にとって興味深いデータが明らかになりました。そこで今回は、高まりを見せる中食への意識やニーズについて解説します。
テイクアウトやデリバリーの利用が増加
調査結果によると、新型コロナの流行後にテイクアウト・デリバリーの利用回数を増やした人が全体の約32%、初めて利用してみたという人が約3%でした。これまでにも、デリバリー関連の新規出店や提供メニューの変化に伴う利用頻度の増加はみられましたが、ここまでの大きな変化は過去に類を見ません。全体の約半数がコロナ下の前と変わらない頻度でテイクアウト・デリバリーを利用している状況からも、中食市場へのニーズは高まっているといえます。
コロナ下の影響で自宅での食事が増加
コロナ下の影響で営業時間を短縮する飲食店が多い中、時間を気にせず自宅でゆっくり食事をしたいという人に中食が支持されています。調理や後片付けの時間を節約して「おうち時間」を充実させたい人にも、中食は魅力的です。自宅でテレワークに取り組む人には、テイクアウト・デリバリーの豊富な選択肢からランチを選ぶのも楽しみの一つでしょう。ネット注文やキャッシュレス決済といった利便性の高さを支持する人も多く、コロナが収束した後も中食のニーズは堅調に推移するものと考えられます。
中食の人気ジャンルは弁当と惣菜
中食の人気ジャンルは弁当と惣菜で、日々の食事の延長として中食を活用していることがうかがえます。新型コロナが流行する前から持ち帰り弁当店が力を入れている分野であり、プチ贅沢したいという需要をデパ地下が取り込む流れもみられます。揚げ物・煮物といった、自宅での調理に手間がかかるメニューを購入したり、多くのおかずを少しずつ食べたい時に弁当を選んだりする傾向もあるため、中食文化は多くの人に根付いているといえるでしょう。
今後も中食を利用したいと考える人は9割以上
テイクアウト・デリバリーを利用した人の9割以上が、今後も中食を利用したいと考えていることが調査の結果からわかりました。受け取りや宅配の時間帯を指定して時間を有効活用する人や、注文サイトが提供するクーポンなどでお得に中食を利用できる機会も少なくありません。テイクアウト・デリバリーに参入する飲食店も増えており、今後も中食を利用する傾向が続くのは確実でしょう。
中食市場全体の需要に大きな変化あり
消費者の中食ニーズが高まっている一方で、これまで拡大を続けてきた中食(惣菜)市場はコロナ下の影響を受けて2020年度は前年度を5%ほど下回りました(※1)。一方、外食業態のデリバリー市場は前年度と比べて約150%と大幅に伸びています(※2)。
中食市場が落ち込んだ原因の一つとして、テレワークの普及に伴う外出頻度の低下が考えられます。オフィス街のコンビニを中心にランチ需要の低下がみられた他、百貨店などでは仕事帰りのテイクアウト・買い物需要も落ち込みました。緊急事態宣言の発令などによる外出自粛の要請も、買い物需要の落ち込みに拍車をかけたといえます。
ただ、自宅近くのコンビニやスーパーなどで買い物するニーズは堅調な他、デリバリーを提供する飲食店も増えています。出前館やウーバーイーツといった食事宅配サービスも拡大傾向にあるため、中食市場のニーズは総じて高いといってよいでしょう。
※1 一般社団法人日本惣菜協会プレスリリース「2020年惣菜市場規模 速報 9兆8,195億円」 ※2 エヌピーディー・ジャパン株式会社「<外食・中食 調査レポート>2020年計の市場動向、外食・中食売上は18.3%減 出前市場規模は50%増の6264億円」
飲食業界に新規参入するなら今がねらい目!?

市場規模の成長から見ても、デリバリーやテイクアウト・中食を取り入れた飲食業界に今参入するメリットは大きいといえます。以前からテイクアウトに対応していた大手飲食チェーンでも、コロナ下を受けてテイクアウトの売上比率が増加傾向です。
店内での飲食とは異なり、緊急事態宣言などに伴う営業時間の制限を受けない(2021年9月時点)ので、消費者のニーズに幅広く対応できるのも中食ビジネスの特徴といえます。さらに、少子高齢化社会の進行や共働き世帯の多さから見ても、中食の利用者は一層増えるでしょう。
国や自治体が中食を推進
コロナ下で打撃を受けた飲食店を支援するため、テイクアウトやデリバリーに参入する際の費用を補助する自治体も出始めました。例えば東京都では、新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店に対し最大100万円まで、販促費用や食事宅配サービス業者に支払う手数料などの助成金・補助金の支援を行なっています。各地で中断されていた国の「Go To Eatキャンペーン」も、テイクアウト・デリバリー限定で再開する動きもみられます。SNSを活用して中食の情報発信に取り組む自治体もあるなど、中食事業に参入するための公的なサポートが充実する傾向です。
日本の共働き世帯と少子高齢化社会から見る飲食業界のこれから
独立行政法人労働政策研究・研修機構のデータ(※)によると、2020年時点での共働き世帯は1,240万世帯でした。パートやリモートワークといった多様な働き方を選択できる企業も増えており、共働き世帯は今後も増加が見込まれるでしょう。 お年寄りや子供のいる共働きの家庭では、家事と仕事の両立を図るためにテイクアウト・デリバリーは重宝する存在です。
※早わかり グラフでみる長期労働統計「Ⅱ労働力、就業、雇用 図12 専業主婦世帯と共働き世帯」
アプリの充実とキャッシュレス決済で顧客も店舗側も便利に

国は、インバウンド対策や高齢化社会における人手不足の解消など、さまざまな理由からキャッシュレスの促進を行なっています。2020年の6月まで行なわれた「キャッシュレス還元」によって店舗側のキャッシュレス端末の導入が進み、もともと現金での支払い率が高かった日本もキャッシュレス時代に向けて大きな進歩を遂げました。
スマホ決済や電子マネーを取り入れたり、ポイント還元を活用した決済方法を取り入れたりする店舗も増えています。消費者にとっても残高を確認しやすく手軽に決済できるメリットがあり、PayPayをはじめとするさまざまなバーコード決済や、クレジットカードを活用した非接触決済ツールが開発され、現在進行形で浸透し続けています。
また、今はUber Eatsが飲食デリバリー業界で有名なアプリではありますが、大手飲食ブランドでは独自のアプリを導入することで、差別化を図っています。Uber Eats以外にも「出前館」や「menu」といったデリバリーサービスのアプリは既に存在しており、今後も数を増やしていくことが予測されます。
アプリとキャッシュレス決済の導入で、中食業界への新規参入も行ないやすくなっているのではないでしょうか。
[PR]ニーズ拡大!テイクアウト特集
中食やテイクアウト事業に参入する際のポイント
中食のニーズが高まるにつれて、テイクアウト・デリバリーに参入する飲食店の増加が予想されます。大手飲食チェーン点のテイクアウト事例も参考にしながら、消費者に選ばれて生き残っていく戦略を立てましょう。中食事業に参入する時のポイントを紹介します。
中食に参入するメリット、デメリット
中食事業に参入することで、店舗だけでは取り込めなかった顧客も獲得できるのがメリットです。新規に飲食店を開業する人にとっては、中食を専門に手がけることで店舗スペースと賃料を節減できる点も魅力的でしょう。食事を専門に宅配するサービスも充実しているため、スモールスタートで始められる環境も整っています。
一方、調理から食事をするまでタイムラグがあるため、風味が損なわないよう味付けや盛り付けの工夫が必要です。店舗と異なり飲食中の追加注文が見込めないため、客単価を上げるためには画像・動画を活用しながらメニューを売り込むなど、リピーターを獲得する戦略を練るとよいでしょう。
利用者に選ばれるためには
テイクアウトやデリバリーを利用する人の多くが、注文時の利便性や提供メニューそのものに魅力を感じています。
ネット注文では配達時間帯を指定できるのが一般的で、送料や食事代金の割引クーポンを提供するサイトも少なくありません。キャッシュレスで決済すれば非接触で料理を受け取れるサービスもあるため、顧客のペースで利用できる仕組みを構築できれば利便性がさらに高まります。自分で作るには手間がかかる料理や普段食べられない料理に根強いニーズがあるため、定番メニューだけでなくオリジナリティのあるメニューも用意するとよいでしょう。
売り上げは伸びる?
在宅勤務や学校の臨時休校といった理由で高まっている中食需要にいち早く対応した外食チェーンが、売り上げを伸ばしています。ファストフード業界ではネットオーダーを積極的に導入して、店内での待ち時間を最小限にするだけでなく好きなメニューをじっくり選べるように配慮しています。ファミリー向けのメニューを充実させるなど、客単価アップにつなげているのも特徴的です。公式アプリやグルメサイト・SNSなどによる宣伝効果も相まって、中食を提供する飲食店の約半数が売り上げアップを実現しています。
ゴーストレストランという方法もある
オンラインショップと同様に、デリバリーサービス上で複数の飲食店を展開する「ゴーストレストラン」(クラウドキッチンという業態が注目されています。既存の設備や人員を活用して、提供する料理のバリエーションを豊かにできるのがメリットです。メニュー開発やブランディングなどを通じてゴーストレストランへの参入をサポートするフランチャイズチェーンも登場し始めました。異業種からでも中食事業に参入するチャンスが増えているのです。
テイクアウトやデリバリーを行なう時の注意
テイクアウトやデリバリーを始める際は、使い捨ての容器や割り箸などの資材を準備するコストがかかります。食中毒を防ぐために、保冷剤やおしぼりを提供する配慮も必要です。同じメニューでも店舗飲食とデリバリーで価格を変える店舗も出ているため、付加価値アップに伴う対価の上乗せも今後は許容されるかもしれません。
季節ごとにテイクアウト・デリバリーのメニューを変えることで衛生面でのリスク軽減につながり、しかもメニュー選びの楽しみも顧客に提供できるでしょう。実店舗と比べて目立つチャンスが減るため「Google マイビジネス」と活用するなど宣伝に力を入れることも大切です。
中食事業に参入するときの資金や物件
中食事業に参入するためには、飲食店を管轄する保健所から飲食店営業許可を得る必要があります。キッチンカーなどの車両でも、飲食店としての営業は可能です。店舗物件を契約したりや車両を購入したりする前に、営業許可の基準を保健所に確認しておきましょう。
新たにテイクアウト・デリバリー事業に参入する場合、物件契約や厨房設備の費用などで約500~600万円の開業資金がかかります。自分で資金を準備できるに越したことはありませんが、日本政策金融公庫などの金融機関から融資を受けたり、自治体の補助金を受給したりして資金を調達するのも一つの方法です。
話題の大手飲食チェーンのテイクアウト事例
店舗での営業に特化していた大手飲食チェーン店がテイクアウトに参入する事例も増えています。
例えば、店舗ごとにシェフが在籍することで知られるロイヤルホストではフローズンミール「ロイヤルデリ」を展開し、自宅で世界各国の料理を味わえると訴求しています。丸亀製麺もテイクアウトに参入。ほぼすべてのメニューの持ち帰りに対応するだけでなく持ち帰り専用メニューも展開して、麺類のテイクアウトが難しいというイメージを打破しました。
飲食業界の参入はフランチャイズがおすすめ
フランチャイズでの独立開業にはさまざまなメリットがありますが、特に強みと言えるのは、さまざまな変化に対応できるということです。フランチャイズならではの商品開発力やブランドの力は大きく、これから飲食業界へ参入を考えている人には、フランチャイズを利用した独立開業は特に注目です。
そしてフランチャイズ業界の飲食店では、今までテイクアウトをしていなかったブランドが積極的にテイクアウト事業に参入してきています。ここからはテイクアウト事業を取り入れ始めたフランチャイズをご紹介します。
テイクアウトを取り入れた飲食フランチャイズ
VANSAN
自家製生パスタや石窯ピッツァをお持ち帰りできるほか、従来ではお店でしか味わうことができなかったコース料理のテイクアウト販売も行なっており、自宅で本格的なイタリアンが楽しめます。家族での食事をはじめとし、女子会、一人飲みなどさまざまなシーンに合うコースを提供しています。
やきとり家すみれ
ミシュラン掲載店舗でも使用される希少銘柄「大山どり」を使用した、焼き鳥を自宅で味わうことができます。事前に電話での予約を受け付けており、焼きたて・揚げたての焼き鳥をテイクアウトすることができます。
じねんじょ庵
豊富なメニューを提供する蕎麦屋、じねんじょ庵では、謹製そばつゆ付き「店打ち二八蕎麦」や、自然薯料理、天ぷら、丼メニューなどを自宅でも楽しむことが可能です。
リンガーハット
ちゃんぽん業界トップのフランチャイズブランドのリンガーハットでは、麺と餡をセパレートした容器の工夫などにより、できたての温度を長時間保つことを可能にしました。時間が経ってもおいしく食べることができるのは、うれしいですね。
このように、今までお店に足を運ばないと楽しめなかったさまざまなグルメが、気軽に自宅でも味わえるようになってきています。
[PR]宅配・フードデリバリービジネス特集
テイクアウト・デリバリーで中食を取り入れた生活や事業展開を考えよう

テイクアウト・デリバリーの需要は大幅に増えており、大手飲食チェーン店をはじめ個人が経営する飲食店でもテイクアウトメニューを提供する事例が増えてきました。デリバリーでは、出前館やウーバーイーツ以外も参入しており、消費者の選択肢も増えています。
コロナ下が収束後は一時的な需要減が見込まれますが、待ち時間の短縮やキャッシュレス決済といった利便性が評価されており、長期的に見ると利用客は伸び続けるでしょう。メニューの選択肢も幅広く、家事の時短にもつながるため中食は飲食業界にマッチした事業だといえます。
飲食店の参入を考えるのであれば、ノウハウの提供、ブランド知名度、アプリやサービスの充実を可能にするフランチャイズを視野に入れてみることも一つの選択肢になるのではないでしょうか。
中食事業参入についてのよくある質問
中食事業に参入するにあたっての、よくある質問を紹介します。
テイクアウトに参入する際に注意する点がありますか?
調理してから料理を食べるまでにタイムラグがあるため、冷めても風味や見た目が損なわないよう調理方法や味付けに工夫が求められます。食中毒を防ぐために消費期限を明確に示し、必要に応じて保冷剤などを提供する配慮も必要です。厚生労働省公式ツイッター(@Shokuhin_ANZEN)では食品の安全に関する情報が掲載されているので、定期的に確認するようにしましょう。
中食に参入するときに、使える支援はありますか?
各地の商工会議所や国が運営する「よろず支援拠点」では、中食ビジネスに参入に向けたさまざまなアドバイスを受けられます。資金面では日本政策金融公庫の創業融資を活用できる他、一部の自治体では補助金・助成金制度の活用も可能です。例えば東京都では、テイクアウトやデリバリー・移動販売に参入する飲食業を対象とした助成金制度が設けられています。
デリバリー時にトラブルを起こしたときの対処法はありますか?
商品が途中でこぼれてしまった、あるいは注文を間違えた場合は顧客にお詫びし、早急に新しい商品を用意してお届けします。デリバリー代行会社を利用している場合は、トラブルが発生した事実を伝え、再発防止に向けて協議しましょう。なお、2021年2月に業界団体(一般社団法人日本フードデリバリーサービス協会)が誕生しました。デリバリー業界特有の課題を解決し、サービス品質の向上に期待が持てそうです。
テイクアウトでの食中毒の対処法は?
万が一食中毒になったと顧客から申し入れを受けた場合は、医療機関への受診をお願いします。医療費や交通費・見舞金の支払いについても検討が必要です。あわせて管轄の保健所に連絡して、今後の対応について指導を仰ぎます。店舗の運営状態に起因する食中毒の場合は、数日間の営業停止処分になります。顧客への賠償責任や店舗の売上減などの損害を補填する事業者向け保険もあるので、加入しておくことをおすすめします。
[PR]新着フランチャイズ