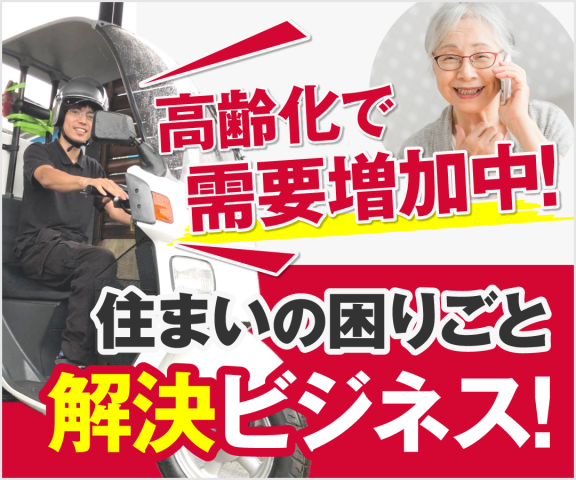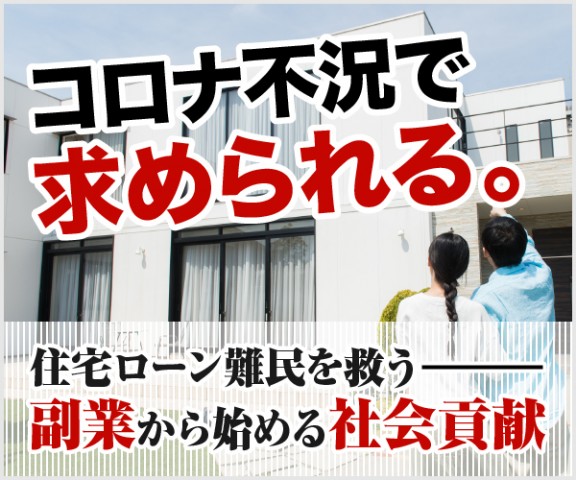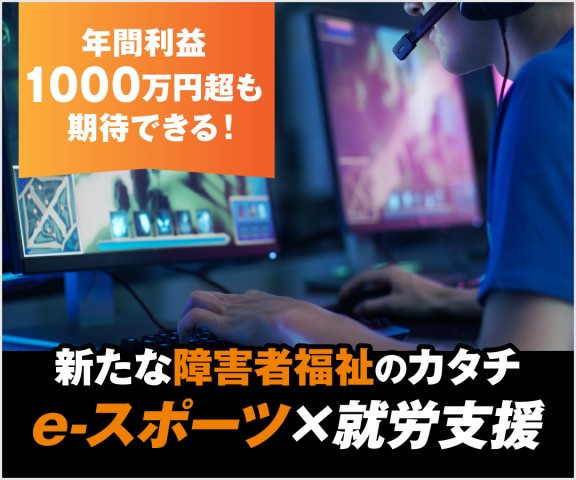パン屋の開業に必要な資格とは?営業形態による免許の違いについて解説

独立開業に人気の高いパン屋。パン屋をオープンするというプランを立てている人は、資格や免許の有無など、いろいろな予備知識を仕入れておく必要があります。
そこでこの記事では、パン屋開業のために持っていなければならない営業形態ごとの免許や、取得しておくとメリットがある資格などについても分かりやすく解説します。
パン屋の開業にあたって必要な準備
パン屋開業の前には準備しなければならないことが多いため、まずはやるべきことを整理しておくと良いでしょう。ここでは、パン屋の開業にあたって必要な準備を簡単に紹介していきます。
コンセプトを明確にする
販売するパンは手作りするのか、それとも仕入れるのか、イートインコーナーは設けるのかといったように、パン屋にはさまざまな営業形態があります。適した営業形態はコンセプトに応じて変わってくるため、まずは自分が目指すパン屋のコンセプトを明確にしましょう。設定したコンセプトに従って、ターゲットやメニューなどのディテールも徐々に決まっていきます。
コンセプトを決めるときは、取り扱うパンの種類やセールスポイントなどを事業計画書に書きこみながらアイデアを固めていくと良いでしょう。また、競合店を調査したうえで独自のコンセプトを考えることも大切です。近所のパン屋だけではなく、スーパーやコンビニも競合となるため、オリジナリティのあるコンセプトを立てることが効果的な生き残り戦略となります。
立地を決める
立地はパン屋経営の成否を左右する重要なポイントです。客単価が低い傾向にあるパン屋の経営を成り立たせるためには、毎日多くの客に来店してもらう必要があります。そのため、ある程度の集客が見込める場所に出店するのは大前提といえるでしょう。
駅前などの往来が盛んな場所は客を集めやすい代わりに、物件の価格が高めに設定されています。開業資金が足りるかどうか計算しながら物件を選ぶと良いでしょう。郊外に出店する場合は、客が車で来店できるように駐車場が完備されている物件を選ぶのが賢明です。
そして、出店する場所に目星がついたら忘れずに競合店を調査しておきましょう。
許可申請や資金調達を行う
必要な許可申請や取得すべき資格を事前に調べ、開業前に過不足なく準備しておくことも大切です。また、開業にあたって必要な資金は営業形態や立地、提供するメニューなどによって変動します。
開業資金がどれくらい必要になるのかを計算し、十分な金額を調達しておきましょう。それでは、ここからパン屋の開業に必要な資格や許可について詳しく紹介します。
[PR]脱サラした先輩が選んだビジネス
パン屋の開業に必要な資格や許可
パン屋としてパンを焼くこと自体は、資格がなくても大丈夫です。しかし、自分でパンやクッキー、ジャムなどを作って、それを販売するとなれば話は別です。ビジネスの規模が大きいか小さいかも関係ありません。作って販売する食品の種類に応じて、それに見合った許可が必要です。
菓子製造業許可
自分で焼いた菓子パンやジャムのみを店頭で売る場合には、菓子製造業許可を受ければ営業することができます。
ただ、ホットドックなどスイーツ系でないものの製造と販売についても、菓子パンの製造に付随する形で行なう程度なら、菓子製造業許可だけでも差し支えないとしている自治体もあるようです。
飲食店営業許可
甘い菓子パンを焼いて販売するだけならば、菓子製造業許可証のみを受ければ十分です。しかし、野菜やハム、ソーセージなどを入れた総菜パンや、サンドイッチを製造して売りたいケースでは、飲食店営業許可の取得が必要となってきます。
当然のことながら、もし、菓子パンと総菜パンの両方を作って、店頭で売りたいとなれば、菓子製造業許可証と飲食店営業許可証を2つとも取得しなければなりません。
食品衛生責任者
菓子製造業許可や飲食店営業許可は、パン屋を営むための施設に対する許可です。しかし、パン屋として営業をおこなうためには設備だけではなく、人的な要件も満たしていなければなりません。これにあたるのが食品衛生責任者です。
パン屋や飲食店など、食品を扱う営業をおこなう場合は、施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を置くという決まりがあります。食品衛生責任者は、施設内で食中毒や食品衛生法違反などが起きないように、管理運営を担うのです。
食品衛生責任者になるためには、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります。
パン屋の営業形態によって必要な許可が異なる
パン屋をどのようなスタイルで営業していくかによっても、必要となる許可は違ってきます。この段落では、営業形態ごとの視点から説明しましょう。
持ち帰りのみのパン屋
パン屋の事業形態には、販売した商品を持ち帰る、いわゆる、テイクアウトだけを専門としているスタイルがあります。
持ち帰りに特化した店で菓子パンを扱いたい場合には、菓子製造業許可証が必要です。総菜パンやサンドイッチなど、焼き上げたパンに加工して販売するケースでは、飲食店営業許可証も合わせて取得しなければなりません。
ただ、同じく焼いたパンを加工するとはいえ、たとえば、クロワッサンにチョコレートコーティングをしたり、粉砂糖を振りかけたりしても、菓子製造業許可のみで事足ります。一方、焼いた後に加工をしなくても、ピザなどは調理パンとみなされて、飲食店営業許可も必要となる場合があることも覚えておきましょう。
店舗内で食べるベーカリーカフェ
パン屋の施設内で焼いたパンを、そのまま店舗の中で食べるスタイルのベーカリーカフェならば、飲食店営業許可を取得するだけで対応可能です。
イートインだけのベーカリーカフェでしたら、店で扱うパンがスイーツ系であろうと、総菜パンやサンドイッチであろうと種類は問いません。どのようなパンであっても、飲食店営業許可証を受けるだけで大丈夫です。
しかし、店の中で食べるだけではなく、持ち帰りもできるようにしたい場合は事情が変わります。イートインコーナーだけでなく、持ち帰りもあるパン屋を運営したいのならば、菓子製造業許可証も取得しなければなりません。
仕入れたパンのみを扱うパン屋
パンを店内で焼いて販売するのではなく、外部から仕入れた調理済みのパンを売るというケースでは特別な許可を取得する必要がないこともあります。
しかし、他から仕入れるパンが、すでに個別包装されている状態なのか、自身の手で小分けしてから販売するのかによっても必要な許可が異なります。詰め直したり、小分けしたりした後に売るのならば、食料品等販売業の営業許可が必要になることもあります。
自治体によって判断基準も異なるので、店舗を構える土地を所轄する保健所に問い合わせ、確認することが重要です。
移動販売のパン屋

キッチンカーなどを利用してパンを販売したい場合、菓子製造業許可証を得なければなりません。サンドイッチや総菜パンも扱いたい場合では、飲食店営業許可も一緒に取得する必要が出てきます。
この2種類の許可証のほかにも、自動車でパン屋を運営するケースならではの手続きがあります。パンがすでに出来上がっていて、あとは売るだけという形になっているのならば食品移動販売車の申請をおこないましょう。
自動車の中で調理をする場合は、食品営業自動車の申請です。営業に使用する自動車の構造には要件が設けられているため、許可の申請を通すためには改造する必要も出てきます。
[PR]飲食店ビジネス特集
パン屋の開業に向けて!取得しておくとよい資格
パン屋を新規にオープンしたいと考えている場合、資格は必要ないですが、取得しておくとよい資格はいくつかあります。次の項では、これらの資格について紹介していきます。
パン製造技能士
パン製造技能士は、パンの製造に関わる仕事をする上で身に付けたり、必要とされるスキルの習得レベルを評価したりするための技能検定です。厚生労働省が所轄する国家試験で、この試験に合格すると技能士を名乗ることができます。
パン製造技能検定は、レベルによって特級、1級、2級の3等級に分かれています。都道府県職業能力開発協会が実施しており、学科試験と実技試験の両方を受けなければなりません。合格ラインは、学科試験は100点満点中65点以上、実技試験では100点満点中60点以上を原則としています。
受験資格は、2級で実務経験が2年以上、1級では7年以上となり、特級は1級合格後5年以上です。しかし、必要となる実務経験年数は、学歴や職業訓練受講歴に応じて短くなります。
パンシェルジュ検定
パンシェルジュ検定はパンの製法や使用する器具、材料についての知識などが問われる試験で、2009年から開始となりました。そのほかにも、パンの歴史や海外のパン事情、衛生に関する基本など、パンにまつわる広い知識を身に付けることができる資格です。
検定のグレードは3段階に分かれていて、ベーシックの3級、プロフェッショナルの2級、マスターの1級があります。公式ホームページによれば、合格率の目安は、3級が82%、2級が65%、1級が60%とのことです。
なお、パンシェルジュ検定の試験方法は学科試験です。3級2級はマークシート方式で、1級はマークシート方式に加え、記述式の問題も出題されます。
パンコーディネーター
パンコーディネーターは、パンに関するプロフェッショナルに向けた資格です。ただし、パンを製造する側を対象としているのではなく、食べる側の視点からのパンに関するプロフェッショナル資格試験である点が特徴です。
3つの等級に分かれていて、指定の講座を受講してから、筆記による認定試験を受けます。パンについての幅広い知識が身に付くため、アドバイスをおこなったり、企画や開発のアイディアを出したりすることも可能になります。
パン屋の開業に必要な資金
開業資金
パン屋開業に必要な資金の目安は、数百万円から1000万円程度となります。開業資金の内訳の中でも、大きな負担となりやすいのが不動産取得費用です。敷金や礼金などを含めて、50万~300万円程度は用意しておく必要があるでしょう。
また、設備費や内装工事費も金額が膨らみやすい項目です。居抜き物件などを利用すれば安く抑えられますが、一から店舗を構える場合は多額の初期投資を覚悟しなくてはなりません。提供するパンの種類によって必要な設備が変わってくるため、種類が多いほど設備費用も高くなるということは認識しておきましょう。
運転資金
そして、不動産取得費用や設備費用に並んで重要なのが運転資金です。開業当初は集客がはかどらないことも多く、経営は赤字になりやすいものです。経営が軌道に乗るまでの時期を支えるために、十分な額の運転資金を用意しておきましょう。経営が黒字になるまで半年以上かかることもあるので、生活費として100万~200万円程度は用意するべきだといえます。
その他、広告宣伝費や材料費、人件費などについても計算に入れておきましょう。特に、インターネットからの集客を考えている場合、ホームページ作成費として数十万円程度の資金が必要になります。
[PR]中食ビジネス特集
パン屋の経営を成功させるポイント
ライバルが多いパン屋の経営を成功させるためには、集客方法や内装などに工夫を凝らして自分の店舗の価値をアピールしていくことが大切です。開業当初は経営もうまくいかないものですが、運任せにするのではなく、努力によって成功を引き寄せましょう。ここからは、パン屋の経営を成功させるためのポイントを3つ紹介します。
集客方法を工夫する
一般論として、存在が知られていなければ店に客が来ることはありません。そのため、開業時から積極的に宣伝を行い、店の存在を広く知ってもらうことが大切です。
インターネットが普及して以来、パン屋の情報もインターネットで集める人が多くなっています。まずはホームページを開設し、写真などで店の雰囲気やパンの種類を紹介しましょう。
また、SNSを利用した宣伝も効果的です。特に、おしゃれな内装やパンを宣伝したいときは、ビジュアルに特化したInstagramを利用すれば高い集客効果が期待できます。ホームページやSNSを利用したマーケティングで多くの人にリーチするコツは、定期的にコンテンツを更新することです。そうすれば、検索結果画面でホームページが上位に表示されやすくなり、SNSでも話題に上りやすくなるはずです。
その他、チラシのポスティングで地域住民に店を知ってもらうのも確実な集客方法だといえます。このように、さまざまな角度から集客を狙っていくことでパン屋の経営を軌道に乗せることができるでしょう。
内装をおしゃれにする
パン屋の客層は20代~40代の女性が多く、内装がおしゃれかどうかという点が集客に大きく影響します。内装をおしゃれにするためのアイディアとして、間接照明を取り入れて光の濃淡を表現すると良いでしょう。また、木目調のカウンターなどを設置すれば、ぬくもりを感じさせる雰囲気が演出できます。
さらに、パンをインテリアに見立てて陳列方法を工夫したり、パンを販売するスペースとイートインスペースを完全に分けたりするのも効果的な方法です。
このように、内装をおしゃれにすれば競合店との差別化も図ることができ、経営が成功しやすくなります。
人気のパン屋で修行する
繁盛している小さなパン屋で3年ほど修行するのも良い方法だといえます。大きなパン屋は就業条件が比較的整っていますが、作業を効率化するために分業が進んでおり、パン製造全体の流れがつかみにくいという欠点があります。
自分でパン屋を経営することを目指して修行するのであれば、パン製造の全工程に関われる小さなパン屋がおすすめです。忙しく働くうちに、パン屋で成功するためのノウハウが自然と身に付くでしょう。
[PR]カフェや喫茶店を開業・経営
フランチャイズのパン屋という選択肢もある
パン屋を個人で開業するためには、パンの焼き方や経営のノウハウなどを自力で習得しなければなりません。そうした技術や知識を自分一人で経営できるレベルまで高めるためには、最低でも3年の修業期間が必要となるでしょう。しかし、フランチャイズに加盟すれば、研修などを通してパン屋経営に必要な技術・知識を短期間で身に付けることができます。
また、パン屋経営で意外に大変なのが商品開発です。客を店に引きつけておくためには新商品を定期的に発売することが大切ですが、経営に気を取られるあまり、商品開発をおろそかにしてしまうこともあります。一方、フランチャイズなら商品開発も本部が行なってくれるため、経営のみに専念することができるのです。
パン屋の開業には業態に合った許可が必要!
パン屋を開業するにあたっては、なにか特別な資格を持っていなければならないわけではありません。しかし、販売するためには許可が必要で、自治体ごとで基準が違っているため開業に必須となる許可や届出も異なります。したがって、各々で所轄の保健所に問い合わせ、しっかりと確認することが重要です。パン屋開業に向けて必要となる許可を受け、成功を手に入れましょう。
[PR]ニッチビジネス特集